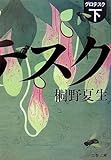| 死の棘 (新潮文庫)島尾 敏雄新潮社このアイテムの詳細を見る |
「いったい、どういうのかしら/あなたのきもちはどこにあるのかしら。どうなさるつもり? あたしはあなたには不必要なんでしょ。だってそうじゃないの。十年ものあいだ、そのように扱ってきたんじゃないの。あたしはもうがまんはしませんよ。もうなんと言われてもできません。十年間もがまんをしつづけてきたのですから、爆発しちゃったの。もうからだがもちません。見てごらんなさい、こんなに骸骨のようにやせてしまって。あたしは生きてはいませんよ。生きてなどいるもんですか。でもあなたにめいわくはぜったいにかけませんからね。誰にもわからないようにじぶんを処分するくらいのことはあたしにできます。あたしはそのことばかりずっと研究していたようなものだわ。あたしはあなたを解放してあげます。そのあとであなたは好きなようにその女とくらしたらいいでしょ」(P6-7)
島尾敏雄の『死の棘』を読んだ。と言っても、知らない人が多いかもしれない。僕も、高橋源一郎先生が「昭和(戦後?)で一番」かなんかとベタ褒めしていたので読んでみたのである。小説の内容は、完全な私小説。正直なところ、進行中の事件について並行して私小説を書いて掲載していた作家の考え方というのはよくわからない。良い悪いの問題ではなくて、私生活で小説の中でこんな風に振舞ったら面白いだろうな、という演技の要素が入ってしまうのではないかと思ってしまうのである。だから、私小説というノンフィクションに近い小説のジャンルのはずなのに、そもそも描くべき私生活の方がフィクション的であり、フィクションについてのノンフィクションという妙な構造になってしまうのではないかと思うのだが。
さて、この小説であるが、救いようのないことが救いようのないまま決着らしい決着もなく600ページほども続く、ある種の地獄のような小説である。作家である主人公の不貞(不倫)と家庭を顧みなかった年月をずっと耐えてきた妻が、主人公の日記を盗み読んだのをきっかけに、神経に異常をきたし(率直に言えば、ほとんど発狂し)夫とその過去を追及しはじめるのだが、追及すれば追及するほど夫からは不貞の事実が明らかになり、しかもそれでも夫は隠しごとをし、また追及され明らかにされるという繰り返しが延々と続く。途中、不貞の相手から逃げるため住居を何度か変えたり、不貞の相手が乗り込んできたり、妻をついに精神病院に入院させたり(電気ショックまでされている)と、これでもかというどろどろの地獄を読者は見せつけられることになる。しかも、その描き方も当然ながらうまくて、こちらがいたたまれなくなるほどありのままを見せている。比喩や描写も秀逸で、不貞について「その時は羽ばたき、後には腐り落ちた行為」(うろ覚え)とかぐっと迫る文句をところどころに置いている。よくもこれだけ、人間性についてどぶさらいをした小説を書いたものだと思う。むろん、いい意味で。
というわけで、一言で言えば、この世の地獄について描いた、地獄のような小説。正直、かなりの読書経験を積んだ文学マスターがまだまだ俺をうならせる小説はあるのか、とか言いながら読むかという難度。だいたい村上春樹から文学に入り、小説は英米ベースの僕には荷が重かった。それでも、我こそはという猛者はぜひチャレンジしてほしい。