昨日は、江南市立宮田中学校 研究発表会でした。
アトラクションでは、有志生徒による『エッサッサ』が披露されました。

若さみなぎるエネルギーにあふれた演舞でした。
かつての荒れを経験したことのある教員の中に、一部突出した生徒よりも、一般生徒の「まじめを馬鹿にする風潮」がもっと大きな問題だったと言う人がいます。
私もそう考える1人です。
まじめに掃除をする生徒を馬鹿にする。馬鹿にされたくないから掃除をしない。学校が汚れ、ますます心が荒れるという悪循環になっていました。
そこを打破するのは、「まじめ」を賞賛することです。
まじめの美しさを見せつけることです。
この『エッサッサ』は、まじめの美しさを見せる、とてもよい素材だと感じました。
開会行事の後には、研究発表がありました。

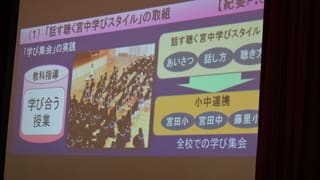

シンプルで、わかりやすい内容でした。
その後は公開授業。
自習を公開したのは、丹葉地区では初めてではないでしょうか。
1年3組では、社会科の教科委員が、答えの確認を行っていました。


各教室では、宮中学びスタイルによる授業が行われていました。
最後に、北方町教育委員会 教育科 教育主幹 後藤喜朗先生による講演でした。
ユーモアたっぷりで、パワフルな、しかも大きな示唆に富んだ内容でした。
以下は私の個人的な感想です。
1 新たな研究スタイルの提案
よくある研究は、大学の研究者の理論により実践をし、検証していくものです。
ただ、他の研究者と差別化を図るために、ユニークな活動が伴います。それが定着すればよいのですが、発表が終わり、人が変わるとなくなってしまうのが通例です。
また、目指すべき子供のイメージが人により異なるために、何をやりたいのかが見えてこない研究もよく見かけます。
今回の宮田中学校の研究は、全く発想が異なります。
理論からではなく、事実から入っているのです。
その事実とは、東長良中学校であり、長良東小学校、長良小学校の先生方であり子供達なのです。
これらの学校は、10年以上、全学級が共通の授業スタイルで行われています。しかも、高い質の教科内容で・・・・。
教師陣は毎年入れ替わるのに、なぜ維持され続けているのか?
そもそも、この子供達はどうやるとこのように育つのか?
何度もこれらの学校に通い、子供の姿から、宮田中学校に合ったものを取り入れていったのです。
学校の研究は子供のためにあります。
今回の研究は、具体的な子供の姿から、共通のイメージをもってそこに近づこうとする、新たな研究スタイルの提案なのです。
2 継続性の保障
人が変わっても、維持されるシステム。
岐阜研修校の特徴です。
実は、その秘密は、学校職員OBによる継続的な指導にあります。
これとは別に大切なのが、他校との連携です。
マラソン練習は1人ではなかなかできません。苦しくなるとつい歩いてしまうか、スピードを落としてしまうからです。
ところが、仲間と走っていると長続きします。苦しさが和らぐのです。
さらに大会では、ペースメーカーがいるととても助かります。
研究実践も同じです。
小中連携は仲間にあたります。
ペースメーカーは長良3校にあたります。
小中連携と長良3校に学び続ける限り、継続性は保障されることでしょう。
3 豊かな人間関係の構築&エンパワーメント
長良3校へ行っていつも感じるのが温かさです。
話し合うときの頭の距離が近く、意見を聞くときのまなざしなど、豊かな人間関係を感じます。
宮田中学校も、さすがにそのポイントを押さえています。
授業中における「相手を見て話す・聴く」、プリントを渡すときの「はいどうぞ、ありがとう」を基盤として、これまで行われてきた教育活動に、温かさという「魂」を入れたのです。
さらに、市全体として活用しているQ-Uアンケート、生徒のエンパワーメントを生かした数々のプロジェクトや教科委員の活動などが、有機的に絡み合い、生徒の学校へに対する所属感を高めていると感じました。
4 全員参加型の研究
義務教育は、全員に学びを保障することが求められます。
その手段の一つが、生徒の全員参加型授業です。
「なぜ話す人を見るの?」
よく受ける質問です。やってみるとわかりますが、発言する子も、安心して、自信を持って発言できるようになります。
しかし、それ以上に私が重要だと考えることは、授業に参加していない子を発見するためです。
さらに、集団から離れようとしている子、心に悩みをもつ子なども見えるようになります。
これら、支援が必要な子を「見える化」するためなのです。
発言する子だけでなく、全ての聴く子を見取ることが、教師の仕事なのです。
「なぜハンドサイン?」
本来は友達の意見に対して自分の考えを明らかにするためですが、重要な点は、意見を聞いていない子を見つけるためです。
もう一つが教師の全員参加です。
職員全員が交代で長良3校へ見に行くのは、イメージの共通化です。
その他にも、教師が全員参加するために、いろいろな縦横・横糸が工夫されています。
その一つが「学び集会」。
全生徒と共に、全教師もこの集会で共通の学びスタイルを学びます。
そして「教科委員」。
教科委員が全校的に指導されているので、全授業で共通した取り組みが可能です。
全クラスが学習課題を黄色の四角で囲み、生徒が唱和します。
どの教室をのぞいても、課題は明確です。
これまで、課題を意識していなかった教師も、これで意識できるようになりました。
ただ、全員参加の見取りには、やや甘さを感じる場面がありました。
ハンドサインで反応していない子がいるのに、スルーする場面がありました。
また、「同じです」という反応も気になりました。
時々、「○○さん、どう同じなのか、自分のことばで説明してごらん。」などと教師がつないでやらないと、「聞いているつもり」で思考しない子が増えていきます。
「同じ」なのか「似ている」のか、新しく知った考えなのかも区別してつぶやけるとよいと感じました。
5 小中連携
こんな話をよく聞きます。
「小学校で、こんなことも指導していないのか。」「県名ぐらい小学校のうちに覚えさせてほしい」
一方では
「せっかく小学校で育てた子が、中学校でダメになってしまった」
小学校と中学校は連携すべきなのに、互いに批判し合うのです。最悪ですね。
先ほど、小中連携により、研究の継続性が保たれると書きました。
今後、宮田小学校と藤里小学校で同じスタイルで学んだ子供達が毎年入学してきます。
小中ギャップは大幅に緩和されることでしょう。
その他、今回の宮田中学校区の小中連携の実践は、参考になる点が多々ありました。
先日見た宮田小学校の体育の授業は、宮田中学校の準備運動を取り入れていました。
中学生へのあこがれも感じました。
小中合同現職教育では、共通した価値観を持つことができたでしょう。
合同で親睦会を行っているとも聞きました。
義務教育9年間は、小中が連携してこそ、その力が何倍にもなるのです。
まだまだ書きたいことがありますが、時間が来たので今日はここまで・・・・。
すばらしい実践を積み上げられた宮田中学校の先生方、そしていっしょに研究に参加された宮田小学校、藤里小学校の先生方。
アドバイスをいただいた、後藤先生始め、研修校の先生方、
なにより、すばらしい姿をみせてくれた生徒諸君に感謝します。
研究発表会の詳細は、宮中HPをご覧ください。
http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2320018
アトラクションでは、有志生徒による『エッサッサ』が披露されました。

若さみなぎるエネルギーにあふれた演舞でした。
かつての荒れを経験したことのある教員の中に、一部突出した生徒よりも、一般生徒の「まじめを馬鹿にする風潮」がもっと大きな問題だったと言う人がいます。
私もそう考える1人です。
まじめに掃除をする生徒を馬鹿にする。馬鹿にされたくないから掃除をしない。学校が汚れ、ますます心が荒れるという悪循環になっていました。
そこを打破するのは、「まじめ」を賞賛することです。
まじめの美しさを見せつけることです。
この『エッサッサ』は、まじめの美しさを見せる、とてもよい素材だと感じました。
開会行事の後には、研究発表がありました。

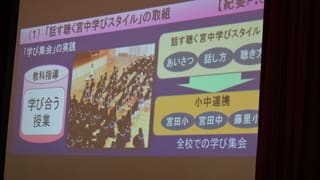

シンプルで、わかりやすい内容でした。
その後は公開授業。
自習を公開したのは、丹葉地区では初めてではないでしょうか。
1年3組では、社会科の教科委員が、答えの確認を行っていました。


各教室では、宮中学びスタイルによる授業が行われていました。
最後に、北方町教育委員会 教育科 教育主幹 後藤喜朗先生による講演でした。
ユーモアたっぷりで、パワフルな、しかも大きな示唆に富んだ内容でした。
以下は私の個人的な感想です。
1 新たな研究スタイルの提案
よくある研究は、大学の研究者の理論により実践をし、検証していくものです。
ただ、他の研究者と差別化を図るために、ユニークな活動が伴います。それが定着すればよいのですが、発表が終わり、人が変わるとなくなってしまうのが通例です。
また、目指すべき子供のイメージが人により異なるために、何をやりたいのかが見えてこない研究もよく見かけます。
今回の宮田中学校の研究は、全く発想が異なります。
理論からではなく、事実から入っているのです。
その事実とは、東長良中学校であり、長良東小学校、長良小学校の先生方であり子供達なのです。
これらの学校は、10年以上、全学級が共通の授業スタイルで行われています。しかも、高い質の教科内容で・・・・。
教師陣は毎年入れ替わるのに、なぜ維持され続けているのか?
そもそも、この子供達はどうやるとこのように育つのか?
何度もこれらの学校に通い、子供の姿から、宮田中学校に合ったものを取り入れていったのです。
学校の研究は子供のためにあります。
今回の研究は、具体的な子供の姿から、共通のイメージをもってそこに近づこうとする、新たな研究スタイルの提案なのです。
2 継続性の保障
人が変わっても、維持されるシステム。
岐阜研修校の特徴です。
実は、その秘密は、学校職員OBによる継続的な指導にあります。
これとは別に大切なのが、他校との連携です。
マラソン練習は1人ではなかなかできません。苦しくなるとつい歩いてしまうか、スピードを落としてしまうからです。
ところが、仲間と走っていると長続きします。苦しさが和らぐのです。
さらに大会では、ペースメーカーがいるととても助かります。
研究実践も同じです。
小中連携は仲間にあたります。
ペースメーカーは長良3校にあたります。
小中連携と長良3校に学び続ける限り、継続性は保障されることでしょう。
3 豊かな人間関係の構築&エンパワーメント
長良3校へ行っていつも感じるのが温かさです。
話し合うときの頭の距離が近く、意見を聞くときのまなざしなど、豊かな人間関係を感じます。
宮田中学校も、さすがにそのポイントを押さえています。
授業中における「相手を見て話す・聴く」、プリントを渡すときの「はいどうぞ、ありがとう」を基盤として、これまで行われてきた教育活動に、温かさという「魂」を入れたのです。
さらに、市全体として活用しているQ-Uアンケート、生徒のエンパワーメントを生かした数々のプロジェクトや教科委員の活動などが、有機的に絡み合い、生徒の学校へに対する所属感を高めていると感じました。
4 全員参加型の研究
義務教育は、全員に学びを保障することが求められます。
その手段の一つが、生徒の全員参加型授業です。
「なぜ話す人を見るの?」
よく受ける質問です。やってみるとわかりますが、発言する子も、安心して、自信を持って発言できるようになります。
しかし、それ以上に私が重要だと考えることは、授業に参加していない子を発見するためです。
さらに、集団から離れようとしている子、心に悩みをもつ子なども見えるようになります。
これら、支援が必要な子を「見える化」するためなのです。
発言する子だけでなく、全ての聴く子を見取ることが、教師の仕事なのです。
「なぜハンドサイン?」
本来は友達の意見に対して自分の考えを明らかにするためですが、重要な点は、意見を聞いていない子を見つけるためです。
もう一つが教師の全員参加です。
職員全員が交代で長良3校へ見に行くのは、イメージの共通化です。
その他にも、教師が全員参加するために、いろいろな縦横・横糸が工夫されています。
その一つが「学び集会」。
全生徒と共に、全教師もこの集会で共通の学びスタイルを学びます。
そして「教科委員」。
教科委員が全校的に指導されているので、全授業で共通した取り組みが可能です。
全クラスが学習課題を黄色の四角で囲み、生徒が唱和します。
どの教室をのぞいても、課題は明確です。
これまで、課題を意識していなかった教師も、これで意識できるようになりました。
ただ、全員参加の見取りには、やや甘さを感じる場面がありました。
ハンドサインで反応していない子がいるのに、スルーする場面がありました。
また、「同じです」という反応も気になりました。
時々、「○○さん、どう同じなのか、自分のことばで説明してごらん。」などと教師がつないでやらないと、「聞いているつもり」で思考しない子が増えていきます。
「同じ」なのか「似ている」のか、新しく知った考えなのかも区別してつぶやけるとよいと感じました。
5 小中連携
こんな話をよく聞きます。
「小学校で、こんなことも指導していないのか。」「県名ぐらい小学校のうちに覚えさせてほしい」
一方では
「せっかく小学校で育てた子が、中学校でダメになってしまった」
小学校と中学校は連携すべきなのに、互いに批判し合うのです。最悪ですね。
先ほど、小中連携により、研究の継続性が保たれると書きました。
今後、宮田小学校と藤里小学校で同じスタイルで学んだ子供達が毎年入学してきます。
小中ギャップは大幅に緩和されることでしょう。
その他、今回の宮田中学校区の小中連携の実践は、参考になる点が多々ありました。
先日見た宮田小学校の体育の授業は、宮田中学校の準備運動を取り入れていました。
中学生へのあこがれも感じました。
小中合同現職教育では、共通した価値観を持つことができたでしょう。
合同で親睦会を行っているとも聞きました。
義務教育9年間は、小中が連携してこそ、その力が何倍にもなるのです。
まだまだ書きたいことがありますが、時間が来たので今日はここまで・・・・。
すばらしい実践を積み上げられた宮田中学校の先生方、そしていっしょに研究に参加された宮田小学校、藤里小学校の先生方。
アドバイスをいただいた、後藤先生始め、研修校の先生方、
なにより、すばらしい姿をみせてくれた生徒諸君に感謝します。
研究発表会の詳細は、宮中HPをご覧ください。
http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2320018









