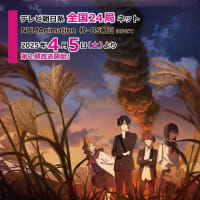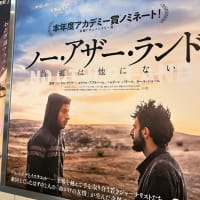前から観たかった木下恵介『女の園』を、GW最終日に家でまったりのお供にチョイスして鑑賞。まったりしてる場合じゃないような壮絶な映画で、一人で観ながら色々なところで声をあげながら鑑賞してしまった。
悪い社会(マスコミだったり権威だったり差別団体だったり)vs一市民(だったり新聞社だったり警察だったり)
とにかく物語として分かりやすく、感情移入しやすく、テーマを訴えやすくするため、なんならエンタメ性持たせるため、対立構造を単純化する。
しかし実際のところ世の中はそんなに単純ではなく、対立構造は複雑なものだ。
単純化により成功した社会派映画もあるが、失敗した映画もある。『リチャード・ジュエル』は(個人的には好きだが)単純化のため実在の人物数名を一人にしてしかも事実と異なる言動をさせたことで炎上にちかいくらいに物議をかもした。
そして社会正義を語りたがるリベラルな映画人たちに特に言いたいのだが、単純化はリベラルの敵である側にとっても最も好む手法である。
トランプをみなさい
正義vs悪の単純構図で社会の変革を訴えるのは本質を見誤る恐れがあるし、それで勝ったとしても分断を深めてしまう恐れがある
などと言っといて自分自身、単純化して自民党ガーって言う傾向があることは承知している。どの口が言うのだと思われるかもしれないが、まあでも一歩引いて自分を見る気付きをこの映画は与えてくれた
--------
話を『女の園』に戻すが、『女の園』は社会の変革を訴えたり、社会の問題をついたりする映画の常とう手段である「単純化」をさけ、それとは真逆に、構造の複雑さをむしろ強調して描いている。その点が凡百の社会派映画と一線を画すくらい独特で、しかもうまい。
本作のクライマックスは、様々な人間がそれぞれの立場での正義を語り、それぞれの立場で本気の涙を流している。
一人の女学生(高峰秀子)の、
ルームメイト(岸恵子)
彼氏(田村高廣)
父(松本克平)
活動に引き込んだ女学生(久我美子)
監視役の寮母(高峰三枝子)
指導役の教師(金子信雄)
皆言っていることは正しい面もあるし、でもすべてが正しいわけではない
高峰秀子のある事件を契機に学生たちの怒りに火が付き、運動が一気に激化する
改革せよ
権利を守れ
自由をよこせ
すべて学校のせいだと
しかし映画は単純化することなく丁寧に物語を追っており、契機となったある事件は100%学校のせいだけではない
父のせい、だけでもないし
お前のせいで、という父の言葉も、絶対に間違っているとは言えないし
お預かりしたお嬢様たちのために、という学校の言い分も、聞く耳はもつべきだし
しかし人々は単純化を望む
『戦艦ポチョムキン』みたいに、スープにウジがわいてる、軍部の兵士に対する扱いはひどすぎる、許さん! みたいな
『波止場』のように、港湾労働組合が実質マフィアで仕事を取り仕切っていて、シマを荒らすやつ、言うこと聞かない奴は脅したり殺したりしている。許さん! みたいな
しかし『女の園』は違う
自由のため立ち上がった女たちも事件の一面しか見ずに闘争に結び付けているともとれるし
女学生を最前線で抑圧してきた寮母にも、女として抑圧されてきた過去があるし
生活指導の教師も生活の問題がある
学生闘争のリーダーは学校のスポンサーの財閥の娘で、にもかかわらず闘争に参加する。他の学生と違い学校ににらまれるリスクは少ないし、最悪退学になってもどうとでもなる。他の学生たちとは立場が違うのにけしかけるようなことは止めてと、グループ内も一枚岩ではない。
そこをついてわざと軽い処分にして不公平を出し学生間の結束にくさびを打つ学校のやり方は狡猾だが、運動つぶしの上手さについ感心してしまった。
大事なのは、皆が色々な立場の人たちみんなが本気で怒り、本気で泣いている
そして映画は勝っただの負けただのという結末は見せずに終わる
複雑な事件を俯瞰するわけではなく、一人一人に深入りして、個人個人の事情や性格や立場をしっかりと見せて、そして大きな運動へと展開していくが、みんなが表層をなぞっているだけのような、事件の構造を見せる
完全な悪も完全な正義もないことを
淡々と、ではない
むしろ熱く、みなに寄り添いながら、しかし対立は止められない、そうした社会の断片を見事に描き切っている
リアルタイムで観ていたら、野武士vs百姓の単純な映画よりこっちの方を支持したくなる気持ちはわかる(あの映画もけっしてそんな単純な話ではないけれど)
七人の侍を差し置いての年間2位というランキングは伊達じゃないと思った
それにしても木下恵介監督の熱い熱い時期だったのだろう。
こんな野心的な剛腕社会派の力作と『二十四の瞳』という超のつく泣かせ名作を同年に発表できるとは
1954年
熱い年だ
-----
伝説的名作がまとめて公開される「映画奇跡の年」というものがある。
1977年は『スターウォーズ』と『未知との遭遇』が公開され『アニーホール』が公開されたり『アーノルドシュワルツェネッガー鋼鉄の男』が公開されたりもして奇跡の年と言われる
1968年も『猿の惑星』『ナイトオブザリビングデッド』『2001年宇宙の旅』が公開された奇跡の年だ。
そして我が国の場合1954年(昭和29年)が奇跡の年と言われる。『七人の侍』『二十四の瞳』『ゴジラ』が公開された年だ。
1954年のキネマ旬報ベストテンを見てみると、3位に『七人の侍』、1位が『二十四の瞳』となっている。(ちなみに『ゴジラ』はベストテンはおろか26位までにも入っていない。多分1票も入っていないのではないか)
2025年の時点から1954年の映画でベストテンを選べば多分1位『七人の侍』2位『二十四の瞳』3位『ゴジラ』となるだろう。
さて、七人が3位で二十四が1位の年の第2位は何だったのかと言えば、木下恵介の『女の園』だったわけである。
つまり木下恵介は、映画史上最強クラスのライバル作品を3位に押しやってワンツーフィニッシュを決めたということになる。最高潮に乗っていた時期と言えるだろう。
しかし、現在において、『二十四の瞳』はいまだに名作として語り継がれているけれども、『女の園』という映画が語られることはほとんどない。
前置きが長くなったが、ようやっとU-Nextで鑑賞。
すさまじく面白かった。
なんとなく、本作のキネ旬における順位が納得いった気がした
本作は昭和29年における現在進行形の社会問題を扱った、正真正銘の社会派映画である。
この年リアルタイムでこれを見ていたら、「この飯おろそかには食わぬぞ」などと言って勘兵衛ごっこをしている場合じゃないと思うのも仕方ない気がする。
一方で昭和29年という時代をすぎて何十年も経ってもなお輝き続ける普遍性までは持っていない。
だからといって現代の目線でも本作は抜群に面白いのだけど
----
全寮制の女子大学で、生徒たちが封建的・前時代的な学校に対して女学生たちがわずかな自由を求め団結し学生運動へと展開していく。オープニングで、タイトルバックで女学生たちがシュプレヒコールをあげて、学校に抗議するべく進みだすところから始まる。なぜそのようなことになったのか、時間をさかのぼってその経緯を追う、という展開。
おしとやかなお嬢様を育成するためのような学校で起こる、学生たちの若者たちの権利と自由を訴える物々しい闘争が起こる様を描くわけである。
女たちは戦時中、どれほど抑圧されてきたことだろうかと
時代は変わった、というかいままさに変わりつつあることを描いていて、同時代に生きて見ていれば胸も熱くなろう。
しかし本作が秀逸なのは、学生と学校の対立を、あるいは旧時代的なるものと新時代的なるものの対立を、「単純化」していないことではないかと思う。
-----
近年、社会派映画と呼べるものは少なくなってきたように思う。日本映画にはほとんどなく、あってもデキが悪い(具体的に言うのは控える)
イギリスはケン・ローチを筆頭に社会派映画はわりとコンスタントに作られているし、アメリカ映画も最近だと『スポットライト』『ブラッククランズマン』『リチャード・ジュエル』といくつか思いつく。
ただ英米のそうした社会派映画、傑作もあればうーーんな出来のもあるけれど、いずれにせよほぼすべてで物語の単純化が図られているように思う。
伝説的名作がまとめて公開される「映画奇跡の年」というものがある。
1977年は『スターウォーズ』と『未知との遭遇』が公開され『アニーホール』が公開されたり『アーノルドシュワルツェネッガー鋼鉄の男』が公開されたりもして奇跡の年と言われる
1968年も『猿の惑星』『ナイトオブザリビングデッド』『2001年宇宙の旅』が公開された奇跡の年だ。
そして我が国の場合1954年(昭和29年)が奇跡の年と言われる。『七人の侍』『二十四の瞳』『ゴジラ』が公開された年だ。
1954年のキネマ旬報ベストテンを見てみると、3位に『七人の侍』、1位が『二十四の瞳』となっている。(ちなみに『ゴジラ』はベストテンはおろか26位までにも入っていない。多分1票も入っていないのではないか)
2025年の時点から1954年の映画でベストテンを選べば多分1位『七人の侍』2位『二十四の瞳』3位『ゴジラ』となるだろう。
さて、七人が3位で二十四が1位の年の第2位は何だったのかと言えば、木下恵介の『女の園』だったわけである。
つまり木下恵介は、映画史上最強クラスのライバル作品を3位に押しやってワンツーフィニッシュを決めたということになる。最高潮に乗っていた時期と言えるだろう。
しかし、現在において、『二十四の瞳』はいまだに名作として語り継がれているけれども、『女の園』という映画が語られることはほとんどない。
前置きが長くなったが、ようやっとU-Nextで鑑賞。
すさまじく面白かった。
なんとなく、本作のキネ旬における順位が納得いった気がした
本作は昭和29年における現在進行形の社会問題を扱った、正真正銘の社会派映画である。
この年リアルタイムでこれを見ていたら、「この飯おろそかには食わぬぞ」などと言って勘兵衛ごっこをしている場合じゃないと思うのも仕方ない気がする。
一方で昭和29年という時代をすぎて何十年も経ってもなお輝き続ける普遍性までは持っていない。
だからといって現代の目線でも本作は抜群に面白いのだけど
----
全寮制の女子大学で、生徒たちが封建的・前時代的な学校に対して女学生たちがわずかな自由を求め団結し学生運動へと展開していく。オープニングで、タイトルバックで女学生たちがシュプレヒコールをあげて、学校に抗議するべく進みだすところから始まる。なぜそのようなことになったのか、時間をさかのぼってその経緯を追う、という展開。
おしとやかなお嬢様を育成するためのような学校で起こる、学生たちの若者たちの権利と自由を訴える物々しい闘争が起こる様を描くわけである。
女たちは戦時中、どれほど抑圧されてきたことだろうかと
時代は変わった、というかいままさに変わりつつあることを描いていて、同時代に生きて見ていれば胸も熱くなろう。
しかし本作が秀逸なのは、学生と学校の対立を、あるいは旧時代的なるものと新時代的なるものの対立を、「単純化」していないことではないかと思う。
-----
近年、社会派映画と呼べるものは少なくなってきたように思う。日本映画にはほとんどなく、あってもデキが悪い(具体的に言うのは控える)
イギリスはケン・ローチを筆頭に社会派映画はわりとコンスタントに作られているし、アメリカ映画も最近だと『スポットライト』『ブラッククランズマン』『リチャード・ジュエル』といくつか思いつく。
ただ英米のそうした社会派映画、傑作もあればうーーんな出来のもあるけれど、いずれにせよほぼすべてで物語の単純化が図られているように思う。
悪い社会(マスコミだったり権威だったり差別団体だったり)vs一市民(だったり新聞社だったり警察だったり)
とにかく物語として分かりやすく、感情移入しやすく、テーマを訴えやすくするため、なんならエンタメ性持たせるため、対立構造を単純化する。
しかし実際のところ世の中はそんなに単純ではなく、対立構造は複雑なものだ。
単純化により成功した社会派映画もあるが、失敗した映画もある。『リチャード・ジュエル』は(個人的には好きだが)単純化のため実在の人物数名を一人にしてしかも事実と異なる言動をさせたことで炎上にちかいくらいに物議をかもした。
そして社会正義を語りたがるリベラルな映画人たちに特に言いたいのだが、単純化はリベラルの敵である側にとっても最も好む手法である。
トランプをみなさい
正義vs悪の単純構図で社会の変革を訴えるのは本質を見誤る恐れがあるし、それで勝ったとしても分断を深めてしまう恐れがある
などと言っといて自分自身、単純化して自民党ガーって言う傾向があることは承知している。どの口が言うのだと思われるかもしれないが、まあでも一歩引いて自分を見る気付きをこの映画は与えてくれた
--------
話を『女の園』に戻すが、『女の園』は社会の変革を訴えたり、社会の問題をついたりする映画の常とう手段である「単純化」をさけ、それとは真逆に、構造の複雑さをむしろ強調して描いている。その点が凡百の社会派映画と一線を画すくらい独特で、しかもうまい。
本作のクライマックスは、様々な人間がそれぞれの立場での正義を語り、それぞれの立場で本気の涙を流している。
一人の女学生(高峰秀子)の、
ルームメイト(岸恵子)
彼氏(田村高廣)
父(松本克平)
活動に引き込んだ女学生(久我美子)
監視役の寮母(高峰三枝子)
指導役の教師(金子信雄)
皆言っていることは正しい面もあるし、でもすべてが正しいわけではない
高峰秀子のある事件を契機に学生たちの怒りに火が付き、運動が一気に激化する
改革せよ
権利を守れ
自由をよこせ
すべて学校のせいだと
しかし映画は単純化することなく丁寧に物語を追っており、契機となったある事件は100%学校のせいだけではない
父のせい、だけでもないし
お前のせいで、という父の言葉も、絶対に間違っているとは言えないし
お預かりしたお嬢様たちのために、という学校の言い分も、聞く耳はもつべきだし
しかし人々は単純化を望む
『戦艦ポチョムキン』みたいに、スープにウジがわいてる、軍部の兵士に対する扱いはひどすぎる、許さん! みたいな
『波止場』のように、港湾労働組合が実質マフィアで仕事を取り仕切っていて、シマを荒らすやつ、言うこと聞かない奴は脅したり殺したりしている。許さん! みたいな
しかし『女の園』は違う
自由のため立ち上がった女たちも事件の一面しか見ずに闘争に結び付けているともとれるし
女学生を最前線で抑圧してきた寮母にも、女として抑圧されてきた過去があるし
生活指導の教師も生活の問題がある
学生闘争のリーダーは学校のスポンサーの財閥の娘で、にもかかわらず闘争に参加する。他の学生と違い学校ににらまれるリスクは少ないし、最悪退学になってもどうとでもなる。他の学生たちとは立場が違うのにけしかけるようなことは止めてと、グループ内も一枚岩ではない。
そこをついてわざと軽い処分にして不公平を出し学生間の結束にくさびを打つ学校のやり方は狡猾だが、運動つぶしの上手さについ感心してしまった。
大事なのは、皆が色々な立場の人たちみんなが本気で怒り、本気で泣いている
そして映画は勝っただの負けただのという結末は見せずに終わる
複雑な事件を俯瞰するわけではなく、一人一人に深入りして、個人個人の事情や性格や立場をしっかりと見せて、そして大きな運動へと展開していくが、みんなが表層をなぞっているだけのような、事件の構造を見せる
完全な悪も完全な正義もないことを
淡々と、ではない
むしろ熱く、みなに寄り添いながら、しかし対立は止められない、そうした社会の断片を見事に描き切っている
リアルタイムで観ていたら、野武士vs百姓の単純な映画よりこっちの方を支持したくなる気持ちはわかる(あの映画もけっしてそんな単純な話ではないけれど)
七人の侍を差し置いての年間2位というランキングは伊達じゃないと思った
それにしても木下恵介監督の熱い熱い時期だったのだろう。
こんな野心的な剛腕社会派の力作と『二十四の瞳』という超のつく泣かせ名作を同年に発表できるとは
1954年
熱い年だ