2017年に読んだ本(およそ170冊)の中から
心に残った10冊を
選んでみました。
4冊目は「利き蜜師物語」シリーズの3巻目
「歌う琴」(小林栗奈 2017年11月刊)
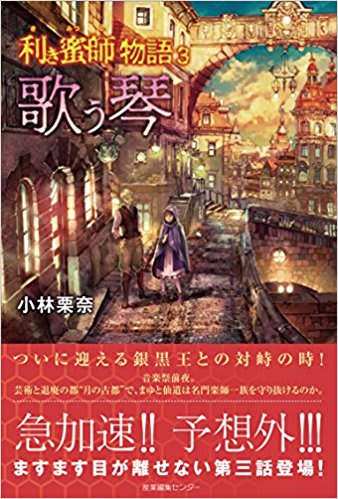
利き蜜師の仙道と弟子の少女まゆは
旅の途中に飛行船の事故によって月の古都に降りることになる。
普段は門が閉ざされていて人を立ち入らせない町・月の古都。
町では
おりしも音楽祭が開かれようとしていた。
年に一度だけ門が開く7日間。
仙道とまゆと同道して来た幼いユーリーは
飛行船で知り合ったエイラの屋敷に泊めてもらうことになる。
エイラがそれを強く望んだのだ。
エイラの家は琴の流派の名門・ザクセン家だった。
北の塔、南の塔、東の塔、西の塔
四つの塔を持つ広大な館には
エイラの父・宗家ハウルと祖父のクレイヴが
弟子たちとともに住んでいた。
館の空気はピリピリとしていた。
祭での演奏の稽古が思うように進んでいなかったのだ。
天才的な演奏者だったエイラの帰還と
天性の耳を持つユーリーの出現が
館の人々の気持ちをかき乱して
小さな嵐となっていく。
一方まゆは
町の宝飾店のウインドウで
銀蜂の彫刻を飾った「箱」を見つける。
銀蜂
・・・・
銀黒王
・・・・
師の仙道の抱える秘密。
師を信頼しながらも新たな想いを芽生えさせるまゆ。
(影が濃くなって立体感を増す人物たち)
「晴れ着姿の子どもたちが、
手にした鈴を鳴らして駆けていく」
祭りの情景。
「何もかも、なくしてしまったわ。
琴の他には何もかも。
だからわたしは西風(琴の銘)を弾くわ」
というエイラのすがた
が心に残ります。
5冊目は
「ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由」(小林せかい 2016年12月刊)
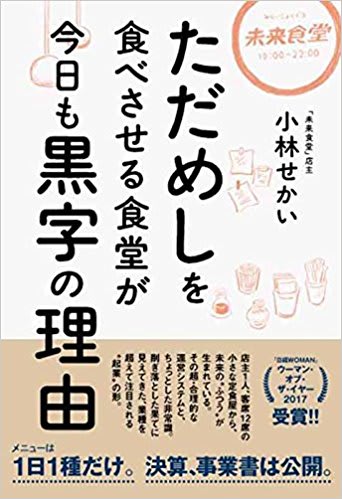
筆者は神保町にある「未来食堂」の店主です。
筆者はひとの居場所になるような
お金のない人が無料で食事ができるような
場所をつくりたい
と思った。
そう思う人は他にもいるだろう。
(あちこちで地域カフェや子ども食堂などの活動もさかんになってきている)
だけど筆者の工夫はひとあじ違う。
(未来食堂は定食1種類だけ(900円)を出す食堂で
その定食は毎日なかみが変わる)
未来食堂には4つの独特のシステムがある。
「まかない」は
50分働くと一食分のチケットが貰えるというシステムだ。
まかないさんはお客でもあるので
店の中は(厨房も)すべてお客にオープンにされることになるし
何の仕事をしてもらおうか考えなくてはならない。
(便の検査を受けていない人は調理はできない)
慣れない人がそばにいる緊張感もある。
「ただめし」というのは
「まかない」で貰ったチケットを店の入り口の掲示板に貼ってもらい
(何時間分ものチケットが溜まってしまっている人など)
他の人に自由につかってもらうシステムだ。
「あつらえ」は
定食の他に何か食べたい人に
小鉢1つ400円で
冷蔵庫にある材料の範囲内で作って提供するシステムだ。
(ランチタイムは除く)
そして「さしいれ」は
飲み物の持ち込み代を無料にする代わりに
その半分を店に寄付してもらうというシステムだ。
ワインやお酒は料理に使われたりもするし
ジュースなどはお客に振る舞われたりもする。
こう書くと常連客がいっぱいの内輪っぽい店のようだけど
筆者が目指すのは螺旋型のコミュニケーションだという。
だれかに好意を受けたとき
その相手に直接返すのではなく
別の誰かに贈る
それが螺旋型コミュニケーションだ。
だからまかないさんの会のようなものもつくらない。
たくさんお金を使ってくれる強いお客をつくらない。
常連客にも「知っていて知らないふりをする」=毎日が記憶喪失のような接客
・・・
知と情のバランスの絶妙さに感心させられます。
6冊目は
「おもちゃ絵芳藤」(谷津矢車 2017年4月刊)
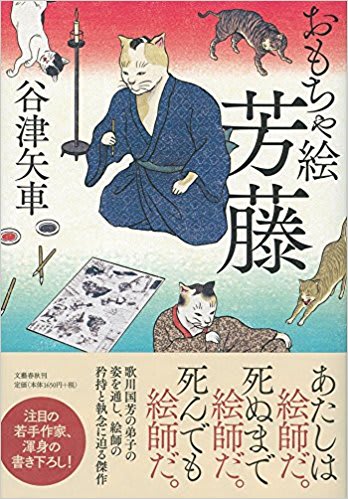
物語は歌川国芳の葬儀の場面からはじまる。
国芳の画塾を手伝っていた弟子の中で一番の年かさの芳藤は
高弟たちに使いに出して葬儀の日を報せるとともに
画塾を引き継いでくれるかどうかの打診もしていた。
才能のない自分では不足だろうと思ってのことだった。
だが
誰も引き受けるものはいない。
結局国芳の次女のお吉が名義を引き受け
実際の運営は芳藤がすることになった。
時代は幕末から明治へと大きく動いていく。
その中で
才能のある弟弟子たちは
みな見事にハンドルを切っていく。
お雇い外国人のコンドルから「アート」という概念を教えられた暁斎は
「アーティスト」への道を歩み出す。
幾次郎は新しく出た「新聞」というものの
「新聞錦絵」に活路を見出す。
西洋画の写実に影響を受けた清親は
光線画というものを描いてもてはやされるようになる。
浮世絵の時代は
もう終わったのか・・・
どんな「機会」が目の前に開けても
芳藤は踏み出すことをしなかった。
小さな違和感がざわざわとするうちは
それは自分の道ではないと思い定めていた。
子どもの「おもちゃ絵」を描いて
僅かの賃金をもらう日々。
どんな安い賃金でも
芳藤は精魂込めるのを忘れなかった。
「虚飾でも虚勢でもない。
おもちゃ絵を作っているとき
どうすれば子供が喜ぶだろうかと首をひねったり
新しい趣向をどう取り入れようかと唸っているのが好きだった」から。
読んでいくうちに
芳藤がどんどん好きになって
この人の人生をどんなふうに着地させるつもりなの・・・
と目が離せなくなってしまいます。
心に残った10冊を
選んでみました。
4冊目は「利き蜜師物語」シリーズの3巻目
「歌う琴」(小林栗奈 2017年11月刊)
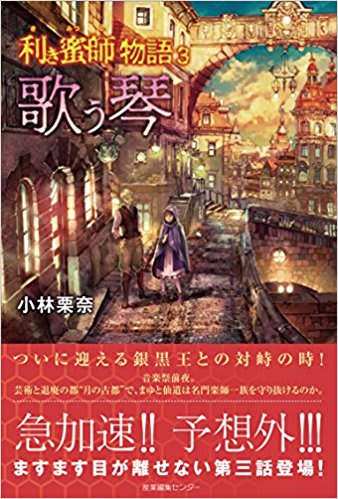
利き蜜師の仙道と弟子の少女まゆは
旅の途中に飛行船の事故によって月の古都に降りることになる。
普段は門が閉ざされていて人を立ち入らせない町・月の古都。
町では
おりしも音楽祭が開かれようとしていた。
年に一度だけ門が開く7日間。
仙道とまゆと同道して来た幼いユーリーは
飛行船で知り合ったエイラの屋敷に泊めてもらうことになる。
エイラがそれを強く望んだのだ。
エイラの家は琴の流派の名門・ザクセン家だった。
北の塔、南の塔、東の塔、西の塔
四つの塔を持つ広大な館には
エイラの父・宗家ハウルと祖父のクレイヴが
弟子たちとともに住んでいた。
館の空気はピリピリとしていた。
祭での演奏の稽古が思うように進んでいなかったのだ。
天才的な演奏者だったエイラの帰還と
天性の耳を持つユーリーの出現が
館の人々の気持ちをかき乱して
小さな嵐となっていく。
一方まゆは
町の宝飾店のウインドウで
銀蜂の彫刻を飾った「箱」を見つける。
銀蜂
・・・・
銀黒王
・・・・
師の仙道の抱える秘密。
師を信頼しながらも新たな想いを芽生えさせるまゆ。
(影が濃くなって立体感を増す人物たち)
「晴れ着姿の子どもたちが、
手にした鈴を鳴らして駆けていく」
祭りの情景。
「何もかも、なくしてしまったわ。
琴の他には何もかも。
だからわたしは西風(琴の銘)を弾くわ」
というエイラのすがた
が心に残ります。
5冊目は
「ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由」(小林せかい 2016年12月刊)
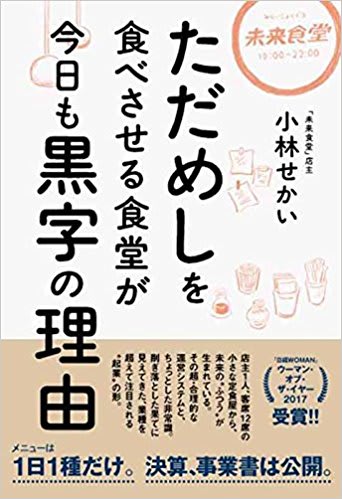
筆者は神保町にある「未来食堂」の店主です。
筆者はひとの居場所になるような
お金のない人が無料で食事ができるような
場所をつくりたい
と思った。
そう思う人は他にもいるだろう。
(あちこちで地域カフェや子ども食堂などの活動もさかんになってきている)
だけど筆者の工夫はひとあじ違う。
(未来食堂は定食1種類だけ(900円)を出す食堂で
その定食は毎日なかみが変わる)
未来食堂には4つの独特のシステムがある。
「まかない」は
50分働くと一食分のチケットが貰えるというシステムだ。
まかないさんはお客でもあるので
店の中は(厨房も)すべてお客にオープンにされることになるし
何の仕事をしてもらおうか考えなくてはならない。
(便の検査を受けていない人は調理はできない)
慣れない人がそばにいる緊張感もある。
「ただめし」というのは
「まかない」で貰ったチケットを店の入り口の掲示板に貼ってもらい
(何時間分ものチケットが溜まってしまっている人など)
他の人に自由につかってもらうシステムだ。
「あつらえ」は
定食の他に何か食べたい人に
小鉢1つ400円で
冷蔵庫にある材料の範囲内で作って提供するシステムだ。
(ランチタイムは除く)
そして「さしいれ」は
飲み物の持ち込み代を無料にする代わりに
その半分を店に寄付してもらうというシステムだ。
ワインやお酒は料理に使われたりもするし
ジュースなどはお客に振る舞われたりもする。
こう書くと常連客がいっぱいの内輪っぽい店のようだけど
筆者が目指すのは螺旋型のコミュニケーションだという。
だれかに好意を受けたとき
その相手に直接返すのではなく
別の誰かに贈る
それが螺旋型コミュニケーションだ。
だからまかないさんの会のようなものもつくらない。
たくさんお金を使ってくれる強いお客をつくらない。
常連客にも「知っていて知らないふりをする」=毎日が記憶喪失のような接客
・・・
知と情のバランスの絶妙さに感心させられます。
6冊目は
「おもちゃ絵芳藤」(谷津矢車 2017年4月刊)
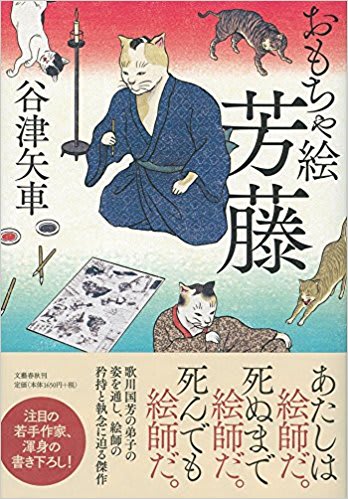
物語は歌川国芳の葬儀の場面からはじまる。
国芳の画塾を手伝っていた弟子の中で一番の年かさの芳藤は
高弟たちに使いに出して葬儀の日を報せるとともに
画塾を引き継いでくれるかどうかの打診もしていた。
才能のない自分では不足だろうと思ってのことだった。
だが
誰も引き受けるものはいない。
結局国芳の次女のお吉が名義を引き受け
実際の運営は芳藤がすることになった。
時代は幕末から明治へと大きく動いていく。
その中で
才能のある弟弟子たちは
みな見事にハンドルを切っていく。
お雇い外国人のコンドルから「アート」という概念を教えられた暁斎は
「アーティスト」への道を歩み出す。
幾次郎は新しく出た「新聞」というものの
「新聞錦絵」に活路を見出す。
西洋画の写実に影響を受けた清親は
光線画というものを描いてもてはやされるようになる。
浮世絵の時代は
もう終わったのか・・・
どんな「機会」が目の前に開けても
芳藤は踏み出すことをしなかった。
小さな違和感がざわざわとするうちは
それは自分の道ではないと思い定めていた。
子どもの「おもちゃ絵」を描いて
僅かの賃金をもらう日々。
どんな安い賃金でも
芳藤は精魂込めるのを忘れなかった。
「虚飾でも虚勢でもない。
おもちゃ絵を作っているとき
どうすれば子供が喜ぶだろうかと首をひねったり
新しい趣向をどう取り入れようかと唸っているのが好きだった」から。
読んでいくうちに
芳藤がどんどん好きになって
この人の人生をどんなふうに着地させるつもりなの・・・
と目が離せなくなってしまいます。
















