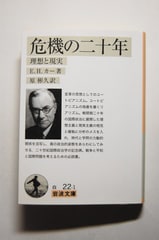
当ブログ2014.4.2「E.H.カー『危機の二十年』から学ぶ ①」で、E.H.カー『危機の二十年─理想と現実─』(岩波文庫/訳・解説=原彬久/2011年)の「序文」と第1部を取り上げた。今回の「②」では、第2部「国際的危機」の第3章「ユートピア的背景」と第4章「利益の調和」を取り上げる(*前回「①」で述べた予定を変更)。
*< >内は本書からの引用。「・・・」は略。引用中の下線は、引用者(星徹)が付けた。[ ]内は引用者が補った。「十九世紀」を「19世紀」とするなど、数字の表記を変更した部分もある。
第2部「国際的危機」
第3章「ユートピア的背景」
(1)第1次大戦後に功利主義原理が復活
<なかば見捨てられたこの19世紀の仮説[*「ベンサム流の仮説」]は、20世紀の20年代および30年代に国際政治という特異な分野に再びその姿をみせ、新しいユートピア的殿堂の礎石となった。>(P68)
*下線部の「(ジェレミー=)ベンサム(*英の哲学者)流の仮説」
→善を「最大多数の最大幸福」という合理的倫理によって定義した。
→自然法の内容における19世紀的定義となった。(P62)
(2)国際連盟(1920年設立)の理想(信念)
<国際連盟は合理的基盤に立って国際政治問題を標準化しようとする最初の大がかりな試みで>あった。(P71)
<国際連盟は・・・最初から一対の信念と固く結びついていた。つまり世論は必ず勝利すべきものであること、そして世論とは理性の声である、ということである。>(P81)
【(2)の考察】
国際連盟を設立・主導した人たちが、「世論とは理性の声」→「世論は必ず勝利すべきもの」(当為)→「理性・正義は勝利する」といった論理展開をしていたならば、「希望的観測」しか言っていない、ということになるはずだ。本当にそんな事があるだろうか。
下線部の「べき」(当為)を「る」(一般法則)として、「世論は必ず勝利するもの」とした方が、実態を捉えていたのではないか。原文(英文)に当たっていないので、カーの意図は分からないのだが。
しかし、たとえ世論が「理性の声」に近いとしても、それらが総体として「国家の声」となるとは限らない。世界には、非民主国家・独裁国家が数多く存在するのだから。
国際連盟を設立・主導した人たちが、それくらいの事を知らなかったはずはない。諸国家の現実を見ずに、また国家間のパワーゲームの現実を見ずに、「性善説」を前提にして物事を考えていたのか? 彼らにも、言い分があるはずだ。
(3)国際連盟の限界
①主権国家と国際連盟の相違
<民主主義的合理主義を国内領域から国際領域へと移植したことは、予期せぬ多くの困難をもたらした。>(P70)
【(3)①の考察】
「国内領域」と「国際領域」の対は、大枠では(主権)国家と国際連盟の対に置き換えることができるだろう。
(主権)国家とは、マックス=ヴェーバーが規定したように、「ある一定の領域の内部で・・・正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体」だろう(*当ブログ2013.10.6「ヴェーバー『職業としての政治』から学ぶ」参照)。
つまり、事前にルールを定め、違反者を取り締まり、処罰する。「手順は踏むが、違反者を許さない」ということだ。しかし、これはある程度以上の民主国家についての事だ。非民主国家・独裁国家においては、「正当な」というよりも「より強力な『棍棒』による」と言った方が、より現実を捉えているのではないか。
他方の国際連盟には、もちろん主権はなく、世界を仕切る「独占的な暴力装置」もない。だから、加盟国すべてがお行儀よくルールを守る限りでは問題ないが、「違反者・無法者が好き勝手なことをし始めた時にどうするか」が問題になってくる。
独立した国際連盟軍はもちろん存在せず(*現在、国際連合軍も存在しないが)、集団安全保障が有効には機能することもなかった。そして、第2次世界大戦を避けることができなかった。
②国際連盟の限界(日本について)
<満洲の危機[*満州事変(1931.9.18~)]は・・・「国際世論の非難」があまり頼りにならないものであることをみせつけた。> (P86)
【(3)②の考察】
当ブログ2013.8.6「川田稔『戦前日本の安全保障』から学ぶ」の中で、私は以下のような感想を述べた。
<米英などの欧米列強諸国は、「人道的理由」を主たる根拠として、日本の満蒙・中国本土への侵略的政策を批判した訳ではない。これら諸国と日本は、基本構造としては、中国における権益を維持・拡大したいという点で、同じ側にいた。
そのための取り決めが、ワシントン会議(1921-22年)で締結された九カ国条約(1922年)だった。そして、国際連盟の枠組みや不戦条約なども相まって、日本の突出した侵略的政策はますます許容されない状況になっていった。
満州事変(1931年)とそれに続く「満州国」の建国は、欧米列強諸国の許容範囲を超えていた。それでも、国際連盟が設置したリットン調査団の報告書(附属書を含む)では、①(日本の)関東軍の行動は自衛行為ではない、②「満州国」の建国は九カ国条約に抵触し不当、などとしながらも、「経済的権益が中国側に侵害された」との日本側主張についてはほぼ認める記述もしている。(加藤陽子『戦争の日本近現代史』(講談社現代新書/2002年)P272-273など参照)
結局、欧米列強諸国は、より効率よく中国における権益を維持・獲得するシステムと枠組みを作り上げたが、日本はその状況変化に適応しなかった(*又はできなかった)、ということではないか。>
日本の中国(満州を含む)への圧力・侵攻に対して、「国際世論の非難」という名の「欧米諸国の非難」は確かにあった。しかし、その「非難」の深層は、中国を効率よく搾取する欧米諸国システムの秩序を乱す日本への非難、ということだったのではないか。
だから、「「国際世論の非難」があまり頼りにならない」というよりも、「欧米先進諸国の本気度があまり高くなく、腰が引けていた」のであり、「日本側は、彼らのタテマエ性と欺瞞性を見抜き、自らに都合よく状況を解釈した」ということではないか。
③理論と現実の断層→1930年代の国際秩序崩壊
<[日本やナチスドイツなどの侵略的行動が続き、]1919年の諸前提が数多く崩れても、ユートピア学派の知的指導者たちはあくまでも自説にこだわった。イギリスでもアメリカでも・・・理論と現実との断層は驚くほど大きかった。> (P89)
【(3)③の考察】
そういった批判は、ある面で当たっていたのかもしれない。
現在の国際連合体制ではどうなのか? そう問いを立ててみると、「内実は、国際連盟の時代からさほど進歩していないのでは」との疑念が強くなる。
今年(2014年)、ロシアはウクライナ(主権国家)のクリミア地区を併合した。こういったロシアの行状に対し、欧米諸国の多く(*特に米国)は「侵略行為だ」などと批判し、部分的な「経済制裁」も行なっているが、ロシアは聞く耳を持たない。そして、国際連合はほとんど何もできない状況だ。
ロシア批判の急先鋒の米国も、威張れたものではない。米国は2003年、イラクに対して「大量破壊兵器があるはずだ」「悪の帝国だ」などと決めつけ、国連安保理決議が無いままに軍事攻撃に踏み切った。「先制的自衛」「予防戦争」等のこじ付けの“理屈”を押し通したのだ。こういった米国の暴走も、国連と国際社会は止めることが出来なかった。
国連安全保障理事会の常任理事国(米・ロ・中・英・仏)やその「お友達」が国際ルールを破り、侵略行為に打って出ても、それを止める手立てはなかなか見つからない。この状況は、国際連盟の時代のあり方と通じるところがあるのではないか。
確かに、第2次世界大戦後は、他国の領土を併合・植民地支配するような侵略戦争は減った。この点では、大きな「進歩」と言えるのかもしれない。しかし、それは「国際連合の成果」「人類の努力の賜物」なのか?
他国の領土を併合・植民地支配すれば、人民を含めた「負の遺産」も一緒に付いてくる。コストと政治的安定性を考えれば、そういった直接支配は賢いやり方ではない、との認識が徐々に広まっていった。つまり、よりスマートな「間接統治」のやり方が広まったのだ。
第4章「利益の調和」
(4)19世紀後半における国際関係の利益調和とは?
<「国際関係の基本問題は、誰が犠牲者たちを切り裂くのかということであった」。利益調和は「不適者」のアフリカ人やアジア人を生贄にして成立したのである。> (P109)
【(4)の考察】
この場合の「利益調和」とは、殺す側・搾取する側にとっての「利益調和」であった。殺される側・搾取される側の「利益」などは、ほとんど考慮されることがなかった。
そして、国際連盟体制の真髄とは、「新たな侵略・植民地支配はやめよう」という事だったのだろう。しかしそのことは、先発帝国主義諸国(英・仏など)の既得権益が温存・固定化される、ということを意味した。
徐々に国力を増してきたや日本やドイツ・イタリアの側は、「ふざけるな!」という思いを強くしただろう。そして、日中戦争・太平洋戦争と第2次世界大戦への火種が、徐々に作られていくことになった。
(5)ユートピアニズムの限界
<他者を害して利益を得る人など誰もいない、などという19世紀の軽薄な常套句のうつろさがみえてきた。ユートピアニズムの前提が崩れ去ったのである。> (P132)
<1世紀半にわたって政治経済思想を支配し続けた道義の概念が完全に破産した[。]・・・国際的には、正しい理性の働きから善徳を導き出すことはもはや不可能である。> (P132)
<現代国際危機の隠れた意味は、利益調和の概念に基づくユートピアニズムの全構造が崩壊したということである。今日の世代は、根本からこれを再構築しなければならない。> (P133)
【(5)の考察】
上記部分は、第4章の最後の部分であり、結論とも言えるところだ。前回の「──①」(2014.4.2)で述べたように、本書執筆が終わったのは、第2次世界大戦勃発(1939.9.3)の直前(1939年7月中旬)だ。ナチスドイツの拡張政策に拍車がかかり、大戦前夜の様相を呈していただろう。
しかし、国際連盟を主導した人たちの考えが、現実をそれほど無視したユートピアニズム(空想主義)だったのか? カーの批判が少し主観的に聞こえるため、「ちょっと待てよ」という思いにさせられる。「アイデアリズム(理想主義)に偏りすぎ、リアリズム(現実主義)の面が弱すぎた」という批判ならば、もっと説得力があったと思うのだが。
これらカーの主張に対する私の考えは、今のところ「保留」ということだ。
≪つづく≫
*< >内は本書からの引用。「・・・」は略。引用中の下線は、引用者(星徹)が付けた。[ ]内は引用者が補った。「十九世紀」を「19世紀」とするなど、数字の表記を変更した部分もある。
第2部「国際的危機」
第3章「ユートピア的背景」
(1)第1次大戦後に功利主義原理が復活
<なかば見捨てられたこの19世紀の仮説[*「ベンサム流の仮説」]は、20世紀の20年代および30年代に国際政治という特異な分野に再びその姿をみせ、新しいユートピア的殿堂の礎石となった。>(P68)
*下線部の「(ジェレミー=)ベンサム(*英の哲学者)流の仮説」
→善を「最大多数の最大幸福」という合理的倫理によって定義した。
→自然法の内容における19世紀的定義となった。(P62)
(2)国際連盟(1920年設立)の理想(信念)
<国際連盟は合理的基盤に立って国際政治問題を標準化しようとする最初の大がかりな試みで>あった。(P71)
<国際連盟は・・・最初から一対の信念と固く結びついていた。つまり世論は必ず勝利すべきものであること、そして世論とは理性の声である、ということである。>(P81)
【(2)の考察】
国際連盟を設立・主導した人たちが、「世論とは理性の声」→「世論は必ず勝利すべきもの」(当為)→「理性・正義は勝利する」といった論理展開をしていたならば、「希望的観測」しか言っていない、ということになるはずだ。本当にそんな事があるだろうか。
下線部の「べき」(当為)を「る」(一般法則)として、「世論は必ず勝利するもの」とした方が、実態を捉えていたのではないか。原文(英文)に当たっていないので、カーの意図は分からないのだが。
しかし、たとえ世論が「理性の声」に近いとしても、それらが総体として「国家の声」となるとは限らない。世界には、非民主国家・独裁国家が数多く存在するのだから。
国際連盟を設立・主導した人たちが、それくらいの事を知らなかったはずはない。諸国家の現実を見ずに、また国家間のパワーゲームの現実を見ずに、「性善説」を前提にして物事を考えていたのか? 彼らにも、言い分があるはずだ。
(3)国際連盟の限界
①主権国家と国際連盟の相違
<民主主義的合理主義を国内領域から国際領域へと移植したことは、予期せぬ多くの困難をもたらした。>(P70)
【(3)①の考察】
「国内領域」と「国際領域」の対は、大枠では(主権)国家と国際連盟の対に置き換えることができるだろう。
(主権)国家とは、マックス=ヴェーバーが規定したように、「ある一定の領域の内部で・・・正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体」だろう(*当ブログ2013.10.6「ヴェーバー『職業としての政治』から学ぶ」参照)。
つまり、事前にルールを定め、違反者を取り締まり、処罰する。「手順は踏むが、違反者を許さない」ということだ。しかし、これはある程度以上の民主国家についての事だ。非民主国家・独裁国家においては、「正当な」というよりも「より強力な『棍棒』による」と言った方が、より現実を捉えているのではないか。
他方の国際連盟には、もちろん主権はなく、世界を仕切る「独占的な暴力装置」もない。だから、加盟国すべてがお行儀よくルールを守る限りでは問題ないが、「違反者・無法者が好き勝手なことをし始めた時にどうするか」が問題になってくる。
独立した国際連盟軍はもちろん存在せず(*現在、国際連合軍も存在しないが)、集団安全保障が有効には機能することもなかった。そして、第2次世界大戦を避けることができなかった。
②国際連盟の限界(日本について)
<満洲の危機[*満州事変(1931.9.18~)]は・・・「国際世論の非難」があまり頼りにならないものであることをみせつけた。> (P86)
【(3)②の考察】
当ブログ2013.8.6「川田稔『戦前日本の安全保障』から学ぶ」の中で、私は以下のような感想を述べた。
<米英などの欧米列強諸国は、「人道的理由」を主たる根拠として、日本の満蒙・中国本土への侵略的政策を批判した訳ではない。これら諸国と日本は、基本構造としては、中国における権益を維持・拡大したいという点で、同じ側にいた。
そのための取り決めが、ワシントン会議(1921-22年)で締結された九カ国条約(1922年)だった。そして、国際連盟の枠組みや不戦条約なども相まって、日本の突出した侵略的政策はますます許容されない状況になっていった。
満州事変(1931年)とそれに続く「満州国」の建国は、欧米列強諸国の許容範囲を超えていた。それでも、国際連盟が設置したリットン調査団の報告書(附属書を含む)では、①(日本の)関東軍の行動は自衛行為ではない、②「満州国」の建国は九カ国条約に抵触し不当、などとしながらも、「経済的権益が中国側に侵害された」との日本側主張についてはほぼ認める記述もしている。(加藤陽子『戦争の日本近現代史』(講談社現代新書/2002年)P272-273など参照)
結局、欧米列強諸国は、より効率よく中国における権益を維持・獲得するシステムと枠組みを作り上げたが、日本はその状況変化に適応しなかった(*又はできなかった)、ということではないか。>
日本の中国(満州を含む)への圧力・侵攻に対して、「国際世論の非難」という名の「欧米諸国の非難」は確かにあった。しかし、その「非難」の深層は、中国を効率よく搾取する欧米諸国システムの秩序を乱す日本への非難、ということだったのではないか。
だから、「「国際世論の非難」があまり頼りにならない」というよりも、「欧米先進諸国の本気度があまり高くなく、腰が引けていた」のであり、「日本側は、彼らのタテマエ性と欺瞞性を見抜き、自らに都合よく状況を解釈した」ということではないか。
③理論と現実の断層→1930年代の国際秩序崩壊
<[日本やナチスドイツなどの侵略的行動が続き、]1919年の諸前提が数多く崩れても、ユートピア学派の知的指導者たちはあくまでも自説にこだわった。イギリスでもアメリカでも・・・理論と現実との断層は驚くほど大きかった。> (P89)
【(3)③の考察】
そういった批判は、ある面で当たっていたのかもしれない。
現在の国際連合体制ではどうなのか? そう問いを立ててみると、「内実は、国際連盟の時代からさほど進歩していないのでは」との疑念が強くなる。
今年(2014年)、ロシアはウクライナ(主権国家)のクリミア地区を併合した。こういったロシアの行状に対し、欧米諸国の多く(*特に米国)は「侵略行為だ」などと批判し、部分的な「経済制裁」も行なっているが、ロシアは聞く耳を持たない。そして、国際連合はほとんど何もできない状況だ。
ロシア批判の急先鋒の米国も、威張れたものではない。米国は2003年、イラクに対して「大量破壊兵器があるはずだ」「悪の帝国だ」などと決めつけ、国連安保理決議が無いままに軍事攻撃に踏み切った。「先制的自衛」「予防戦争」等のこじ付けの“理屈”を押し通したのだ。こういった米国の暴走も、国連と国際社会は止めることが出来なかった。
国連安全保障理事会の常任理事国(米・ロ・中・英・仏)やその「お友達」が国際ルールを破り、侵略行為に打って出ても、それを止める手立てはなかなか見つからない。この状況は、国際連盟の時代のあり方と通じるところがあるのではないか。
確かに、第2次世界大戦後は、他国の領土を併合・植民地支配するような侵略戦争は減った。この点では、大きな「進歩」と言えるのかもしれない。しかし、それは「国際連合の成果」「人類の努力の賜物」なのか?
他国の領土を併合・植民地支配すれば、人民を含めた「負の遺産」も一緒に付いてくる。コストと政治的安定性を考えれば、そういった直接支配は賢いやり方ではない、との認識が徐々に広まっていった。つまり、よりスマートな「間接統治」のやり方が広まったのだ。
第4章「利益の調和」
(4)19世紀後半における国際関係の利益調和とは?
<「国際関係の基本問題は、誰が犠牲者たちを切り裂くのかということであった」。利益調和は「不適者」のアフリカ人やアジア人を生贄にして成立したのである。> (P109)
【(4)の考察】
この場合の「利益調和」とは、殺す側・搾取する側にとっての「利益調和」であった。殺される側・搾取される側の「利益」などは、ほとんど考慮されることがなかった。
そして、国際連盟体制の真髄とは、「新たな侵略・植民地支配はやめよう」という事だったのだろう。しかしそのことは、先発帝国主義諸国(英・仏など)の既得権益が温存・固定化される、ということを意味した。
徐々に国力を増してきたや日本やドイツ・イタリアの側は、「ふざけるな!」という思いを強くしただろう。そして、日中戦争・太平洋戦争と第2次世界大戦への火種が、徐々に作られていくことになった。
(5)ユートピアニズムの限界
<他者を害して利益を得る人など誰もいない、などという19世紀の軽薄な常套句のうつろさがみえてきた。ユートピアニズムの前提が崩れ去ったのである。> (P132)
<1世紀半にわたって政治経済思想を支配し続けた道義の概念が完全に破産した[。]・・・国際的には、正しい理性の働きから善徳を導き出すことはもはや不可能である。> (P132)
<現代国際危機の隠れた意味は、利益調和の概念に基づくユートピアニズムの全構造が崩壊したということである。今日の世代は、根本からこれを再構築しなければならない。> (P133)
【(5)の考察】
上記部分は、第4章の最後の部分であり、結論とも言えるところだ。前回の「──①」(2014.4.2)で述べたように、本書執筆が終わったのは、第2次世界大戦勃発(1939.9.3)の直前(1939年7月中旬)だ。ナチスドイツの拡張政策に拍車がかかり、大戦前夜の様相を呈していただろう。
しかし、国際連盟を主導した人たちの考えが、現実をそれほど無視したユートピアニズム(空想主義)だったのか? カーの批判が少し主観的に聞こえるため、「ちょっと待てよ」という思いにさせられる。「アイデアリズム(理想主義)に偏りすぎ、リアリズム(現実主義)の面が弱すぎた」という批判ならば、もっと説得力があったと思うのだが。
これらカーの主張に対する私の考えは、今のところ「保留」ということだ。
≪つづく≫
























