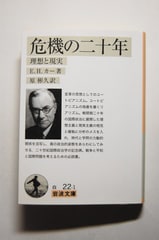
今回の「⑤」では、E.H.カー『危機の二十年─理想と現実─』(岩波文庫/訳・解説=原彬久/2011年)から第4部「法と変革」の第10章「法の基盤」・第11章「条約の拘束性」・第12章「国際紛争の司法的解決」を取り上げる。
*< >内は本書からの引用。「・・・」は略。 [ ]内は引用者(星徹)が補った。「十九世紀」を「19世紀」とするなど、数字の表記を変更した部分もある。
第4部「法と変革」
第10章「法の基盤」
(1)個々の国家と国際法の関係
国際法の弱点は、それが機能する(はずの)共同体[*国家など]が未成熟であることから来る。(P341)
【(1)の考察】
立憲主義・デモクラシーという点で未成熟な国家が大多数であれば、それら国家によって支えられる国際法の運用が民主的で成熟したものになるのは、極めて難しいだろう。
それでも、一部の強大な国家(群)が強力な指導性を発揮すれば、短期的には国際秩序が保たれるのかもしれない。しかし、下記(2)の問題のために、不安定要因を抱え続けることになるだろう。
(2)国際法の公平性における限界(P341-343)
国際法は、形式としてどれほど一般的に作られていても、絶えずある特定国家(群)に向けられ、政治化していく。
→<法自体が依拠する政治的基盤や、それが仕える政治的利益とかかわりのないところで法を理解することはできない>
【(2)の考察】
支配国家(群)が国際社会をうまく機能させようとして、弱者・敗者に「支配者のルール」を押し付け(*「合意の上で」との形が取られるとしても)、言う事を聞かなければペナルティーを科す、という事が考えられる。
しかし、「押し付けられる」側からすれば、腹の虫が治まらないだろう。だから、支配者らとの力関係が接近してくれば、「権力関係の改変」「ルール改定」を目論み、様々な挑戦を仕掛けてくる、という事が考えられる。
「支配国家(群)」とは英・米・仏などの第1次世界大戦戦勝国であり、「支配される」側は敗戦国のドイツなどであった。そして、ドイツは恨みを募らせ、旧支配国家群に挑戦を仕掛けていった。
第11章「条約の拘束性」
(3)戦間期における「条約の拘束性」に対する理解の相異
①「国際法の原則」論(A)と「国際倫理(道義)の原則」論(B)の対立(P347)
<1914年以前の国際法は、条約義務の拘束性を絶対のものとすることには消極的であった。>(P347)
②第1次世界大戦前における「柔軟な国際法理解」の現実
(a)1914年以前にも、Aが原則としてあったのは確かだ。しかし、Bを正当化するために「事情変更の原則」(B-1)や「当事者間の権力関係の変化」(B-2)なども理由として挙げられ、Aが守られないことも稀ではなかった。(P347-348)
(b)また、「必要性の原則」(B-3)や「死活的利益の原則」(B-4)といった柔軟性のある原則も、国際義務不履行のために時どき援用された。(P351)
(c)さらに、「あらゆる条約は本来は権力の手段であり、したがって道義的価値を欠くものだ」との疑問も、マルキストなどから投じられた。(P360)
③第1次世界大戦後に「国際法の原則」の厳格化へ(Bの後退)
→こういった戦勝国の善意ある努力が、国際法の諸規則が[ドイツなどによって]一層頻繁かつ公然と犯される事態を招いていった。(P354)
④ヴェルサイユ条約破棄(1935年)におけるナチスドイツの「道義的」言い分(P355-359)
(a)強要・脅迫に基づく条約だ。
(b)内容が過酷すぎ、道義にもとる(理不尽な)条約だ。
(c)当事国間の現行の権力関係を著しく矛盾する条件を(敗戦国に)課しており、不公平だ。
⑤国際法の相対性
「合意は守られなければならない」という原則は、道義的原理ではない。しかも、この適用は倫理的理由から常に正当化される、というわけでもない。それは国際法の原則である。(P363)
(4)「ルール変更」により「遅れてきた帝国主義国」に不満
①第1次世界大戦を境に「戦争ルール」変更(P364)
≪第1次世界大戦以前(1914年以前)≫
国際法は、現行国際秩序変革のための戦争を「非合法」として非難する、という事はなかった。
≪第1次世界大戦後(1918年以降)≫
現状を変える目的で戦争に訴えることは、国際法上「違法」とされるようになった。
②新旧帝国主義国間の不平等固定化
しかし、「違法」とされても、<それに代わる効果的な選択肢を用意しなかった>
→<現代国際法は・・・現行秩序の擁護者になってしまったのである。国際法に対する尊重の精神が近年低下してきたその最も根本的な原因は、まさにここにある。>(P364-365)
【(3)(4)の考察】
私たちの多くは、現在的視点で見て、「ドイツは戦争に負けて、(ヴェルサイユ)条約を受け入れたのだから、それを守るのは当然だ」と考えるだろう。戦間期に於いても、「勝者」の側からすれば、そういった考えが「当然のこと」だっただろう。
ドイツ側の不満と恨みが強まり、また同国の軍事力が強大化して対外膨張圧力が極限まで強まる中で、カーの思いは「何とか戦争は避けたい」という切実なものとなっていった。
東京外国語大学の篠田英朗(ひであき)教授(*現在、専攻は国際関係論)は、『「国家主権」という思想─国際立憲主義への軌跡─』(勁草書房/2012年)の中で次のように述べている。
<『危機の二〇年』[で]・・・カーはむしろ主権を相対化して軽視し、その代わりにユートピアニズムとリアリズムの対話を、つまりアメリカ・イギリスとドイツの対話を望んだ。それはむしろ・・・「宥和政策」の性格すら持つ書であった(注52)。それはまた・・・戦争を回避するためにヨーロッパ大陸の不満足諸国との和解を模索する試みであった。[P193]
(注52)
カーは1939年に出版された『危機の二〇年』の初版において、ミュンヘン会談[1938年9月]においてチェンバレン[英首相]がヒトラーに対してとった懐柔的態度を賞賛していた。ただし、第2次世界大戦勃発後に公刊された第2版においては、その文章を削除してしまった。[P211]>
現在の日本では、「リアリスト→強硬派」「リベラリスト(アイデアリスト)→穏健派」といったイメージを持つ人が多いだろう。しかし、「リアリスト・カー」のあり方を見ていると、想像とは違った実相が見えてくる。
カーはもちろん、「強硬一辺倒のリアリスト」ではなかった。「ナチスドイツの不満をなだめ、懐柔してでも、戦争だけは何としても避けたい」との思いだったのだろう。
近年になっても、「ミュンヘン会談の誤りを繰り返すな」というような事が、様々な場面でよく言われる。しかし、その事は「その後の結果を知っている」からこそ言えることであり、別の「××会談」を引き合いに出せば、正反対の結論に導くこともできるはずだ。
要するに、「どの選択が正しいか」については、そう簡単に答えの出ることではない、ということだ。
第12章「国際紛争の司法的解決」
(5)国際法は政治・社会状況によって限定されるのか?
<われわれは、国際紛争の司法判断適合性という問題のなかに次のようないま一つの事実を確認することができる。すなわち、法は政治社会の一機能であること、法の発展はその社会の発展に左右されること、そして法は社会が共有する政治的前提条件に規定されるという事実である。>(P376)
<国家共同体に・・・[これまで適用してきた]法規制ないし法制度は、アナロジー[*類推]によって国際法に導入されてもよいのかどうか、これを人に決定させる法的原則など、これまたあろうはずはないのである。唯一正当な基準は、国際共同体における政治的発展の現段階が問題の規則ないし制度の導入を正当化できるほどのものになっているかどうか、ということである。>(P377)
<戦間期の多くの思想家たちは、国際関係における司法手続きの範囲を控えめにかつ漸進的に拡大していくだけの計画には満足せず、これをはるかに越えて考察を進めていった。・・・国際連盟規約は常設国際司法裁判所の設立を規定し・・・>(P378)
<国内的にも国際的にも、政治的争点は法的権利の争点よりもはるかに厄介である。・・・戦争以外の手段によって国際社会に変更を加えることは、現代国際政治における最も死活的な問題である。その第一歩は、仲裁ないし司法手続きの袋小路──ここではこの問題の解決策はみあたらない──から抜け出すことである。この第一歩を踏み出すことによって、われわれは・・・もっと有望な道を通って問題解決へと近づいていくことができるのである。>(P392)
【(5)の考察】
要するに、カーが言いたいのは、▽国際法はまだ発展過程であり、「国際法の原則」は絶対ではない ▽国際法は様々な社会的・政治的要因によって限定されるものだ──という事だろう。しかし、このように国際法を相対化し過ぎてしまうと、世界秩序は第1次世界大戦前の段階に退歩してしまうのではないか。
多くの問題があったとしても、この「国際法の原則」を維持・発展させる方向性自体は、正しかったのではないか。もちろん、その方法論については、様々な批判があるのだろうが・・・。
確かに、第1次世界大戦後の諸条約は「敗戦国のドイツに厳しすぎた」「もう少し柔軟に対応すべきだった」との評価もでき得るだろう。しかし、もっと前の段階でドイツ側の言い分をくみ取り、懐柔していれば、ドイツの侵略的行動は抑制されたのか? 第2次世界大戦には至らなかったのか? その辺のところは、よく分からない。
≪つづく≫
*< >内は本書からの引用。「・・・」は略。 [ ]内は引用者(星徹)が補った。「十九世紀」を「19世紀」とするなど、数字の表記を変更した部分もある。
第4部「法と変革」
第10章「法の基盤」
(1)個々の国家と国際法の関係
国際法の弱点は、それが機能する(はずの)共同体[*国家など]が未成熟であることから来る。(P341)
【(1)の考察】
立憲主義・デモクラシーという点で未成熟な国家が大多数であれば、それら国家によって支えられる国際法の運用が民主的で成熟したものになるのは、極めて難しいだろう。
それでも、一部の強大な国家(群)が強力な指導性を発揮すれば、短期的には国際秩序が保たれるのかもしれない。しかし、下記(2)の問題のために、不安定要因を抱え続けることになるだろう。
(2)国際法の公平性における限界(P341-343)
国際法は、形式としてどれほど一般的に作られていても、絶えずある特定国家(群)に向けられ、政治化していく。
→<法自体が依拠する政治的基盤や、それが仕える政治的利益とかかわりのないところで法を理解することはできない>
【(2)の考察】
支配国家(群)が国際社会をうまく機能させようとして、弱者・敗者に「支配者のルール」を押し付け(*「合意の上で」との形が取られるとしても)、言う事を聞かなければペナルティーを科す、という事が考えられる。
しかし、「押し付けられる」側からすれば、腹の虫が治まらないだろう。だから、支配者らとの力関係が接近してくれば、「権力関係の改変」「ルール改定」を目論み、様々な挑戦を仕掛けてくる、という事が考えられる。
「支配国家(群)」とは英・米・仏などの第1次世界大戦戦勝国であり、「支配される」側は敗戦国のドイツなどであった。そして、ドイツは恨みを募らせ、旧支配国家群に挑戦を仕掛けていった。
第11章「条約の拘束性」
(3)戦間期における「条約の拘束性」に対する理解の相異
①「国際法の原則」論(A)と「国際倫理(道義)の原則」論(B)の対立(P347)
<1914年以前の国際法は、条約義務の拘束性を絶対のものとすることには消極的であった。>(P347)
②第1次世界大戦前における「柔軟な国際法理解」の現実
(a)1914年以前にも、Aが原則としてあったのは確かだ。しかし、Bを正当化するために「事情変更の原則」(B-1)や「当事者間の権力関係の変化」(B-2)なども理由として挙げられ、Aが守られないことも稀ではなかった。(P347-348)
(b)また、「必要性の原則」(B-3)や「死活的利益の原則」(B-4)といった柔軟性のある原則も、国際義務不履行のために時どき援用された。(P351)
(c)さらに、「あらゆる条約は本来は権力の手段であり、したがって道義的価値を欠くものだ」との疑問も、マルキストなどから投じられた。(P360)
③第1次世界大戦後に「国際法の原則」の厳格化へ(Bの後退)
→こういった戦勝国の善意ある努力が、国際法の諸規則が[ドイツなどによって]一層頻繁かつ公然と犯される事態を招いていった。(P354)
④ヴェルサイユ条約破棄(1935年)におけるナチスドイツの「道義的」言い分(P355-359)
(a)強要・脅迫に基づく条約だ。
(b)内容が過酷すぎ、道義にもとる(理不尽な)条約だ。
(c)当事国間の現行の権力関係を著しく矛盾する条件を(敗戦国に)課しており、不公平だ。
⑤国際法の相対性
「合意は守られなければならない」という原則は、道義的原理ではない。しかも、この適用は倫理的理由から常に正当化される、というわけでもない。それは国際法の原則である。(P363)
(4)「ルール変更」により「遅れてきた帝国主義国」に不満
①第1次世界大戦を境に「戦争ルール」変更(P364)
≪第1次世界大戦以前(1914年以前)≫
国際法は、現行国際秩序変革のための戦争を「非合法」として非難する、という事はなかった。
≪第1次世界大戦後(1918年以降)≫
現状を変える目的で戦争に訴えることは、国際法上「違法」とされるようになった。
②新旧帝国主義国間の不平等固定化
しかし、「違法」とされても、<それに代わる効果的な選択肢を用意しなかった>
→<現代国際法は・・・現行秩序の擁護者になってしまったのである。国際法に対する尊重の精神が近年低下してきたその最も根本的な原因は、まさにここにある。>(P364-365)
【(3)(4)の考察】
私たちの多くは、現在的視点で見て、「ドイツは戦争に負けて、(ヴェルサイユ)条約を受け入れたのだから、それを守るのは当然だ」と考えるだろう。戦間期に於いても、「勝者」の側からすれば、そういった考えが「当然のこと」だっただろう。
ドイツ側の不満と恨みが強まり、また同国の軍事力が強大化して対外膨張圧力が極限まで強まる中で、カーの思いは「何とか戦争は避けたい」という切実なものとなっていった。
東京外国語大学の篠田英朗(ひであき)教授(*現在、専攻は国際関係論)は、『「国家主権」という思想─国際立憲主義への軌跡─』(勁草書房/2012年)の中で次のように述べている。
<『危機の二〇年』[で]・・・カーはむしろ主権を相対化して軽視し、その代わりにユートピアニズムとリアリズムの対話を、つまりアメリカ・イギリスとドイツの対話を望んだ。それはむしろ・・・「宥和政策」の性格すら持つ書であった(注52)。それはまた・・・戦争を回避するためにヨーロッパ大陸の不満足諸国との和解を模索する試みであった。[P193]
(注52)
カーは1939年に出版された『危機の二〇年』の初版において、ミュンヘン会談[1938年9月]においてチェンバレン[英首相]がヒトラーに対してとった懐柔的態度を賞賛していた。ただし、第2次世界大戦勃発後に公刊された第2版においては、その文章を削除してしまった。[P211]>
現在の日本では、「リアリスト→強硬派」「リベラリスト(アイデアリスト)→穏健派」といったイメージを持つ人が多いだろう。しかし、「リアリスト・カー」のあり方を見ていると、想像とは違った実相が見えてくる。
カーはもちろん、「強硬一辺倒のリアリスト」ではなかった。「ナチスドイツの不満をなだめ、懐柔してでも、戦争だけは何としても避けたい」との思いだったのだろう。
近年になっても、「ミュンヘン会談の誤りを繰り返すな」というような事が、様々な場面でよく言われる。しかし、その事は「その後の結果を知っている」からこそ言えることであり、別の「××会談」を引き合いに出せば、正反対の結論に導くこともできるはずだ。
要するに、「どの選択が正しいか」については、そう簡単に答えの出ることではない、ということだ。
第12章「国際紛争の司法的解決」
(5)国際法は政治・社会状況によって限定されるのか?
<われわれは、国際紛争の司法判断適合性という問題のなかに次のようないま一つの事実を確認することができる。すなわち、法は政治社会の一機能であること、法の発展はその社会の発展に左右されること、そして法は社会が共有する政治的前提条件に規定されるという事実である。>(P376)
<国家共同体に・・・[これまで適用してきた]法規制ないし法制度は、アナロジー[*類推]によって国際法に導入されてもよいのかどうか、これを人に決定させる法的原則など、これまたあろうはずはないのである。唯一正当な基準は、国際共同体における政治的発展の現段階が問題の規則ないし制度の導入を正当化できるほどのものになっているかどうか、ということである。>(P377)
<戦間期の多くの思想家たちは、国際関係における司法手続きの範囲を控えめにかつ漸進的に拡大していくだけの計画には満足せず、これをはるかに越えて考察を進めていった。・・・国際連盟規約は常設国際司法裁判所の設立を規定し・・・>(P378)
<国内的にも国際的にも、政治的争点は法的権利の争点よりもはるかに厄介である。・・・戦争以外の手段によって国際社会に変更を加えることは、現代国際政治における最も死活的な問題である。その第一歩は、仲裁ないし司法手続きの袋小路──ここではこの問題の解決策はみあたらない──から抜け出すことである。この第一歩を踏み出すことによって、われわれは・・・もっと有望な道を通って問題解決へと近づいていくことができるのである。>(P392)
【(5)の考察】
要するに、カーが言いたいのは、▽国際法はまだ発展過程であり、「国際法の原則」は絶対ではない ▽国際法は様々な社会的・政治的要因によって限定されるものだ──という事だろう。しかし、このように国際法を相対化し過ぎてしまうと、世界秩序は第1次世界大戦前の段階に退歩してしまうのではないか。
多くの問題があったとしても、この「国際法の原則」を維持・発展させる方向性自体は、正しかったのではないか。もちろん、その方法論については、様々な批判があるのだろうが・・・。
確かに、第1次世界大戦後の諸条約は「敗戦国のドイツに厳しすぎた」「もう少し柔軟に対応すべきだった」との評価もでき得るだろう。しかし、もっと前の段階でドイツ側の言い分をくみ取り、懐柔していれば、ドイツの侵略的行動は抑制されたのか? 第2次世界大戦には至らなかったのか? その辺のところは、よく分からない。
≪つづく≫
























