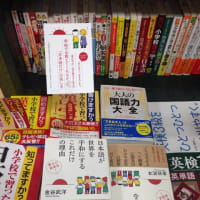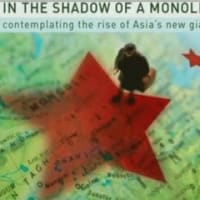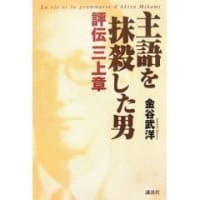前回、モントリオール大学の日本語3年生と日本人が対戦した弥生歌留多大会の様子を書きました。すると「北海道の木の板の取り札が懐かしい」とか、「作戦があったにしても日本人が負けたなんて信じられない」などの声が聞こえてきました。読者の皆さんのコメント、ありがとうございます。こうした反応に気を良くして、今回もさらに百人一首にまつわる話を続けたいと思います。実は、学生が「百人一首」に大いに関心を示したのは、歌留多というゲームに対する興味だけでなく、百人一首にまつわるエピソードあるいは「裏話・秘話」を大いに楽しみ、いえ、むしろ怖がってくれたからなのです。それでは、日本人にさえ意外に知られていない「百人一首の謎」を、お話ししましょう。
何を隠そう、ずっと昔からこの百人一首は謎に包まれてきた歌集なのです。選者は藤原定家(1162-1241)ですが、その定家が日記「名月記」にこんなことを書いています。「小倉山にある私の山荘のすぐ近くに住む僧の蓮生に頼まれて、障子に貼る色紙用に天智天皇から今日までの歌人100人の和歌を一首づつ選んでみた。私は達筆ではないので気が進まなかったが、仕方なく筆を取って書いた。それらの和歌を選んだ基準は私の心の中にある」当時の知識人の習慣として、この日記の原文は漢文で書かれています。なお、蓮生というのは定家の息子の妻(つまり嫁)の父親のことです。ここで問題なのは、最後の「選んだ基準は私の心の中にある」という個所ですが、定家は何故こんな謎めいた言葉を残したのでしょうか。
それもその筈、定家は実に不思議で不可解な和歌の選び方をしています。これまで多くの研究者が指摘してきた疑問点は主に次の3点です。(1)当時の有名な歌人が多数選ばれていないのは何故か(2)多くの歌の中から、いかにも駄作、愚作と思われる歌を敢えて選んでいるのは何故か(3)同じ様な歌がとても多いのは何故か。(2)でよく槍玉に挙げられる例は22番の「吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風を嵐と言ふらむ」で、これは単に「山」と「風」を重ねると「嵐」になるという駄洒落にすぎません。(3)の例では1番の「秋の田のかりほの庵のとまをあらみわが衣手は露にぬれつつ」と15番の「君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」の下の句がそっくりですし、さらにこの15番は4番の「田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高ねに雪は降りつつ」と全く同じ終わり方をしています。かと思うと「ひとりかも寝む」で終わる和歌も二首あって、3番の「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」と91番の「きりぎりすなくや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む」です。以上、(2)と(3)の問題点を調べると、定家が当時の有名な歌人の代表作を選んだとは、とても思えません。定家自身、「一体どういう基準で選んだんですか」と問われるのを予想した上での答えが日記に書いた「和歌を選んだ基準は私の心の中にある」だったと想像出来ます。ではその隠された基準とは何だったのでしょうか。
この問題に見事に答えたのが大阪市立大学名誉教授(経済学)の林直道(1923-)です。日本語のクラスでその答えを紹介したところ、教室には数秒間の沈黙が訪れ、その後全員の顔に恐怖と「それで納得した」という表情が浮かびました。出典は林直道『百人一首の秘密:驚異の歌織物』(青木書店1981)ですので、ご興味のある方は是非お読み下さい。また、自身も歌詠みで作家の織田正吉著『絢爛たる暗号:百人一首の謎を解く』(集英社1978)も大変参考になる一書です。
林は百人一首は定家が後鳥羽上皇の怨霊・祟りを畏れ、上皇の愛した水無瀬川離宮の絵を描いたのだと、驚くべき主張をします。後鳥羽上皇と言えば1221年に鎌倉幕府打倒を目指したクーデターを起こした歴史上の人物ですが、結局これに失敗し、上皇は隠岐、子の順徳天皇は佐渡にそれぞれ流されました。そして、苦境の中で二人とも流刑地で亡くなります。後鳥羽上皇の場合、隠岐で18年後に崩御するのですが、亡くなる前によく京へ手紙を送りました。その中で、まだ定家が若かった頃、水無瀬川離宮にも招待し、様々な形で援助してやったのに、最近は自分の歌人としての力量に慢心し、都を追われた自分に対して敬意に欠いているという恨みの言葉があったのです。真っ赤な呪いの手形を押した置文まで残っており、「言霊」という意識がまだ生きていたこの時代、定家は上皇の呪いが何より怖かったのです。それで、同じ言葉が使われている和歌を集め、それを縦横に並べ繋げると一幅の絵になる一世一代の試みを企て、「文学的絵巻物」に仕立て上げました。つまり後鳥羽上皇がこよなく愛した水無瀬川離宮の絵を、絵筆の代わりに和歌で織り上げたのが百人一首なのです。そうすることで、過去にお世話になった恩人で、今は流罪の罪人と化した後鳥羽上皇を追悼、顕彰しようとした訳です。そしてその秘密は自分の胸だけに留めておきました。
それこそが「それらの和歌を選んだ基準は私の心の中にある」と定家が書いた真の理由であることを初めて見抜き、定家の深い恐怖心と800年間闇に包まれていた意図を明るみに出した林直道先生の洞察力にはただただ驚嘆するしかありません。しかも、林先生ご自身の専門は経済学なのですから、百人一首研究は日本文学の研究者も舌を巻くアマチュア探偵の成果です。因みに、百人一首は99番が後鳥羽上皇、そして掉尾を飾る100番が順徳天皇の歌で締めくくられていることも決して偶然ではないでしょう。(2012年5月)
応援のクリック、どうぞよろしくお願い申し上げます。

何を隠そう、ずっと昔からこの百人一首は謎に包まれてきた歌集なのです。選者は藤原定家(1162-1241)ですが、その定家が日記「名月記」にこんなことを書いています。「小倉山にある私の山荘のすぐ近くに住む僧の蓮生に頼まれて、障子に貼る色紙用に天智天皇から今日までの歌人100人の和歌を一首づつ選んでみた。私は達筆ではないので気が進まなかったが、仕方なく筆を取って書いた。それらの和歌を選んだ基準は私の心の中にある」当時の知識人の習慣として、この日記の原文は漢文で書かれています。なお、蓮生というのは定家の息子の妻(つまり嫁)の父親のことです。ここで問題なのは、最後の「選んだ基準は私の心の中にある」という個所ですが、定家は何故こんな謎めいた言葉を残したのでしょうか。
それもその筈、定家は実に不思議で不可解な和歌の選び方をしています。これまで多くの研究者が指摘してきた疑問点は主に次の3点です。(1)当時の有名な歌人が多数選ばれていないのは何故か(2)多くの歌の中から、いかにも駄作、愚作と思われる歌を敢えて選んでいるのは何故か(3)同じ様な歌がとても多いのは何故か。(2)でよく槍玉に挙げられる例は22番の「吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風を嵐と言ふらむ」で、これは単に「山」と「風」を重ねると「嵐」になるという駄洒落にすぎません。(3)の例では1番の「秋の田のかりほの庵のとまをあらみわが衣手は露にぬれつつ」と15番の「君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」の下の句がそっくりですし、さらにこの15番は4番の「田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高ねに雪は降りつつ」と全く同じ終わり方をしています。かと思うと「ひとりかも寝む」で終わる和歌も二首あって、3番の「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」と91番の「きりぎりすなくや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む」です。以上、(2)と(3)の問題点を調べると、定家が当時の有名な歌人の代表作を選んだとは、とても思えません。定家自身、「一体どういう基準で選んだんですか」と問われるのを予想した上での答えが日記に書いた「和歌を選んだ基準は私の心の中にある」だったと想像出来ます。ではその隠された基準とは何だったのでしょうか。
この問題に見事に答えたのが大阪市立大学名誉教授(経済学)の林直道(1923-)です。日本語のクラスでその答えを紹介したところ、教室には数秒間の沈黙が訪れ、その後全員の顔に恐怖と「それで納得した」という表情が浮かびました。出典は林直道『百人一首の秘密:驚異の歌織物』(青木書店1981)ですので、ご興味のある方は是非お読み下さい。また、自身も歌詠みで作家の織田正吉著『絢爛たる暗号:百人一首の謎を解く』(集英社1978)も大変参考になる一書です。
林は百人一首は定家が後鳥羽上皇の怨霊・祟りを畏れ、上皇の愛した水無瀬川離宮の絵を描いたのだと、驚くべき主張をします。後鳥羽上皇と言えば1221年に鎌倉幕府打倒を目指したクーデターを起こした歴史上の人物ですが、結局これに失敗し、上皇は隠岐、子の順徳天皇は佐渡にそれぞれ流されました。そして、苦境の中で二人とも流刑地で亡くなります。後鳥羽上皇の場合、隠岐で18年後に崩御するのですが、亡くなる前によく京へ手紙を送りました。その中で、まだ定家が若かった頃、水無瀬川離宮にも招待し、様々な形で援助してやったのに、最近は自分の歌人としての力量に慢心し、都を追われた自分に対して敬意に欠いているという恨みの言葉があったのです。真っ赤な呪いの手形を押した置文まで残っており、「言霊」という意識がまだ生きていたこの時代、定家は上皇の呪いが何より怖かったのです。それで、同じ言葉が使われている和歌を集め、それを縦横に並べ繋げると一幅の絵になる一世一代の試みを企て、「文学的絵巻物」に仕立て上げました。つまり後鳥羽上皇がこよなく愛した水無瀬川離宮の絵を、絵筆の代わりに和歌で織り上げたのが百人一首なのです。そうすることで、過去にお世話になった恩人で、今は流罪の罪人と化した後鳥羽上皇を追悼、顕彰しようとした訳です。そしてその秘密は自分の胸だけに留めておきました。
それこそが「それらの和歌を選んだ基準は私の心の中にある」と定家が書いた真の理由であることを初めて見抜き、定家の深い恐怖心と800年間闇に包まれていた意図を明るみに出した林直道先生の洞察力にはただただ驚嘆するしかありません。しかも、林先生ご自身の専門は経済学なのですから、百人一首研究は日本文学の研究者も舌を巻くアマチュア探偵の成果です。因みに、百人一首は99番が後鳥羽上皇、そして掉尾を飾る100番が順徳天皇の歌で締めくくられていることも決して偶然ではないでしょう。(2012年5月)
応援のクリック、どうぞよろしくお願い申し上げます。