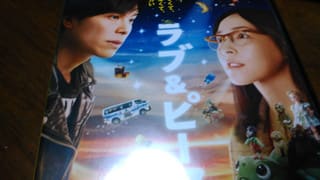終戦直後に書かれた、小山弘健の資本主義論争の本を読んでいたら、冒頭あたりに、共産党関係者が獄中にあらずとも「非命に仆れ」たとでてきたので、やはりこのあたりでは、死をそんな意識で捉えていたひとがかなり多かったのかもしれないと思った。
我々には天命があるのではなかろうか。
映画の「アイアムアヒーロー」は原作とはかなり異なった物語である。われわれはつい見落としがちであるが、――この映画を撮っている監督である佐藤信介氏は「ガンツ」とか「図書館戦争」の監督であって、名前よりも作品がメジャーな人である。「アイアムアーヒーロー」は日本では珍しいハリウッドみたいなゾンビ映画であり、カーアクションもハリウッドや韓国映画を思わせる(よく知らんけど)。作者の死を地でいくと、こういうことになりかねない(知らんけど)
主役は、大泉洋とか有村架純とか長澤まさみとかである。大泉洋はかなりのイケメンであるとわたくしはおもうのであるが、美女二人を守るために、怖じ気づく性格(売れないマンガ家←彼らに失礼な設定だと思う)を乗り越えて、襲いかかるゾンビを皆殺しにする、という映画である。有村架純は、ゾンビに噛まれているので、半分ゾンビになりかけているが、それでも可愛いということで大泉洋が銃刀法を破ってぶっ放し続けるのである。
わたくしは、原作を裏切って、半分ゾンビになった有村架純がゾンビとして覚醒し、大泉洋を助けて大暴れするのかと思っていたが、まったくそんなことはなく、有村架純は最後までへなっとしている。本当は、ただへなっとしている人は唯のお荷物なので、介護要員として登場するのが長澤まさみである。長澤まさみは、この映画を訴えていいと思う。
大泉洋は、最後に、自分の名前「鈴木英雄」――を長澤まさみに伝える。で、画面一杯に「IAMAHERO」とでて終わり。
大量殺人をやらかしてまで自分のアイデンティティを確認しなければならないのはきつすぎる。
最近、映画の世界を征服しつつあるアメリカンコミックスの最初あたりの「アイアンマン」では、主人公が記者会見で「私がアイアンマンだ」と告白して終わっていたが、これは自分の正体がばれてもアイアンマンであり続けようとする、資本家の社会的責任みたいな話であって、むしろ彼にはこれからゾンビみたいな大衆との闘いが待っているのであった。一連のアメリカンコミックスの映画は、このあと、ヒーローたちが乱立する偏執狂的な「社会映画」に向かっている。美少女を助けて殺人をおこなってまで自分を確認する、そんな地点で戦っている「アイアムアヒーロー」とは大きく違う。原作でもそうだったが、主人公はちょっと気を抜くとゾンビたちの群れに同化してしまいそうになる。
なぜ、自分が自分であることを自明の理として乗り越えられないのか。天はどこにもないから、天命は却って無根拠なアイデンティティを作り上げるのに観念として向いていたのかもしれない。
最悪なのは、ミッションとか言っている連中である。