
その最終回に財部誠一さんがテレビ業界の危機について苦言を呈していたのを興味深く見ました。テレビ業界が番組製作などで下請け会社を搾取し、その従業員の収入格差も3倍くらいの大きなものになっていることは良く知られていました。またこの不況下でCM収益が大きく損なわれたことで、派遣切りに等しい人員調整をしていながらも、他の製造業のそれらを大々的に批判するだけで、自らの業界の構造疲労については全く報道しないことについても触れ、その遅れた体質に本質的な改革を促していました。
最近本や雑誌などでも、新聞・テレビの経営の未来が見えにくい状況のことが報じられています。インターネット広告の増加と反比例して、新聞やテレビCMの収益は毎年減っていく一方です。そして世界不況と地上放送デジタル化のための設備投資がWで重荷になっているようで、許認可制度に守られてきたこれらマスコミ業界も、他の業界と同じように再編の声が聞かれるようになってきています。
何にしてもテレビの番組でこのようなタブーのような話題が最終回に放送されたというのは、変わらなければというその自省や危機意識の一端でもあるのかなと感じました。
 | 新聞・TVが消える日 (集英社新書) 猪熊 建夫 集英社 このアイテムの詳細を見る |











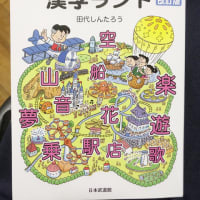



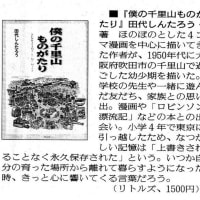


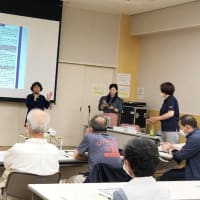

私は日経と日経産業、それも事実のみに目を通すのみで、新聞記者の意見は読みません。大事な情報源として、1843年からロンドンで発行されている経済週刊誌「The Economist」は注意深く読みます。世界の経済、政治、軍事、技術などを毎週伝え、米国や欧州の経済界に強い影響を与えています。米国のITバブルを予測した38ページの論文は感銘深いものでした。中国の現状も正確に伝えています。
ロンドン・エコノミストや英国の軍事問題専門誌発行のジューン社は、長い歴史の間に培った、事実の着眼点と分析能力を持っています。
「護送船団に守られた新聞」とはよく言われたもので、結局そういう形では競争力の付けようが無くなるのが分かります。
日本の新聞には配達という独自の販売形態があって、買収などで経営的に総崩れ状態になっているアメリカ新聞業界とは少し違うようですが‥‥。
グローバルな時代になっても製造業は頑張っています。インターネット時代になると、情報産業にとってはやはりコンテンツの力が問われます。例えば日本のマンガはアメリカのヒーローものコミックを抑えて3倍位の売り場面積を占めているそうです。元々は日本語ですが翻訳されて再出版されています。日本の新聞のコンテンツにそのような本質的な発信力があれば言葉の壁は無いはずです。
何にしても危機意識というものは行動や変化を促すと思われますので、日本人としても情報産業のそこに期待したいですね。