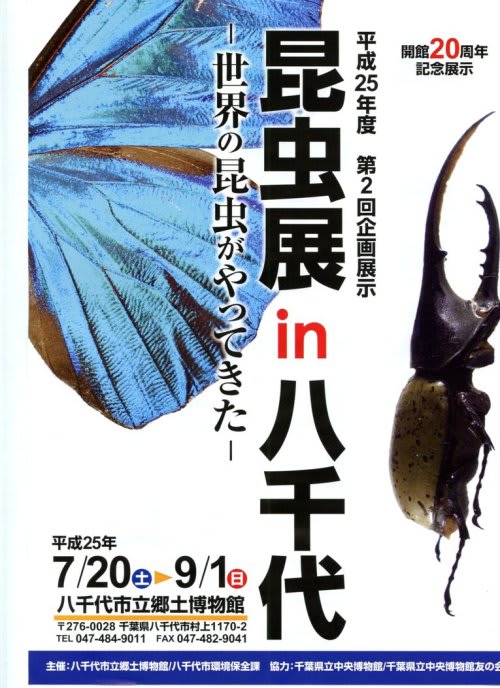装束着用の写真、もちろん、下の写真のように真正面から撮るのが常道ですが、このように、ストーリー性のあるポージングも素敵です。ぜひご参考になさってください。

終了後はぜひ「もぬけ」をご注文ください。

(掲載許可いただいております)
あの大雪の2月9日から順延すること1ヶ月、本年も八千代市立郷土博物館の装束体験が始まりました。当初1日だけだったものを、本日と明日の2日間にわけての実施です。装束本もいろいろ置きました。

襟洗いの上がった韓国装束も揃っています。

いよいよ初日がスタートです。
常設展示に「三山の七年祭り」で使われる大和田の山車の模型が加わりました。伝統文化資料室でも展示したことがあります。

東京藝術大学保存修復彫刻研究室によって模刻された正覚院の清涼寺式釈迦如来、金丸先生が解説しておられます。

さあ、週末は雪で順延となった装束体験の本番です!
浅見光彦シリーズといえば、優に100冊を越える内田康夫氏の大人気シリーズですが、2011年に出た『黄泉から来た女』(通算111冊目)は、出羽三山を舞台にしています。このなかに、「八千代郷土資料館」が登場し、学芸員の「惣領さん」が重要な役割を果たすのですが(さすがの慧眼、蕨さんが「さわらび通信」で取り上げています)、なぜそんなことになったのか、というのが、このたび出た新潮文庫版のなかの、内田氏の「自作解説」によって明らかになりました。
連載が始まった二〇一〇年の夏に突然思いついて、再度、羽黒山に出かけた・・・その日、たまたま宿坊で一緒になった千葉県八千代市の学芸員・佐藤誠(せい)氏から、「講」の話を聞くことができた。羽黒山を信仰・参詣する仲間で作るいわゆる講は各地にあり、八千代市周辺にも、古くから熱心な講組織があるそうだ。その偶然のように仕入れた知識が、ストーリー上きわめて重要な部分の発想に繋(つな)がった。
やるなぁ、佐藤さん。八千代市立郷土博物館が「八千代と出羽三山~奥州参り~」企画展を実施したのは2008年7月~9月のことですから、佐藤さんの出羽行きは、その展示の取材ではなかったでしょうが、天下の内田康夫氏と宿坊で隣り合わせるとは、なんたる強運の持ち主でありましょうか。しかもそれが、八千代市立郷土博物館への取材につながり、ほぼそのまま、小説のプロットの根幹をなしているということには、文学作品の生み出される現場を覗いたようで、少しく興奮を禁じ得ません。

(・・・入口に門の代わりに、教会のベルのような鐘を六個吊るしたモニュメントが建っている・・・本文308ページ)
内田氏は続けて次のように言います。
こう書いてくると、僕の創作手法はいかに取材に裏打ちされているかがよく分かる。僕の小説を「旅情ミステリー」と命名したのはかつて「光文社」の編集長を務めていた多和田輝雄氏だが、確かに過去のどの作品についても、取材なしには生まれなかっただろうと思えるものがほとんど、今後もその傾向は続けるつもりだ。
かくて、八千代市立郷土博物館は、日本を代表する人気小説のなかに、永遠の姿をとどめたのであります。出羽三山講のこともとてもよくわかりますよ。八千代の方はぜひ一読を。
千葉県北西部地区文化財企画展示会「文化の絆~モノとヒトの出会い~」
日 時 : 1月25日(土)~3月2日(日) 9時~16時30分
内 容 : 千葉県北西部地区各市(鎌ヶ谷市・習志野市・我孫子市・松戸市・柏市・流山市・市川市・八千代市)は、発掘調査の成果や歴史・文化等について、統一テーマにより共同で展示会を開催します。古代から、ヒトは様々な手段でほかのヒトに思いを伝え、「絆」を結び、文化を創ってきました。この展示会では、モノに残された様々な事柄から、ヒトとヒトとの結びつきを探ります。

「栗谷式土器」も展示されます。準備の様子。