
中国旅行記でウイグルについて書いてきましたが、ここで一つフン族の話を。まずはwikipediaの記述を引用する。
「フン族はヴォルガ川東方から現れた遊牧民の集団で、370年頃にヨーロッパへ移住して大帝国を築いた。彼らは恐らく300年程前に中国の北隣に居住していた匈奴の子孫であり、テュルク系民族のユーラシア大陸にまたがる最初の拡張であろう」引用おわり
フンは匈奴だった説というのは、昔から囁かれていた話である。その根拠とされているものは以下の理由からであった。
1:匈奴は現代中国語ではシュンヌと発音するが、古代中国語ではフンヌと発音した。(音が酷似している)
2:匈奴は北匈奴、南匈奴に分裂し北匈奴は西へ進み消息を絶った。匈奴が文書上から消えたのが、ちょうど五胡十六国の時代。すなわち西暦300年の前半である。フン族は370年頃にヨーロッパに移住した。
これが17~18世紀に中国に渡ったフランス宣教師が言った、フン=匈奴説の初出である。
3:この他に、ソグド人の手によって残された文書である、ソグド語「古代書簡」がある。これは1907年に敦煌西方の玉門関遺跡の中から発見したもので、年代についてはさまざまな説があるが、現在では312~314年という見解が有力である。この書簡の中に、匈奴がフンと呼ばれていたことが確認できるのである。ソグド人の故郷は中央アジア、現在のフェルガナ、サマルカンドあたりの地域で、かつてこの地域はソグディアナと呼ばれていた。
さらにwikiの引用をする。
さらに、ミュンヘン大学のF・ヒルト博士は『ヴォルガフンネンと匈奴について』(1899年)において、『魏書』西域伝に見える「粟特国」を、アッティラの死後フンが退居したクリミア半島の「スグダク」に比定し、西史に見える「フンのアラン族征服」を、『魏書』西域伝の「匈奴の奄蔡(阿蘭)征服」に比定し、「フルナス(アッティラの末子)」を「忽倪」に比定した。また、『魏書』西域伝に見える「(粟特国の)別名は溫那沙」に注目したJ・マルカルトは『ブルガール王侯表中に於ける非スラブ的表現』(1910年)において、「溫那沙=Un-na-sa」の「-sa」の中に、オセット語の接尾語「ston」、アラン語の「stān」が存在すると論じ、「溫那沙」はアラン語またはペルシャ語の「Hūnastān」すなわち「フンの国」の音訳であるとし、ヒルト説を補強した。その後もさまざまな研究者によってフン=匈奴説が支持され証明された。
しかし、これに反対する研究者もいた。日本の白鳥庫吉は「粟特国はスグダクではなくソグディアナであり、匈奴が粟特国を征服したとあるのは、フンがアランを征服したのではなく、エフタルがソグディアナを征服した記述である」とし、ドイツのJ・クラプロートは「フンの言語はフィノ・ウグル語であるのに、匈奴の言語はテュルク語であって両者は言語を異にする異民族である」とした。
引用おわり
後段のwikiの引用は、内容が極めて専門的であるので細かい解説はしないが、白鳥説ではヒルト博士説の反駁になっている。
つまり、ヒルト説が間違いであったのだとすると、フン=匈奴説は1~3の根拠によるものということになる。
ただし、この論拠は事実上名称の類似のみであり、遊牧民の集団は首長家の婚姻や政治的連合によって集団構成要素が容易に変動するため、フン族集団が匈奴の西走集団と系譜的につながるとしても、中国北方で活動した匈奴国家の部民がそのままの形で西方にフン族として登場した可能性は疑問視されている。西ゴート族襲撃以前のフン族について、正確に分かることは何も無いのが現状である。(wikiから引用)
という事である。
考えてみれば、月氏も匈奴に敗れて中央アジアに移動して大月氏になったし、突厥も東突厥と西突厥に分裂し、唐に敗れて西突厥は河西回廊の西に移動したし、さらにいえば遼(契丹)も金に滅ぼされて、西に移動して西遼(カラキタイ)となった例がある。とにかく遊牧連合は、敗れて西進する例が非常に多く、それもフン=匈奴説を後押ししているといえよう。
なんともロマンのある話だなぁと思った方は、クリックを。











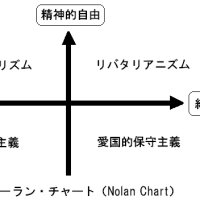








遊牧民の多くは文字による記録を残さなかった。そのため文字を持った周辺の定住民族の記録に頼ることになる。フン族はどのような民族であり、どのような言語を使っていたのか。少なくともインドヨーロッパ語でなく、その他の言語(昔はウラルアルタイ語系と分類されていた)の一つであったのは確か。文字や文法の制約がなければ土地、生活形態に合わせて言語は自由に独自に発達する。遊牧民族は農耕民族に比して人口が少ないからか、悲しいかな、文明という土着の文化に触れると言語とともに人種的にも飲み込まれる。
が、記録を残した文明や定住民族の歴史が正確な歴史とは必ずしもいえない。満州族の国家・清国がそうであったように、国家滅亡とともに本来の領土・満州を漢民族に乗っ取られ飲み込まれ、あっという間に消え去った。後には勝者の歴史のみが生き残る。
去勢や蹄鉄、鐙、鞍といった技術的な貢献だけではなく、小文明同士をくっつける接着剤的要素など、遊牧民が文明に寄与した点も多々あったのではないかと思う。
定住民族の、文明の界外にあった、国境という観念を持たぬ、真にユーラシア大陸を自由に駆け回った人々。彼らフン族もまたその一種族、一民族だった。
多分にわれわれ現代人の想像を掻き立て、ロマンを醸し出しますなあ。