
【この記事のポイント】
・円安の要因は日米金利差だけではない
・いま起きているのは円の価値の再評価
・しばらくは150円より円高にならず
1ドル=150円台の為替レートが定着しつつある。
エネルギーの輸入額や、米テック企業への支払いなど「デジタル赤字」が膨らむ一方、輸出で稼ぐ力が落ちた。金融緩和からの脱却も簡単ではなく円安の歯止めが見えない。
通貨政策を取り仕切る財務省財務官を務めた国際通貨研究所の渡辺博史理事長に「強い円」を取り戻す方策を聞いた。
財務官は主要国の担当者と為替政策の交渉・調整にあたる「通貨マフィア」の異名を持つ。通貨の攻防を最前線でみてきた。
――円安の原因は日米の金融政策の方向性の違いがもたらした金利差拡大との解説が多い一方、日本の国力低下を映すという指摘もある。
「2022年2月にロシアがウクライナを侵略し、3月に米国が利上げを始めた。そこから円安が始まった。
対ドルのレートは当時の115〜118円ほどから、足元では150円台まで下がった。日米金利差に関心が集中してきたが、当時からそうした見方に違和感を感じていた」
「およそ35円下がったうちの半分は金利差で説明できる。しかし、残り半分は円の価値に対する過大評価が剝がれたことが要因だとみている。金利差が縮まっても115円の水準には簡単には戻らないだろう」
――円はリーマン・ショック後も東日本大震災後も買われる通貨だった。世界最大の債権国という評価があったのではないのか。
「有事の際にドル以外に買われる通貨といえば円とスイスフランだった。
特に1999年に欧州でユーロが導入されて仏フランも独マルクもなくなり、市場は円とフランを相対的に変動幅が小さい通貨とみなすようになった。
この『安全通貨』という理解が、そもそも誤解だったのではないかと考えている」

渡辺氏は、円の価値の再評価がおきていると語る
「円が買われたのは利回りが高くてもうかるからではない。
大幅な変動が起きた際に、政府や中央銀行が修正に乗り出すからだ。
ユーロは導入国が多く合意が難しい。円とフランは一国の判断で変動の波を小さく出来る通貨ということで保有されてきた。
それが本当に正しかったのかという点検が始まった。円の価値の再評価がおきている」
経済体力に市場が疑問符
――同じ安全通貨とされたフランをはじめ、ユーロ、ポンドなど主要通貨のなかで円だけが突出して下落している。
「日本はエネルギー自給率は1割ほどにとどまり、食料自給率も4割ほどしかない。
かつては70年代の繊維や90年代までの白物家電のように輸出で稼ぐ力があった。
近年は欧州が電気自動車(EV)へのシフトを強めハイブリッド車の先行きも見通しづらい。
為替は貿易収支だけで決まるわけではないが、赤字が続く国の通貨は『強い通貨』ではないとの認識が市場に広がった」
「原油価格は2008年には1バレル147ドルまで上昇した。
現在80ドル前後で落ち着いているものの、上昇すれば貿易赤字は拡大する。日本の経済体力への疑問符はそう簡単には解消しない」
――過大評価の修正が原因ならば、円安は恒常化するのか。金利差はいずれ縮小するのでは。
「まだ誰も明確に説明していない点がある。
11年の東日本大震災後に政府・日銀が円売り・ドル買い介入するまで、米長期金利が日本より3%ほど高いと為替は安定する傾向があった。
通貨の使い勝手の差などから落ち着きのいい水準なのだろう。現在、金利差は4%を下回ってきたが、3%の金利差に収まるのは早くても25年末だとみる」
「米連邦準備理事会(FRB)が利下げに動くとしても年内に1〜2回だろう。
日銀は7月、あるいは10月に利上げしても、利上げ幅は0.1%と小さいかもしれない。
金利差は24年末でも3%に近づくとは思えず、150円よりも円高にはならないとみている」
財務官在任中に為替介入せず、市場重視派として知られる。近視眼的に為替水準の是非を議論するのではなく、円を取り巻く日本経済の構造変化を分析すべきだと説く。
――円安は輸出企業の業績底上げにもつながる面がある。どの水準が適正なのか。
「為替レートはその時々の日本経済全体の強さの反映であり、どの水準なら良いという議論はナンセンスだ。
これまでは貿易立国に傾きすぎて『円高恐怖症』に陥り、経済実態にあわせた為替のレベルを超えて円安になるようバイアスをかけ続けてきた。
輸出にとって円安が良かったのは90年代初頭ぐらいまでが実態で、その後は神話の世界になった」
「80年代の日米貿易摩擦時は日本は国内資本、国内の労働者を使い、全ての付加価値を日本で生み輸出の恩恵を享受していた。
その後、日本の賃金が当時はまだ高かったため、アジア諸国で中間財や部品を製造し、川上のデザインや最後の組み立ては日本で行う体制になった。
日本への輸入は円建て取引が普及しなかったためドル建てだ。円安になれば輸入コストは確実に上がる。一方で円安になれば輸出が増えるというのは単なる希望に過ぎなかった」

――いま国際収支は海外からの配当など第1次所得収支の押し上げで黒字を保っているが、直接投資収益のおよそ半分は再投資に使われ日本に還流していない。
「そのズレも起きている。
収支としては黒字だが円買いにはつながっていない」
――海外からの食料購入を抑えて自給率を上げるのは短期では難しい。
東日本大震災以降に原発再稼働のハードルも上がった。
「1億2000万人ほどの人口が当面続くとすると食料を自給できるとは思えない。
学習のために電力を大量消費する人工知能(AI)が普及すれば、トータルの電力量が増える。
再生可能エネルギーに移行するだけでは絶対量が足りない。
何を抑制するのかを政治が説かなければ、為替もエネルギーの問題も解決しない」
「売れるもの作り」に挑め
――そうなると外貨を稼ぐ力の回復が喫緊の課題となる。
「民間産業が売れるものを作らなければならない。
いまでも東京エレクトロンや信越化学工業といった半導体関連の製造装置や素材で先を行く日本メーカーはあるものの、1億数千万人を養うには足りない。
国内総生産(GDP)は増えてもあまり雇用を必要としないため、賃金に反映されず消費につながらない。
車や家電がそうだったように、雇用を伴いながら海外に売れる製造業が必要だ」
「サービスでもよい。(米テック企業へのクラウドサービスの支払いなど)デジタル関連の収支はいま年間6兆円ほどの赤字に膨らみ、今後10兆円を超えるかもしれない。
バブル崩壊後の日本は外国がお金を払って買ってくれるものを生み出せていない」

政府主導ではなく、民間が新たな製品・サービスを生み出す力を重視する
――海外への投資から生まれる収益だけでは日本経済を維持できないということか。
「そういうことだ。加えて人口が減るまでの間に高齢化が加速する。
そうなれば生産力は落ちていく。
ロボットを導入するのであれば、高齢男性の筋力でも生産量を上げていけるようにしなければならない。
女性もその分野に入っていける。本気で進めるなら、そこまでやる必要がある」
「もたもたしていれば例えばコールセンターのサービスなどはAIで代替できる世界になってしまう。
お金を稼いでさえいれば済む状況ではなくなる。
為替の問題が部分的な議論に終始すれば、極端な答えに行き着きかねない。長期的な視座で考えなければならない」
わたなべ・ひろし 1949年生まれ。72年に大蔵省(現財務省)に入省し、国際局長、財務官などを歴任した。財務官在任は04〜07年。08年に日本政策金融公庫副総裁に就任し、12年に国際協力銀行副総裁、13年から16年まで同行総裁を務めた。16年10月から国際通貨研究所理事長
足腰を鍛え直すために(インタビュアーから)
為替レートは一国の相対的な経済力を映す鏡だ。足元の円安は日米金利差に着目した投機筋の円売りが主導しているとはいえ、日本の経済力低下が売り安心感につながっている。
日経平均株価は34年ぶりに最高値を更新し、春季労使交渉の賃上げ率は2年続けて30年前の水準に達しそうだ。日本経済は一見、「失われた30年」を脱したかに見える。
ただ日本の潜在成長率は2003年を最後に20年ほど1%を下回り続け、主要7カ国(G7)で最下位に甘んじる。
日銀の植田和男総裁が利上げについて「大きな間違いを犯さないように慎重に進めたい」と語るのは、日本経済の力強さが欠けている裏返しでもある。
経済の足腰を鍛えるには、国民に都合の悪い施策を選択しなければならない局面もある。
この30年の改革の頓挫は、世論が痛みを伴う政治を暗黙のうちに避けたからでもある。
(広瀬洋平)
写真 佐藤七海
ひとこと解説
超円安でもJカーブ効果は起きていない。輸出数量はほとんど増えていない。日本の輸出の契約通貨は外貨建てが多いが、円安でも契約通貨建て輸出価格は低下していない。
ドルなどの外貨建てでみると輸出額は増えていないので、輸出シェアを拡大し輸出大国への復活を目指しているわけではないようだ。
円安は円ベースの輸出価格を急増させ、輸出企業の利益を押し上げたが円安が是正されれば、押し上げ力は減衰する。
輸出数量を増やす傾向がみられないのは、直接投資を優先し、国内の人手不足や市場縮小を予想して生産設備の積極的な増強を行っていないからなのかもしれない。
日米の設備投資や生産性の格差が円ドルレートに反映されている可能性もある
<button class="container_cvv0zb2" data-comment-reaction="true" data-comment-id="43236" data-rn-track="think-article-good-button" data-rn-track-value="{"comment_id":43236,"expert_id":"EVP01096","order":1}"> 18</button>
18</button>
<picture>

</picture>
白井さゆり
慶應義塾大学総合政策学部 教授
国際派エコノミスト。国際通貨基金(IMF)エコノミストや日銀審議委員を歴任。金融政策や国際金融に精通し、脱炭素・ESGに詳しい。
多数の海外メディアに英語で情報発信し多くの国際会議で講演。パリ政治学院客員教授、アジア開発銀行研究所の客員研究員も務めた。
2020-21年には英国のESGスチュワードシップサービス会社EOS at Federated Hermes上級顧問を兼任。米コロンビア大博士(経済学)。
【注目するニュース分野】金融政策、ESG投資・経営、国際経済
日経記事2024.06.22より引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6664c450cc30c63d280146e8ec59ed62 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=532&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c727771013b055feb06da125bee6ba05 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6664c450cc30c63d280146e8ec59ed62 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=532&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c727771013b055feb06da125bee6ba05 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6664c450cc30c63d280146e8ec59ed62 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=532&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c727771013b055feb06da125bee6ba05 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6664c450cc30c63d280146e8ec59ed62 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=532&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c727771013b055feb06da125bee6ba05 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6664c450cc30c63d280146e8ec59ed62 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4982891018062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=532&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c727771013b055feb06da125bee6ba05 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e855d8c2010203e30858f729e6c7e25e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=992&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3781883cba122596a510eb160d6aa6c5 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e855d8c2010203e30858f729e6c7e25e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=992&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3781883cba122596a510eb160d6aa6c5 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e855d8c2010203e30858f729e6c7e25e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=992&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3781883cba122596a510eb160d6aa6c5 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e855d8c2010203e30858f729e6c7e25e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=992&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3781883cba122596a510eb160d6aa6c5 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=496&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e855d8c2010203e30858f729e6c7e25e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4954085011062024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=992&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3781883cba122596a510eb160d6aa6c5 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>




 </picture>
</picture>












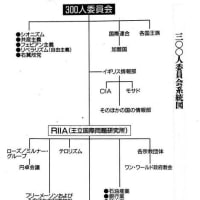

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます