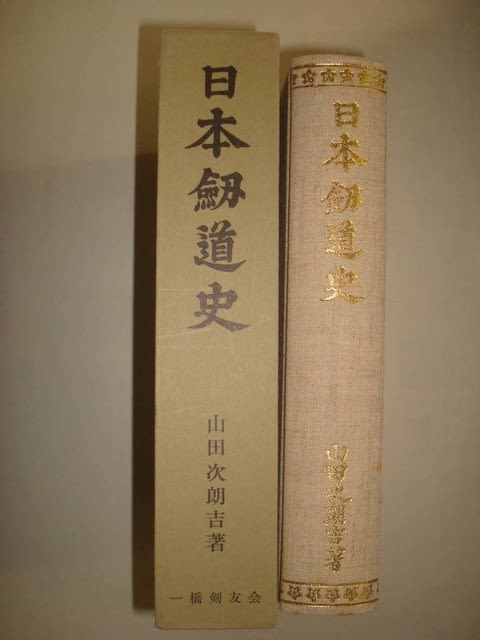従来の日本史が唐書に合わせ下敷にし作られてきたのに朝鮮歴史書の〈三国史記〉や〈三国通紀〉が和訳されだしてからは、韓史を基にして考え直す思考発生は如何なものか。 日本と韓国歴史家の交流が始まってから、ますますもって黒潮や寒流を無視した、大陸渡来日本人説が広まりました。 しかも北朝鮮側と違い韓国史学は極めて自由な立場で、日本列島歴史を韓国だけの立場からのみ解明説明しようとし、古代史研究の人々はその朴蒼岩説に全面的信頼を寄せている。
そもそも、一国の歴史というのは、その国の権力者が偽史を作成するのに対して、周囲の国々の歴史を付け合せて、その誤りを訂正してゆくものですが、 日韓併合の際に伊藤博文が現地へ赴き殆んどを統治上の必要から朝鮮の歴史書は、強制的に没収焚書しました。 だから朴史観は、初めて照合できるものが出現と感謝されます。
しかしこの、韓国史観でゆきますと、日本列島を支配したのは中国勢力ではなく、ずっと隣接した朝鮮半島だったのだ、としてしまうのが困りものである。
白村江の敗戦で唐軍の郭将軍、劉将軍らが九州から、男っ気なしの奈良時代の御所へ入ってきたのが西暦六六四年から。高麗が唐軍によって滅ぼされた六六八年を経て3年後、 百済系の中大兄皇子の天智帝が崩御なさると、次の皇位をつがれる大友皇子の弘文帝を仆したのは、どう考えても高麗や百済亡国の朝鮮半島の勢力ではなく、 大化改新のフィクサーだった藤原鎌足の率いていた岡山の華夏王朝なのである。つまり唐でない事には、六六九年から唐より又も二千余の軍が追加進駐してきているのだから、 辻つまが合わぬのに、まったくこれを無視しているのです。これは困ります。
弘文帝が殺されて天武帝に代わられた後も、朝鮮半島で唯一国、まだ反唐勢力を辛うじて保っていた新羅との関係は順調で、この頃までに既に亡国の民である高麗人らを東北へ移住を強い、 彼らによって東国から陸奥は開発されたものとします。天武帝のバックアップは鎌足の死後とはいえ渡来唐人及び従前より岡山にいた桃原と名のる鉄剣集団ゆえ、 大陸で敵対していた新羅と仲よくする訳はなく高麗人を関東へ追放したら、次は新羅人も同じ運命で、いまの群馬、埼玉辺りと想われる。
韓国史観には全くでてきませんが、黒潮暖流で安房の小湊や尾張一の江、津島から明石や淡路島に漂着し、定住していた古代海人族らを、遙か東北へ追い出しだのは、 アメリカで非農耕の狩猟氏族のイッデアンを居留地へ追いこみ、彼らが馴れぬコーン栽培を渋々しだし、どうにか荒地が耕地になると司政官が取り上げ、 もっと奥地へ移転命令。拒めば騎兵隊が突入し皆殺しの西部劇と同じことです。
韓国史観は、西暦七〇七年天智王未余勇の第四女元明女帝が即位なさると、奥羽開発政策が積極化したとし、佐伯石碣を征越後蝦夷将軍に任命し、巨勢麻呂を陸奥鎮東将軍にし、境土拡張を下命とします。
つまり開拓でき農地化されたのを没取して王土とし、さらに荒野へ武力で追いたてて、そこを新居留地にさせたのが本当です。 だから〈古事記〉ができたと伝承される七百十二年の翌年には出羽も国守をおかれる迄になったのです。 が、それでも出羽三山の密教の修験者たちが、みな揃いも揃って、「望海」「懐海」と海を懐かしんで、海号を誰もがつけるのも、彼ら古代海人族が追われていった例証ではないでしょうか。
韓国は日本列島とは違い黒潮が直突してこないせいか、海流無視しすぎるのは困りものです。また関東六国の富民一千戸を移すというのも、彼らに強制的に新農地を当てがい年貢を取りたてる為に、 分散して農奴を使わせるよう送りこんだのであるし、尾張の一揆を起した七十四戸を席田雨近に命じて、美濃山中の山奥へ送りこんだが反抗したというのも〈続日本紀〉に出ております。
〈文徳実録巻四〉には、美濃席田郡に妖しき者らの反乱あるを、新美濃の国務次官の介となった藤原高房が武力討伐したのは天長四年。 ようやく彼らが飛騨へ追われたのが七一五年ゆえ、八二七年迄も一世紀の余もレジスタンスを続けたのは、大陸系に対する山中へ入られたゆえの、 海人族ら日本原住民たちの抵抗とみるべきでしょう。 尾張は「塩尻」美濃は[ヒタ]とよばれ日本原住系八の者の根拠地である。
日本の原住民をすべて朝鮮半島から釜山経由で流れこんだ韓国人としてしまう史観では、西暦七一六年に駿河、相模、上総といった黒潮暖流で接岸した定着民さえ海人族でなくなってしまいます。彼らを武蔵へ移住させ高麗郡となったのだから、彼らは高麗人であったとしてしまいますのは承服できません。これは大間違いだと指摘する。
なにしろ武蔵は前から高麗語の「主」のムと、城の「サシ」の土地で、つまり前からの高麗系騎馬民族の本貫の土地です。 なのにそこへ仲の悪い異種の海人族千七百九十九人を奴として放りこんだというのでは、夷をもって夷を制させる為の苛酷な政策でしょう。
やはり百済系の元正女帝につぎ元明女帝がたつと、東海道、東山道、北陸道の内で農耕地帯に一変した肥沃な土地を官土として召し上げるため、その二百戸を出羽へ強制移住させた。 まったく西部劇のカスター将軍のインデアン弾圧時代と同じ具合です。実際の国家権力は唐からの人々が握っていたのに、百済系の女帝を次々とたてていたのも、 憎まれ役を押しつける為の毒をもって毒を制す六韜三略の兵法そのものです。
韓国史観は、日本列島が馬韓・辰韓・弁韓の三韓時代の支配が長かったので、高麗・新羅・百済とその国名が変ってからも、まず唐勢力はまっ先に自分らに帰順帰化した百済系を操って、 古代海人族の天の王朝系を奴隷としている彼らを互いに潰し合いさせていたのを伏せているのではありませんか。
「土毛」とよぶ、地面に毛のごとくはえる農耕物と、海中よりの魚介、海藻や塩だけが国富であった時代ゆえ、黒潮で西南から漂着した海人族の奴隷の奪い合いが共に国益に通じていたのでしょう。 またそれゆえ12世紀たった今日でも、私共のような古代海人族の血をひく奴隷の末裔が、今もこの日本の総人口の六割五分をも占めているのでしょう。 韓国史観では、百済が今の南朝鮮半島に位置していた国であったせいか、「摂津国に百済部を設け、彼らは厚遇された」としまして、大阪市生野区に当るそこは後の平清盛の本拠地なりと、 さも平氏までが百済系みたいに拡大解釈をします。
平家は古平氏北条にしろ新平氏にしろ、西南よりの海流によっての漂流者である事は〈東大寺社寺雑事記〉に「僧にならぬ三条囲地者には古来よりの定法にて、平の姓を賜る」とある日本史が正しいのです。天武帝の頃に陸続と、大陸からの食いつめ者が入ってきたものの、彼らは日本列島では「貴種」とされていた。 それゆえ、中国のロボットみたいな恰好だった奈良王朝において、百済系の敬須那利を甲斐国司や、義慈六世の孫にあたる余敬福を陸奥国司に任命されましたのも、持統女帝や孝謙女帝の保護政策ではなく、 弁髪の当時のフィクサーが美女は御所においたが、男は邪魔者で不要ゆえ遠く派遣しただけのことです。
また手柄をあげて百済系体制を護持しようと言うので、余敬福は陸奥で海人族の奴隷使役で黄金九百両をえて献上している。それを孝謙百済女帝は唐へ送り、 機嫌とりに仏教のため奈良東大寺建立の資金に、次々と採鉱した金をあてた。銅は武蔵で新羅人金上元が銅脈をみつけ、よって元明女帝は年号を慶雲から和銅に改元して、 日本列島を銅鐸時代にとしてゆくのですが、「李氏朝鮮」の記録では、「申宗三十七年大司憲申瑛」の申告では銀の造練精製は日本へ技術者を遣わした。つまり日本へ教えたとします。 それはそうでしょうが、正倉院御物にも、古代海人族がもたらした銀器が現にあるのです。
黒潮渡来サラセン細工と韓国製とでは、同じ銀細工でも模様や柄が違います。一見すぐ判ります。 韓国の歴史ですから自国本位になるのは、やむをえない事ですが、日本ではそれに対比できうる歴史家や史料が皆無なので、一方的にこうしたものが邦訳されて押し付けられてきては堪りません。 もはや対応できるのは吾々の常識しかありません。しかし庶民の何割かは新羅や高麗系の向こうの騎馬民族の血をひく白山王朝の子孫ですからして、こうした向こうの歴史に対し、 直ぐ納得合点したがる人々も多いのはやむをえないかもしれません。とは言え、これこそ危険思想で、わが日本の国体を危うくするものかも知れないと不安に想うのは、杞憂であればよいと考えさせられます。
日韓宣言20年に寄せて
さて、韓国のこうした御都合主義歴史に迎合する日本人が多い訳だが、現在に目を向けてみよう。
1998年10月8日の日韓共同宣言から20年を迎えた。 「未来志向の関係発展」をうたったこの宣言を機に、両国の交流は進み、人の往来は3倍以上に増えて昨年は945万人に上った。 一方で従軍慰安婦など歴史問題での溝はなお深く「真の和解」に至っていないのが現状である。
北朝鮮の非核化を巡る米朝父渉が動きだしている。北東アジアの安定や日本人拉致問題の解決には、日韓の連携が欠かせない、というが果たしてそうなのか。 また日本の植民地時代に動員された元徴用工への補償問題が再燃されている。 さらに、日本政府は65年の日韓請求権協定で解決済みとし、韓国側も同じ認識だったが、文氏は昨年8月、個人請求権は消滅していないとの見解を明らかにした。 巨額の賠償が認められれば、日本企業への打撃は計り知れない。 こうして次々と韓国は「解決済み問題」を吹っ掛けてきて、この国は、まさに疫病神である。
「未来志向の関係構築」とは程遠い。 両国が、如何に冷え切った関係でも日本の立場を貫き、高みから見下ろす姿勢で日本は微動だにしてはならないし、実際問題として、少なくとも戦後の韓国との関係で、 日本の国益になったことなど、何一つないのだから。
(注)この項を記述している最中に、韓国最高裁は(2018年10月30日)、元徴用工の個人請求権を認定した。これにより新日鉄など数十の会社の賠償額はいか程になるのか見当もつかない。 日本政府は国際司法裁判所への提訴も辞さないというが、先行きは全く不透明である。