
先ほど、ひぐらし会館の前を通った時は公園しか気づかなかったがそんな神社があったとは。
(詳しくは一つ前のブログを参照してね)
 音無神社から見える対岸の「ひぐらし会館」
音無神社から見える対岸の「ひぐらし会館」
せっかくなので「岡橋」を渡って日暮八幡社へ行ってみようと川沿いをあるくと、
野良猫が欄干で昼寝をしていた。

なんともほのぼのしている風景である。
 岡橋の欄干 青い空と共に美しい
岡橋の欄干 青い空と共に美しい
 橋には頼朝と八重姫の逢瀬のレリーフが・・・
橋には頼朝と八重姫の逢瀬のレリーフが・・・
 欄干から二つの神社を・・・
欄干から二つの神社を・・・
右側は音無神社 左側が日暮八幡社

日暮八幡社はひぐらし会館の向かいの公園の奥にあり、音無神社から比べると、小さい。
 こちらにも由来の看板が。
こちらにも由来の看板が。
短いバージョンと長いバージョンがあった。
「ひぐらしの森と
日暮八幡神社」
日暮(ひぐらし)の森は、若き日の流人源頼朝
が、伊東祐親の娘八重姫との逢う瀬を楽しみに、
日暮し過ごしたというロマンスの伝承を秘めて
いる場所で、明治中期の絵図では、田んぼの中に
大きくこんもりと繁った日暮の森が川のふちまで
続いている。
この周辺の発掘調査により、弥生時代(約二千
年前)から古墳時代(約千五百年前)にかけての
集落群が発見され、日暮(ひぐらし)遺跡と名づ
けられて、出土品の一部は伊東市文化財セン
ターに展示されている。
この神社の創建年月の明らかな記録は無いが、
古くから村民の五穀豊穣、家内安全、安産の守護
神として崇敬されてきた。
祭神 誉田別命(ほむたわけのみこと)
傍祭日 九月十五日
平成十一年記 伊東市教育委員会



「日暮神社 ひぐらしの森 由来」
源頼朝は、伊豆流人の約二十年の一時期、
伊東の「北の小御所」に暮らした。その時、
伊東領主・伊東祐親の娘八重姫とのロマン
スが生まれたのである。二人は対岸の音無
の森で逢瀬を重ね、その折頼朝が日暮れを
待ったのが、ここひぐらしの森であったと
伝えられている。
二人の愛は、一子千鶴丸の誕生を迎えた
が、平家をはばかる祐親の激怒に触れ、仲
を引き裂かれ、多くの悲劇の中ではかなく
消え去った。
最近のひぐらしの森付近の考古学調査によ
ると、弥生時代前期(二千年前)から古墳
時代前期(千七百年前)に及ぶ遺跡が発見
され、勾玉・壺・石斧等と共に、当時
の墓も発掘され、まさにひぐらしの森は、
先人達の生活の場であったことを物語って
くれている。
この森の最も古い記録は、文禄三年
(一五九四年)午、八月の「岡村差出帳」であ
る。同書によると、頼朝とのかかわりの事
蹟を伝え、「道法、村より四町御座候」と
記録している。(当時は名主の家を中心に
道法を出していて、その頃の名主は瓶山下
の堀井家であったと考えられる。)
また嘉永年中の「伊東誌」によると、こ
の地に程近い所に、日暮山龍明寺という寺
があったと伝え、建久三年(一一九二年)
八月十五日に頼朝が、寺領五十三石を永久
の祈願料として与えたと記している。
このような点から、鎌倉幕府創建の人、
頼朝にとって生涯の忘れ得ぬ思いで深い森
であったと想像出来る。
日暮神社は、祭神「誉田別命」が、村民
の五穀豊穣、縁結び、安産の守護神として
崇敬され「日暮八幡」として祀られた。
神社として風格を現したのは江戸時代中期後で、
以来地域住民の氏神として篤く信仰される
に至ったのである。
 「日暮神社」と達筆で書かれている。
「日暮神社」と達筆で書かれている。
社の周りにはあら塩がまかれていた。
音無神社より日暮八幡社の方が小さかったけど、独特の不思議な気を感じた。

神社左手には祠もあった。
■日暮八幡神社
静岡県 静岡県伊東市桜木町一丁目2番10号
(詳しくは一つ前のブログを参照してね)
 音無神社から見える対岸の「ひぐらし会館」
音無神社から見える対岸の「ひぐらし会館」せっかくなので「岡橋」を渡って日暮八幡社へ行ってみようと川沿いをあるくと、
野良猫が欄干で昼寝をしていた。

なんともほのぼのしている風景である。
 岡橋の欄干 青い空と共に美しい
岡橋の欄干 青い空と共に美しい 橋には頼朝と八重姫の逢瀬のレリーフが・・・
橋には頼朝と八重姫の逢瀬のレリーフが・・・ 欄干から二つの神社を・・・
欄干から二つの神社を・・・右側は音無神社 左側が日暮八幡社

日暮八幡社はひぐらし会館の向かいの公園の奥にあり、音無神社から比べると、小さい。
 こちらにも由来の看板が。
こちらにも由来の看板が。短いバージョンと長いバージョンがあった。
「ひぐらしの森と
日暮八幡神社」
日暮(ひぐらし)の森は、若き日の流人源頼朝
が、伊東祐親の娘八重姫との逢う瀬を楽しみに、
日暮し過ごしたというロマンスの伝承を秘めて
いる場所で、明治中期の絵図では、田んぼの中に
大きくこんもりと繁った日暮の森が川のふちまで
続いている。
この周辺の発掘調査により、弥生時代(約二千
年前)から古墳時代(約千五百年前)にかけての
集落群が発見され、日暮(ひぐらし)遺跡と名づ
けられて、出土品の一部は伊東市文化財セン
ターに展示されている。
この神社の創建年月の明らかな記録は無いが、
古くから村民の五穀豊穣、家内安全、安産の守護
神として崇敬されてきた。
祭神 誉田別命(ほむたわけのみこと)
傍祭日 九月十五日
平成十一年記 伊東市教育委員会



「日暮神社 ひぐらしの森 由来」
源頼朝は、伊豆流人の約二十年の一時期、
伊東の「北の小御所」に暮らした。その時、
伊東領主・伊東祐親の娘八重姫とのロマン
スが生まれたのである。二人は対岸の音無
の森で逢瀬を重ね、その折頼朝が日暮れを
待ったのが、ここひぐらしの森であったと
伝えられている。
二人の愛は、一子千鶴丸の誕生を迎えた
が、平家をはばかる祐親の激怒に触れ、仲
を引き裂かれ、多くの悲劇の中ではかなく
消え去った。
最近のひぐらしの森付近の考古学調査によ
ると、弥生時代前期(二千年前)から古墳
時代前期(千七百年前)に及ぶ遺跡が発見
され、勾玉・壺・石斧等と共に、当時
の墓も発掘され、まさにひぐらしの森は、
先人達の生活の場であったことを物語って
くれている。
この森の最も古い記録は、文禄三年
(一五九四年)午、八月の「岡村差出帳」であ
る。同書によると、頼朝とのかかわりの事
蹟を伝え、「道法、村より四町御座候」と
記録している。(当時は名主の家を中心に
道法を出していて、その頃の名主は瓶山下
の堀井家であったと考えられる。)
また嘉永年中の「伊東誌」によると、こ
の地に程近い所に、日暮山龍明寺という寺
があったと伝え、建久三年(一一九二年)
八月十五日に頼朝が、寺領五十三石を永久
の祈願料として与えたと記している。
このような点から、鎌倉幕府創建の人、
頼朝にとって生涯の忘れ得ぬ思いで深い森
であったと想像出来る。
日暮神社は、祭神「誉田別命」が、村民
の五穀豊穣、縁結び、安産の守護神として
崇敬され「日暮八幡」として祀られた。
神社として風格を現したのは江戸時代中期後で、
以来地域住民の氏神として篤く信仰される
に至ったのである。
 「日暮神社」と達筆で書かれている。
「日暮神社」と達筆で書かれている。社の周りにはあら塩がまかれていた。
音無神社より日暮八幡社の方が小さかったけど、独特の不思議な気を感じた。

神社左手には祠もあった。
■日暮八幡神社
静岡県 静岡県伊東市桜木町一丁目2番10号










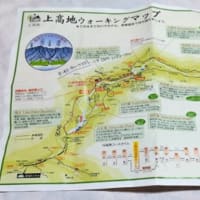














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます