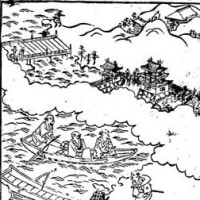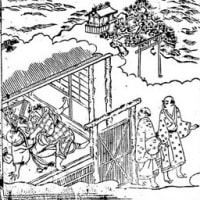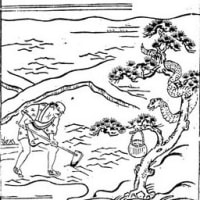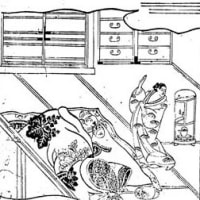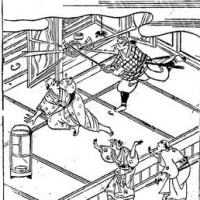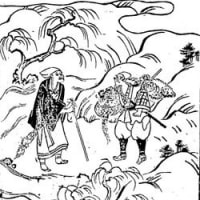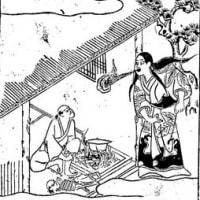ご訪問ありがとうございます→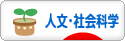 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
↓今回は、この文章の続きです
「天然の奇人・和蘭人の化物」
江戸の雰囲気を味わいたくて古文書解読の勉強を始め、1年少し経って、楷書に近く、平仮名の多い文書なら何とか読めるようになったのが、駄文の頃です。
しかしまだまだ、草書で、しかも平仮名が使われていない和漢文(注参照)の文書は半分も読めなかったのですが、いつかは読めるようになりたいと、引き続き勉強に精出していました。
(注)和漢文
ほぼ漢字のみで書かれている文書だが、私たちが国語の授業で習う「漢文」とは違い、日本人が作り上げた、漢文に似てはいるが、文法や語句が本来の漢文とは違う、いわば和製の漢文。中世以降、公文書によく使われ、江戸時代からは、広く文書に用いられるようになった。
そして、この駄文を綴ったのが2013年11月ですから、それから3年半が経過しました。
梅雨の中休み、大分県立先哲資料館と、臼杵市歴史資料館へ出かけてまいりました。
大分県立先哲史料館では昨年新たに収蔵された資料を、また臼杵市歴史資料館では臼杵藩主が参勤交代をした様子を、多くの図説とともに、記録されている文書も、数多く展示されており、当時の様子がよく分かる内容でした。
もちろん、私の目的の一つは、展示されている古文書をできる限り読んでやろうということで、鼻息荒く出かけて行ったのですが・・・
ほとんど読めました。
書かれている文字の95%くらい、物によっては100%完璧に。いや~、嬉しかったですね~。
嬉しさのあまり、誰かに読んで聞かせたいぐらいでしたが、周りは知らない人たちばかりだし、聞かされる方はたまったものではないでしょうから、自制しておきましたが。
古文書を読みたいと思って勉強を始めたのが、かれこれ5年近く前。
1年半ほどで、十返舎一九の戯作本など、ひらがなの多い文書は読めるようになりましたが、漢字ばかりの文書には全く歯が立たず、ネットから拾ってきた資料を見ても茫然とするばかりでした。
あまりにも高い壁を前に、もう、ここで止めようかとも思いましたが、まあ、やるだけやってみて、無理だと思ったところで止めればいいやと、無謀なもう一歩を踏み出しました。
が、思っていたより壁は高く、ひらがなが読めるようになるには1年ちょっとだったものが、和漢文が読めるようになるには3年以上かかってしまいました。それでも、昨日読めなかったものが今日は読めた、ということの繰り返しで、遂に、95~100%の読解率となったわけで、まさに継続は力なりです。
ただ、展示されている文書は公文書のようなもので、右筆や、それなりの教養を備えた役人の手による、比較的きれいな文字ばかりですが、もちろん古文書はそうしたものばかりでなく、癖字や、殴り書きに近い文書も数多くあり、まだまだ私の技量では、そのような文書を読むことは叶いません。
また和漢文でない、本物の漢文で書かれた文書は、そもそもチンプンカンブンでした。
さらには、江戸時代の文書は読めるようになったのですが、それ以前の、中世の文書は、書体も文体も違い、なかなか読めません。
要するに、「読めた読めた」と威張ってはいますが、そもそも「読みやすい」文書だった、というに過ぎないのが、悔しいところです。
さて今後、癖字や殴り書きの壁は、楽観的に、いつか越えられるものと、挑戦していこうと考えています。
その後、本物の漢文に挑戦するかどうかは・・・その時に決めましょう。
↓今回は、この文章の続きです
「天然の奇人・和蘭人の化物」
江戸の雰囲気を味わいたくて古文書解読の勉強を始め、1年少し経って、楷書に近く、平仮名の多い文書なら何とか読めるようになったのが、駄文の頃です。
しかしまだまだ、草書で、しかも平仮名が使われていない和漢文(注参照)の文書は半分も読めなかったのですが、いつかは読めるようになりたいと、引き続き勉強に精出していました。
(注)和漢文
ほぼ漢字のみで書かれている文書だが、私たちが国語の授業で習う「漢文」とは違い、日本人が作り上げた、漢文に似てはいるが、文法や語句が本来の漢文とは違う、いわば和製の漢文。中世以降、公文書によく使われ、江戸時代からは、広く文書に用いられるようになった。
そして、この駄文を綴ったのが2013年11月ですから、それから3年半が経過しました。
梅雨の中休み、大分県立先哲資料館と、臼杵市歴史資料館へ出かけてまいりました。
大分県立先哲史料館では昨年新たに収蔵された資料を、また臼杵市歴史資料館では臼杵藩主が参勤交代をした様子を、多くの図説とともに、記録されている文書も、数多く展示されており、当時の様子がよく分かる内容でした。
もちろん、私の目的の一つは、展示されている古文書をできる限り読んでやろうということで、鼻息荒く出かけて行ったのですが・・・
ほとんど読めました。
書かれている文字の95%くらい、物によっては100%完璧に。いや~、嬉しかったですね~。
嬉しさのあまり、誰かに読んで聞かせたいぐらいでしたが、周りは知らない人たちばかりだし、聞かされる方はたまったものではないでしょうから、自制しておきましたが。
古文書を読みたいと思って勉強を始めたのが、かれこれ5年近く前。
1年半ほどで、十返舎一九の戯作本など、ひらがなの多い文書は読めるようになりましたが、漢字ばかりの文書には全く歯が立たず、ネットから拾ってきた資料を見ても茫然とするばかりでした。
あまりにも高い壁を前に、もう、ここで止めようかとも思いましたが、まあ、やるだけやってみて、無理だと思ったところで止めればいいやと、無謀なもう一歩を踏み出しました。
が、思っていたより壁は高く、ひらがなが読めるようになるには1年ちょっとだったものが、和漢文が読めるようになるには3年以上かかってしまいました。それでも、昨日読めなかったものが今日は読めた、ということの繰り返しで、遂に、95~100%の読解率となったわけで、まさに継続は力なりです。
ただ、展示されている文書は公文書のようなもので、右筆や、それなりの教養を備えた役人の手による、比較的きれいな文字ばかりですが、もちろん古文書はそうしたものばかりでなく、癖字や、殴り書きに近い文書も数多くあり、まだまだ私の技量では、そのような文書を読むことは叶いません。
また和漢文でない、本物の漢文で書かれた文書は、そもそもチンプンカンブンでした。
さらには、江戸時代の文書は読めるようになったのですが、それ以前の、中世の文書は、書体も文体も違い、なかなか読めません。
要するに、「読めた読めた」と威張ってはいますが、そもそも「読みやすい」文書だった、というに過ぎないのが、悔しいところです。
さて今後、癖字や殴り書きの壁は、楽観的に、いつか越えられるものと、挑戦していこうと考えています。
その後、本物の漢文に挑戦するかどうかは・・・その時に決めましょう。