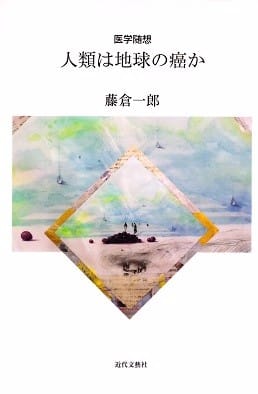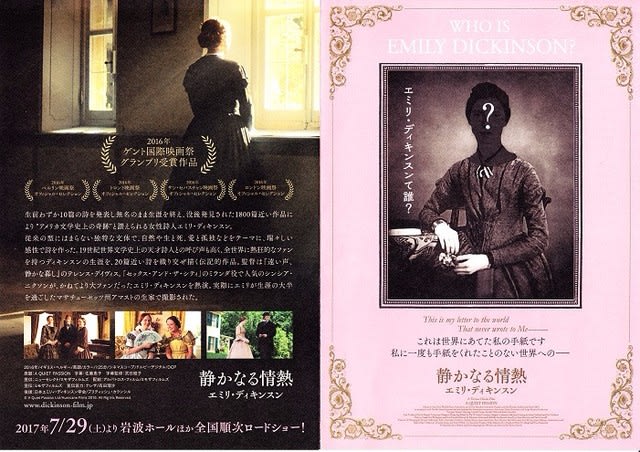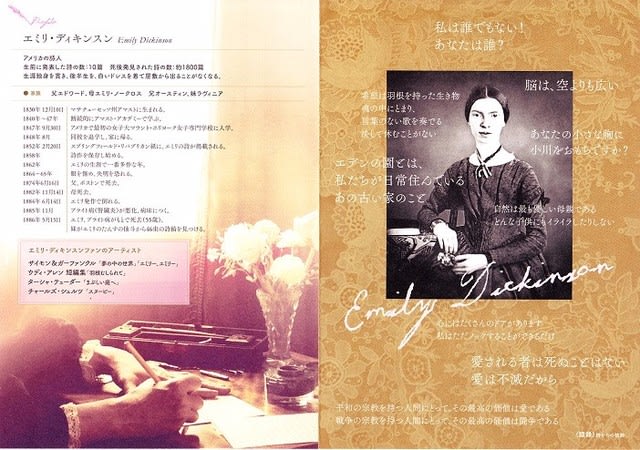8/18(金)、千葉劇場にて。監督アンヌ・フォンテーヌ。フランス語、ポーランド語、ロシア語。原題は『Les Innocentes』でフランス語だが、英語の「innocence(純潔)」と考えていいだろう。実話を基にした作品だという。
1945年12月、ポーランドのとある田舎にあるカトリック修道院。ドイツめざして進駐してきたソ連兵に集団暴行を受けていたシスターたちの中で7人が懐妊し、出産の日を迎えようとしていた。命の危機を回避するため、ひとりの修道女が、フランス赤十字の女医マチルドに必死に助けを求める。彼女は、事実の残酷さに打たれながらも、なんとか新たな命の誕生を助けようとするが・・・。
ヨーロッパという複雑な地域の抱える諸問題―宗教・言語・習慣などを巧みに織り込みつつ、性、あるいは人の宿命的な苦しみを描いた優れた作品だった。アンヌ・フォンテーヌという女性監督は、1959年ルクセンブルクの生まれで、フランスで主に活動しているらしい。この人の作品を観るのは初めてだったが、アンジェイ・ワイダ亡きあとのヨーロッパ映画界を支えるだけの力量があるのではないか、と感じた。


主演のルー・ドゥ・ラージュ他、女優達の演技は真に迫り秀逸。単なる演技ではなく、なにか使命感のようなものさえも感じた。演劇界のことは詳しいわけではないが、日本の俳優さんであんな演技が出来る人がいるかなあ、と残念ながら考えざるを得なかった。
1945年12月、ポーランドのとある田舎にあるカトリック修道院。ドイツめざして進駐してきたソ連兵に集団暴行を受けていたシスターたちの中で7人が懐妊し、出産の日を迎えようとしていた。命の危機を回避するため、ひとりの修道女が、フランス赤十字の女医マチルドに必死に助けを求める。彼女は、事実の残酷さに打たれながらも、なんとか新たな命の誕生を助けようとするが・・・。
ヨーロッパという複雑な地域の抱える諸問題―宗教・言語・習慣などを巧みに織り込みつつ、性、あるいは人の宿命的な苦しみを描いた優れた作品だった。アンヌ・フォンテーヌという女性監督は、1959年ルクセンブルクの生まれで、フランスで主に活動しているらしい。この人の作品を観るのは初めてだったが、アンジェイ・ワイダ亡きあとのヨーロッパ映画界を支えるだけの力量があるのではないか、と感じた。


主演のルー・ドゥ・ラージュ他、女優達の演技は真に迫り秀逸。単なる演技ではなく、なにか使命感のようなものさえも感じた。演劇界のことは詳しいわけではないが、日本の俳優さんであんな演技が出来る人がいるかなあ、と残念ながら考えざるを得なかった。