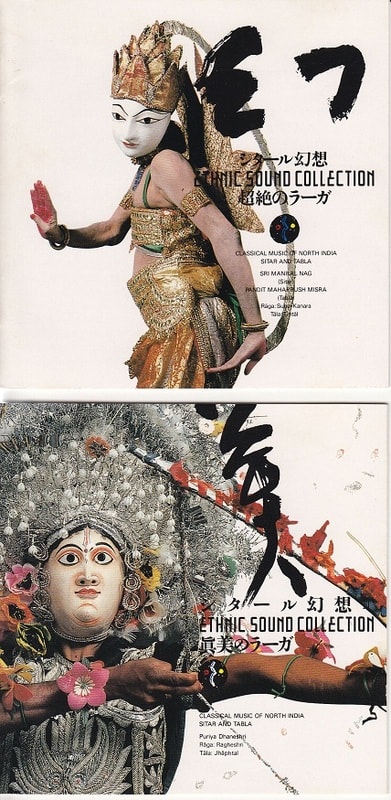しかし、未曽有の災害だったとはいえ電気の供給量が少なくなるくらいで首都圏がこれほど混乱するとは思わなかった。
昨日は、千葉県内の電車はほとんど止まってしまった。しかも、JRが電車を止める決定をしたのが始発の約1時間前だったというのだから利用者は戸惑うばかりだ。こういう事態に備えて優先順位をあらかじめ決めておかなかったのだろうか。スーパーやホームセンターに行ったが、生活必需品はみな争うように買うので、米・カップめん・缶詰類は早々に棚から消え、電池やトイレットペーパーも夕方には無かった。駅のショッピングセンターは、従業員が来られないため臨時休業。
寝たきりの母は介護ベッドなので、電気が止まるとベッドは動かなくなり手動操作はついていないのでお手上げだ。正確な停電時間と地域が知りたいのだが情報は錯綜している。エアーマットは災害対策仕様なので、2日位は空気が抜けることは無いということなのでとりあえずは安心だが、東北の被災した人たちの中にも母のように介護ベッドを必要としている方も多いだろう。早く対応してもらいたいものだ。
神保町の岩波ホールで、映画を観たのは地震前日の3月10日だった。今日あたりも東京の映画館や寄席などの娯楽施設はしまっているだろう。一日ずれていたら、と思うとぞっとする。東京の危うさを身に染みてわからせてくれた地震だった。

タイトルとはうらはらに重い映画だ。岩波ホールを出た後足が重くなったように感じた。もっとも、英題は『On The Path』になっていて特に「希望」を表す表現は無い。
宗教・生活習慣・言語・風習・・・・様々な民族的文化の違いを人は乗り越えられるのか。あるいは、乗り越えられないのか。
仲の良かった恋人同士が、やがて文化的差異による溝を深めてゆき、妊娠した女に男は「産んでくれ、あんなに欲しがっていたじゃないか」と言い、女は「あなたの子を産む気はないわ」と言い放ち背を向けて去ってゆく。「帰ってくれ」とすがるように叫ぶ男。「あなたこそ帰って」と一言言い残して女が「街角」から消えてゆくシーンで映画は終わる。そこにあるのは、理解し合うことの困難さと心に残る虚しさ。
それにしても、主演したルナ役のズリンカ・ツヴィテシッチという女優さんの演技には圧倒された。日本であれだけの演技が出来る俳優さんはいるだろうか。
岩波ホールでサラエボを舞台にした映画を観るのはこれが3本目だ。『パーフェクトサークル』、『サラエボの花』、そしてこの『サラエボ、希望の街角』。後者2本はヤスミラ・ジュバニッチという女性の監督の作品。どれも優れた作品だが、そこに映し出された映像を見る限りサラエボの復興はかなり進んでいるように見えた。しかし、街がきれいに整備されてゆくのと逆行するかのように、文化的には溝が深まってゆくかのような現実的危機をこの映画からは感じざるを得なかった。
昨日は、千葉県内の電車はほとんど止まってしまった。しかも、JRが電車を止める決定をしたのが始発の約1時間前だったというのだから利用者は戸惑うばかりだ。こういう事態に備えて優先順位をあらかじめ決めておかなかったのだろうか。スーパーやホームセンターに行ったが、生活必需品はみな争うように買うので、米・カップめん・缶詰類は早々に棚から消え、電池やトイレットペーパーも夕方には無かった。駅のショッピングセンターは、従業員が来られないため臨時休業。
寝たきりの母は介護ベッドなので、電気が止まるとベッドは動かなくなり手動操作はついていないのでお手上げだ。正確な停電時間と地域が知りたいのだが情報は錯綜している。エアーマットは災害対策仕様なので、2日位は空気が抜けることは無いということなのでとりあえずは安心だが、東北の被災した人たちの中にも母のように介護ベッドを必要としている方も多いだろう。早く対応してもらいたいものだ。
神保町の岩波ホールで、映画を観たのは地震前日の3月10日だった。今日あたりも東京の映画館や寄席などの娯楽施設はしまっているだろう。一日ずれていたら、と思うとぞっとする。東京の危うさを身に染みてわからせてくれた地震だった。

タイトルとはうらはらに重い映画だ。岩波ホールを出た後足が重くなったように感じた。もっとも、英題は『On The Path』になっていて特に「希望」を表す表現は無い。
宗教・生活習慣・言語・風習・・・・様々な民族的文化の違いを人は乗り越えられるのか。あるいは、乗り越えられないのか。
仲の良かった恋人同士が、やがて文化的差異による溝を深めてゆき、妊娠した女に男は「産んでくれ、あんなに欲しがっていたじゃないか」と言い、女は「あなたの子を産む気はないわ」と言い放ち背を向けて去ってゆく。「帰ってくれ」とすがるように叫ぶ男。「あなたこそ帰って」と一言言い残して女が「街角」から消えてゆくシーンで映画は終わる。そこにあるのは、理解し合うことの困難さと心に残る虚しさ。
それにしても、主演したルナ役のズリンカ・ツヴィテシッチという女優さんの演技には圧倒された。日本であれだけの演技が出来る俳優さんはいるだろうか。
岩波ホールでサラエボを舞台にした映画を観るのはこれが3本目だ。『パーフェクトサークル』、『サラエボの花』、そしてこの『サラエボ、希望の街角』。後者2本はヤスミラ・ジュバニッチという女性の監督の作品。どれも優れた作品だが、そこに映し出された映像を見る限りサラエボの復興はかなり進んでいるように見えた。しかし、街がきれいに整備されてゆくのと逆行するかのように、文化的には溝が深まってゆくかのような現実的危機をこの映画からは感じざるを得なかった。