
四.大師、化身して楊胭脂の難を避く
年老いた大師は、武帝と神光を救い損ねて暫くは慨嘆していましたが、やがて東緑関(とうりょくかん)に向かって歩き始めました。関内に入ると、一人の婦人に遇り逢いました。その婦人の名は楊胭脂(よういんし)と言い、大師が来られたのを見て
「老僧は何処から来られ、そして何処へ行かれるのですか」
と問いました。
大師は、度重なる失敗に懲りて、余り気乗りがしなかったが
「私は西域からやって来て武帝と神光とを救おうとしたのですが、二人とも縁に欠けているので、また西へ帰るところです」
と答えました。
これを聞いた楊胭脂は、この人は相当有徳な非凡の僧に違いないと思い、自宅に迎えて大いに歓待して上げれば決して損はないと心に邪心を抱き
「どうぞ、私の家にお越し下さい。私は幼い時から佛法に帰依して經堂を持っています。ここでご静養いただければ幸いでございます」
と言いました。
大師は、この婦人に邪念があるのを視透しましたが、人の心を試すのも一つの法と考え、招じられるままに楊胭脂の經堂に案内されました。楊胭脂は、大師を法座に上らせ、自分は法座の下に跪き大師を礼拝して申しました。
「弟子楊胭脂は、多年に亘って斎戒を持して参りましたが、未だ明心見性の域に至っておりません。今日縁がございまして、ここに明師のご降臨を仰ぐことができました。これは、終世の幸せでございます。私はここに喜んで願を立て、老師の徒(でし)になりたいと存じます。願わくば師のご慈悲を蒙り、私を徒とされ、正法を開示下さいますようお願い申し上げます」
大師「今、汝が願を発して道を求めたことは小さい事ではない。しかし女の体は穢れ多く、また愆(つみ)も多いので、正法を得るためには、更に天のように高く海のように深い大願を発し、三皈五戒(さんきごかい。三皈は仏・法・僧に皈依すること。五戒は殺・盗・淫・妄・酒の戒め)を堅持し、正しい念を強く抱いて行わなければならない。もし願に違えば、反って墜落(地獄に墜ちること)の目に遭うだけで萬劫(まんごう。永遠に)救われ難いであろう。よくよく考えた上で行なうことが賢明であり、軽々しく誓願を立てるべきではない」と嗜(たしな)めました。
断られると逆に思いの募るのが人情というもので胭脂は、大師の言葉を聞いて、また一段と辞を低くして申し上げました。
「佛を証(あかし)として願を立てさせていただきます。もしも私が法を得てより師の恩を忘れ、規(のり)や戒律を守らず、中途で道から退嬰(たいえい)するようなことがあれば、永遠(とこしえ)に苦海(塵界)に沈み萬劫三界を越えられません。是非お助け下さいませ」
しかし大師は、楊胭脂の心に虚(いつわ)りがあるのを見抜いて、僅かに幾句かの偈を告げ語られました。
「若(も)し三苦(さんく。三界)に在(あ)って正法を求めようとすれば、只ひたすら身中の動静の功を明らかにすべきである。
法は萬物を生じ、三界を穿つ。道は天地を包み、虚空に満ちる。
骨を穿ち髄に透り至らざる所なく、八方に応現してその妙、窮りなし。
四大(しだい。地水火風)に周流してこれを眞の主とし、内に形相なく、外に踪(あとかた)もなし。
常に三家(道・儒・佛の各開祖)と相會う。内外一体であって共にその金容を現わす」
楊胭脂は感激して、熱心に聞き入っていました。大師は更に言葉を続け
「人法両(ふたつ)を忘れるのは、これ即ち眞空である。活発動静(どうじょう)、允(まこと)にその中(ちゅう)を執れ。自家の眞人を認め透すことが出来れば、詔を待って極楽宮に飛昇することが適う」
胭脂は大師の法話を一言一句も洩らすまいと熱心に耳を傾け、その全てを記憶に留める努力を重ねる日々を何日か過ごしました。こうして大師から傳授された言葉を口授心印と錯覚した胭脂は、遂に本性を暴露し始めました。
――これで私も、明師と同じ位になった。明師の実質的な後継者は私である。天下に並ぶべき人がいない今は、大師が生きていては邪魔である。老師を毒殺してしまおう。大師を殺してしまえば、かの有名な武帝や神光がやって来て私を師と仰ぐことになろう。そうなれば、眞に光栄の至りである――
このように考えて胭脂は、大師を毒殺する機會を窺っていました。大師は始めから胭脂の心を見抜いておりましたが、わざとその謀(はかりごと)に掛かろうとされました。
或る日、楊胭脂は飲み物の中に毒を盛って大師に捧げました。大師は事前に片方の草履(ぞうり)を脱いでそれを自分の化身とし、わざと胭脂が捧げた毒入りの飲み物を飲み、死を装った化身だけを残し、ご自身は身を隠してしまわれました。
楊胭脂は、大師が亡くなったのを知って喜びながらも表面は嘆き哀しみ、葬儀一切を済ませた後、大師の亡骸(なきがら。実は大師の化身である草履の片割)を東緑関の郊外に埋葬しました。
大師は残りの片方の草履を手に持って東緑関を出て、歩きながら胭脂の一件を大いに嘆じ、偈を作ってその心を表しました。
「婦女を歎く。迷昧多く、自性(じしょう)を明らかに出来ない。
既に回心(改心)して斎戒を持してはいても、未だ生死を究めることが出来ない。
全く五漏(ごろう)の体(たい)は罪過甚だ大であるにも関わらず、そこまで思いを致すことがない。
前劫に際して迷昧することが多かったために、修行することを知らない。
故に女身に変じ、いろいろ不便多く難儀して尽きることがない。
三従(さんじゅう。婦人の従うべき三つの事柄、即ち家にあっては父母に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う)四(しとく。婦人の守るべき四つの、即ち婦徳、婦言、婦容、婦工)に従い、命を人に聴く。
楊胭脂が既に我に出會ったことは、三生の幸があると言える。
今まさに一貫不二の法門を求めようとする。
我、胭脂をよく観察すると、口は達者であるが、心はこれに反して正しくない。
このような者に、正法を軽々しく傳授するわけには行かない。
禅の奥義について話を合わせられることを幸いに、吾を毒殺することを思い立ち、そしてあわよくば人の師となろうと考えた。
これらの点から推察するに、我が来た時は一条の路經があったが、
我が去った後は、数知れぬ宗門をぞくぞく輩出する虞が多分にある。
更に信心の固い人を捜し出し、道統の後継ぎを定めねばならない。
慧眼によって四部州を見渡しても、そのような人は一人もいない。
只、那(か)の神光のみが信ずるに足る人物と思われる。
我、再び彼の許に去(ゆ)き、転化することなければ、
他に人を訪ねて度そうとしても、枉(むだ)であろう」
五.大師、再び化身して神光を覚ます
間もなく大師は、一旦身を退き、嵩山(すうざん。中国河南省北部にある山)の北麓にある少林寺に暫く寄寓して、道脈の行く末を案じられました。
密(ひそか)に思われるに・・・天命を体して東土に来ながら縁者を得ずして、どうして復命できようか。このままの状態では、足に任せて全国に有縁を求めても所詮は無駄に過ぎない。名の高い梁の武帝と徳の高い神光を除いて、果たしてこの国に道の後継者として相応しい人物がいるであろうか。そうだ、神光を除いて他には私から道脈を受け継ぐ人はいない。どうしても、神光を捨て去ることはできない・・・このように決断された大師は、ある方法を心に秘めて黙すること暫し、手に持った数珠から十個の珠を外し、地に撒きました。すると忽ち十個の球は、地獄十殿の各閻君に化身してしまいました。
これらの化身した十殿閻君は、飄然と洛陽に現れ、神光が丁度法話を始めようとする寸前に法台の前に立ちはだかり、神光の登壇を遮りました。神光は台に登ることができず、良く見ればそこに十位の秀士が並んで立っているので、訝しげに声を掛けました。
「各位は、何処の方々ですか。私の説法を聞きに来られたのですか」
十位の閻魔は首を振り、声を揃えて
「我われは、幽冥地獄におる十殿閻君である。汝の法話を聞きに来たのではない。汝の陽寿(寿命)が既に満ちたことに因って、ここに来たのである。今から汝の生魂を連れて行くために、地獄から特別に出向いて来たのである。跟(つ)いて来るがよい」
神光は、びっくり仰天して
「私は曾て説法して衆生を度すこと四十九年の間、窮りなき辛苦を重ねてきました。従って、無量の功徳を積んでいる筈です。それでも、閻君の手を躱すことができないのですか」
「どんなに法を説き經典を講ずるとも、我われの手を避けることはできない」
「天下で、あなたがたの手を經なくてもよい人はいないのですか」
「今、天下に只一人の人を除いては、我われの手を躱す事はできない」
「只一人の人とは誰ですか」
「その人は、汝もよく存知の前日此処に来た達摩大師と言う、黒い顔をした和尚である」
「どうしてその和尚だけが、あなたがたの手から逃れることができるのですか」
「それは、天命を受けているからです」
「天命とは何ですか」
「天命とは、上天の特命を奉じて道脈を受け継ぎ、時代を治め、人々の心眼を點破し、口授心印を以って人の生死を解脱させ、究竟涅槃(くきょうねはん)に至る法を授ける御命のことです」
「その法を得れば、誰でも生死を脱れ、地獄のあなたがたの手を躱すことができるのですか」
「そうです。しかしその法は誰にでも傳えられるものではなく、単傳独授のままに傳えられています。その法を直接得た人は、即身成佛を得、人であっても既に人ではありません。一般に説法修行するに留まる人は、ただひたすら口頭三昧の念佛を唱え妄修瞎練(もうしゅうかつれん。専ら偽道邪教を信じること)こそすれ、心傳の眞法を求めようとはしません。一般の修行者は、口では自分こそ脱れることができると言っているが、その実我われの手を脱することができないのです」
神光は、これを聞いて、気も転倒しそうになりました。そのとき一人の閻君が、むんずとばかりに神光の胸倉を捉えて言いました。
「もう時刻です。我われに跟いて来なさい」
神光は自分が縁を失ったことに気付いて周章狼狽し、急いで両手を地に着き
「どうか私の罪を許して、死を逃れさせて下さい」
「それはできません」
「それでは私がこれから直ちに達摩大師を追って行きますので、大師からご指示を受けるまでの間暫しの猶予をお与え下さい」
「縁は、熟する時と熟さない時とがある。その時まで待つことはできない」
「では私に、三日間だけ猶予を与えて下さい。それを過ぎれば、ご命令に従います」
「よかろう。では汝の四十九年間の説法、勧導の功徳に免じて三日間の猶予を与えよう」
神光は咄嗟(とっさ)にその場に平伏し、熱涙を流して感激しました。ややあって頭を上げて見ると、十位の閻君は忽然と消えていました。神光は深く謝恩して身を起こし、荷物の準備もなく、法台も踏み倒して急いで大師の後を追い掛けようとしました。
これを見た人天百萬の弟子たちは、神光の前に立ち塞がり、各々神光の手足に取り縋って
「師父よ。我々を捨てて一体何処へ行こうとなさるのですか。その後我々は、一体誰に救いを求めればよいのですか」
それでも神光は皆を振り切って行こうとしましたが、誰もが泣き叫んで行かせようとはしません。
「私は生死を超脱する道を得るために、どうしても大師を追い掛けて行かなければならないのです」
「では我々は、誰を主と仰げばよいのですか。主は、何時お帰りになられますか」
神光は、逸(はや)る心を抑え
「皆、落ち着いて私の言葉を聞くがよい。今の私は、一心に眞傳を求める気持ちで一杯です。今までの私は、終日法を説くことはできても、実は未だに正法を得ていないのです。自分の生死が救えなくて、どうして他人の苦厄を滅することができるでしょう。後日正果を成就することができた暁には、必ず皆様を度(すく)って涅槃(ねはん)を証させましょう。師と弟子の情愛は、私とて変りはありません。しかし今捨て難い情愛を捨てなければ、共に地獄に落ちなければなりません」
切々たる神光の声涙下る言葉を聞いて一同は、一層声を張り上げて別れの寂しさを訴えました。神光は、一同に向かって
「では皆、静かにして私の最後の嘱咐(ことづけ)を聞くがよい。そして各自が家に帰った後もこの嘱咐を胸に秘め、不退転の決意を以って私が帰るまでの心得としてもらいたい」
そして神光は、おもむろに次のような嘱咐を申し渡しました。
「一つに嘱咐す。佛に帰依するには、完全に眞心に頼るようにしなければならない。
恩を貪り、愛に恋(ひ)かれ、名利を争うような事があってはならない。
大衆に勧める。佛と共に、常に親しくし常に近付くように心掛けなさい。
四時(子・卯・午・酉)の中に信香を焚き、佛恩に報答しなさい。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。無明が未だ尽きることない故である。
大衆に勧める。煩(わずら)いに耐える必要があることを牢(かた)く心に刻みなさい。
二つに嘱咐す。法に帰依するには、佛規を厳格に遵守しなければならない。
二六時中、功果に勤め、法によって修行に励みなさい。
この帰戒は、修行者の大いなる把柄(とりえ)である。
雑念を起こし、物事を胡(みだ)りに為し、乱(みだ)りに行なうことのないよう切に願う。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。神気を既に消耗し尽くした故である。
大衆に勧める。常に存養することを牢く心に刻みなさい。
三つに嘱咐す。僧に帰依するには、清静を学ぶことが肝要である。
佛門に投じ清規を守り、別に旁門を開くような事があってはならない。
有為の法、夢幻泡影を学ぶことのないよう切に願う。
あるいは静坐し、あるいは観空して雑念を生ずる事のないようにしなさい。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。自らの性が未だに明らかでない故である。
大衆に勧める。相を飛ばすことが必要であると牢く心に刻みなさい。
四つに嘱咐す。殺生を戒め、仁徳を本とすること。
西天の佛は、全てこれ慈悲の大仁である。
修行の人は、生霊と仇恨を結ぶような事があってはならない。
地獄の苦しみを免れ得て、初めて輪廻転生を免れることが出来る。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。寃孼(えんげつ。業罪)甚だ太(おお)い故である。
大衆に勧める。多く放生(ほうしょう。生命あるものを大事にすること)すべきことを牢く心に刻みなさい。
五つに嘱咐す。偸盗(ちゅうとう)を戒め、義を以って本としなさい。
一根の草、一条の線(いと)たりと雖も、各々に持ち主がある。
他人が来て我を虧刻(そこな)えば、我はこれを耐え忍ぶことが難しい。
我が人を虧刻えば、人はこれを許さず、禍根の種を蒔くこととなろう。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。刻薄(こくはく。冷酷)甚だしい故である。
大衆に勧める。道は厚き志を持して行なうべきことを牢く心に刻みなさい。
六つに嘱咐す。邪淫を戒め、名節を本とすること。
修道の人は、関睢(かんしょ。周の文王夫妻の家庭和楽のを讃えて詠じた詩經)に傚い、快楽を求めて邪淫に溺れるような事があってはならない。
西施(せいし。越国春秋の美人。呉王夫差の寵姫)に賽(まさ)る美貌の持ち主であっても、淫(おぼ)れれば畜生道に堕ち、禽蠢(きんしゅん。鳥や虫)と作(な)るであろう。
欲念を起し、本眞を喪失するような事がないよう切に願う。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。欲念が尽きない故である。
大衆に勧める。色(しき。色情)これ空なることを牢く心に刻みなさい。
七つに嘱咐す。酒肉を戒め、清濁を混じえることなかれ。
酒は性を乱し、肉は性を濁す。佛の道を汚穢(よご)してはならない。
二六時中あるいは經を念じ、あるいは静坐するようにしなさい。
眞に欲念を断ち、明心見性することが肝要である。
我は閻君を躱すことが出来ない。心に純静が少ない故である。
大衆に勧める。精進のものを食することを牢く心に刻みなさい。
八つに嘱咐す。妄語を戒め、信ある言を発するよう心掛けなさい。
五戒を守り、五常を貫き、また五行を貫くよう努めなさい。
諸行萬物全て、信によって運化されないものはない。
我は閻君の手を躱すことが出来ない。未だに性(しょう)、高ぶり傲(おご)る故である。
大衆に勧める。血性(けつせい)を低くすることを牢く心に刻みなさい。
九つに嘱咐す。紅福、富貴の物を修める者達よ。
今より後は、八徳(孝・悌・忠・信・禮・義・廉・恥の徳目)を体し、更に五倫(人の守るべき道、即ち、君臣義あり、父子親あり、夫婦別あり、長幼序あり、朋友信あり)を体すよう努めなさい。
花斎・月斎(かさい・げっさい。斎食の総称)を食するのは、随意である。
人の上に立つよう修め、智慧光明と輝くように努めなさい。
我が達摩の後を追って行くのは、只性命の指示を求める為である。
大衆に勧める。広く済(すく)い施すことを牢く心に刻みなさい。
十に嘱咐す。諸々の善人、常に行を講ずるよう心掛けなさい。
大善を行ない、小善を行ない、力の量(かぎ)りに行(つと)めること。
財ある人は財を捨てる必要あり、済(すく)い施しを吝(おし)んではならない。
財の無い者は方便を行ない、勤めて功行に励むようにしなさい。
我が達摩の後を追って行くのは、心印の指示を求める為である。
大衆に切に仰(ねが)うのは、各々功を立て同(とも)に彼岸に登ることである」
嘱咐する神光の両眼から涙が酒々(しゃしゃ)と流れ、また弟子の中からも嗚咽(おえつ)が洩れ、胸が締め付けられるようでしたが、神光はきっぱりと衆徒に別れを告げ、一路大師を追うために出発しました。
途中で人に訊きながら、やっと東緑関に到着しました。ここで大師が一婦人の家に立ち寄ったことを聞いて、その家を訪れました。
楊胭脂は、高名な神光の突然の訪問を受けてその眞意を量りかね、不審そうにしておりました。神光は、性急に言葉を発しました。
「聞けばこちらへ一方の色黒で髯の多い老和尚が立ち寄られたと承って参りましたが、只今もいらっしゃいますか」
楊胭脂は、これを聞いて
「先日、そのような老僧が私の茅屋(あばらや)にお出で下さり、七日間を過ごされました」
「今その老僧は、どちらに在(お)られますか」
楊胭脂は、哀しそうな表情を作り
「重い病に罹って、急にご遷化(せんげ。昇天)なさいました」
神光は、肝を潰さんばかりに吃驚(びっくり)して
「それでは、老僧は何れに葬られましたか」
「謹んで、東緑関の郊外に葬らせていただきました」
これを聞いて神光は、痛く嘆き哀しみ、胸を捶(たた)いて自分の無縁を後悔し
「ここまで来たのに、何故明師に去られてしまったのか」
と深く激しく泣き悶えました。生死一大事の問題であるだけに、無理からぬことです。
暫くの間神光の嘆き哀しむ様子を見ていた楊胭脂は、やがて
「老僧は亡くなられたとは言え、道根は未だに存在しております。そんなに哀しんで、心を傷付けることはりません」
と、親切そうに神光を慰めました。神光は、この言葉を聞いて驚き、涙に濡れた顔を擡(あ)げ
「大師の道は、一体どなたが得られたのですか」
すると楊胭脂は、座を正して厳かに言いました。
「道は、既に私に尽く傳えられました」
神光は、これを聞いて訝しいと思ったが、ここが自分の縁、不縁を験す時であると考え、辞を低くして
「その道を私にもお傳えいただけませんか」
「あなたに傳えるにしても、あなたは心を降し、忍耐の念を存さなければなりません」
神光は、これを聞いて慌てて深く一礼し、地に跪いて懇願しました。
「道は、軽々しく傳えられません。必ず天に対する立願を要します。そこで初めて、傳授が許されるのです」
「修行中の弟子は、未だに玄に通じません。専心一意、明師を拝して参禅を学びます。私がもし法を軽んじたならば、苦を離れ難いでしょう。師を忘れるような事があれば、性命は還元できないことを誓います」
楊胭脂は、これを聞いて燭台に灯を点し、上座に座って徐に口を開いて語り始めました。
「修行の工夫は、全く心に憑(たよ)る。匪人(あしきひと)に傳授すれば、その罪は決して軽くはない。山を穿ち、海を透して時(つね)に現れ応ず。天を包み地を穿つは人身にあり。活溌動静(かっぱつどうじょう)、性天を養う。千度生まれ、初めて佛の凡に臨むこと能う。乾坤を貫き満たすは、眞性に憑ることによる。放ち去り収め来て本原に還る」
「では身中の性命、生死の根本由来は何れにありますか」
「生死、性命の原(もと)として、内外の分別があります。内には能く骨を穿ち、髄に透り、遍く人身を覆い、当に現れて物を化します。即ち六門(眼・耳・鼻・舌・身・意)の動静です。外には能く山を穿ち、海に透ることができ、天地を包み、十方に貫き満ち、放ち去るも収め来たるも動静は活溌です。これが、劫外の眞人です。金剛經に『現在・過去・未来の心、倶(とも)に得るべからず。人・我・衆生・寿者相、切に有すべからず』とありますが、ここに至って初めて輪廻の苦しみを逃れることができ、閻君の刑罰を脱することができます」
「いや、只今の道理は、曾て私が常に講義し論じたものばかりです。どうか私に、先天の大道をお傳え下さい」
「法は既に傳え尽くしました。再び別の法はありません」
神光の心に、疑いの雲が広がってきました。先天の道は、經典の文句を羅列しただけで、生と死を解脱できるとは思われません。これには何か深い訳があると考え込んでいると、突然門の外から大きな声で誰かが叫んでいるのが聞こえました。
「東土の衆生は無縁である。惜しむらくは、西天の達摩がわざわざ佛駕を東土に臨ませたが、みすみすそれを放ってしまった」
神光と楊胭脂はこれを聞いて驚き、急いで外に飛び出して見れば、一人の和尚が立っていました。神光は、早速その和尚に訊きました。
「あなたは、何処で達摩老僧に會われましたか」
「私は、西域から東土に来るときに、一日一夜同伴しました」
和尚は神光の衝撃の表情を眺め、更に言葉を継いで話しました。
「私は前日、西洋湖で体を洗っているときに、また大師に巡り會いました。手に便鏟(べんさん。木削り鉋)を持ち、その先に片方の草履を挿して布団を背負い、葦を千切って江(かわ)に投げ、その上を踏んで長江を渡って行きました。そのとき私は大師に『どこへ行かれるのですか』と尋ねましたが、すると大師は『先に武帝を救いに行ったが縁が無く、逆に玉棍(棍棒)で殴られ傷を受けた。次に神光を度しに行ったが縁が無く、逆に鉄の数珠で顔を打たれ前歯二本を折られてしまった。次に楊胭脂を救いに行ったが、危うく毒殺されるところだった。今はただ、熊耳山(ゆうじさん)に行って、静かな所で暫く休みたい』と言われ、そのまま立ち去ってしまいました」
神光は、この言葉に眞実があると察して、楊胭脂を激しく詰問しました。
「あなたは大師が病気で亡くなられたと言ったが、ご健在ではないか」
「亡くなられたのは事実です。信じられないならば、私と一緒に東緑関郊外にあるお墓に参って見られたらよいでしょう」
神光と楊胭脂が一緒にお墓に参り、大師の墓を掘り起こしてみたところ、棺の中には片方の草鞋があるだけでした。神光がその草鞋を手にとって裏を見る
と、次のような字が刺繍してありました。
「達摩、西より来たりて一隻(かたあし)の草鞋、千針萬線を以って繍出す。東土の衆生、我を識らず。片方の草鞋を把(と)りて死人として埋める」
神光は、これを見て、楊胭脂の悪毒な心に呆れ返って言葉も出なかったが、それよりも大師の神通広大、変化無窮に感嘆いたしました。
(続く)














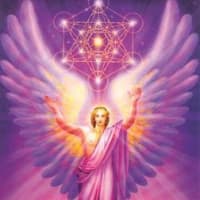


![大天使ガブリエル : 皆さんの魂の神聖なる統合との一致 [大天使ガブリエル]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/77/461d9a7f10657c86bc2070a8eeb1ba6c.jpg)
