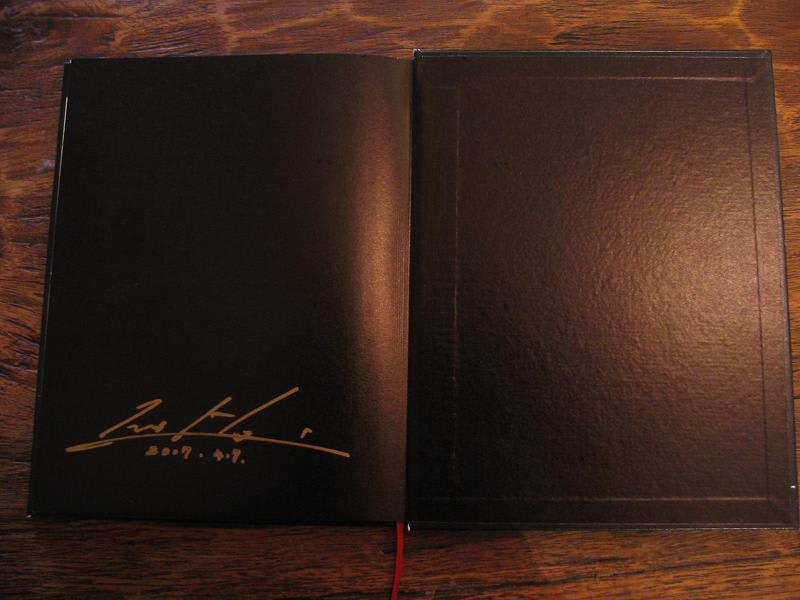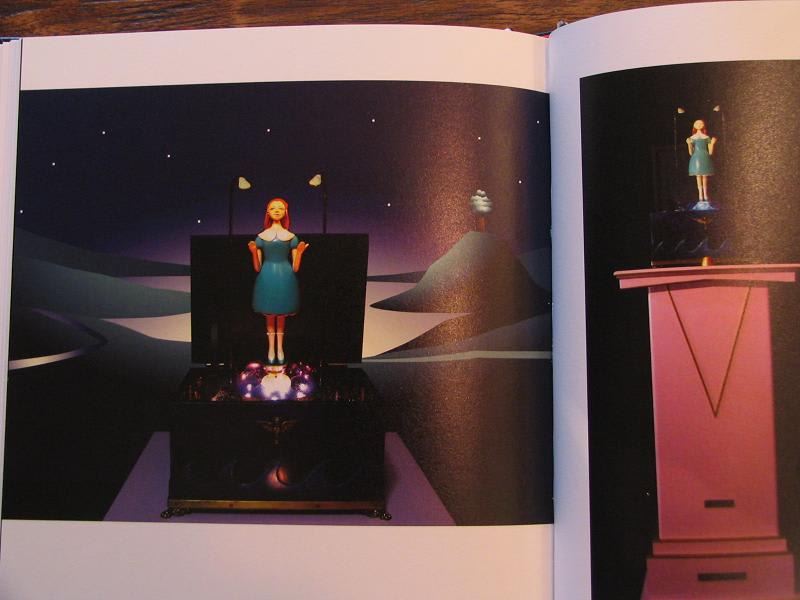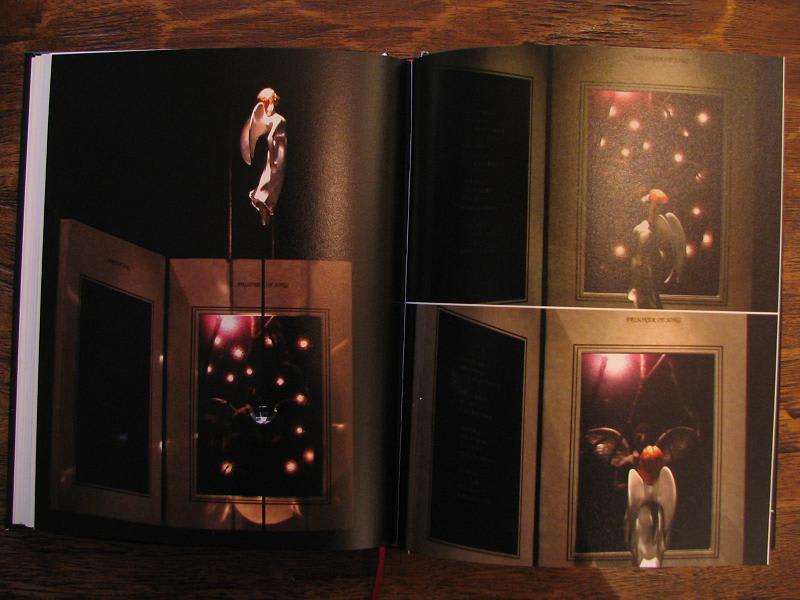森屋邸をあとに、ぶらぶらと川沿いの道を歩いていくと、
木漏れ日の中に真砂邸が見えてきた。
道がそのまま私道になっていて、いつの間にか花のアーチを
くぐり、到着。
木々に溶け込んだ家は、自然の邪魔をせず、やすらかだ。
開け放たれた土間のような、テラスのような、はたまた部屋の
ような展示室を心地よい風が抜けていく。
インディアンフルート奏者であり、このような
プリミティブな版画絵も描かれるのだ。
フルートの音色が静かに流れる部屋にしばし佇んでいると、
「おや、またお会いしましたね」
と、声をかけられた。
見れば森屋邸にいらした男性だ。
Tシャツにジャージというラフな格好から地元の方だろうとは
思っていたが、彼は私に自宅へ来いとさかんに誘うのだ。
奥様もいっしょに誘ってくださるので、お言葉に甘えてよらせ
ていただくことにした。
私にどこから来たのか、と尋ねるので、東京だと答えると、
「ええ!こんな田舎に来なくても東京のほうが楽しいのに。
そりゃあ、空はきれいだし、空気もいい、自然はいっぱい
だけれど、飽きちゃうよ。
いいな~、東京に住むのが僕の夢だ!」
とおっしゃる。
「はあ、そんなもんでしょうか…」と私。
さて、ほどなく到着した彼の家。
大きな門の脇には、竹筒の花器に菖蒲が活けてある。
道行く人が休憩できるように縁台も置いてある。
ぬぬ、オヌシ、実は風流人だな…と思いつつ、
すすめられるままに庭に入っていくと、なんと!
花が咲き乱れている上の写真は、彼の庭のほんの一角。
写真をあまり撮るのを控えたのが、
今となっては残念無念なほど美しかった。
奥様が庭のテーブルにお茶を運んで
くださり、花の中でお茶会となった。
突然のこの贅沢なシーン…神に感謝!
広い庭には天草も干してあった。
自家製ところてんか、いいなあ。
←これは麦。観賞用と麦茶用に栽培して
いるそうだ。
また、工作好きの彼は納屋を工作室に改造して、
何隻ものカヌーを作っている。
もちろんカヌーで海へ漕ぎ出す。
「東京に住むのが夢」とは、なんぞや!
彼は現役時代は葉山から日本橋まで
通勤していたそうだが、とにかく東京が恋しいのだとか。
「だってさ、街全部が東京は博物館のようだよ。
六本木ヒルズなんかいいなあ。大好きだよ。」
と東京恋歌を連発する彼の横で、奥様は「やれやれ…」
と笑っていらっしゃった。
仕事で多くの国々を巡られた話や、葉山の海や山の話、
裏を流れる川の鯉の話、菜園の話、花の話…と
旧知の友人のように話込んでしまったのであった。
おいとまを、と腰をあげると、私が好きだと言った麦を
束にして、花も添えてみやげにとくださった。
いやあ、海は見られなかったけれど、楽しい一日だった
なあ。こういう予期せぬ出会いがいいんだなあ。
と、麦の束を大切に抱えて帰路に着いた。
しかしこの後、帰り方を迷ったあげく、やけに遠回りを
してしまい、しかも見知らぬ駅に間違って降りてしまう、
という予期せぬオマケまでついていたのだった。