『緩和ケア』Vol.19 No.3
がんを患う患者が、なぜ精神症状を併発させるのか?そしてどのような症状がおこり、どういった治療が望ましいのか…についての概要を述べている。
見開き1ページの論文なので、広く浅く…という感じで述べられている。
引用
・ある研究(アメリカ?)結果によると、がん患者の47%が精神医学的な診断基準を満たし、そのうち、68%が適応障害、13%がうつ病、8%がせん妄であるとのこと。
⇒「適応障害」と「うつ病」は何が違う?と今更ながら思ったので、おまけの情報として…適応障害=「明らかなストレス要因があり、それに対する直接的な反応として、精神的に具合が悪くなっている状態」、うつ病=「特にはっきりした体の病気もないのに、体も心も調子が悪く、日常生活に支障をきたす病気」
・「精神医学的な介入は患者の苦痛を軽減し、QOLを高め、がん治療における適切な意思決定を遂行し、介護する家族の負担を軽減するためにも必要である」

 抗うつ薬の投薬状況が少ないという調査結果を踏まえて「医師・看護師の両者ともに見逃す可能性が高い」
抗うつ薬の投薬状況が少ないという調査結果を踏まえて「医師・看護師の両者ともに見逃す可能性が高い」


「がんの告知」は「初期に見つかれば治る可能性が高い病気」と言われていても、やはりツラい知らせである。
本論文では、抗うつ薬の投薬状況について、終末期患者を対象としたものが紹介されていた。再発の可能性におびえながら、そして「告知」の場面を引きづりながらもなお、「生き続けている人」こそ、精神的ケアの対象者であろう。
親族で初期のがんを発症し、摘出手術を受けた人がいる。全国から患者が集まるほどの「有名な病院」で手術を受け、今も半年ごとに定期健診を受けている。少なからず精神的なダメージを受け、退院後の初診でその旨を主治医に伝えたところ、「精神科はあるけれども、うちのはおすすめできない。ご近所で探してみてはどうか?」というコメントだったとのこと。
大きな病院は、入院期間も短く、患者数が多いために継続的なケアは難しいだろう。退院後の外来患者に対しては尚更のことだ。
しかし、ガンを撃退してもなお、「晴れ晴れとして生活」が送れていない人のケアはどこが行うのだろうか?
医療技術が発達し、がんを撃退し生存する人も増えていくだろう。大病院と家庭医との連携、もしくは病院内での医療連携(ケアの連携)…様々な課題があると痛感した。
がんを患う患者が、なぜ精神症状を併発させるのか?そしてどのような症状がおこり、どういった治療が望ましいのか…についての概要を述べている。
見開き1ページの論文なので、広く浅く…という感じで述べられている。
引用

・ある研究(アメリカ?)結果によると、がん患者の47%が精神医学的な診断基準を満たし、そのうち、68%が適応障害、13%がうつ病、8%がせん妄であるとのこと。
⇒「適応障害」と「うつ病」は何が違う?と今更ながら思ったので、おまけの情報として…適応障害=「明らかなストレス要因があり、それに対する直接的な反応として、精神的に具合が悪くなっている状態」、うつ病=「特にはっきりした体の病気もないのに、体も心も調子が悪く、日常生活に支障をきたす病気」
・「精神医学的な介入は患者の苦痛を軽減し、QOLを高め、がん治療における適切な意思決定を遂行し、介護する家族の負担を軽減するためにも必要である」

 抗うつ薬の投薬状況が少ないという調査結果を踏まえて「医師・看護師の両者ともに見逃す可能性が高い」
抗うつ薬の投薬状況が少ないという調査結果を踏まえて「医師・看護師の両者ともに見逃す可能性が高い」

「がんの告知」は「初期に見つかれば治る可能性が高い病気」と言われていても、やはりツラい知らせである。
本論文では、抗うつ薬の投薬状況について、終末期患者を対象としたものが紹介されていた。再発の可能性におびえながら、そして「告知」の場面を引きづりながらもなお、「生き続けている人」こそ、精神的ケアの対象者であろう。
親族で初期のがんを発症し、摘出手術を受けた人がいる。全国から患者が集まるほどの「有名な病院」で手術を受け、今も半年ごとに定期健診を受けている。少なからず精神的なダメージを受け、退院後の初診でその旨を主治医に伝えたところ、「精神科はあるけれども、うちのはおすすめできない。ご近所で探してみてはどうか?」というコメントだったとのこと。
大きな病院は、入院期間も短く、患者数が多いために継続的なケアは難しいだろう。退院後の外来患者に対しては尚更のことだ。
しかし、ガンを撃退してもなお、「晴れ晴れとして生活」が送れていない人のケアはどこが行うのだろうか?
医療技術が発達し、がんを撃退し生存する人も増えていくだろう。大病院と家庭医との連携、もしくは病院内での医療連携(ケアの連携)…様々な課題があると痛感した。










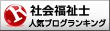
 わが国におけるインフォームドコンセントの解釈は、「説明と同意」とされることが多い。そのことについて、心の機能を表す「知情意」という言葉になぞらえて考え、「説明」を受けて「同意」に至る間に「情」が抜けている…と指摘している。医師は気持ちへの配慮も欠かせないとしている。
わが国におけるインフォームドコンセントの解釈は、「説明と同意」とされることが多い。そのことについて、心の機能を表す「知情意」という言葉になぞらえて考え、「説明」を受けて「同意」に至る間に「情」が抜けている…と指摘している。医師は気持ちへの配慮も欠かせないとしている。 『診療報酬を在宅に誘導し、在宅死率を上昇させようという動きがある。それ自体は良いことだと思うが、「在宅死」を支える要件(緩和医療技術の水準確保、情報共有の方法、アセスメント、ガイドラインのチーム内共有などの、最低限持つべき技術)を考慮せず、安易に在宅医療を参画しようとする、危うい社会的機運が醸成されつつある』
『診療報酬を在宅に誘導し、在宅死率を上昇させようという動きがある。それ自体は良いことだと思うが、「在宅死」を支える要件(緩和医療技術の水準確保、情報共有の方法、アセスメント、ガイドラインのチーム内共有などの、最低限持つべき技術)を考慮せず、安易に在宅医療を参画しようとする、危うい社会的機運が醸成されつつある』



