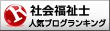『社会福祉学』第62巻第2号
福祉事務所ワーカーに求められる専門性について、「公務員の専門性」にも焦点をあて、現役ワーカーへのインタビュー調査をもとにその全体像の素描を試みている。
インタビュー調査対象者は3名と少ないが、その声を丁寧に分析、考察している印象を受けた。
引用
・最低生活保障は必ずしも経済給付だけを意味するのではなく、相談支援の実践と一体となった生活保護実践によって達成される。
・調査結果から導き出された概念的カテゴリー:面接、人権保障、連携、計画的実践、法適用、能率性、専門性の自覚、外部視点
・調査回答より:
「ケースワークをしたというより訪問数をこなして記録を書いて事務処理を早くするという方がやっぱり評価されるところに多少のジレンマを感じる」
「数字の評価となってしまって、日々の実践、目に見えない努力が軽視されていないか不安」


公務員のお給料は税金から捻出されているため、その公平性と効率性が求められているのであろう。
しかし一方で、公的な立場だからこそ、指導や強い忠告を率先して行ってくれる立場であって欲しいとも思う。
最近の私の勤務先での経験。いわゆる生保ビジネスで、管理人さんが経済的搾取をしているかもしれないとヘルパー事業所から連絡があった。
地域包括の職員は区の窓口にその報告について相談をした。「それでそちらはどう考えていますか?」としか聞いてこない。
虐待の定義として当てはまるのか?という外枠をとても気にしている。
「他の業務に追われ、このケースに関わる時間がないのかもしれない」と推測し、地域包括とヘルパー事業所で経過を慎重にみていた。
そして数日後、「そういえば、先日のケースは虐待の定義に入りましたか?答えは出ましたか?」と区から問い合わせが入った。
定義の範疇に入るかどうかがグレーであるが、食材を買うお金を奪われている様子であったため、
フードバンクと連携をしていることを説明すると、「では虐待という定義に入ったら、教えてください」と電話を切られた。
定義優先?地域住民の人権優先?どこに向かって仕事をしているのか。
本論文を読み、ジレンマを抱えながらも地域住民を向いて仕事をしている公務員の方々が、もっと報われそして増えて欲しいと切に思う。
そのためには何が必要なのか。現業員のたくさんの声なのか、地域住民からの感謝の言葉なのか、関係機関からの報告なのか…。
大きな組織であるがゆえに、難しいことなのだろうということだけは、理解できた。