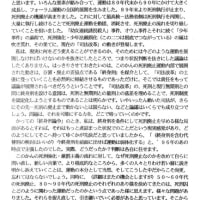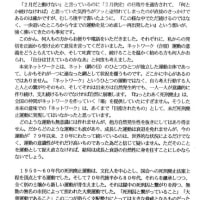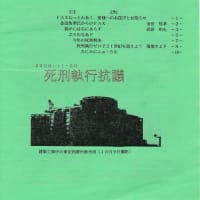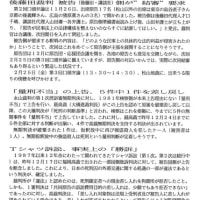(二) 11・30当日の経過は以下の通りであった。
当日我々の参加者は5名。会場で永六輔に直接回答を求め、もし暴力的に排除され追及が不可能になれば外からマイク車で抗議するつもりであった。先着2名が5時少しすぎより会場前でビラをまいた後、1名に車置きをまかせて4名が6時少し前に会場に入った。
6時開演時で参加者約50名。永六輔が出て来て「主催者は時間を遅らせてはと言っているが、遅れてくる人民はその人の事情があるのであり6時に始めるといった以上はじめます。しかしプログラムには入らずしばらく私が話します」ということで、自分の旅先の経験―ロシアンティーは出来る(店にジャムはある)が、メニューにないのでジャムトーストは作れないと言い、ロシアンティーの中のジャムをすくってつけさせられたという店の話を行ない、「プログラムにこう書かれてないから出来ない」という人が多い、としめくくった。6時15分頃、矢崎泰久、中山千夏のにこやかな司会で集会が始まり、女性ピアニストが「これは死刑囚が処刑前夜にふるさとを想う歌です」といって「グリーングラス」をひき語り、という〝雰囲気″で進行。
そのあと永六輔が登場したので、すぐに舞台向って右の脇より、ハンドマイクで「永六輔氏に、〝連続射殺魔″永山則夫の反省=共立運動より、この場をかりてやむにやまれぬ訴えをします」と呼びかけると、永六輔は「はい」と対応。
それで「週刊読売」の件を話し出すと、「死刑廃止の会」の女性二名が横に来て「あんた、これ、やめなさいよ」とつっついた。処が永六輔は「こちらに上って来た方が話しやすいでしょう。どうぞ」と言い、武田はハンドマイクを置いて壇上にあがり、「発言の機会をくださって感謝します」と言って話を続けようとすると、主催者の一人、救援センター事務局長の水戸巌がいきなり、飛びかかって来たのである。更に一人ほど上って来てもみ合いとなったが、私の妻が見かねて上って来、彼らの暴力に抗議したところ、男達はなぜか私を放して妻の方へ向かっていった。
その間に「死刑には反対だがあくまで無期」等の永発言の真意や、永山裁判減刑判決後のマスコミのキャンぺーンの中での永の責任、等について続けたが、彼らは何とか私の発言を封じようとあせり、とうとうマイクのコードを引きちぎってしまった。仕方なく武田は素声で「死刑廃止をダシにし、ショーにするこの集会に抗議する!」と客席Kむけて発言。この頃Kは舞台上K多数の人間が上り、収拾のつかない状態になった。
この段階でKさん(当時の永山則夫の奥さん)も舞台上に上ったが、あとで聞くと永に対して自己紹介し永も「あなたと話しましょう」と言ったがこれにも水戸がわって入り、更にもう一人の男が彼女を「はき気のする程」引っぱり舞台から落とそうとしたという。我々の側で舞台に上っだのは、この3名だけであったし、水戸の暴力で混乱する前、つまりあえてプログラムに抵触する形で発言したのは武田一人であった。
このあと、「一般参加者です」と称して、救援センター関係者と思われる老婆が登場、「いろんな考えがあるので一つの考えだけきくわけにいかない。私は永さんの話を、遠くからお金をかけて聞きにきているので、プログラム通りやってほしい。」と発言した。この集会の終了までを通じてこの発言が最も聴衆(その時点で約二五〇名位)の拍手をうけた。
何の集会なのかという事を全く欠落させ、「様々な意見がある」事をタテに少数意見を圧殺するという、集会の政治性を最も端的に示すものであった。私は「さっきジャムトーストの話をしたばかりではないか」(向うで六輔氏うなずく。)と対応したが、永六韜が「楽屋で話し合う」というので、楽屋に入り約30~40分位、話した。集会終了後、彼は「週間読売の件は必ずはっきりさせるが時間か全くないので、もう少し待ってほしい」と言い、我々は「資料を送る」ということで別れたのだが、その後、二度の話合い(二度目は取材した読売記者も立会い)をもったが、取材側の責任を強調し、話の進展をみなかった。
集会第二部では、各発言者の頭上に死刑にされた人をあらわした人形がぶら下げられており我々を驚かせた。これは死刑囚やその家族の気持を全く無視するものだから降ろす様、矢崎泰久に言ったが、出来ないと言い、(作成者は妹尾河童だという)水戸は「あなた方こそ密室主義の権力のやり方と同じだ!法務省の手先だ!」と稠錯した事を口走った。かのハリコ人形に我々は、刑務官も酒びたりにならざるを得ない処刑の残虐さなど全く感ずることは出来ず、死刑囚をダシにし。さらし者にし、侮辱して恥じない不真面目さ、思い上りをみたのである。
三
あの様な「死刑廃止ショーー」の延長上に、いまの日帝権力に死刑廃止をせまる斗いは展望しえなかった事は明白である。集会第一部の〝粉砕″は下層「犯罪」者・死刑囚と市民とが、その殺し、殺される関係を変革して共に生きれる団結をめざす斗いを、永山裁判斗争に集中させてきた我々と「誰も殺すな」という一般的「善意」から、「死刑」を支える具体的状況に切りこむことなく死刑制度=「法」という抽象性への斗いを主要とし、政治焦点を拡散させる「巾広イズム」の斗いをしてきた部分との衝突であり、後者が前者の斗いの切り拓いた地平に無自覚なまま、自分達本位の「運動」によって足を引っぱる行為をおこない、前者が抗議すると「様々な意見の存在」をタテにそれを少数意見として圧殺せんとあせった為に集会を自滅させてしまった事件であった。
その意味で、主催者側の人が、あの事態を「死刑廃止運動にとっても大きなマイナスだったと思います」というなら(「囚人新聞」より)、彼らはその責任を、永山個人にではなく、死刑囚をはじめとする人民総体に対して自己批判するべきである。我々の介入がなく、あの様な「死刑廃止ショー」がことも無く行なわれるなら、それは死刑廃止の斗いにとって「大きなマイナス」どころか「致命的」なものであったろうから。
「永山個人」は、この問題を、「永山の妻に対する暴行を自己批判させる」という一点に収約させていった為、彼らに対する自らの相対的な正しさを絶対化し、矛盾を固定化していった。「減刑」以降の状況の重みを痛感するが故に、元々大衆組織でありメンバーも流動的である「死刑廃止の会」などには、以降は中に入っていって訴える必要もあるという武田とも対立し、その極端な個人主義を前面に出して斗争を売り渡す中で、全ての死刑囚にとって「致命的」な敗北を喫したのである。
83年7月「反動」まで、永山裁判の動向が他の全ての死刑裁判の動向を規定していた。然しそれ以降は、最高裁を頂点とするまき返しが、個々の死刑裁判の動向をそのメルクマールとしているのであって、全ゆる意味で「死刑」に反対し、「死刑」に抗議しこれと斗う全ての勢力の動向が、死刑裁判総体にどう反映されるかという事が、個別「永山裁判」自体の結果をも左右するであろう。
それだけに、「〝連続射殺魔″永山則夫」を助ける論理、〝救いようのない凶悪犯″を生かす論理を放棄し、「〝三百年に一人の天才″〝全人類への最高度の貢献者〟 永山則夫」だから助けよというブルジョア論理の体現者永山が、『「悪い」とは思わずに行なう』他の死刑囚仲間を足げにする言動が、限りなく権力を利するものとなるのである。 我々が「死刑」をめぐる状況を正確に分析し、そして、どの様な人達を、人間として真に生かし、共に生きるのかという斗いの根拠、方向性を明確にし、限られた力を最大限に生かし拡げていく為にも、「11・30」の問題は正しく総括されねばならないであろう。
(85年9月30日)
抜粋以上

※永山氏は、永六輔さんに、四季の挨拶状なんて送ってないそうです。