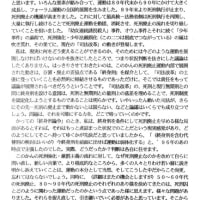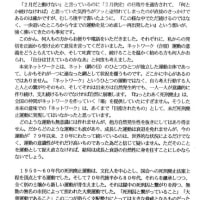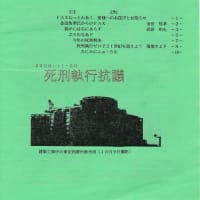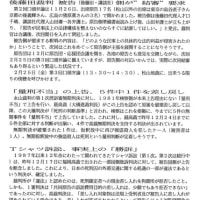永山則夫元支援者の武田和夫さんが、永山から追放された後、発行された『沈黙の声』という会報を冊子にまとめたものです。『沈黙の声』14号の記事を、以下に載せます。
文章が長いので、2つに分けましたが、この後に続く(その2)の方が壮絶な内容になっているので 、読まれるのを薦めます。武田和夫著【死者はまた闘う】にも書かれてますが、永六輔さんが呼ばれた「死刑廃止ショー」での惨劇(?)が詳しく書かれてます。
、読まれるのを薦めます。武田和夫著【死者はまた闘う】にも書かれてますが、永六輔さんが呼ばれた「死刑廃止ショー」での惨劇(?)が詳しく書かれてます。
『沈黙の声』第14号(85年10月15日発行)
「'81年 11.30 死刑廃止ショーは何故粉砕されたか」
一
本年5月31日、法相嶋崎均の執行命令により、名拘大島卓士氏、大枸古谷惣吉氏の二名の死刑確定囚が処刑された。これは「54年り降は毎年一人の執行」とマスコミも指摘する最近の傾向にも逆行し、それも任期切れ間際に命令書に印を「押し逃げ」するといわれる「通例」とも異なる任期中の執行である。この強権執行は、直接には、平沢貞通氏の「死刑執行時効」による釈放請求に対する報復としてなされているが、同時に、83年7月の最高裁による永山裁判「差し戻し」以降の反動攻勢が、人民からの抗議と死刑裁判支援の前進のまえK鈍りがちである状況K対する法務省からのテコ入れとしての性格も有するものであり、これをうけて七月には1ヵ月に三件の死刑判決(東京高裁、広島・大阪地裁)が相次いでいる。「どんどん殺れ。こちらはこれだけやっているぞ」という、中曽根反動政府の、血にまみれた帝国主義者の本質を露骨に示す今回の攻撃は77~79年の法務省「弁護人ぬき裁判」策動と性格を同じくする、司法分野でのファシズム攻撃であるといえよう。
「弁護人ぬき裁判」攻撃は、当時、下層「犯罪」者=死刑囚の解放に基準をおいた人民の団結を具体的な斗いの中に展望しつつ、刑事裁判制度、死刑制度の眼底にせまる斗いをすすめていた永山裁判斗争に対し、攻撃に屈服した弁護士会に一人三千万円の生命保険付で三名の国選弁護人を送り込ませ、これを圧殺せんとするものであった。
81年8月21日の永山裁判高裁「減刑」は、この攻撃に屈せず、静岡事件をめぐる権力犯罪追及を主要軸として斗い続ける斗争主体に対する権力側からの「懐柔・取り引き」という性格を有した。そしてそれは。斗いの緊張関係に支えられてはじめて成り立つ「取り引き」であり、それ故に人民の側に有利な地平でのそれとなったのであった。然しこの他方で、権力はマスコミを総動員して永山の、「結婚による人変わり」「温情判決」をキャンぺーンし、「減刑」に至る永山裁判斗争の政治的成果を骨ぬきにしようとした。
そして永山自身が斗いを獄外で主要に担ってきた武田を「スパイ」にデッチ上げで権力に売ることで「減刑を確実に」しようという個人主義的妄動を行ない、さらには「ハイエナ」佐木隆三による「新日本文学賞」選考にからめた朝日新聞による「斗争放棄」キャンぺーン(83年4月23日夕)をゆるした。この斗争破壊・売り渡しKつけ込み、83年7月8日の「反動」はなされたのであった。 以降の反動攻勢は、81年8月「減刑」以降停止されていた死刑上告審を再開し、具体的に死刑確定判決を出していくことで「死刑存置」を事実としておしすすめ、下級審での相次ぐ死刑判決を収約していこうとするものであった。この局面で、「死刑存廃」は、個々の、一つ一つの死刑事件裁判の進行のなかで、人民の注視の的とならざるをえず、個別の死刑裁判の動向が死刑をめぐる全状況と密接に関連していくという状況が生まれた。そのなかで〝死刑判決に慎重な最近の動向〟を理由とした高裁減刑判決が出され、また最高裁においては、死刑上告審に斗う人民の抗議・支援が集まり始め、本年4月の判決には公安・警備計40名の動員をよぎなくされるという事態に至った。
こうした状況に対して、法務省が再び司法へのテコ入れをはかったのが、5月31日「同日二名処刑にという強権攻撃の本質なのである。 死刑と斗う人民勢力はまだ少数である。然し権力が恐れるのはたんなる人数ではなくその可能性であり、時宜をえれば広汎な大衆の支持と共感を得る、斗いの道理性である。その為にもわれわれは、「死刑」をめぐる支配権力の本質とその意図をより正確に見究め、またわれわれの、死刑と斗う根拠と内実を更に確かなものとしていく為の、真剣な討論を必要とせねぱならないであろう。
二
(イ)
斗いの原則を売って権力につけ込まれた転向ぶりを具体的に指摘されながら、批判する相手を、「狂人」よばわりして居直る永山則夫は、個人誌「囚人新聞」を獄内外に配布し、権力に売収された挑発分子としての現在をさらしている。この、「囚人新聞」が81年H月30日の「死刑は止めて」集会での、「永山の妻」への集会主催者らの暴行問題をとりあげているのだか、その基本姿勢に制約されて、「当時の」問題の本質を正しく示したものになっているとはいえない。
この81年11月30「死刑廃止」集会の一部が、当時永山裁判斗争を斗っていた部分の問題提起の前に粉砕された出来事は、今もって様々な、重要な意味をもっている。本紙では、これを含め、このかんの斗いの総括を順をおって行なっていく予定であるが、権力のこのかんの攻撃の中で、「死刑との斗い」の深化と拡大が要請されているこの時期に、特にこの「11・30」の問題を全面的に総括し、今後の斗いにむけての提起としていきたいと考えるものである。
(口)
まず8111・30をめぐる当時の状況を説明しておこう。同年8月21日に永山裁判高裁「減刑」判決があり、これをめぐって全ての大新聞と「週刊新潮」「週刊文春」「週刊読売」などの週刊誌でこぞって、この判決の本質を隠蔽するキャンペーンがなされた。
とりわけ、サンケイ新聞は9月5日以降5回の「連載」で、植松正、青柳文雄らの反動御用学者による感情論をバックに、被害者遺族を前面に立ててあからさまに検事上告支持を唱え、週刊文春は「なぜ死刑にならぬのか」と書きたてる、「減刑反対」の世論操作を行ない、運動が、サンケイ、文芸春秋本社に対するマイク抗議 ・ビラまきの波状攻撃を頂点として、各社に抗議し反論文掲載要求を行なっているのがこの時期であった。
こうした中で、11・30集会は、「週刊読売」の誌上で「永山から四季の挨拶状がくる」と事実に反する事を述べて「親密さ」を印象づける中で「死刑には反対、ただし仮釈放ヌキの無期とすべきである」とのべている永六輔を、集会第一部の「死刑は心めまショー」の主人公として招いたのである。
この永六輔に対しても、その誌上発言の根拠・真意について再三の問い合せがなされたか、永六輔は「調査しようと思っている」というだけで何の返答もなく、「公に追及せざるをえない」と申入れていた矢先であった。主催者内部にこれに関するどの様な意見の相異があったにせよこの時期に、「死刑廃止」集会と銘うって永六輔をたててくるというのに、永山裁判斗争に対する挑発行為といってよく、永山裁判斗争を他の「死刑廃止」グループから分断孤立させることを望む権力の意図にまさにそうものといえた。 もっとも、そうであるからこそ、彼らの無理解をのりこえて少しでも連合していく可能性を追及していかねばならなかったことも事実である。然しながら、当初、「相当な時間をよこすなら(尤も、その事自体が対立点となりうる状況でもあった)発言を要求する」事も考え、「参加者全員に反省させる為、集会に参加せず外からマイクとピラで糾弾すべきである」と主張する永山と方針の上で対立していた武田が、最終的に、〝あくまで会場の中に入って問題を提起するが、主催者へ発言を求めるのではなく、主催者への糾弾を内容とし、実力で発言をかちとる″というあの様な形での介入を決めたのは、「読書新聞」11月16日号の「死刑廃止の会」、(文責森修)の文章によってであった。
―『最近一人の死刑囚が無期刑に減刑されました。』で始まるこの文は、「永山裁判」が当時有していた固有の政治的意味を抜き去り「減刑」K至る斗い総体を無視黙殺したうえで、この「減刑」に「多く」の人が反対した事を強調し、それに対し何の主体もかからぬ弱々しい良識を対置して集会への招請につなげたものであった。単に無理解なのでなく、意識はしながらその斗いがどの様なものであったのか知ろうともせず。利用できるところだけ利用するという対応であり、斗う者に対するこの上ない侮辱であり圧殺行為であった。それが公然とまかり通る状況だ、ということであった。
(ハ)
次に、「11・30」当時の、「死刑廃止」運動総体の状況は、どうであったろうか。まず基本的に、8・21減刑から三ヵ月たっても、彼らのほとんどが永山裁判斗争の、死刑廃止の斗い総体にとっての意味を分っていなかったし分ろう 永山裁判斗争(当時までの)は、下層「犯罪」者解放=死刑廃止=反ファシズムの斗いであった。そして皮肉なことに、権力・マスコミが、この斗いを「死刑廃止か存続か」の一点にきりつめ、「減刑維持は実質的な死刑廃止につながる!」とキャンぺーンして「差し戻し」への布石を打つ様になってはじめて、「死刑廃止」運動の中心メンバー達も、「個別永山裁判」の波及力に気付き、永山裁判最高裁弁論―判決に「注目」する様になったが、それは余りにも状況に立遅れたものだったのである。
「11・30」当日にいても、我々の斗いへの認識は
「武田は永山オンリーだ」
「あなた方は永山氏だけ助ければいいのですか」
というのが、死刑廃止グループや救援戦線の主だつた人達の言葉であった。
「11・30」の事態は、それまでの永山裁判斗争と「死刑廃止」グループ総体との矛盾対立の収約でもあった。「死刑廃止の会」結成の前段階として、79年5月27日、7月29日の二度、シンポジウムが行なわれたが、この7・29シンポジウムの席上、運動が永山則夫のアピールを代読したところかって死刑囚孫斗八氏を支援し、それを「さかうらみの人生」という本に著している丸山友岐子が「獄中の死刑囚を主体とする運動はするべきではない」「自分は死刑囚には関わらず〝制度″と斗っていく」と発言したのである。
永山のアピール中、彼女が問題にしたのは「死刑制度は、死刑囚の仲間を1人殺したら、その関係者10人以上殺す報復機関があれば、早期に消滅します」という個所であった。「誰も殺すな」という事を死刑廃止の原則にしなければいけない、という訳である。
「誰も殺すな」というのは、一般的に全く正しく、どこからも反論の余地のない「コトバ」である。
しかし「全く反論の余地のない一般論」というものは、現実をかえる力を持たない。我々は、げんに殺人があり、それに対する死刑という殺人行為が存在している、それを支える具体的な権力・市民・下層「犯罪」者の関係性をかえる斗いをしてきていた。それはなにも「一人殺されたら10人殺せ」と叫ぶのでなく、法務省・最高裁・弁護士会一体となった死刑強行攻撃K対して、相手が生命の危険を感ずる程の斗いをやり、敵に多大の政治的犠牲を支払わせ、高裁「減刑」へとつなげる斗いであった。単に「誰も殺すな」では斗えなかった。
そしてかのアピール文も、主要には、「人民弁護人制度」―各刑事裁判を監視・支援する市民の輪を広げていこうという訴えであり、現在の死刑との斗いに於ても有効な内容をもつ訴え(昨今の永山の言動はこれに逆行しているが)であって、その肯定面があったからこそ我々は「代読」したのであった。
処が丸山は、「救援」誌上に「私の死刑廃止論」を14回にわたって連載しその結び(80年10月号)として
『〝連続射殺魔″と、それがあたかも立派なクン章であるかのように名乗る獄中者をかつぎあげ」 「「一人の死刑囚の死刑執行にかかわった10人の関係者を殺せ」というようなアホらしくもムチャクチャなメッセージを、わざわざコピーして…」 『「殺せ、殺せ」と叫ぶ男たち』 「個人の感性よりも、いつも組織の利害を優先させる男たち」と強調し、死刑廃止〝女の会″をつくる、としめくくったのである。
私は、この彼女の「党派性」が「男の論理」である事を前号「沈黙の声」で指摘したが、「党派性」そのものは否定しない。そして真の≪党≫には、男の論理としての党派性(区別の論理、原則的徹底性)と、女の論理としての大衆性(結合の論理、実践面での包容力)の双方がそなわっていなければならないと考える。この一方を欠落させたものが「セクト主義」という代物で、後者を欠くものが多くの「党派にみられる現象であるが逆に前者を欠くものも、運動をおしすすめる為には必然的に要請される原則性、区別の論理をたえず否定しなけれぱならないことから必然的に「区別の論理」を持ち〝反対物″に転化してしまうのである。
「様々な意見がある」と強調することで我々の提起を圧殺しようとした「11・30」集会もそのひとつであり、丸山友岐子の我々への対応もそうであり、そしてこの立場を水戸巌が「救援」の自筆記事や丸山「死刑廃止論」の掲載で全面的に支持していったことで、はっきりと運動上の対立となっていったのであった。 「射殺魔」というのは、犯罪者を人間とみなさないこと、死刑で殺してよいとすることであり、自ら名のるのはその殺人の責任を負いつつその差別と斗う姿勢によるものである。
これを「クン章のごとく」云々と茶化す丸山に対し、彼女をパネラーとして招いた81年1・24死刑廃止集会で抗議し直接彼女に訴えたが、その事は分ったとしながらも「私は殺人なんて感覚に合わなくて」と言い集会参加者の多くがこれに同調して笑うという状況を呈し、殺し殺される現実の階級社会とは無関係の高みからの「運動」という印象を持たざるをえないものであった。そして、この集会の「救援での報告文が真実を記していないとして反論掲載を求める武田を、文責者水戸巌が〝破壊者″とののしる等のことがあり、その場で水戸は「以降、永山裁判をことわりなく記事にしない」旨の一文をしたためた。
この事もあって、81年8月21日の「減刑」時には、り前一審死刑求刑時に国選弁との対立を「弁護方針の対立」と誤記され訂正を要したこともある為、無理解故に内実をわい曲されても困ると一切の記事を断ったのであり、「救援」が「永山裁判」の記事を一方的に掲載しはじめ、しかも最高裁差し戻し判決を一片の抗議もなく「事実」のみ掲せるという悪意ある対応をしたのは、武田の脱退以降のことである。(武田が永山の悪意にみちたデマ中傷は公然と糾弾しながら、最高裁「差し戻し」判決は『沈黙の声』で正確に分析・批判している事実をみよ)
高裁「減刑」までの緊迫した斗いのなかで、我々はこうした部分と歩調を合わせていく余裕など全くなかった。そればかりでなく我々は内部的にも、旧「あつめる会」部分の反動と斗い、彼等の居直りと脱落をくり返してきたが、その都度戦斗性を高めてきていたのである。「孤立」を恐れては斗い続けることは出来なかった。
然しながら、「減刑」に際し、武田はそれが斗いの結果であると確信する反面、権力側の〝フトコロの深さ″も感じていた。やたらと強権をふるう簑原の様な、〝先兵〟よりも、「話し合おうや」と招き入れる「敵」の方が手強いのであって、「減刑」は、権力側の弱さの表われでなく、むしろ強さの表われであった。それだけに、永山裁判斗争の切り拓いた地平をより広汎な仲間が共有せねばならず、その為の訴えが必要になっていた矢先、まさにそれに挑戦するが如き「死刑廃止ショー」が設定されたのであった。