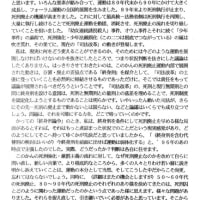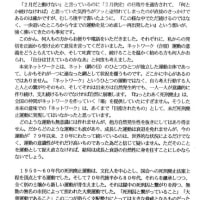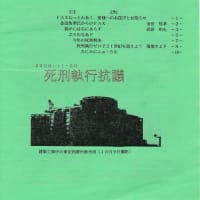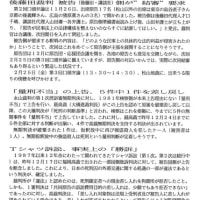(その1)から続く
近代国家は、「前近代の遺物」であれ、その支配に必要なものを自ら手放しはしない。
前近代の遺制を「近代的」に手直ししつつ存置させ続けることは、近代ブルジョア国家の本性でもあるのだ。中世封建時代の死刑は、裁判権、刑罰権を独占した封建領主が、農民への実力支配による搾取を正当づける為、被支配民の身体に無制限に加えうる権力を誇示する身体刑であった。
近代国家に必要なのは、その様な民衆に対するむき出しの暴力ではない。農村共同体の自給自足経済の「外」から実力で搾取する必要のあった封建制に対し、賃労働と資本の関係そのものの内部で「剰余価値」が生み出される資本制社会においては、その生産関係を「秩序」として正当づける合理的「法」的支配が必要なのである。搾取階級と被搾取階級とは、この秩序の中で、「商品購買者」として、平等な 「人権」が与えられねばならない。
この「人権」に基いた「法」的、合理的支配、それが近代国家の在り方である。その「人権」が単なるタテマエでなく、その「法」的合理的支配が真に対等な社会契約に基くものであれば、個人への無制限な権力行使に他ならない「死刑」は必然的に廃止されねばならない。然しながらその「法」支配は、生産関係に於る隠された搾取-被搾取関係、生産力を有する個人をモノにまでおとしめる支配関係を維持する為のものであり、「人権」とはその関係を隠蔽する為のタテマエでしかないのである。
この「秩序」に耐えきれず、必然的にそこから逸脱し、それに敵対する者は次々と生み出される。
「法」はその事象に対して解決能力を持たない。そこに働くのは実力支配による排除、抹殺の原理しかないのだ。「死刑」は、前近代的なむき出しの暴力性を極力隠蔽された形で、ひっそりと持ち込まれる。非公開の、密室での処刑。その執行すら隠され、通信にスミヌリの山を築く処刑。それは「封建時代の思想」によるのではなく、近代ブルジョア国家の原理そのものによる、死刑の在り様なのである。
死刑廃止が「先進資本主義国家群」の間で、すう勢となってくるのは、20世紀後半においてであら、資本主義一般の特質ではなく、国家独占資本主義時代の傾向、「死滅しつつある」危機にひんした資本主義が、国家の全面介入によって、社会主義的政策―計画経済や「福祉」主義を、「改良」としてとり込み、国民を再編統合していく時代の特質なのである。その過程で、死刑廃止は体制内改良派(社民)の手動によって実現されてきているのだ。
日本においては、明治以降の天皇制によって規定された、特殊な近代国家としての在り方が、死刑制度にも反映されている。 似た様な議論である。 ‐天皇制=前近代の遺物。然し明治以降の天皇制が、有名無実であった 「前近代」でのそれの〝遺制〟とは言い難い。 明治以降、諸外国の脅威の中で急速に近代国家体制を整える必要のあった日本の支配層が、いまだ地方的農村共同体に根をおろしていた日本社会の上に、近代国家の中央集権的支配を貫徹する為の国民意識統合を果たすものとして天皇幻想体が形成されたのであった。それは当初から、絶対主義権力のような、自身の実力による中央集権化をなしたものとしてでなく、国民意識を統合するイデオロギーとして、国家中枢に〝寄生〟したのであった。
そうであるが故にそれは、抽象的「法」的支配、という近代国家支配の幻想的性格を十全に代位し、日本資本主義の成長とともに、自らの〝神話〟を更に増幅させ、肥大していったのである。天皇制は「前近代の遺物」―いずれ消滅の運命にある存在ではなく、日本資本主義と密接不可分に統合し、日本近代国家の特殊性を形づくり、それと運命をともにする存在である。その性格は、より「近代的」に手直しされた戦後天皇制のなかでも明確に示されている。
明治天皇制国家の「法」的反映は、「天皇は神聖不可侵」の帝国憲法第一条であり、「大逆罪」という他に例をみない強力な死刑罪であった。では「天皇に国民統合の象徴」と手直しされた戦後憲法のもとで、「大逆罪」はどうなったか。それは法文上は姿を消したが、戦後象徴天皇制にみあった形姿、つまり「隠れた大逆罪」として存続し続けたのだ。一般殺人罪、そして「爆取罰則」等の治安立法の中に。日本の死刑制度がそのような 「隠れた性格」をもつ以上、日本国家はあくまで死刑存置に固執するであろう。
***
この「死刑廃止論」連載から一年後に開始された、最高裁による、東アジア反日武装戦線の天皇攻撃未遂への報復的性格をもった極刑・重刑確定攻撃、それを突破口とする死刑攻勢は、天皇国家日本の死刑制度の本性を赤裸々にさらけ出した。そしてそれは、われわれの死刑廃止の闘いそのものをも真剣に問い直し、とらえ直すことを要求しているのである。 楽観論的「死刑」観は、死刑廃止を資本主義国家の「ブルジョア的改良」の課題としてとらえ、人道主義を前面に掲げ、「違いをみとめあう、巾広い運動」をめざしていた。その姿勢を「廃棄」する必要は、全くない。
然し今の状況は、それをより深めてのりこえていく=「揚棄」していく必要にせまられているのだ。
死刑廃止を、ブルジョア的改良として要求する際にも、社会総体の変革のなかでそれを展望する意識性が必要であろう。人道主義は、変革の根本を流れる人間解放にまで深められねばならない。「違いをみとめ合う」だけでなく、共通点を探し合い、それをより拡げていくような巾広さが、必要とされるのではないか。
われわれのめざす死刑廃止は、先進資本主義国型の、刑罰の改良要求ではなく、ニカラグア革命におけるそれのような、人間の根源的解放の質をもった闘いである。そのような闘いこそが、日本天皇国家の特殊性によく対峙し、死刑廃止を勝利に導く原動力となるだろう。
*ニカラグアの《可能性》
「戦いが終って、私を拷問したものが捕えられた時、私は彼らにいいました。私の君らに対する最大の復讐は、君らに復讐しないこと、拷問も殺しもしないことだと。私たちは死刑を廃正しました。革命的であるということは、真に人間的であるということです。キリスト教は死刑を認めますが、革命は認めません」(現内相トマスーボルヘの言葉―太田昌国『死刑を認めぬ革命』麦の会編著『死刑囚からあなたへ』(インパクト出版会所収)
抜粋以上