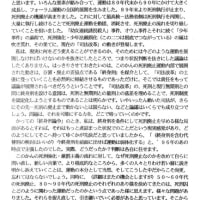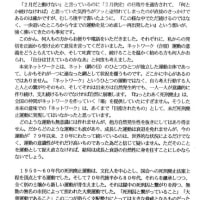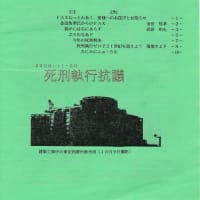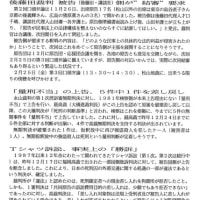永山則夫元支援者の武田和夫さんが、永山から追放された後、発行された『沈黙の声』という会報を冊子にまとめたものです。『沈黙の声』15号の記事を、以下に載せます。
『沈黙の声』第15号(85年12月15日発行)
「加賀乙彦『宣告』について」(1)
一
小説とは、思想をなまの形で伝えるものではないし、多くの場合それを期待されてもいない。しかしいかなる小説も、それが作者の世界観に基いた現実の再構成であるな上、そこには作者の思想が―場合によってはそれが、「思想」という硬質な言葉自体を拒否するような情緒的表現の中に漂っていようとも―息づいている事に間違いはなかろう。 ここでとりあげる小説「宜告」は、その様な作者の世界観、人生観が比較的はっきりと表現された作品であり、作者は別の場でそれを直接語ってもいる。本文がかかわり合うのは、この小説の、ひとつの作品としての全体性ではなく、そこに反映された作者の思想との対話をつうじて、われわれ自身の現在の課題を再倹討しようということである。
この小説は、拘置所の精神医であった作者による、死刑を確実な近い将来にひかえた死刑囚の、「死」を越えた人間的自由の問題を描いた作品である。 『死刑という極限の状況にあっても、なお人間は希望を失わない。いや、死と直面することからはじめて真の希望が生れてくる。……死の恐怖にあって、人間性を失い、逃避する人たちがいることも事実である。私はそういった死刑囚たちも見落さないように努めた。
が、私がおもに関心をもったのは、監獄という極端な管理社会にありながら、自由を失わないでいる人、死刑囚でありながら愛と希望を暖かく胸にいだき続けた人である。闇黒の世界でありながら、光明に充ちた楽土であること、これが私の目差したところである。」(「犯罪ノート」潮出版P20) ある抑圧的な機構や制度によって人間が本当に不自由であるのは、それが単に外的な強制力をふるうだけでなく、これが人間の内面に喰い込み、人々の精神そのものを支配する場合である。これはわれわれの、「死刑」との斗いにおいても問われる問題であろう。「さしせまった死」は、仲間達の内面に深く喰い入り、その視界全体K暗くおおいかぶさってくる。それは仲間の生と斗いを、展望のない、浮足立った、せつな的なものにおとし込めようとする。
ところで、この様な「外的」な抑圧に対して人間が内面の自由を獲得した時、この「外的」制度そのものはどうなるのだろうか。この小説においては、制度は制度として存在し続ける。ここでは人間一般に共通する。「死に直面した人間」の精神性のみが関心の対象なのである。
この対極に、「制度の廃止」のみを共通項とする「死刑廃止」の運動が存在する。その「死刑廃止」は、死刑囚自身の精神性、思想性とは、さしあたって無関係である。死刑廃止の斗いをつうじて、またその結果として死刑囚であった者がどの様に生きるのかにかかわらず、要するに死刑は社会に「不必要」であり、人を殺す基準が「恣意的」であり、「野蛮で残酷な」刑罰だから反対だという訳だ。
それも殺された被害者の問題をつきつけられると、極めて歯切れが悪くなってしまう。
支配者がある制度や機構によって人々を支配する場合、それが強権による恐怖によってであれ、イデオロギー的操作によってであれ、人々の内面を支配することなしには、それは決して成功しない。だから、人々がその制度の支配から真に内面の自由を獲得したとするなら、それは原理的に、その制度そのものの崩壊の第一歩でなければならない筈なのだ。先程の、「制度そのものはどうなるのだろうか」という疑問は、そのためである。
これらのことを考えていく前に、現在のわれわれの社会において、「死刑囚」とはいかなる人間存在として、「外的条件」によって規定されているかを、少し考えてみよう。
二
死刑の残虐さを問題とする時、中世の身体刑から我々が感取する「残虐性」が、多かれ少なかれ想起される。中世の身体刑のようなのを残虐というのであって、現代の死刑にはその様な要素はない、いや、質や程度の変化はあれ残虐であることにはかわりはない。という議論がなされる。ここで注意すべきは、中世の身体刑と近代国家の死刑との本質的な違いを度外視するかぎり、それは「残虐性の程度」の問題にスリかえられてしまうだろうという事である。
まず、中世封建社会において、裁判権、刑罰権を占有していた領主とは、農民に対する直接的な搾取階級であった。近代国家においては、自ら生産手段をもたない労働者が、食うために資本主義的生産機構のなかで働くことが「自動的」に剰余価値を生み資本を肥え太らせる。国家の役割はその様な「経済秩序」を確実に維持することである。
これに対し中世の支配権力は、自給自足経済を営む農民に対して、「保護」の名目で寄生しその生産物の一部を武力でもぎ取らねばならなかっだ。中世の身体刑は、領主権力の強大さを民衆に見せつける為の公開処刑であった。それは時として、被処刑者を奪い返そうとする民衆の、斗いの場ともなったという。
「有罪宜告を行なった権力側と、他方の、処刑の目撃者・参加者・不慮のしかも《顕著な》犠牲者たる民衆が、死刑囚の身体を介して対決していた」(M・フーコー「監獄の誕生」新潮社P69)
被処刑者はただ殺されるのではなく、手足をもがれ、熱湯で煮られ、火で焼かれることによって反抗者の肉体に無制限に加えられる支配者の力を立証せねばならなかった。権力の「恣意性」とはその絶対性を意味した。これに対し、「資本主義的秩序」が、合理的K、あたかも自明のものの如くに、維持されていくことを理想とする近代国家の刑罰にとって必要なのは、力の誇示ではなく、それが恣意性を排した客観的な基準にもとづいて確実に執行されることである。
「犯罪を予防する最良のクツワは、刑罰のきびしさではなく、刑罰の確実さである」(ベッカーリア「犯罪と刑罰」岩波文庫P114)
「人間が社会という形態に結合することを必要と仮定し、各個人の相対立する利害の意識によって彼らの間に規定された社会契約を仮定してみれぱ、そこからおのずと犯罪の段階づけが見出される。そのもっとも重いものは社会じたいの破かいを目的とする犯罪であり、もっとも軽いのは個人に対して犯されたささいな侵害行為である。そしてこの両端の間に、公共の福祉に対する違反行為がその段階の順にならぶことKなる」(同P125)
段階的な「計測可能性」の要請は、「拘留期間」を共通の尺度とする懲役刑への、刑の一律化を結果する。被処刑者は、権力の強大さを立証する肉体の苦痛に代って、社会的諸権利の停止を伴う「時間」を支払わされるのである。
監獄が対象とするのは、ただそこに一定の期間、抽象的に存在する「法的客体」のみである。ところで抽象的に存在する人間というものはおらず、そこには自己の「抽象化」にたえず反逆しようとする生ま身の肉体と感性が必ず付随してくる。そこでこれに対する徹底した監視と処罰による管理が、監獄にしかれることとなるのである。
生きるとは、生ま身の肉体と感性と思考とをもって、生産し、人々と交流し、生活を営むことである。近代国家の刑罰は、かかる人間の具体性のはく奪であり、ただ「法」のまえに抽象的人間として、あたかも近代ブルジョア法が「抽象的」に規定している「自由で平等な基本的人権」を、ある期間、制限されていることのみをその身体で示すべく存在することを、―死んだように存在していることを―求めるのである。
当然、身体は様々な形でこれに反逆する。
「拘禁反応」とは、行き場を失った肉体と感性が崩壊しつつ発するうめきに他ならない。
筆者が入獄していた刑務所では、ツメが徐々に消失していく奇病があった。監獄医とは、かかる肉体と精神が、定められた刑期の「時間」を間違いなく担いきるために監獄に配置されるのである。
「矯正」を名目とする囚人労働は、囚人のかかる身体に対する、経済的配慮を加味したひとつの管理策であろう。
どの監獄でもそうだと思うが、『「禁箇刑」者は「請願作業」という形で工場におりるのが通例とされている。独居拘禁の心身に及ぼす破壊性は、当局が誰よりもよく承知しているのである。近代の刑罰の矛盾性とは、獄中者の人権云々という以前に、そもそも刑法は、その刑罰の在り方が必然的に結果するところの心身の破壊については何一つ規定していないこと、肉一ポンドを切りとるべしとしか証文にないのに、遠慮会釈もなく血をどんどん流させているところにある。しかもその事を指摘すれば、司法権力は「肉を切りとれば血が流れるのは当然だ」と居直るのである。
ところで、かかる近代国家の刑罰における最高刑とは、この様な「抽象人間」としての存在期間を最高度に引き延ばされた存在、「終身徒刑囚」であるはずである。死刑とはその「期間計算」を放棄した異質な段階への飛躍である。たしかに、被処刑者を出来るだけ瞬時に殺すよう、肉体的苦痛を排した端的な「死」そのもののみを与えるよう「配慮」した現代の死刑は、「処刑によって完了される終身刑」という側面をもつかも知れない。
然し何ゆえに、かかる「死」が必要なのであろうか?
終身刑の心身の過度の消耗と、それを管理する側の経済的負担の大きさ、という事は、消極的理由でしかあるまい。結局のところ、死刑とは、ある人間に対する絶対的な権力の行使をいみすること、ある期間がすぎれば彼にその身体的具体性を返還してやるというのでなく、それを根こそぎ奪い去る権限があるのだと示すことである。近代国家がその権限をなかなか手放そうとしなかったということは、それが単なる社会契約の仲介者でなく、あくまで「支配権力」として、その絶対的権限を被処刑者の身体への「生殺与奪権」として示し続ける必要があったという事にほかならない。
とくに日本のように、支配権力が生ま身の身体を有する一人の人間と密接に結合し、融合しあっている場合、支配はその対極にも被処刑者の生ま身の身体をいけにえとして要求せずにはおかない。
「沈黙の声」は、日本における死刑存置は、端的に天皇殺害者に報復する必要があるためだと指摘してきたが、フーコーはこれに対し、以下の様な示唆的な文章を示してくれている。
「どんな犯罪〔=法律違反〕のなかにも、一種の大逆罪(crimen majestatis)が存在し、どんな些細な犯罪者のなかにも、小型の国王殺害者が潜在的に存在しているという次第である」(「監獄の誕生」前出P56)
この様にして、現代の死刑囚は、その身体的具体性を奪われた「抽象人間」の極限の存在、再び「具体化」することなく。
その死までを文字どおり「死んだように生きる」事を強いられた存在であると同時に、その「死」が近い将来に確実に予定された者として、その「死に至る生」は日々の処刑宣告の予感のなかで逆に最小限にまで短縮され、日々を「殺されつつ生きる」くり返しの中に置かれるのである。
われわれは、死刑囚とされた人達が、この様な外的条件のなかで、どの様な内面の自由を獲得したのかではなく、かかる外的条件による人間の、「抽象化」によっては否定し去る事の出来ない生ま身の人間の肉体、感性、精神の沈黙の叫びが、どの様な具体的な在り方・生き方・斗い方に結実した時、それはかかる外的条件を越えて、多くの人々と結びあい、その人間としての具体性を再び復権していくことになるのか、をみるべきだと思う。
(その2)に続く