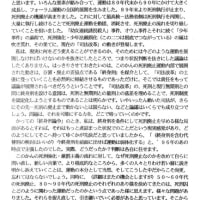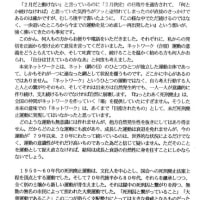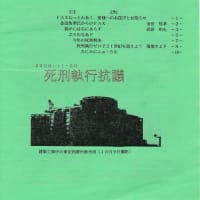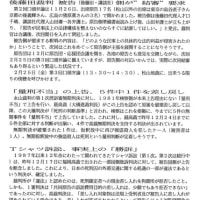永山則夫元支援者の武田和夫さんが、永山から追放された後、発行された『沈黙の声』という会報を冊子にまとめたものです。『沈黙の声』11号の記事を、以下に載せます。 ここでは、永山則夫についてではなく、太田竜の思想に対する指摘のようです。
『沈黙の声』第11号 1985年3月30日発行
マルクス主義・宗教・天皇制あるいは太田竜の転向最深部へ向けての果てしなき退却について
序ノ一
本文は、単なる”批判’の為のものではない。
序ノニ
1980年4月の時点で、太田竜は『・・・宗教論とマルクス論という、現代世界の核心に触れる二つの重要テーマ』 (「宗教と革命」まえがき)と述べている。
82年4月、太田は『…日本原住民=縄文人的伝統を今巳的な形で復活させ、発展させるという口的意識を以て』 「日本原住民と天皇制二なる書物を発行(前掲文は同序章)した。そして八三年五月発行の「琉球孤独立と万類共存」(以上いずれも新泉社)では、『私たち人類はいま、切迫した自己破壊、自己絶滅の危機に直面している。すべての先入見、偏見を卒業して、生きのびる道を探究しなければならない」(同、冒頭)と語っている。
80年代に入ってからの、三著書における太田の以上三つの「テーマ」を記憶しておいていただきたい。
一、マルクス主義
太田竜のマルクス「批判」の前提は。マルクスが原始共産制の解体、人類社会の階級社会への分化を「歴史の必然」として「肯定」している、 という主張である。 マルクスに代表される弁証法的唯物論者の歴史観は、人類社会の段階的移行は、外的要因によって決まるのではなく、その社会内部の矛盾性によるものであり、ある歴史段階自身がその内部K育成する矛盾か、その段階の解体と新しい段階への移行を必然化するものである(外的要因もその社会内部の矛盾性に作用しなければ、社会を変化させない)こと、その歴史の主要な推進力は人間の生産力と生産関係との矛盾性であり、歴史推進の主体は(「政治」的地平に登場すると否とを問わず)生産階級であること、この様な観点にたっている。
まず、太田のいう「マルクスの歴史観」なるものは、“へーゲル歴史哲学の「継承」”であるところの 原始共産制(テーゼ)/階級社会(アンチ・テーゼ)/より高次の共産主義社会(ジノーテーゼ)である((宗教と革命」204貞)という「一見尤もらしい」俗流解釈のデマであることを確認しておこう。
太田の主張によると、「原始共産制」は、階級社会に移行する否定的媒体を内包しないものでなければならず、階級社会は原始共産制の「外からにもたらされたものでなければならない。と卜う事になる。 太田自身は、原始共産制から「階級国家の成立」の「過渡期」(太田によると、エングルスはこの本質にまったくせまっていないという)をどう考えているであろうか。
『人類は、数十万年ないし二百万年におよぶ、原始共産制社会の共同の労働を通じてその身体・諸器官・その五感・その頭脳をつくり出した。数十名ないし数百名の個体からなる、原始共産主義的社会組織(「氏族」組織において頂点K逐した)という、この「生産関係」において、人類はみずからを他の生物、動物のすべての種属から決定的に区別し、止揚する、そのような種属へと、つくり変えた』(前掲176頁)
ここまでは、原始共産制社会の内的必然性による過程とみてよいのであろう。ところで、この過程で人類は地球上のすべての地域に広がり、治水技術の開発、大規模な定着農業と大規模な家畜産業の発明、生産力の飛躍的な発展とともに 『右の原始共産主義的「民族」相互の関係に一つの質的変化が生じた」 (同176頁)ここではまだI輿から質しの変化が論じられているだけで、外的要因は介入していない。ここにおいて、それまで「偶発的」であった「氏族」(および「氏族連合体」)相互の「斗争」は、 「非和解的で、相互絶滅的なものに転化した」(同)というのである。 このような「原始共産主義的氏族社会」。の排他性、侵略性は、「家族、私有財産、国家の起源ににおけるエングルスによっても語られていないほどである。
太田によると、かかる「相互絶滅戦」において偶然的に「地の利」をえた勝者が敗者を奴隷にする過程(かかる人種的植民地支配が階級支配の「原基形態」であり、マルクスの階級斗争史観はこの観点を切りすてている、という)で、敗者たる氏族連合体内部の原始共産主義的同胞関係が解体され、この奴隷とその生産力の分配をめぐって勝者たる氏族連合体内部の原始共産主義的関係がくずされ、所有者(貴族)と無産者(平民)への分化が発展する、というのである。(同177・178頁)
もしこの様な「原始共産主義的氏族社会」内部に、いっさいの私的所有、ないしその萌芽が形成されていなければ、たとえ「相互絶滅戦」をやって他の氏族を打倒しても、それを奴隷として「所有」しようという考えは生じないはずである。エングルスは、そういった段階の社会について、征服した敵を「男は殺されるか、または勝利者の部族に兄弟として迎えられるかした。女はめとられるか、またはその生き残りの子といっしょに同じく養子に迎えられるかした」(「家族よ岩波文庫72頁」とのべている。彼らは、その死生覿の違いから「殺す」ことにそう抵抗は持ってなかった様だが、敵とか味方とかいう事については太田の考えるよりずっとおおらかであった様だ。
被征服者を奴隷とする社会とは、すでに奴隷制を必。要とする杜会であり、その原囚は原始共産制社会内部の分業と生産力の拡大に伴なう私有制の開始である。それは、人間の労働が、第一義的には他の動物と同じく「食」うためのものであるがその「意識的活動」としての性格から、分担と協働、道具の発明等々により生産力拡大を必然化するという「自然的過程」の結果として、剰余生産物が発生することに端を発していた。「分業」が共同体における個人の重要さに位階をつけていったことが、この剰余物の分配を不均等にし、「持てる」者と「持たざる」者をつくっていったのである。
太田の様に、階級社会の発生は、原始共産主義的氏族の争闘の結果あるものが征服者となり。他のものが被征服者。収隷となったという様な説明は、階級社会発生の「本質」について、なにごとをも語っていないのである。 さて、太田は、市民の「歴史的論理的起源」は征復された奴隷の「一部分を彼ら(支配者)の側に抱き込む)に(同172頁)ところに求められるとする。「市民」とは転向奴隷、「解放奴隷」であって、『(マルクスは)もっぱら市民社会を分析するのであるから、それを基礎とする「革命論」は、支配者と転向奴隷だもの八百長芝居の演出計画に、必ず帰結するのである。」 (173頁)というのである。 「市民」が「買収された奴隷」に起源を発する、というのは、現在の「市民社会」に対する直感的感覚的な印象からはいかにももっともらしくうけとられる。然しただそれだけのことであって、こ
の様に、物事の本質を「遠い過去のエピソード」に還元して説明しようという傾向は、真実を追及する者が厳にいましめねぱならぬものである。 古代国家における「市民」とは、所有階級内部の争闘で政族政を打倒した平民が、主体であって、「解放奴隷」はその一部にすぎない。古代国家社会の生産階級たる奴隷が「市民」へと買収されるには、以降の二千年余の年月を要する。古代社会の奴隷は「市民」の所有物であって、法的人格を与えられていなかった。
そして古代国家の没落と奴隷反乱の教訓から、支配(搾取)階級は奴隷に代えて、「法」の前に人格をみとめる「農奴」をつくった。然しながらこの中世封建国家の「法」は、人間の不平等を前提としたものであり、農奴を力づくで収奪するための「法」であった。この「法」を権威づけたのが中世の「宗教」である。ブルジョア近代国家において、農奴はおそかれ早かれ「解放」され、生産階級は搾取階級とともK「平等」な人格をみとめられ「市民」とされたかそれは資本制的搾取経済が、その恨本原則たる「等価交換」で社会全体をおおい尽くす必要があるためであった。この様にして奴隷は、現実には奴隷のままで、抽象的な「平等」的人格を与えられ、「市民」として支配に組み込まれたのである。だからこそマルクスは、この「市民社会」を分析し、生産階級がこの社会を内から破壊する必然性を明らかにしたのである。
弁証法的唯物論者は、全ゆる事物、全ゆる組織体は、その内的矛盾性によらないでは変化(解体)しない事を知っている。機械的唯物論者でしかなかった太田は、社会を、「下から」 「引っくりかえす」とかいう力学的、機械論的な「革命」観しかもたず、日本帝国主義の打倒はその「市民社会の揚棄」なしにはありえない事を理解せず、アイヌ、沖縄の人民の斗いに寄生しそれを後ろダテとした反マルクス主義、「反共主義」のデマゴギーを流して日帝に貿収され挑発分子となり下るのかその必然的結果なのである。
二、宗 教
太田は、共産主義(マルクス主義)を「無神論、唯物論」と規定している。これは太田自身が、かつて単なる無神論者、(機械的)唯物論者であったにすぎない、という以上の何も意味しない。
弁証法的唯物論者に、「神」という概念を前提とした「無神論か有神論かにではなく、「神」自体が人間の自然的本性の反映であることを理解するものである。 マルクスは、モノが人を支配することを説いたのではない。人がいかにモノに支配されてきたか、その歴史的法則を明らかにし、モノの支配から自由になる途をさし示したのである。歴史的必然性を知るという事は、その必然性から自由になる前提であって、それは各人の主体性にかかっている。ブルジョア学者はそこから「経済学」をしか引き出さず、俗流ブルジョアイデオローグ(デマゴーグ)はこれを「モノの支配の理論」としか理解せず、自らはただ現実に「抗議」するだけである。斗う被抑圧人民のみがこれを未来を切拓く武器とすることができる。
太田竜は、「宗教批判」の「若干の結論」として、『宗教現象とは(A)正確、厳密にいって「宗教」と呼ぶべきではないが「祭り」を通じて人間と宇宙が合一する体験(B)共同体を破壊されて狂気に走る人々の病いをなおす(安心立命を与える)ことが「宗教」の基礎である」 (同116頁)とのべている。これで「宗教」のなにを結論づけたのかと言いたいが、太田は、「自然宗教」をいとなむ『自己を自然から分離しない』人々の中に真実を見出すべきであるといってマルクスを論難(同31頁)している。
それで、ここでは人間と「自然」との関係が問題とされねばならない。
太田が、『自己を自然から分離しない』あるいは「原始宗教においては、人間は自然から自己を分裂させておらず、自己を自然の一部であると信じている』(同15頁)という時、人間と自然の関係を決定するのはあくまで人間の主観でしかない。 マルクスによると、人間と自然との関係は次の様になる。 「人間は自然によって生きてゆく、という意味は、自然は人間の身体であり、人間は死なないためにはたえずこれとかかりあっているのでなくてはならないということである。人間の肉体的および精神的な生活が自然と連関しているといることの、ほかならぬ意味は、自然が自然自身と連関しているということだ。人間は自然の一部分であるから。」 「意識的な生活活動が人間を動物的生活活動から直接に区別する。まさしくこれによってのみ人間は一つの類的存在である。あるいは、人間が一つの意識的存在であるのは、すなわち、彼自身の生活が彼にとって対象であるのは、ただ、まさしく彼が一つの類的存在であるからにほかならない。」(「経済学・哲学手稿」国民文庫105、106頁)
全ゆる動物は、自然に働きかける(食物として摂取する)ことでその生命体(という自然)を再生産するのだが、人間はその意識的な生活活動によって、自然そのものを(自己の外に)再生産する。人間の労働とは、人間の自然的本性の外化、対象化の行為であり、それによってはじめて人間 は自己の外なる自然を「対象」として意識するのである。この意識的生活活動の収約されたものが「社会」であって、これは原始共産制社会においてもかわらない。そして、かかる人間の自然との関係は、ただあるがままの外的自然にどの様な態度をとるかで決まるのではなく、人間社会がどの様な意識的生活活動によって自然を対象とするのかによって決まる。端的にいえば、それが個々に分断された中で、一部の者の支配と収奪という関係性においてなされるならば、対象化された「自然にそのものが人間に対してよそよそしい関係としてたちあらわれ(これを「疎外」という)、人間による生産は自然を収奪し、これを破壊するものとしてしかあらわれないであろう。人間各人が自己の生産活動の主人公となり、共に生産し共にわかち合う共同的存在となるならば、人間はその生活活動において自然を「疎外」せず、自然の本性にそった生活を回復する事が出来よう。 太田は、人間と自然を区別するこの意識的生活活動そのもの忙反対することになるのだが、それだと「原始共産制社会」そのものをもさかのぼりまさに人類の発生期に「真実を見出す」しかない。
なるほど、太田は「人間が動物でなくなるということ(人間が自然から絶対的に自己を区別すること)は、疑いもなく、人間の種属の現実的な消滅となる」(前掲30頁)という。人間はまさにヒトとして種属的に発生した地点から少しでも前進すれば「種属」でなくなる、というわけだ。 太田のこのような考え方がなにの反映であるの 4かは、太田の「資本論批判」をみれば分る。 太田の資本論「批判」とは、「資本制生産様式の支配する社会の富の原棊形態は、「商品」である」という「冒頭Q一句」に対して、「地球上の空気は、一体「富」であるのかないのか、…太陽の光は「富」であるのかないのか・:地球そのものは「富」であるのかないのか」(同250!一一一頁)と反論することに始まる。つまり、これらは人類に不可欠な要素であるが『資本主義の商品ではない』として、「商品の分析」から始めるマルクスに反対するのである。 マルクスは「社会」を分析しようとしているのである。社会は人間がつくったものであるから、
人間がつくった訳ではない空気や太陽の光や地球を分析しても、社会のことは分らない。それはそれとして、太田はこのことから、マルクスの理論は「労働価値説」であるとし、それは「自然は価値を生まない、ただ人間労働のみが価値を生むとする」 (同252頁)ものだとし、『…つまり、人間労働が価値の源泉である、という説です。…「労働価値説」に立脚するという点では。「社会主義」は「資本主義」と同じ穴のムジナです」 (「琉球孤独立と万類共存」190貞)等々といった形で、再三にわたりくり返している。 太田は、かって「マルクス主義者」であった当時、マルクスの理論とは「すべての価値の源泉は労働である」という「労働価値説」である、と理解していたようだ。 マルクスは、「労働はすべての富とすべての文化の源泉である」という「ドイツ労働者党綱領」を批判して。次のようにいっている。 「労働はすべての富の源泉ではない。自然もまた労働と同じ程度に、諸使用価値の源泉である。…そしてその労働はそれじたい、ひとつの自然力すなわち人間的な労働力の発現にすぎない。」(「コーダ綱領批判」岩波文庫25頁) なぜマルクースがこ5反論するかといえば、「労働のみが価値の源泉である」という古典派経済学者率、「ゴー夕綱領」の主流ラサール主義者は、「労働」そのものにおける疎外を問題にせず、労働生産物の「平等な分配」のみを問題にするからである。マルクスは、この樣な「労働」万能主義と、疎外された労働の結果としての「私的所有」に反対するだけのこのような考え方に対して。
「奴隷たちのよりよい賃金支払よりほかのなにものでもないであろうし、労働者にも労働にもその人間的な使命と尊厳を獲得したことにならないであろう」(「経・哲」前掲115頁)といっている。ところで太田は、「資本論」の内容を 「工場内部の秩序そのものを所与として前提して、労働時間と賃金をめぐるものとして記述されている」 (「宗教と革命」222頁)というのであるが、これは太田白身が、かってどの様な「マルクス主義者」であったのかを示すものである。つまり太田は人間と自然との関係を、ある場合には自然は自然、人間は人間という全く連関性のない二物として(これはブルジョアの自然観である)またある場合にはパク然とした「人間を自然から分離しなどと混然一体としたものとして(これは小ブルの主観的願望である)抽象的にしか理解せずその・結果、マルクスにおいては本来自然によっての「マルクス主義者(?)」、「共産主義者」であった、ということだ。 「労働が全ての価値の源泉である」という労働万能主義は、けっしてマルクスの立場でもなければ、プロレタリア的な考え方(イデオロギー)でもない。むしろそれはブルジョアジーが労働者をおだてて働かせる為のレトリックである。
そして太田の様な小プルは、この前に右往左往し、逆に「労働は美徳である、という「倫理」」に反対する(同111頁)という形で今度は「労働」の全面否定Kおちいるのである。 さて、「宗教」の問題に戻ろう。 「自然宗教」は「宗教」とよぶべきでないという太田に反してこれがあくまで「宗教」であるのは、そこにおける人間と自然との「合一体験」とはあくまで幻想領域のものであり、それは逆に人間が自然に対して社会を形成しつつあることの反映にほかならないためである。
一口にいって「宗教」とは人間の疎外された類意識である。「自然宗教」とは、労働によって自然を「対象」とし、「社会」をつくりはじめた人間が、自然のまえでの「類」としての一体化を「祭」のなかで、幻想体験として実現するものであり、そのようないみで「宗教」の萌芽形態といえよう。 さきの太田の「若干の結論」は、要するに「宗教」の幻想性をのべているだけで、「宗教はアヘ絶対的に制約されたものである労働、自然との関連において人間の本性を外化させるものである労働を、「全ての価値の源泉」と理解していたということ、それ故「労働生産物の分配」の問題としてしか社会主義、共産主義を理解しない、古典派経済学者、社民、「国家社会主義者」ラサール並の「マルクス主義者(?)」、「共産主義者」であった、ということだ。 「労働が全ての価値の源泉である」という労働万能主義は、けっしてマルクスの立場でもなければ、プロレタリア的な考え方(イデオロギー)でもない。むしろそれはブルジョアジーが労働者をおだてて働かせる為のレトリックである。
そして太田の様な小プルは、この前に右往左往し、逆に「労働は美徳である、という「倫理」」に反対する(同111頁)という形で今度は「労働」の全面否定におちいるのである。 さて、「宗教」の問題に戻ろう。 「自然宗教」は「宗教」とよぶべきでないという太田に反してこれがあくまで「宗教」であるのは、そこにおける人間と自然との「合一体験」とはあくまで幻想領域のものであり、それは逆に人間が自然に対して社会を形成しつつあることの反映にほかならないためである。一口にいって「宗教」とは人間の疎外された類意識である。「自然宗教」とは、労働によって自然を「対象」とし、「社会」をつくりはじめた人間が、自然のまえでの「類」としての一体化を「祭」のなかで、幻想体験として実現するものであり、そのようないみで「宗教」の萌芽形態といえよう。
さきの太田の「若干の結論」は、要するに「宗教」の幻想性をのべているだけで、「宗教はアヘンである」という「マルクス主義」的教条と何のかわりもない。「宗教」の二側面を語るのであれば、それは次のようなものであろう。
(イ)人間の類的本質、自然的本性を幻想の領域で経験せしめることによって、人間解放の現実の運動に力を与えるもの
(ロ)人間の将来あるべき類的共同性を、超越者の権威を前提として現牟あるがままの疎外された関係性のなかに実現されたかの如くに装い、そのことによって帰依者の自然的本性を抑圧するもの この両者は表裏一体のものであり、多くの「宗教」がその発展期には著しい革命性を発揮するがいったん権力をにぎると民衆に対する抑圧者に転化するのは、この両側面のいずれが支配的であるかによるものである。
このような現象は、「革命運」のなかにも見られるものであることが分ろう。
理論とはあくまでも現実の反映であること、そして共産主義とはその実現にむけた大衆の一歩一歩の運動であることを理解せず、現実を理論に従属させるところから、革命の「宗教」化がはじまる。この時、かかる人間の宗教性と、それを生んだ現実的基盤の貧困さを問題にせず、それは「革命」そのものの誤りであるとするのか、帝国主義者による反共宣伝であり、それに一理論」的裏付けを与えるべく、「マルクス批判」を試み、かくの如く自らの内実をさらけ出しているのか、太田竜である。
(その2)に続く