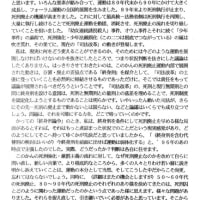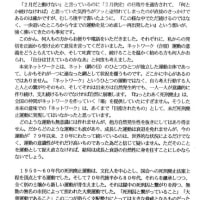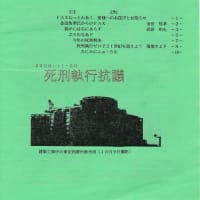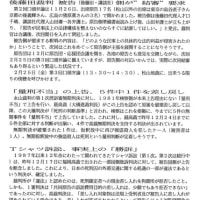永山則夫支援者だった武田和夫さんが永山さんから追放された後、武田和夫さんが「風人社」という死刑廃止団体を立ち上げた。その時、発行していた会報『沈黙の声』を冊子にしたもの…の第二弾。
『沈黙の声』の第26号の記事を、以下に載せます。(その1)(その2)の2つに分けます 
『沈黙の声』第26号(87年12月20日発行)
「死刑との闘いに今何が問われているのか」 (その1)
9月30日、東京と大阪で同日に2名の死刑確定囚が処刑された。
大阪拘置所で処刑された大坪清隆氏は、一審は無期だった。76年12月の事件(被害者2名死亡)で、上告棄却は79年4月。わずか2年半足らずの間に、いったんは生きて償えとされた判決は全ての「審理」を終え死刑に転じたのである。 東京拘置所で処刑された矢部光男氏は、30才半ばの死刑だった。76年6月の事件で上告棄却は80年3月。この3年9ヵ月が、「中学一年のとき伯母の子を殺し少年院に入った」という彼の行なった事件を審理する全期間であった。
処刑の情報は、いずれも法務省、拘置所当局からのものではない。それ故まだこの他に、隠された処刑の事実がないとも限らない。当局は、〝情報もれ〟に極度に緊張し、これに関連する獄内外の通信文に対してはスミヌリの山を築いている。大拘には法務省より、調査の手が入ったほどである。
権力が処刑の事実を隠すのは、「本人の家族その他の関係者への配慮」(法務省の回答)がその真の理由ではない。事件以降、裁判終了まで、捜査当局はマスコミに悪質な虚偽の情報をたれ流して〝凶悪さ〟をあおり立て、記者に特権を与えた公開の法廷で、家族その他の関係者を含めて完全にさらしつくした末に、いざ処刑する時のみ何故、ひた隠しにするのか?
死刑の存置にはあくまで固執する国家権力が、そしてそれ故にこそ、実際の処刑は出来るだけ人の目から遠ざける必要があるためだ。
権力に必要なのは〝法違反者に対しては命も奪いうる〟という国家の権限を、死刑宣告によって誇示することである。誇示はするが、それに必然的に伴う実際の殺人行為が、処刑の度に国民に想起されることがあってはならないのだ。
「…その処刑場面のありのままの姿が、公衆のあたまに思い浮ぶようになったら、その実施はとても困難なものとなるだろう」(A・カミュ『ギロチン』より)
それを行ない続けるには、出来るだけ秘密裡に行なわなければならない国家制度。それに言及する通信をことごとくスミヌリしなければ安心して実施できない様な国家制度。それがいかにして、正義でありうるだろうか。
今年、最高裁では7件8名の死刑上告事件に弁論を強行し、4件5名に死刑確定判決を行なった。更に12月18日にも一人の仲間に対し判決を予定し、来年2月には更に3件の死刑事件に弁論を強行せんとしている。下級審で控訴・上告せず死刑確定した2名を加え現在ですでに7名の死刑確定であり、ここ15年間の死刑確定が平均4名弱であることからみても、異常なペースといわざるをえない。
この動きに主導され、一、二審での死刑判決も昨年の12名に対して今年はH月までで20名と(ネ上っている。これは事件そのものの数や質の統計的反映ではありえない。 今年2月3日の、東アジア反日武装戦線に対する弁論強行以降の死刑攻勢は、歯止めを失った殺人ラッシュとなって続いている。「2・3」は、昨年3件の最高裁弁論を阻止し、年間の死刑確定をゼロとした、このかんの死刑廃止、処刑阻止の闘いに対する権力のまき返しの突破口であった。この「2・3」を、全ての死刑囚仲間への攻撃として闘いきれなかった弱さが、今の死刑攻勢に対する闘う側の反撃の弱さとしてそのまま引きつがれているといえる。真剣な総括が今こそ必要なのだ。今、何か闘いに問われているのだろうか?
***
「死刑の判決数・確定数・執行数は年々減少気味である。今後も特別のことがない限り、さらに減りつづけるだろう」―83年発行のある総合誌の「死刑」特集からの引用である。こうした楽観論は、当時の死刑廃止運動全体の雰囲気としてあった。同誌の別の筆者は次の様にも書いている。
「現在日本の死刑制度は、すでに歴史的に要求されてきた役割を終え、近代法がその内部にかかえる矛盾によって存在基盤を脅かされ、廃止のための制度的条件が整いつつある」-これらの見解は、あらわれた現象をただ表面的にとらえたのみであり、一般論として全く間違いという訳ではないが、近代国家における死刑制度の本質のとらえ返しも、日本国家におけるその特殊性のとらえ返しもなく、また権力側は後退すればする程強権をふるうという、闘争のダイナミズムも反映されていなかった。この楽観論の思想的根拠は、「近代主義的幻想」であった。
同じ筆者はいう。「現在の死刑を支えている思想は、封建時代の法思想の流れをくむものである。」―死刑制度は「前近代の遺物」であるから、早晩消滅するものであるし、早く消滅させねばならない。それは死刑廃止運動内部の一般的な「死刑」観として存在していた。それは死刑廃止運動の在り方や、それへの外からの認識を根底から規定してきたといえよう。
’83年に風人社=「沈黙の声」は活動を開始した。それは83年7月の、永山裁判最高裁「差し戻し」に対して、それ迄主体的に闘ってきた「永山裁判闘争」を総括し、以降の権力のまき返しに対して。 「死刑との闘い」の地平を守って闘い続ける為であった。「沈黙の声」が担った状況をとらえ返す中からは、「死刑廃止」に対する楽観論は出てこなかった。81年の永山裁判高裁減刑以降、最高裁で停止していた死刑確定裁判の再開は、まさに一つ一つの裁判で死刑存廃を問うていくべき状況をもたらした。この攻防のなかで、「死刑」をより本質的にとらえる必要から、「声」2号以降の『死刑廃止論』での一定の分析があった。
(その2)に続く