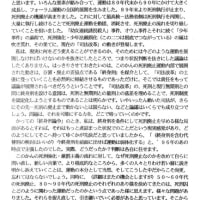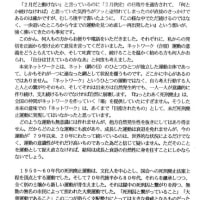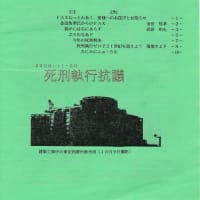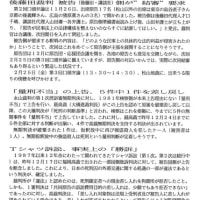三
「宜告」の主人公である死刑囚・楠本他家雄に作者はこう語らせている。
「おれは人間であることを許されてはいない。法律規則という人間の作った文章が、おれから人間の属性を一つ一つ剥ぎとっていった。刑法、刑事訴訟法、監獄法、数多くの訓令、通牒、通達、判例が、目に見えぬメスとなっておれから人間の属性を削ぎ落していった。
しかし……しかし、それでもなおおれは考える。おれは死刑囚でも番号でも一枚の板でもなく、人間でありたいと。なぜならおれは絶望することができるから、一枚の板のように従順に静かに平和に存在するのではなくて、おれには絶望する自由が残されているから。……
それでは絶望とは何か。それは未来に立ちはだかる処刑台に怯え、再び実社会に帰りえぬことを嘆くことではない。そういったことは絶望の外的条件にすぎない。もし何らかの機会におれが減刑され、あるいは実社会に戻れた場合でもなお消えぬ絶望、それが真の絶望である。
ああ、しかし、このことを人はなかなか理解してくれない。人はおれの陥っている外面的な条件ばかりを見、分析し、おれの真の絶望には目を向けてくれない。はっきり言おう。おれは悪人だ。おれは殺人者だ。おれが死刑囚であることは殺人者であることにくらべればとるに足らぬ些事なのだが、同囚たちも看守たちも、そして新聞記者も善良な神父や修道女たちも理解してはくれない。」(「宣告」新潮社版上巻P89)
死刑とは、人間存在のより眼底的な絶望に向き合わせられる外的条件にすぎない、というのが主要なトーンとして流れている。この対極に「外的条件」こそ主要であるとし、自己の犯罪は外なる「社会悪」に対する「革命的行為」と信じている一人の死刑囚が存在させられる。主人公楠本は彼にも、『「……殺す側の人間だけに、お前の視野は限られているが、殺されるのはおれたちの側なんだから、つまり死刑という現象の半分はおれたものものだろう。いや、もしかしたら全部かも知れん。……」「強制されようが、自然に死のうが、また自殺しようが、死は自分の死、自分に属するものだっていうことだ」』(下巻P60)と語っている。
外的条件を否定し去ることはできない。しかしその外的条件にもかかわらず人間は内的自由をうることができ、そこに残されたものがたとえ自己の「死」のみであっても、その「死」から目をそらさず、その「死」によって照射された自己の絶望の生を、わがものとして生き抜くことができる。 かの「革命的犯罪者」は、その犯罪を「ブルジョア権力に飼い慣らされたプチ・ブルジョアの雑貨商夫妻を革命的に抹殺した」「階級敵と斗う」行為であると支持する「革命組織」に支援されている。この「組織」の支離滅裂ぶり、非現実さはとりあえず度外視するとして、この「組織」に対する、作者のもう一人の分身、拘置所配属の精神医・近木の言に耳を傾けよう。
『「死刑制度は現にあるんですよ」近木は、自分の想念が相手に伝わらないのをもどかしく思った。「この頃も死刑の執行は頻繁におこなわれている。河野も確定者である以上、明日にも処刑される可能性がある。ぼくには彼の反抗が、絶望から来る幻想に見える。彼は自分の死を正当化するために被害妄想の体系をせっせと構築した。もしも他人に全責任があるとすれば自分は絶対に無謬でいられる。これが被害妄想の構造ですからね。……本当は彼は自分の死を自分の手に取戻す権利がある。それが、本当に人間の尊厳を守るということになりませんか」』(下巻P60)
たしかに、「強いられた死」をテコに、自分を絶対的無謬者とする「体系」を構築するこの様な死刑囚が仮にいるとすれば、彼の「斗い」はいずれ反動に転落していくであろう。しかしこれを批判し、「取り戻すもの」としては自己の「死」しか残されていない死刑囚に、その「死に至る生」を自分のものとして生き抜くことを要求する近木医官自身は、自分の「生」にどう責任をとろうとしているだろうか。
『「そう、ぼくだって(監獄医を)やめたいですよ」………「しかし、監獄医が全員辞めちゃったらどうなりますか。〔ここに論理の飛躍がある〕拘置所は無医地帯となる。〔囚人を心身の破壊から守って刑を全うさせるのは現代の監獄自身の要請である〕医者がいなくなったところで、拘禁と管理を目的とする監獄なる場所は存在しますよ。〔そうだろうか?もし医者が全員辞める様な事態が生じればそれは監獄の存立にかかわる問題ではないか〕だったら、その場所で、不充分でもとにかく医療行為を続けようという医者がいてもいいでしょう。」』(下巻P88)
このふし穴だらけの論理に、かの非現実的な、「革命組織」の腰ぬけメンバー達は一瞬「気圧されて黙った」というのだが、「囚人に病気がおきたとき、やはり医者が必要なんだ』(同P190)という一般論こそは、この近木のような医官が、その置かれた状況における自分の「役割」を自覚し人間として真に自分を「取り戻す」ことをはばんでいる論理なのである。
『私たちは死を宜告された死刑囚を、気の毒な人間として憐れむ。しかし、自分自身も、神によって死を宣告されているのだ。この悲しい省察が喜びに転化する不思議が宗教なのである。』(「犯罪ノート』前出P75)
死刑囚とわれわれとが人間として同一の地平に立ちうるのは、たんに『人間』一般として、存在への不安を共有するからだけではなく、われわれが自己自身の存在の犯罪性を自覚し、自分も同じ罪人なのだと知るところからではないだろうか。それを見ないということは、逆に死刑囚の「犯罪」を一つの前提としてそのままにしておくこと、そこにわれわれとの区別を、暗黙のうちにみとめ、「死刑」による両者の分断をうけ入れてしまうことではないだろうか。
「どんな悪人も改心によって許されるというのが宗教の原理であって、この原理からもっとも遠いのが死刑制度である」(同P164)と作者はいう。
ところで、人間的な意味で許される、許されないということと死刑とは区別されなければならない。そして、どんな「悪人」も、自らそれに気付く前に、すでに、神の前に救われるべき一人の人間として存在させられているということ、それが宗教の原理であって、これからもっとも遠いのがブルジョア的人間観―「評価」の論理、「功績」の論理、「有効性」の論理-なのである。
「改心しない死刑囚』を、人間性を失い「死から逃避する」死刑囚を、作者はどう見るのだろうか?『自分の過去を反省し、被害者の冥福を祈り、ひたすら悔悟の生活を送っている者が処刑される。その反対に、犯行について何の反省も自覚ももたず、房内でも反則と犯行に明け暮れている者が、いつまでも生かされていた』(同P165)
要するに作者の言いたいのは、死刑の「恣意性」という事なのである。
この小説に登場する他の死刑囚たちの「狂気」や「反抗」や念仏、それらは、全ゆる身体的具体性を削ぎ落された、「死に至る抽象的存在」が、なおかつ生ま身の人間として生きんとするひとつの具体性である。それは、死に至る自己の生を、宗教という高度の抽象性の力を借りつつ自己のものとして生き抜こうとしている楠本の得た「愛」―それは、何らの利己的目的からではなくただ相手を一人の人間として、素直な心で見つめていこうとしている女性と、その彼女にただありのままの自分を受け入れてくれる事だけを求める楠本との、無償の、本来の「愛」の姿であるが―とは「外形」においては大きく異なる、絶望的で、不幸な在り方ではあるが、しかし逆に見れば、楠本の「愛」の様に自己完結することなく、矛盾を矛盾として外在化させているだけに、その矛盾をもたらす「外的条件」の施行者たちを悩ませ続けずにはおかない。
私には、この両者のいずれかを重視するよりは、両者の「分裂」そのものが心に残ってしまうのである。
彼らが意図すると否とにかかわらず、彼らの追いつめられた生の根底からの叫びが、「死刑の残虐性」を心ある人々に訴え続けてきたこと、また彼らのうちから、自分達も人間だとの、より積極的な訴えが、様々な形をとってなされてきたこと、またこの小説の主人公やその親友のモデルであった正田昭氏や、若松善紀氏のような人達が、死に直面した自らの生をより深く見つめ、深い人間的自覚に到達していっだその生き方が、「死刑」の非人間性、無意味性を、見る人に強く印象づけてきたこと。
―これらすべての人々の《斗い》、それこそが、いまの死刑廃止の運動を、根底から支えていることに、われわれは気付くべきではないだろうか。
反省とは真人間にたちかえって生きようとする行為であって、その「前提」を奪う者達との間では本来成り立たない行為である。然しなから、自らの「死に至る生」を直視できない心、ありのままの自己を直視できない心は、自らの「犯罪」を直視することもできず、そこには真の反省もない。
その「前提」を奪う者逹に抗議する道理性もない。それのないところでの「反抗」と弾圧のエスカレー卜がいかに不毛であるかも事実である。
「死刑との斗い」とは、まず何よりも己れ自身の「死」との斗いであること、
死刑囚の仲間たちが、自らの具体的人間としての再生を求める心の叫びを、
まず「死に至る生」を直視できるための自己との斗いにむけることが、「死」によって拘束されることのない自由な内面性にふまえた、「死刑」を圧倒する人間の共同性を可能とすることを仲間たちに知ってもらうために、まずわれわれ自身が、「死」によって限られた自らの個的な生をはっきりと自らのものとしてとらえ返すことにより、「死」に拘束されない無償の人間愛をわかものとしていかなくてはならなのではないのだろうか。
それが可能になった時、「死刑廃止」は、自己の「犯罪」とも真に向き合うことのできる、ほんとうの強さと豊かな内実を伴って、現実のものとなるであろう。
(1985年11月25日)
抜粋以上
【管理人のつぶやきというか叫び】
武田さん、この文章↓はわかりにくいよ~
>「死刑との斗い」とは、まず何よりも己れ自身の「死」との斗いであること、
>死刑囚の仲間たちが、自らの具体的人間としての再生を求める心の叫びを、
>まず「死に至る生」を直視できるための自己との斗いにむけることが、「死」によって拘束されることのない自由な内面性にふまえた、
>「死刑」を圧倒する人間の共同性を可能とすることを仲間たちに知ってもらうために、まずわれわれ自身が、
>「死」によって限られた自らの個的な生をはっきりと自らのものとしてとらえ返すことにより、
>「死」に拘束されない無償の人間愛をわかものとしていかなくてはならなのではないのだろうか。
これは途中で1度、「。」で文章を切ってほしい。わかりにくい。お経か、野坂昭如並に「。」を使わない続け文になってる。長い上に、文末が、「ならなのではないのだろうか。」になっているから、ますます、わかりにくい。さっくり読者の頭に入ってこない気がする。読んでて、え?え?え?となります。
>「囚人に病気がおきたとき、やはり医者が必要なんだ』(同P190)という一般論こそは、この近木のような医官が、その置かれた状況における自分の「役割」を自覚し人間として真に自分を「取り戻す」ことをはばんでいる論理なのである。
看守も刑務官も、全員、辞職するべきってことなのかな…。私は、「誰ひとりとして、刑務官なんかにならなかったら、死刑なんて実行できないのに」なんて思ったことがあります。
>死刑囚とわれわれとが人間として同一の地平に立ちうるのは、たんに『人間』一般として、存在への不安を共有するからだけではなく、われわれが自己自身の存在の犯罪性を自覚し、自分も同じ罪人なのだと知るところからではないだろうか。それを見ないということは、逆に死刑囚の「犯罪」を一つの前提としてそのままにしておくこと、そこにわれわれとの区別を、暗黙のうちにみとめ、「死刑」による両者の分断をうけ入れてしまうことではないだろうか。
納得です。