
法要終了後の午後から、岐阜県大垣市時山から昨年開通した林道(五僧峠まで)を利用して多賀大社まで急に行く事になった。理由は、お隣のおじさんのリクエスト。今から、60年前に前住職(私の父親)と歩いた五僧越えの山岳ルートを車で行きたいとの希望。以前、このブログで関ヶ原の戦い後の島津義弘の敵中突破の事を、昨年の7月19日から7月23日まで17回に分けて書いたことがある。五僧までは、その記事を参照してもらいたい。午後1時拙寺を出発。参加者は、隣のおじさん・私・息子の三人。
時山から五僧峠までは、昨年林道が完成。午後1時50分には五僧峠を通過。アサハギ谷の林道を進む。秋の紅葉は最高だろう。かなり急勾配のアップダウンの繰り返しで保月の集落跡に到着(標高600m)。鈴鹿山脈の滋賀県側は、三重県側に比較すると山が深い。だから、昔は多くの山村集落が存在した。炭焼き等の多くは林業を生活の糧にした集落である。(現在でも、滋賀県側の山林は見事に間伐が。)この保月集落もその一つ。江戸期末期の人口は300人を超えていたという。かって、五僧集落・保月集落・杉集落の三つの集落を合せて脇ケ畑村という村が存在した。その中心が、ここ保月集落。小学校・中学校・郵便局も存在した。廃村になって久しい。もう30年は経過しているであろう。しかし、神社・お寺・学校跡も綺麗に草刈がしてあった。誰かが、今でも定期的に草刈をしておられるのだろう。このお寺は、照西寺という。浄土真宗本願寺派(西)のお寺であった。本堂のみならず鐘楼堂も立派に残っている。そして、吊るしてある大鐘をみれば、立派な大鐘。昭和24年に京都の若林仏具店が鋳造と銘があった。勿論、誰も住む人はいない、無住のお寺。しかし、本堂前の濡れ縁にはお花が備えてあった。調度、私達がお寺の小さな駐車場跡に車を停めた時、先客があった。話を聞くと、先祖はこの保月出身だという。懐かしく時々は、こうして保月集落跡まで来ているとの事。
私の母も、拙寺に嫁いだ頃(60年程前)このルートを歩いて彦根の親戚のお寺まで行っている。その時の様子を子供頃に聞かせてくれた事を思いだした。「霊仙岳と三国岳の山深く滋賀県側に保月という山里がある。ここは、平家の落人集落という。だから、保月の人は品があると思った。特に女性は綺麗な人が多かった。」という話。当時は、まだ人々の暮らしが続いていた昭和20年代中頃の話。不思議な落ち着きを感じる保月の廃村であった。写真は、この照西寺本堂を背景に息子が撮影してくれた。実は、私自身はこのお寺(照西寺)にすこぶる関心があった。
時山から五僧峠までは、昨年林道が完成。午後1時50分には五僧峠を通過。アサハギ谷の林道を進む。秋の紅葉は最高だろう。かなり急勾配のアップダウンの繰り返しで保月の集落跡に到着(標高600m)。鈴鹿山脈の滋賀県側は、三重県側に比較すると山が深い。だから、昔は多くの山村集落が存在した。炭焼き等の多くは林業を生活の糧にした集落である。(現在でも、滋賀県側の山林は見事に間伐が。)この保月集落もその一つ。江戸期末期の人口は300人を超えていたという。かって、五僧集落・保月集落・杉集落の三つの集落を合せて脇ケ畑村という村が存在した。その中心が、ここ保月集落。小学校・中学校・郵便局も存在した。廃村になって久しい。もう30年は経過しているであろう。しかし、神社・お寺・学校跡も綺麗に草刈がしてあった。誰かが、今でも定期的に草刈をしておられるのだろう。このお寺は、照西寺という。浄土真宗本願寺派(西)のお寺であった。本堂のみならず鐘楼堂も立派に残っている。そして、吊るしてある大鐘をみれば、立派な大鐘。昭和24年に京都の若林仏具店が鋳造と銘があった。勿論、誰も住む人はいない、無住のお寺。しかし、本堂前の濡れ縁にはお花が備えてあった。調度、私達がお寺の小さな駐車場跡に車を停めた時、先客があった。話を聞くと、先祖はこの保月出身だという。懐かしく時々は、こうして保月集落跡まで来ているとの事。
私の母も、拙寺に嫁いだ頃(60年程前)このルートを歩いて彦根の親戚のお寺まで行っている。その時の様子を子供頃に聞かせてくれた事を思いだした。「霊仙岳と三国岳の山深く滋賀県側に保月という山里がある。ここは、平家の落人集落という。だから、保月の人は品があると思った。特に女性は綺麗な人が多かった。」という話。当時は、まだ人々の暮らしが続いていた昭和20年代中頃の話。不思議な落ち着きを感じる保月の廃村であった。写真は、この照西寺本堂を背景に息子が撮影してくれた。実は、私自身はこのお寺(照西寺)にすこぶる関心があった。












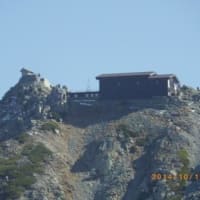







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます