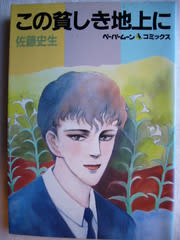↑ 中央公論社 1996年10月25日 初版
「心中天網島 しんじゅうてんのあみじま」
「女殺油地獄 おんなごろしあぶらのじごく」
「鑓の権三重帷子 やりのごんざかさねかたびら」
「曽根崎心中 そねざきしんじゅう」
の4編が入っています。
原作は 近松門左衛門 (1653~1724) がほとんどを人形浄瑠璃の為に創作した物語。のちに歌舞伎の舞台になったものもあります。
近松といえば何と言っても 「心中もの」 が当時大ヒットしました。他にも世間を賑わした実際の事件を元に、ワイドショー的に陰に隠れた個人の事情やしがらみをうまく脚色して世間の好奇心や同情をあおるように書いて見せたのです。
私も心中ものを細部まで読んでみたのは初めてで、なるほど当時の人にとってはこれは死ななきゃならないものだったのか、里中さん上手いわ~、見て来たよう、もちろんしっかりした下調べもなさっているし、と興味深く読みました。
でも、個人的に4編のうちでは
2番目の 「女殺油地獄」 の話が気になっていて、今回細かいところまで良くわかって納得がいきました。
ちょうど明日 (2009/6/3~6/27) から東銀座の歌舞伎座で、上演される 「六月大歌舞伎」 にて、片岡仁左衛門 が 孝夫 の頃 (1964年初挑戦) から当たり役としてきたこの話の主人公、油屋の二男坊である 河内屋 与兵衛 を演じる予定です。
今年65歳の仁左衛門は、これが若い役である 「与兵衛」 を演じる最後として、気合いを入れているようです。それというのも、読売新聞の演劇のページによると、
「このまま現代の服装でやってもおかしくない芝居。
本当の若さが必要なので、もうやめておこうと心に決めていた。」
というのです。
河内屋与兵衛という役は、放蕩の挙句勘当され、借金の返済に困って子供の頃から世話になっている優しい近所のおかみさんを殺して金を奪う、というどうしようもない道楽息子。父親が死んだあと、母親が番頭と再婚して店を存続させた、というような家庭の事情はあるが、それだけではグレたいいわけにはならない。
歌舞伎では油まみれになりながら、こけつまろびつ凄惨な殺しの場面が見せ場となります。この作品でも大事な場面ではありますが、そこに至った与兵衛の身勝手な考え方や周りの人たちの事情や思いが細やかに描かれていて、さもありなんと納得が行くのです。
と言って、作者は与兵衛の味方はもちろんしていませんよ。自分の都合の良い幼稚な考えで行動し、世間をなめきった若者の末路は…。
はて、昨今似たような事件を起こす勝手な若者が多いような。いつの時代にも後先考えない人間というのはいるものです。
次に載っていたこれも歌舞伎の舞台になっている 「鑓の権三重帷子」 といえば、以前TVドラマになっているのを見たな~と調べたらなんと1961年に 「侍」 というシリーズの中で関西テレビが制作したそう。これを見たのかな~ ? ちょっと記憶が流石に曖昧。
郷ひろみが 権三 をやってたの見たことある様な・・と思って調べたら映画の方にありましたよ、『近松門左衛門 鑓の権三』(1986年、松竹、共演:岩下志麻) というやつが。これを後でTVで見たんだなたぶん。
里中氏の描く 鑓の権三 は鑓の名手で茶道の達人、しかも男前、という人も羨む若者なのだが、優柔不断な性格で不幸を招く、という風に描かれいる。当時の爽やかな 郷ひろみ には似つかわしくない役だが、当代の男前ということで起用されたのだろうか。演技開眼に繋がる様な名演だったかは残念ながら覚えていない。(やや笑)
絵師の里中氏は大阪生まれの大阪育ち。知った地名や大阪弁も懐かしく、楽しく作成されたのではないでしょうか。それが伺えるような余裕のある作品でした。












 「江戸時代はまるでシロート」 と告白する少女マンガ家 酒井 美羽さんが描く江戸時代ジェットコースター恋愛ドラマ。
「江戸時代はまるでシロート」 と告白する少女マンガ家 酒井 美羽さんが描く江戸時代ジェットコースター恋愛ドラマ。


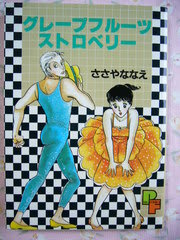




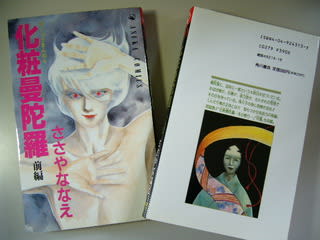



 眼が見えない設定だけれど、ナウシカのおばば様とは大違いですわ。
眼が見えない設定だけれど、ナウシカのおばば様とは大違いですわ。
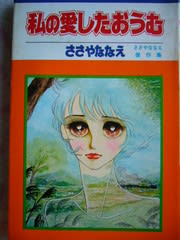
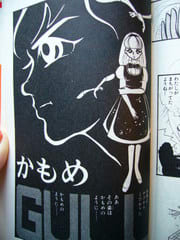

 先日これをゲットしました。定価の半分くらいだったかな。
先日これをゲットしました。定価の半分くらいだったかな。




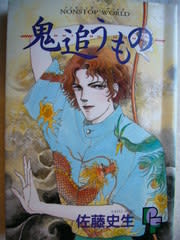
 もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~
もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~