言わずと知れた1997年手塚治文化賞受賞作。
初出 「プチフラワー」 1992年7月号~2001年7月号まで 写真は 小学館 プチフラワーコミックス 1巻~17巻 (16巻抜け)
私は最初はマンガ喫茶で読んだ。暗くて暗くてちょっと読むのがつらかった。一応最後まで読んだけれど、自分で買って置いておくのはやめといた。
萩尾 望都氏は後からでも中古本を集めてみたりしてほとんど読んでいるし、ごく少数好きになれないものがあってブック○フに売ったりしているが、大体本棚に揃えてある。
ところが 「残神」 は最初からそんな気が起らなかった。凄い作品だとは一読しただけでも分かったし、絵柄はとても充実している時期で、ところどころイラスト集のように綺麗なんだけれど…。
9年の長きに渡って連載された長編で、人によっては萩尾氏の代表作としてとても高い評価をしている。もう一度じっくり読まないといけないかな~と最近思うようになってきた。
そこへ、Eブック○フという大変便利なツールを見つけてしまい、さっそく検索したところ、プチフラワーコミックス 1巻~17巻が今は100円から150円位の値段で揃えられるではないか ! はい、しっかり他の本もネット購買にはまってます。(笑)
やっぱり前半読むのが辛い。。。萩尾さん、これでもかってジェルミ♂ (主人公のひとり) を辛い目に逢わせてる。肉体的にもだけど、心理的に追い詰められていく ジェルミ を見るのは辛い。長いのよ又これが。最初読んだ時はもっと短い表現だと思っていたけれど、全17巻のうち 6~7巻くらいまで延々と 虐待場面 が再々出てくるんです。こんなに長くやんなくたってねぇ~と思わないでもないが、ジェルミの絶望を伝えるにはこれだけのページが必要だったのか。
やっと痛くて辛い場面が終わったと思ったら、一度心理的に追い詰められた ジェルミ は元に回復できないくらいダメージを受けている。もう一人の主人公である イアン♂ (おぼっちゃん・イケメン) によって救われるかと、こちらは期待しているのに、イアンも真実を知った衝撃で自分の精神を保つのもやっとの時期もあってなかなかうまくいかない。
イアン も頑張っているんだけどね~。前半は自分勝手な印象の イアン、中盤は事実が信じられない イアン も、後半は ジェルミ に誠実に対応しようとしていて好感が持てる。
ただ、キレやすい イアン は ジェルミ を時に暴力的に扱ったりして、こちらは又ハラハラ。ジェルミも怒らせるようなことをわざとやったりするし。
後半は イアン の物語にもなっている。自分の信じていたものに裏切られた人はどう対応し、再生しようとするのか。
読んだことない人でもこの有名な作品は、一筋縄ではいかないお話である事は知っていると思います。現実にはないかもしれない、でも世の中にはこんな事もあるかもしれない、フィクションの中に真実を見たい読者には、とっても重い物語。
読んでいてとても疲れるのよ。それは、萩尾 望都氏の思惑通り、ジェルミやイアンの精神的困惑に引きずられて読者も大いに困惑し、考え、はては自分の人生のそちこちに引き合わせて考え始めてしまい、思考が止められない・やめられない。
これ読んで寝られなくなりましたっていう人、多いでしょう。再読の私でも不眠になりかけましたもの。
萩尾先生、凄いを通り越して恐いです。なんでこんな物語を作るの、作れるの!
前半の暗い画面で少人数の沈鬱な舞台劇のような場面から、後半は登場人物もぶわっと多くなり、違う作品のよう。多少明るくなるのはいいのだけれど、しかしまだ ジェルミとイアン の苦悩と混沌は廻りの者を巻き込み、読者まで引きずって続く…続く…。
やっと最後に希望の光が。流石に萩尾氏も絶望のままで物語を締めるのは憚られたか。
この、時間にして3年に亘る物語の中で、読者は
親による子供への虐待について、
学校のいじめについて、
父親と息子について、
母親と息子について、
母親と娘について、
親に対する子について、
愛に潜む暴力について、
心の傷を癒す方法について、
そして愛について、
考える。
それは人によって様々でみんな同じではないでしょう。ラスト近く、ボート小屋でのイアンとジェルミの禅問答のような愛についての問いかけは私、久しぶりにマンガのセリフを読んでじっくりと考えましたよ。
この作品だけでHPを作ったり、スレッド立ち上げたりしても十分書き込み者は集まるし、実際もうあるようだ。謎や結局解明されていないツッコミどころ (母親が事実を知っていたか) などもある作品なので、そこでは熱い討論が載っていて、私なぞちょっと引きかける。
読み始める前、記事は1回目は グレッグ の視点から、グレッグという加害者の考えを書いて、それ終わったらジェルミかな、次は辛いけどイアンの気持になって…、書こうかと思っていたのですが、とんでもなかったです~。(泣く) 自分の甘さを思い知りました。
今だ、「残神」 は語れず…のトミー。
初出 「プチフラワー」 1992年7月号~2001年7月号まで 写真は 小学館 プチフラワーコミックス 1巻~17巻 (16巻抜け)
私は最初はマンガ喫茶で読んだ。暗くて暗くてちょっと読むのがつらかった。一応最後まで読んだけれど、自分で買って置いておくのはやめといた。
萩尾 望都氏は後からでも中古本を集めてみたりしてほとんど読んでいるし、ごく少数好きになれないものがあってブック○フに売ったりしているが、大体本棚に揃えてある。
ところが 「残神」 は最初からそんな気が起らなかった。凄い作品だとは一読しただけでも分かったし、絵柄はとても充実している時期で、ところどころイラスト集のように綺麗なんだけれど…。
9年の長きに渡って連載された長編で、人によっては萩尾氏の代表作としてとても高い評価をしている。もう一度じっくり読まないといけないかな~と最近思うようになってきた。
そこへ、Eブック○フという大変便利なツールを見つけてしまい、さっそく検索したところ、プチフラワーコミックス 1巻~17巻が今は100円から150円位の値段で揃えられるではないか ! はい、しっかり他の本もネット購買にはまってます。(笑)
やっぱり前半読むのが辛い。。。萩尾さん、これでもかってジェルミ♂ (主人公のひとり) を辛い目に逢わせてる。肉体的にもだけど、心理的に追い詰められていく ジェルミ を見るのは辛い。長いのよ又これが。最初読んだ時はもっと短い表現だと思っていたけれど、全17巻のうち 6~7巻くらいまで延々と 虐待場面 が再々出てくるんです。こんなに長くやんなくたってねぇ~と思わないでもないが、ジェルミの絶望を伝えるにはこれだけのページが必要だったのか。
やっと痛くて辛い場面が終わったと思ったら、一度心理的に追い詰められた ジェルミ は元に回復できないくらいダメージを受けている。もう一人の主人公である イアン♂ (おぼっちゃん・イケメン) によって救われるかと、こちらは期待しているのに、イアンも真実を知った衝撃で自分の精神を保つのもやっとの時期もあってなかなかうまくいかない。
イアン も頑張っているんだけどね~。前半は自分勝手な印象の イアン、中盤は事実が信じられない イアン も、後半は ジェルミ に誠実に対応しようとしていて好感が持てる。
ただ、キレやすい イアン は ジェルミ を時に暴力的に扱ったりして、こちらは又ハラハラ。ジェルミも怒らせるようなことをわざとやったりするし。
後半は イアン の物語にもなっている。自分の信じていたものに裏切られた人はどう対応し、再生しようとするのか。
読んだことない人でもこの有名な作品は、一筋縄ではいかないお話である事は知っていると思います。現実にはないかもしれない、でも世の中にはこんな事もあるかもしれない、フィクションの中に真実を見たい読者には、とっても重い物語。
読んでいてとても疲れるのよ。それは、萩尾 望都氏の思惑通り、ジェルミやイアンの精神的困惑に引きずられて読者も大いに困惑し、考え、はては自分の人生のそちこちに引き合わせて考え始めてしまい、思考が止められない・やめられない。
これ読んで寝られなくなりましたっていう人、多いでしょう。再読の私でも不眠になりかけましたもの。
萩尾先生、凄いを通り越して恐いです。なんでこんな物語を作るの、作れるの!
前半の暗い画面で少人数の沈鬱な舞台劇のような場面から、後半は登場人物もぶわっと多くなり、違う作品のよう。多少明るくなるのはいいのだけれど、しかしまだ ジェルミとイアン の苦悩と混沌は廻りの者を巻き込み、読者まで引きずって続く…続く…。
やっと最後に希望の光が。流石に萩尾氏も絶望のままで物語を締めるのは憚られたか。
この、時間にして3年に亘る物語の中で、読者は
親による子供への虐待について、
学校のいじめについて、
父親と息子について、
母親と息子について、
母親と娘について、
親に対する子について、
愛に潜む暴力について、
心の傷を癒す方法について、
そして愛について、
考える。
それは人によって様々でみんな同じではないでしょう。ラスト近く、ボート小屋でのイアンとジェルミの禅問答のような愛についての問いかけは私、久しぶりにマンガのセリフを読んでじっくりと考えましたよ。
この作品だけでHPを作ったり、スレッド立ち上げたりしても十分書き込み者は集まるし、実際もうあるようだ。謎や結局解明されていないツッコミどころ (母親が事実を知っていたか) などもある作品なので、そこでは熱い討論が載っていて、私なぞちょっと引きかける。
読み始める前、記事は1回目は グレッグ の視点から、グレッグという加害者の考えを書いて、それ終わったらジェルミかな、次は辛いけどイアンの気持になって…、書こうかと思っていたのですが、とんでもなかったです~。(泣く) 自分の甘さを思い知りました。
今だ、「残神」 は語れず…のトミー。














 読めば読むほど読みたいものが増えて困るトミー。
読めば読むほど読みたいものが増えて困るトミー。
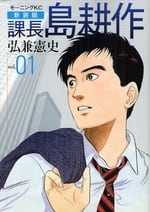
 ビートルズみたいに祭り上げられて、神様になっちゃわないでね。(なるわきゃないか)
ビートルズみたいに祭り上げられて、神様になっちゃわないでね。(なるわきゃないか) 
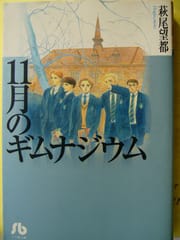


 )
)








 プレゼントに最適というあおりの文句がむなしい。確かにプレゼントなら多少高くても買うか。
プレゼントに最適というあおりの文句がむなしい。確かにプレゼントなら多少高くても買うか。