小学館文庫 1995年8月10日 初版 写真は1998年12月1日の 第8刷
最近はお借りしているマンガの記事ばかり書いていたので、自分の持っている古いマンガの記事をたまには書かなけりゃと。
この文庫が出たのは1995年と比較的新しいものの、収められている短編14編は1976年8月から1983年7月までのビック・コミック系やSFファンタジア、マンガ少年、マンガ奇想天外などに発表されたもの。もう30年経っているものもあります。
大体がSFものですが、日常に潜む知られざる恐怖(?)とかブラックユーモアが効いているものが多く、ひとつひとつは短いのにちょっと考えさせられます。同じ作者の初めての大人向けSFマンガ 「ミノタウロスの皿」 から続く系列の作品たちですね。
全体的に、よりブラックユーモアのきつい 星 新一 といったら感じが分かるでしょうか。それをあの どらえもん の絵柄で描いているんです。見たこと無い人は え~、でしょうが、この方のこういう作品は評価が大変高いのです。皮肉が効いてて私も好きですね。
簡単に作品紹介
値ぶみカメラ
その名のとおり、写したものの値段が、本価(原材料費)・市価(正札価格)・産価(将来被写体が生み出す利益)・自価(ここでは自分にとっての価値)の4つとも分かるカメラ。求婚する大金持ちの青年と、まったり付き合ってきた居心地のいい貧乏なカメラマンを写した竹子の自価はどちらが高いのか。
女には売るものがある
表紙を入れても6ページの超短編ながら、いやこれ傑作。この中で一番好きかも。近未来が舞台。夜の歩道で客の男を物色するおんながひとり。さえない中年男を捕まえ、値段の交渉を済ませていざホテルへ。風呂場で轟然と女に体を洗わせて 「ああ久しぶりだなぁこんな気分」 とご満悦な男。
新聞や茶を持ってこさせたり腰をもませたり、そのくせ女が裸でベッドに入ろうとすると 「金を払ってまでそんなことするか !」 と突き飛ばす。
その後二人は警察につかまってしまうのだが、さて、罪状は ? 最期のコマの前のコマでやっと明かされます。どんな世の中になっても、女には売るものがあるのね。 いいんだか、悪いんだか。
いいんだか、悪いんだか。
同録スチール
「値ぶみカメラ」で登場の、怪しげなカメラのセールスマンが又登場。このシリーズに良く出てきます。今度の商品は写真を複写して手を触れると、最初に写真を写した時の音を10分間再生するカメラ。友達に映して貰った、好きな女の子のしゃべった言葉とは。
並平家の一日
45歳会社員並平 兵順(ひょうじゅん)、妻、子供二人生活意識は中流の中、起床から出勤までの所要時間が38分。妻、凡子(なみこ)40歳、自由時間は平均一日4時間54分。子供二人も流行に敏感なイマドキ子供。熱心にこの家を隠しカメラで観察する隣人がいた。その隣人の旺盛な商魂とは。
夢カメラ
またまたカメラのセールスマン氏登場。今度のカメラは寝ている人を写すと、見ている夢がセリフ付で写るカメラ。無理やり預けられた係長さん。会社の好もしい女の子の夢を見たのはいいが…。
親子とりかえばや
これはなんとなく分かりますよね。立場を換えれば相手のことがよく分かる…。
懐古の客
4回目出演のカメラのセールスマン、ヨドバ氏。今度はセールスでなく、旅行客として過去にきたようです。ここに出てくるボロアパートはまんま トキワ荘 がモデルのようで、玄関、2階に上る階段、懐かしがって描いているのが分かります。未来のパック旅行 「グッドオールドデイズ一週間」 の滞在先として押しかけられた、かけだしマンガ家君は6泊2食つき20万円という大枚に目がくらみ、ヨドバ氏の世話をするが…。
パラレル同窓会
人生の転機に過たず正しい決断をしてきたと自負する高根氏、今は極東物産の社長だ。成功したといえる彼の唯一の趣味は、深夜つかの間小説を書くことである。そんな彼に「パラレル同窓会のお知らせ」というハガキが届く。それは一生に一度、人生の転機に枝分かれしたすべての自分が一同に会するという 自分だけの同窓会 だった。しかもそこでは人生を取り替えることも出来るという…。
その他 「コラージュカメラ」「かわい子くん」「丑の刻禍冥羅(カメラ)」「ある日」「四海鏡」「鉄人をひろったよ」などなど題名を見ているだけでも内容がわかるようなわからないような。
しかし、鉄人みたいなロボットを拾ったら凄い迷惑だよなぁ~。庭にも置いとけないからこの作品の主人公の中年男性の戸惑いも分かります。たとえ一国が命運をかけて開発し、三つの国が大いなる犠牲を払って追い求めたものであってもね。SFと現実のギャップがおかしい藤子F氏のSF好きなセンスにひたすら脱帽。
※ 最近又、拙ブログをお訪ねくださる方が多くなり、大変ありがとうございます。多分昔のまんが関係を見に来られる方が多いと思います。画面左のカテゴリー マンガ家○行 と まんがエリートのためのCOM をチェックして、マンガ雑誌 COM の表紙や石森(当時) 章太郎、水野 英子、西谷 祥子氏などの表紙絵だけでもご覧になっていってくださいませ。
又、記事にまさったコメントを下さる方も数多く、ぜひそちらもお見逃しなく、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
最近はお借りしているマンガの記事ばかり書いていたので、自分の持っている古いマンガの記事をたまには書かなけりゃと。
この文庫が出たのは1995年と比較的新しいものの、収められている短編14編は1976年8月から1983年7月までのビック・コミック系やSFファンタジア、マンガ少年、マンガ奇想天外などに発表されたもの。もう30年経っているものもあります。
大体がSFものですが、日常に潜む知られざる恐怖(?)とかブラックユーモアが効いているものが多く、ひとつひとつは短いのにちょっと考えさせられます。同じ作者の初めての大人向けSFマンガ 「ミノタウロスの皿」 から続く系列の作品たちですね。
全体的に、よりブラックユーモアのきつい 星 新一 といったら感じが分かるでしょうか。それをあの どらえもん の絵柄で描いているんです。見たこと無い人は え~、でしょうが、この方のこういう作品は評価が大変高いのです。皮肉が効いてて私も好きですね。
簡単に作品紹介
値ぶみカメラ
その名のとおり、写したものの値段が、本価(原材料費)・市価(正札価格)・産価(将来被写体が生み出す利益)・自価(ここでは自分にとっての価値)の4つとも分かるカメラ。求婚する大金持ちの青年と、まったり付き合ってきた居心地のいい貧乏なカメラマンを写した竹子の自価はどちらが高いのか。

女には売るものがある
表紙を入れても6ページの超短編ながら、いやこれ傑作。この中で一番好きかも。近未来が舞台。夜の歩道で客の男を物色するおんながひとり。さえない中年男を捕まえ、値段の交渉を済ませていざホテルへ。風呂場で轟然と女に体を洗わせて 「ああ久しぶりだなぁこんな気分」 とご満悦な男。
新聞や茶を持ってこさせたり腰をもませたり、そのくせ女が裸でベッドに入ろうとすると 「金を払ってまでそんなことするか !」 と突き飛ばす。
その後二人は警察につかまってしまうのだが、さて、罪状は ? 最期のコマの前のコマでやっと明かされます。どんな世の中になっても、女には売るものがあるのね。
 いいんだか、悪いんだか。
いいんだか、悪いんだか。同録スチール
「値ぶみカメラ」で登場の、怪しげなカメラのセールスマンが又登場。このシリーズに良く出てきます。今度の商品は写真を複写して手を触れると、最初に写真を写した時の音を10分間再生するカメラ。友達に映して貰った、好きな女の子のしゃべった言葉とは。
並平家の一日
45歳会社員並平 兵順(ひょうじゅん)、妻、子供二人生活意識は中流の中、起床から出勤までの所要時間が38分。妻、凡子(なみこ)40歳、自由時間は平均一日4時間54分。子供二人も流行に敏感なイマドキ子供。熱心にこの家を隠しカメラで観察する隣人がいた。その隣人の旺盛な商魂とは。
夢カメラ
またまたカメラのセールスマン氏登場。今度のカメラは寝ている人を写すと、見ている夢がセリフ付で写るカメラ。無理やり預けられた係長さん。会社の好もしい女の子の夢を見たのはいいが…。
親子とりかえばや
これはなんとなく分かりますよね。立場を換えれば相手のことがよく分かる…。
懐古の客
4回目出演のカメラのセールスマン、ヨドバ氏。今度はセールスでなく、旅行客として過去にきたようです。ここに出てくるボロアパートはまんま トキワ荘 がモデルのようで、玄関、2階に上る階段、懐かしがって描いているのが分かります。未来のパック旅行 「グッドオールドデイズ一週間」 の滞在先として押しかけられた、かけだしマンガ家君は6泊2食つき20万円という大枚に目がくらみ、ヨドバ氏の世話をするが…。
パラレル同窓会
人生の転機に過たず正しい決断をしてきたと自負する高根氏、今は極東物産の社長だ。成功したといえる彼の唯一の趣味は、深夜つかの間小説を書くことである。そんな彼に「パラレル同窓会のお知らせ」というハガキが届く。それは一生に一度、人生の転機に枝分かれしたすべての自分が一同に会するという 自分だけの同窓会 だった。しかもそこでは人生を取り替えることも出来るという…。
その他 「コラージュカメラ」「かわい子くん」「丑の刻禍冥羅(カメラ)」「ある日」「四海鏡」「鉄人をひろったよ」などなど題名を見ているだけでも内容がわかるようなわからないような。
しかし、鉄人みたいなロボットを拾ったら凄い迷惑だよなぁ~。庭にも置いとけないからこの作品の主人公の中年男性の戸惑いも分かります。たとえ一国が命運をかけて開発し、三つの国が大いなる犠牲を払って追い求めたものであってもね。SFと現実のギャップがおかしい藤子F氏のSF好きなセンスにひたすら脱帽。
※ 最近又、拙ブログをお訪ねくださる方が多くなり、大変ありがとうございます。多分昔のまんが関係を見に来られる方が多いと思います。画面左のカテゴリー マンガ家○行 と まんがエリートのためのCOM をチェックして、マンガ雑誌 COM の表紙や石森(当時) 章太郎、水野 英子、西谷 祥子氏などの表紙絵だけでもご覧になっていってくださいませ。
又、記事にまさったコメントを下さる方も数多く、ぜひそちらもお見逃しなく、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m












 まだ連載中です。
まだ連載中です。






















 え~え、こういうのにオバさんはコロリと弱いのよ。
え~え、こういうのにオバさんはコロリと弱いのよ。

 と3歳
と3歳 上の姉妹 (きょうだい) は持ってないわよ~。おほほいつもそんなに上手くはいかないんですが・・・。
上の姉妹 (きょうだい) は持ってないわよ~。おほほいつもそんなに上手くはいかないんですが・・・。
 せっかく新規開店のマンガ喫茶店を割引券で開拓しようと思っていたのに~
せっかく新規開店のマンガ喫茶店を割引券で開拓しようと思っていたのに~ (またかい)
(またかい) 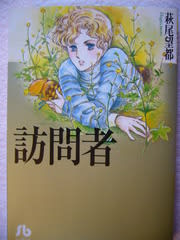




 前述のサイフリートが絡んでくる事件の事ですが、長くなったので、明日つるさんたちのコメントを含めて書きますね~。えっ、ここまで来てひどいって ? 次回をお楽しみにって言うのは連載マンガの常套手段でしょ。
前述のサイフリートが絡んでくる事件の事ですが、長くなったので、明日つるさんたちのコメントを含めて書きますね~。えっ、ここまで来てひどいって ? 次回をお楽しみにって言うのは連載マンガの常套手段でしょ。

 もう、何がなんだか・・・信じられるのはネコのエリザベスだけ
もう、何がなんだか・・・信じられるのはネコのエリザベスだけ 義経ですよ
義経ですよ はぁはぁ。
はぁはぁ。
