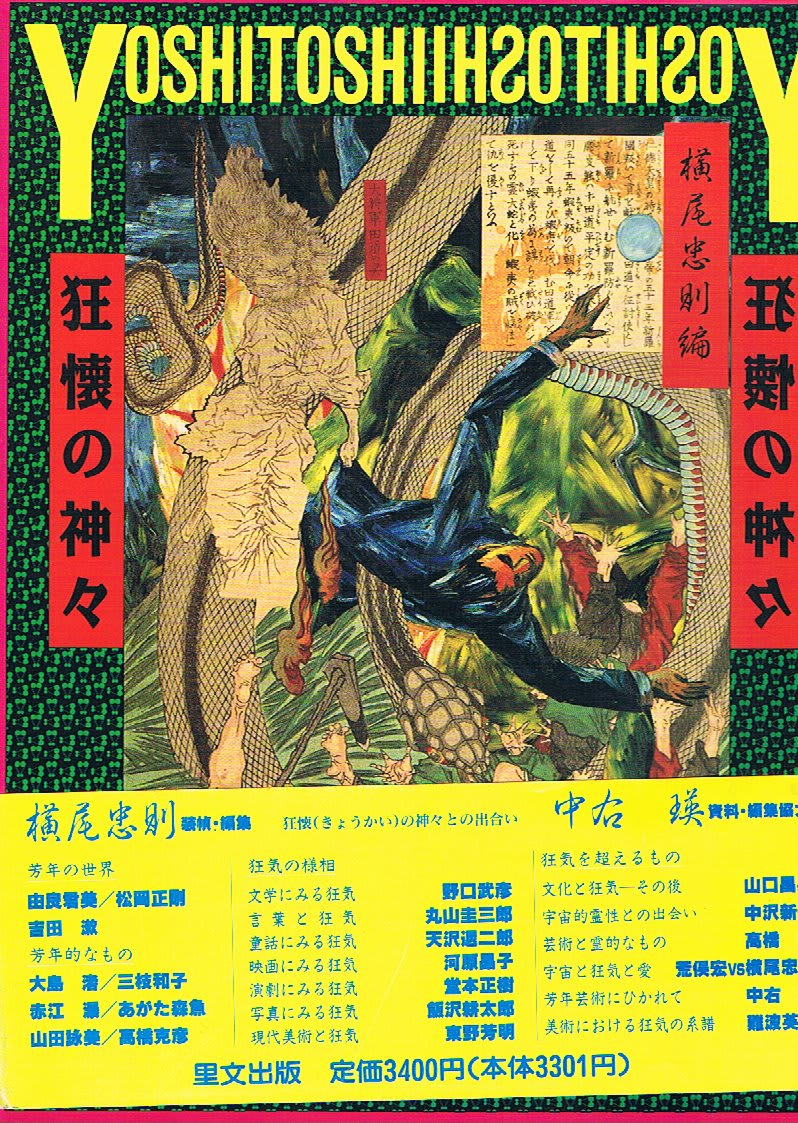桂文楽+林家正蔵+三遊亭圓生+柳家小さんの「落語芸談」
昭和43年冬に企画され、当時円熟の八代目桂文楽+八代目林家正蔵+六代目三遊亭圓生+五代目柳家小さんの芸談(明治・大正・昭和初期の咄家の日常生活や古典落語について収録)をまとめられたのが、本書「落語芸談」(三省堂昭和51年出版)です。現在では稀少本ですが、この頃のわたしは「落語好き」の学生でして、こういった本や落語のレコードなどをずいぶん買っていました。なにせ咄家の会話(芸談)ですので、日常が手に取るように分かるのです、空気感まで、いわゆる臭うように家のうち外まで見えてくるのです。会話に出てくる人もすごいのです、わたしの好きな人達が次々とね、徳川無声さんも出てくるのですからすごい・・・当時のわたしは頭の中が老けていた(ふやけていたのではない)のです・・・。みなさん「故人」になってしまいましたが・・・わたしは時折、この人たちの「落語」をレコードで聴いております・・・目を閉じてね。