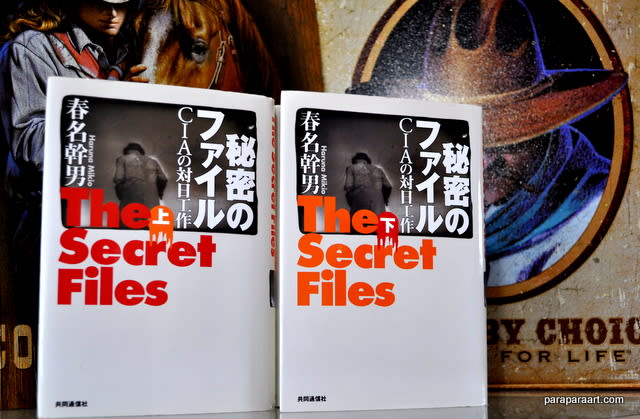本の紹介・米倉斉加年&松永伍一著「風よついてこい」
わたしは米倉斉加年さんの絵本が好きで、それらを買っているうちに、それ以外の本も買うようになったのです。この本は、そのうちの一冊です。「風よついてこい」を読んでいると、穏やかな日差しの下、気の合う二人がそれとなく会話を楽しんでいる、そういった雰囲気が伝わってきます。BS3早朝ですが、朝ドラ「ちりとてちん」が再放送されていますが、おじいさん役に米倉斉加年さんが出ています。もちろん俳優としても好きですが、はまり役です。このような人(多才な人)ですから、松永伍一さんとのやりとりが、絶妙です。エスプリが効いていて、無理がないのですね。持統天皇の「衣ほすてふ天の香具山」について話している、なんでもない美しい情景を歌っているのですが、この二人の会話では、時代のメルヘンそのものととらえている、この辺りがなんともおもしろい。わたしは近頃、平安時代に書かれた資料や物語、絵巻物を調べています。それでいくつか解ってきたことがあるのです、貴族の生活がきわめて装飾化されているのです。平安貴族の生活(現実)が、過剰な装飾を透かして見えてくるのです。文学や絵画に見られる豊かな文化の背景がどうであれ、常に生きた人々の生活が反映されているのかも知れない。その辺りを気づくことが出来れば、わたしたちの歴史ももっと魅力あるものになるのかも知れない。