eAT11-KANAZAWA(文化ホール)を観る
「北陸中日美術展」を、観る。日本の場合、日展を頂点とする美術団体(理事・評議員など組織集団・画壇とも言う)が主催する「美術展」が多い。この「北陸中日美術展」は、地方の新聞社が主催するコンクール形式の「美術展」です。若手作家の登竜門として一定の評価を得てきた。実際わたしも、学生時代に作品を出していたこともあり、詳しい。この頃の審査員に針生一郎さんがいて、多くの示唆と丁寧な助言を頂きました、この場に立つと懐かしく想い出します。24歳以降、この美術展を観ることはなくなりました(作品を出すこともなくなり)が、ここ数年足を運ぶようになったのは、友人の斉田博さんが作品を出しているからです。斉田さんの意欲が画面の細部(随所)に見ることができる、少しまとまりに欠けますがそれが返って不思議な魅力になっています。この「北陸中日美術展」に、針生一郎さんの厳しい眼が無いことが、わたしには残念でならない。
昨夕は「日本舞踊」を観にいきました
金沢市は、文化を街の中心軸にしています。季節の移り変わりに合わせるかのように、街の衣裳も変わります、散策するに楽しい街、わたしの好きな街です。「市民芸術村」の片隅に「古民家」が移築されています、昨夕はそこで「日本舞踊」を観ました。以前このブログで取り上げた「朗読劇」もそうですが、時間を戻すに最適な空間(装置)です。「日本舞踊」もそうですが、指導者層が充実している割に、「お弟子さん」は少なくなっています、「伝統文化」として維持するのは難しい。江戸時代から大正ロマン辺りのイメージを描きながら、ぼんやり眺めていました。この中にも「若い演劇人」が、紛れています。「伝統から学ぶ」環境が、この街にはまだあるのです。薄暗い明かりが揺らぎ、漆塗りの柱・白壁にうごめく影は、「独自の美」そのものです。頑なに守らねばならない「形の美」と「新しい感覚」の鬩ぎ合いを、わたしはつい見てしまう。
昨晩は「怪談屋敷」を訪れ・・・怨霊の凄まじさに身震いする
昨晩は「怪談屋敷」を訪れ・・・怨霊の凄まじさに身震いする想い・・・を味わいました。「ヴォイスライブ」の2回目の公演・・・「幽霊滝の伝説・耳なし芳一(小泉八雲)」「浅茅が宿・吉備津の釜(上田秋成)」「一節切(花衣沙久羅)」・・・を観にいきました。「ヴォイスライブ」の前回公演も観ましたが、今回も場(市民芸術村・古民家)の雰囲気を巧みに生かし、秀逸な演出「朗読劇」になっていました。このグループには、劇団に所属している人も多く、感情を抑えた表現が耳に心地良く、怖さがごく自然に空間全体に染み入る。それにしても、小泉八雲「怪談」や上田秋成「雨月物語」に秘められた情感、豊かな言語表現、その確かさと魅力を再認識せずには・・・貴重な言語文化に他ならない。その中に、「ひとつの試み」がありました。「一節切」、花衣沙久羅さんの作品から、ひとつの「朗読劇」として勢登香里さんが演じています。美しくも妖しい、「人形の情念」を好演しています。昨晩は、原作者の花衣沙久羅さん(東京)も鑑賞していました。「市民芸術村」に集う若き才能に、わたしは期待したい。
旧石川県庁(しいのき迎賓館)周辺を散策する
8月のアトリエ、常に蒸し風呂状態、制作が思うように進みません。天井が高いこともあり、冷房があまり効いていない。このところ何かと雑用も多く、気持ちが集中できていません。「気分転換」が必要とばかりに、時折外に出るものの、増して「暑い」、とても快適とはいえない。旧石川県庁が「しいのき迎賓館」に生まれ変わった(再利用)こともあり、内部を見てみることにしました。見慣れた重厚な表門を入ると、その裏はガラスを多用した「近代建築」、その「見た目(材質)の違い」に多少違和感を覚えた。ギャラリーでは、「ガラスの器」が展示されていました。見ている人も少なく、そのデリケートな美しさに、しだいに気持ちもやさしく・・・それほどには単純ではないのですが・・・気分を紛らわすに充分でした。
南陀楼綾繁さんのトークショーにゲスト小野寺生哉さん
南陀楼綾繁さんの「一箱古書市・前日トークショー」に小野寺生哉さんがゲスト参加していました。小野寺生哉さんがトークショーに加わり、話題が古書から映画に移りましたが、これも楽しいものでした。「2010かなざわ映画祭(9月17日~24日)」が、「シネモンド」「21世紀美術館シアター21」を会場に開催されます。今年のテーマは「怪談」だそうで、オープニングは本多の森公園(下記案内)で・・・PRを兼ねての小野寺生哉さんのトークでした。
昭和42 年夏にテレビ放送され、大人から子供まで日本全国のお茶の間を震えあがらせた幻のホラー映画が、日本語字幕版で43 年ぶりに金沢に帰ってくる!
日時:9月17日(金)20:00開始/21:30終了予定
入場料:無料
場所:本多の森公園(石川県立美術館広坂別館横広場)
雨天の場合は金沢21世紀美術館シアター21にて上映します。
《会場地図》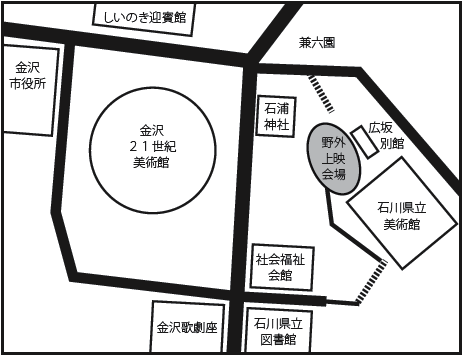
南陀楼綾繁さんのトークショー「一箱古書市」を聴く
金沢へ「仲間たち展」を見に行く



















