前に書いた「会社は本当に株主のものか?という疑問に答える本」という記事に、池田信夫氏から返信記事を頂きました。
反論ではなく、建設的に先生のお立場を明快にしてくださったことを感謝してます。
同じくリンクさせていただいた青木理音さんのブログからも返信を頂きました。
また色んな方からコメントやTBを頂きました。有難うございます。
この記事は皆様への反論ではなく、単に議論を進ませるための補足として。
さて、そもそも何故「会社は誰のものか?」という議論があるのかを考えると、所有と経営と経営目的の分離が起きてるからです。
いまや昔と違い、会社の所有者が多様化し、経営者は所有者ではない。ステークホルダーも多様化し、声が大きくなっている。
すなわち「誰のものか(of)」と「誰による(by)」と「誰のためか(for)」が分離してきて、混乱を起こしてる。
でもって、この中で所有者=株主(of)がbyもforも決めてしまって良いような状況の中、
この株主が、必ずしも経営の専門家じゃなく判断を誤るし(byの問題)、従業員や社会、環境などのステークホルダーを考えてるわけじゃない(forの問題)から、
「会社は株主のものにしておいていいのか?」もっと正確には「株主を主権者としておいていいのか」という議論が巻き起こるのだ。
池田先生の記事より引用。
きのうも書いたように、株式会社が株主のものであることは法的には自明である。しかし企業を公開会社にしなければいけないという法律はないのだから、「株主至上主義」がいやな経営者は、MBOで閉鎖会社にすればよい。現にアメリカでは公開会社の「閉鎖化」が進行している・・・というのが彼女への短い答である。
「法的に自明」と書くと、恐らく法律関係者から反論が来ることでしょうが、先生が「自明」と書いてるのは、恐らくそうつもりではないでしょう。
「株式主権は所与のものとして、嫌ならこの形態は捨てて(非公開にして)規定の枠組みで出来ることをやればよいのでは?
選択の自由はあるのだから」というプラグマチックなお考えなのだと思います。
これに対して、岩井先生は、資本主義経済のあり方によって、必要とされる会社の形態は違ってくるべき。
更にステークホルダーが重要になってることを考えると、「株主主権」は必ずしもベストな形態ではない。
状況によって、何がベストかは違ってくるわけです。
しかし「株式会社」という形態自体は、非常に有用なので、これをただ捨ててしまうのはもったいない。
であれば、「株式会社」の解釈の仕方を、時代に沿うように柔軟に変更していくことは出来ないか?という新しい提案をしてるわけです。
詳しくは岩井先生の本を読んでいただければ、と思うのだけど、私がこの考え方に共感を持つのは、
「公開が嫌ならやめれば?」という方法だと、単に株式会社という形態が形骸化しちゃうんじゃないか、と思うから。
現に池田先生ご自身の指摘するように、「MBOなどアメリカでは公開会社の「閉鎖化」が進行している」わけですから。
その結果、MBOは現実的に出来ない、超大企業だけが市場に残され、株式市場は金融投資の目的のために存在するだけになるんじゃないか。
公開の本来の目的だった資金調達のメリットもいまや無く、公開のためのコストだけがかかり(SOX以降特に)、ウォール街や悪質買収者などの悪影響を受けやすくなる。
このように、「株主主権」を言い過ぎると、株式公開って手法は形骸化してしまうんじゃないかなあ、という懸念が残るのだ。
社会などのステークホルダーにとって、株主公開のメリットは、一般人が株主になることで会社の経営を監視できることです。
例えば、最近は環境問題に真剣に取り組んでる企業にしか投資しないポートフォリオファンドなんかもあります。
こういう株式公開のメリットは残しておきたい。
だから、「株主主権」すぎて企業がメリットを感じず、MBOにどんどん追い込んでしまうような状況って、解じゃない。
じゃあ、どうするか。
岩井先生も、完全な解があるわけではないが、新しい定式化を行おうとしてます。
私も「会社は株主のものだ」と思考停止をせず、
どうすれば「株式公開」を保って社会に責任を果たしつつ、企業の長期的成長を両立させてそちらでも社会に還元できるようにするか、
ということを考えていきたいな、と思ってる。
早々には結論は出ないね、この問題。
まあ、もうちょっと勉強して考えます。
追記) 株式公開には全くメリットがないかのように書きましたが、実際には企業にとって第三者から資本が入ってることのメリットは非常に大きい、ということは追記しておきます。
産業や企業形態によって異なるので(例えば銀行とメーカーでは大分理由はちがう)逐一はここでは書きませんが、だから公開をやめない、それだけのことです。
なのでデメリットは享受すべき、というのはある程度正しい意見と思います。
 |
会社はこれからどうなるのか (平凡社ライブラリー い 32-1) 岩井 克人 平凡社 このアイテムの詳細を見る |











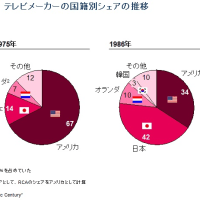
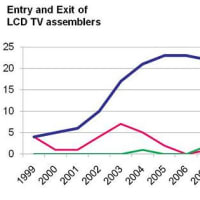
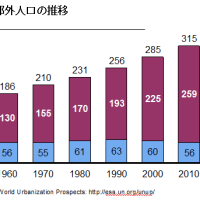
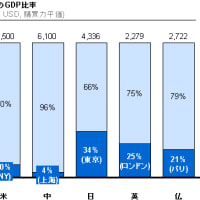

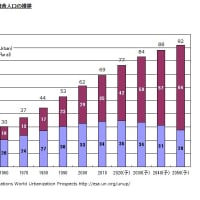
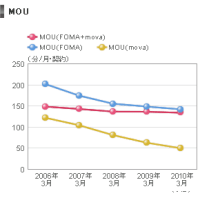
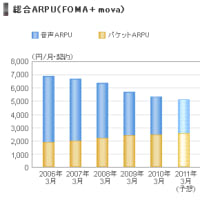
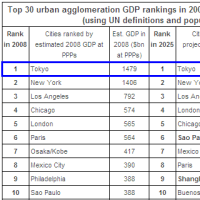
(久しぶりのコメントです.)
センター試験の国語の問題に岩井克人
先生の「資本主義と『人間』」による
小文が出題されていました.
今日試験監督をやっていて文章をみつ
け,(このブログのエントリーを読んで
いたので),私にとってはタイムリーな
出題でした.
内容もここで議論されていることにも
広い意味ではかかわっていると感じた
ので,情報提供まで.
それにしても以外とセンター試験の出
題というものも世相を反映させるもの
なんだなぁ~と妙に関心しました.
(出題者が問題を決めるのが1年前と
するとリーマンショック直後にこの
小文をピックアップすることを決めた
ことになります.)
専門的なことが分からないのですが、気になったのでコメントします。
以前に比べて株式至上主義になっているとは思います。株主の権限を制限すれば、ハゲタカ的な買収はされにくくなるでしょう。
ですが、はたして株主に規制をかたり、株式会社という形態を変えることが現在の問題を解決する手段として正しいのでしょうか?
そもそも、一連の議論が「株主主権をなんとかしよう」といった目的でなされていると感じてしまうのですが、「株主主権をなんとかする」というのは手段ではないかと思います。
つまり、「株主主権」や「株主重視」が仮になくなれば、どのような社会的・経済的問題が解決するのでしょうか?
また、株主主権や株式会社を変える以外にもっと効果的な方法はないのでしょうか?
記事やコメントを見ながら、そんなことを考えてしまいました。
コメント有難うございます。私は知らないことのほうが多いので、こういうコメントはありがたいです。
>少し論点をはずしておられると思います
私は、この本の趣旨は、文中にも書いたように「資本主義経済のあり方によって、必要とされる会社の形態は違ってきたし、今後も違ってくるべき」ということだと思いましたが・・・どうでしょう。
>技術や特許権などを出資して経営権を握ることが、事実上不可能です。これに対し、アメリカには、LLCという、便利な会社形態があります
なるほど、そうすると米国では州によっては技術や特許権などを出資できるということでしょうか。これは面白いですね。
もう少しちゃんと勉強してみたい気がします。
実はMBAの会社法では、州ごとに違うLLCについてはまでは詳しくやらないです。もし参考文献とかご存知なら教えていただければ幸いです。
「株主のもの」であることが自明な、ただ一種類の会社形態しか採れないということこそ、日本経済の競争力を大きく殺いでいます。(ついでにいうと、ごく最近新たに導入された「合同会社」というのは、LLCに似ているようで非なる会社であり、ほとんど魅力がありません。)
それはどなたかもコメントで指摘してましたが、よく言われてる話とも思いますよ。
公開以前の投資銀行に勤めていた人たちは「パートナー制が極端な過熱を防いでいたのだ」と今でも言いますしね。
かといって投資銀行がパートナー制にもどるか、というと絶対にないでしょうね。
第三者からの増資を受けられるEtc魅力的な部分がたくさんありますから。
>Rionさま
本をご紹介してくれてありがとうございます。
>岩井さんの本を丸飲みにしている限り全く先には進めませんよ。
そんなに馬鹿にしたものでもないと思いますよ。
それに彼は問題提起をしているのであって、結論を書いてるわけではない。
>例えば会社の所有者とは残余権者(residual claimant)のことを指します
それは会社が破綻したときの会社資産の所有者でしょう。
「会社」というものの定義が曖昧である以上、その所有者が誰か、と定めること自体には意味がないと思います。
池田氏も指摘してますが、神学論争になりかねませんから。
>satohhideさま
>株主はその名の通り株券の所有者であって会社の所有者じゃないでしょう
これはおっしゃる通りと思います。
議論が起こる理由は記事に書いたとおりだと思ってます。
>フィーロさま
>MBOが続出するというほど続出していないのは、実は非公開化に魅力を感じないからでしょ
これは全くその通りと思いますね。
そうは言っても株式公開にはメリットは多くある、というのが実情ですし。
だから最初のコメントでChikaさんが書いていたように、「いいとこどりしようなんて、贅沢だ」というコメントは当たってると私も思ってます。
保守的な日本で、MBOが続出するというほど続出していないのは、実は非公開化に魅力を感じないからでしょう。非公開化とは、国営化でも天国でもありません。資金調達という一点のみで株式公開を語り、証券取引所が持つリスク分散機能を無視した議論というのは意味がない。証券取引所というのは、形骸化するものではなく、それこそ空気のような存在ですから。そういえば、日本で一番MBOをしたがってたのは、リスクテイカーであり株主資本主義の権化、村上ファンドでしたね。
こちらも読んでるから大丈夫ですよ。匿名の批判を気にしているようではブログなんて書けませんし。
岩井さんの本を丸飲みにしている限り全く先には進めませんよ。まず、もう少しまともな企業のオーナーシップについての文献を読まれることをすすめます。
具体的な文献については池田さんのポストに書いてあったと思います。とりあえずHansmannのThe Ownership of Enterpriseがおすすめです。
例えば会社の所有者とは残余権者(residual claimant)のことを指します。このことを踏まえずに企業の所有者についていくら議論しても意味がありません。
ny47thさんのポストにこの関係の話がよくまとまっています(http://d.hatena.ne.jp/ny47th/20100107/1262875882)。
>岩井先生はポスト産業資本主義の定義として、産業資本主義の拡大が過剰人口の産業予備軍を使いきることを条件に挙げておられますが、現在の失業率や二次産業と三次産業の労働者数のバランスを見ると当てはまりません。
おっしゃるように完全に時代を区切るのはむずかしく、産業や状況によって違うわけです。
例えば、ソフトウェア産業のようにポスト産業資本主義化の先鋒に思える産業も、コモディティ化すればインドから大量のIT技術者が流入したりして、製造コスト(開発費)を下げるのが成功の鍵、というように産業資本主義の性質を持つようになります。
それに、ワインだってテロワールの強いフランスのワインは、いつまでも岩井先生の言う「商業資本主義」の性質を持ち続けてます。
このように、産業や時代によって、「何がコモディティ化するか」というのが違うわけです。
なので、全ての産業に当てはまるベストの企業形態をひとつだけに定めることは難しい。
しかしながら、全体の割合を見ながら、大多数に最適のものを選ぶことは可能かもしれません。
>石川さま
>アメリカは国際社会の中の株式会社という位置づけているのに対して、日本の中で全国民のコンセンサスがとれていないだけです。
アメリカで「株主主権論」が議論になるのは、誰のための株式会社か、というのが決まってないからです。
国際社会とアメリカの見てる方向が違うことはたびたびあります(排出権然りね)、おっしゃってるようにね。
これに対し、池田センセじゃないですが、「会社は株主のためにあるのよ」とさっさと合意してしまい、「あの会社ちょっとひどいんじゃない」と思ったらさっさとカネで株を買い付けて、直してしまったり、
逆に「そういう会社には投資しないわ」とカネを出さなくなってしまったり、というように株主が積極的に活動してる印象がありますね。
それはそれでうまく機能してるんだと思います。
>国の中の株式会社なのか、国際社会の株式会社なのかです。一般的に摩擦になっているところは。
国の中の株式会社ならば、株式会社はその国の国民のためにあるのです。
国際社会に話を広げると、少しまた問題の意味合いが変わってきますね。
ハート・ネグリの「帝国」に倣うと、問題は、今や企業が巨大化し、ひとつの企業が与える影響が国家をも凌駕する可能性があるということです。
もちろん一部の超大企業の話ですが。
彼等が国際社会に与える影響は計り知れないですが、株主は一部の先進国の(そして石川さんの言うように一部のウォール街などの)一部の人間に制限される。
しかしながら結局のところ、それら株主の見識と人間性に問題がなければ、そして利益相反が無ければ、別に株主主権でも問題ないわけですね。
賢明な君主国家とポピュリズムに支配される民主主義とどっちがいいか、という古典的な問題に帰着されるわけですね。
>Haruomiさま
>リーマンショック以後ものすごくたくさん出た種類の本、考え方だと思ってます。
この本は2002年に出版された本の文庫版です。
まあ読んでみてからモノを言って下さいまし。
>日本は株主重視なんかではない
前のエントリにも書いたように、欧米諸国に比べて日本が株主重視であるわけがないです。
昔の日本に比べて、そうであるがために、こういう声が上がるのです。
それは単に急激な変化についていけてなくて、反対の声が上がってるだけともいえます。
しかし、単に全て変えてしまうのが、本当によいのか、という問題もあるんです。
だから、単なる懐古主義に陥らずに、何を残すべきか、という議論をするのは大事だと言ってます。
しかし、少なくとも日本においては決して株主重視などしていません。
むしろ昔の日本の企業は一般株主をあまりにも軽視していたので、大きくリスクを取っている株主に大してそれなりの対価を払うべきという方向性だったのではないでしょうか。
株主利益を無視した過剰な買収防衛策や、最近のメガバンクなどの節操のない公募増資におけるダイリューションなど、株主など金だけ出す貯金箱程度にしか考えていない会社があまりにも多すぎます。
これでは貯蓄から投資へという動きが起こるはずもありません。
ああ、なるほど。納得です。Lilacさんに刺激を受け、ブログ投稿してみました。
・・が、すみません。トラバを2件重ねてしまいました。もしお邪魔でしたら、最初の一つは消して頂けますか。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
残念ながら要約を見る限り、
「世界はアメリカ流資本主義の影響でえらい目にあった」
「だから小泉・竹中とかアメリカ的考えとかこれまでの経済学の蓄積とかいったんゼロにして考えて、自分達の納得できるように考えちゃっていいんだゼ」
「会社は株主のもの、なんていうアメリカが押し付けた屈辱的な考えはナシにしちゃおうぜ。昔の日本人が思ってた、会社は社長が親父、社員の家っていうんだって、ほら歴史をこんな風に解釈すれば、あながちまちがっていないんだゼ」
という、リーマンショック以後ものすごくたくさん出た種類の本、考え方だと思ってます。
この種の本はダメな国民が過去または現状を肯定することで自己満足を得るという意味では、トンデモ戦記もの小説と同じでたいした物ではないのですが、現状の問題を解決するなんの助けにもならず、危機感を麻痺させるという意味で有害です。
リーマンショックだって、日本が超低金利政策を長期間続けていたせいで円キャリー取引でアメリカの不動産に金が流れ込んだってのは有名な話です。半分は日本のせいです。
リーマンショックが示した核心的課題はこれだけ世界中に金とモノと人が流動する世界ではバブルは世界中のどこでも起こりうる「資本主義の限界」の一つであって、それに対してどうやってショックを吸収する対策を講じるか、という点です。
しかし、日本が抱えている問題はこれとは別というのが国外の専門家の意見として一般的なのは、少なくともOECD勧告やWSJの社説が書いている事をみれば明らかです。
これにたいして日本では両者をごっちゃにして、かえって解決から遠ざからせる議論が多すぎ、国際的常識から離れたところに学生や庶民、政治家をミスリードしているように思います。
リーマンショック自体は収束しつつありますが、新たなバブルが新興国で起こりつつあります。
またバブルが弾けたら、今度は「中国の劣悪な経済から日本を守らなければ」なんて言説が蔓延るんでしょうか。
そうこうしている間に日本社会の力はずぶずぶと失われ、取り返しのつかないラインにまで近づこうとしています。
中国自身が国内をコントロールできるようになったから、さらにできるようになれば、国外に影響力を屈指することは確かだと思いますよ。日本海側に軍隊を集結するなんてこともするかもしれないし。それに、中国の歴史の中でも、最強の帝国が完成されているのだし。
なぜ、目先の経済的利益ばかり気にするのかよくわかりません。
国の中の株式会社なのか、国際社会の株式会社なのかです。一般的に摩擦になっているところは。
国の中の株式会社ならば、株式会社はその国の国民のためにあるのです。
で、日本にとって問題になっているのは、アメリカは国際社会の中の株式会社という位置づけているのに対して、日本の中で全国民のコンセンサスがとれていないだけです。日本国内の企業の株主に対して。これは、全産業でもいえます。
さらに、アメリカ側というのは、自分たちの経済的有利のためには、国際社会の同意から外れる国でもあります。もう一つ、アメリカの株式会社制度は不変であるわけではないのです。アメリカこそ最大の民主主義国家だから、民意によって変わる可能性もあるというこどです。悪くなることも良くなることもという点で。
もし、日本国民にとって本当に有利になるならば、いずれグローバル株主を受け入れるし、一方的に不利のままなら態度を保留し続けるというだけです。ただ、態度の保留というのは、国際社会では同意したと取られて、それが実行されなければ無視されるようになるということです。現実的な日本の経済は、無視されるのでしょう。これは、国民性でもあるし解決できないでしょう。
そもそも、国際社会は、日本を相手にしなくてもやっていけるのです。ただ、中国は、どこの国とも経済的に敵になって摩擦が起きることはあきらかなので、日本を味方にしたいということは考えられます。日中関係が良好であるならば、アジアと中国の関係に対する中継経済にもなるし、アメリカやEUとの中国の関係も同様です。中国は欧米の思想や経済学を受け入れたりする国ではありません。
だから、グローバル経済の概念は大きく変わるということです。ただし、中国が逆戻りすれば、変化しません。ただ、日本が疲弊することは確かでしょう。どうにもならないことは、考えてもどうにもらないし。笑
2本の記事を興味深く読ませていただきました。ホントにいろんなことを沢山知ってらっしゃるのに驚きました
ただ、資本主義社会では、ずっと長い間、資本と労働の関係は何も変わっていないのに、現在を「ポスト産業資本主義」というのは誤りだと思います。産業資本は厳然と存在し、労働が価値を生み出すことは以前と同じなんですから、「ポスト」という言葉で新しい時代を先取りした気分になるのは、お正月が来て(去年とは切り離された)新しい年になったと思い込むのと大差ないんじゃないでしょうか。ポストモダンとかポスト鳩山とか、或る命題を捨象したい時にみんな簡単に「ポスト」をくっつけるような気がします。
「資本主義経済のあり方によって、必要とされる会社の形態は違ってくるべき」というのは岩井先生のおっしゃる通りだと思います。でも、どうしても「ポスト産業資本主義」というコトバにひっかかるのです
Lilacさんの引用している本で岩井先生はポスト産業資本主義の定義として、産業資本主義の拡大が過剰人口の産業予備軍を使いきることを条件に挙げておられますが、現在の失業率や二次産業と三次産業の労働者数のバランスを見ると当てはまりません。(この前ハローワークに行ったら2時間半も待たされるほど満員の盛況?でした。過剰人口はいると思います。)
中国では最近、企業は株主の為にあるという議論が盛んになってきています。この背景には、従来ステークホルダーとして企業に影響力を行使し続けてきた「我らの偉大な党」の干渉を避けたいということと、鉄飯碗(いくら粗末に扱っても壊れないご飯茶碗
日本の場合は私の国のように(地方や町レベルまで)圧倒的な影響力を行使できる党がありませんが、今度の日本航空の債務整理を見ても、従業員をステークホルダーとして取り込むことは、コネで入ってきた共産党員をたくさん社内に抱えるのと大差ないように見えます。ものごとは単純な方がいいにきまってるし、ステークホルダーなんか少ないほうが企業は発展すると思います。
ところでワインがお好きなようですね。中国でも新疆地方の白ワインはドライでいいものがあります。赤も長城ワインの華夏農園でできたものでは(中国人にとっては)高いけど(900円ぐらい)いいのがありますよ。
秋
一般論は難しいのは分かった上で、あくまで問題提起してます。
問題提起しないと、人々は思考停止しますからね。
>「会社は誰のものか?」という表現方法には問題があって(中略)少なくとも日本語で「会社は誰のものか?」と問われれば「株主です」と回答せざるを得ないでしょう。
これはその通りと思います。
どのレベルの議論をしてるかにもよりますけど、普通はそんな深い話してると思いませんからね。
>元々の株式会社の本来の目的は
岩井先生が本で書いてるのは株式会社が出来たとこじゃなく、株式の公開のところですね。
それが重化学工業の進展で、Economy of Scale/Scopeが重要となり、少数の資本家ではまかなえなくなったことから、株式の公開で一般の投資家から資本をまかなうことが一般的になった、という議論です。
詳しくは先生の本で緒読み下さい。
>Rion氏の一問一答形式の回答は、議論のための空論でしかないと言わざるを得ませんね。皆さんよく見てください。
まあそういうのは本人のブログでコメントするデスヨ。
スタイルの違いと思いますが、私は本来は一問一答って本質的な答えにたどり着かないので好きじゃないですが。
>岩井氏の本はLilacさんのおかげでAmazonの在庫がなくなったようですね。取次ぎも驚いているかな。
素晴らしいです。
私のこんなエントリだの、他のブログ記事などより、岩井先生の本は100倍素晴らしいので、皆さんがこれを読んで、うーんと唸って思考の一助となっていただけるならこの記事を書いた価値あります。
今の(アメリカの)新興企業は、ベンチャーキャピタルから主に資金調達。
IPOはその株式を保有するベンチャーキャピタルが儲ける手段として行っている。
現在の経済情勢からIPOよりもベンチャーキャピタルから調達する方がメリットが大きいからで経済情勢が変わればIPOも元にもどるのではないでしょうか。手続きの煩雑さが足を引っ張るのは想像できるがそれよりも大きなメリットが考えられる情勢になれば。単にその時の情勢で自分にとって何が徳かで選択しているだけで制度の問題ではない要素の方が大きいでしょう。
「会社は誰のものか?」という表現方法には問題があって、言葉上の問題での議論も多くて実質の議論との峻別を難しくしているので、一般的にも他の表現方法を使うべきですね。公開会社の問題点を議論したくても、少なくとも日本語で「会社は誰のものか?」と問われれば「株主です」と回答せざるを得ないでしょう。そんなことわかりきったことでそんなことを意味しているわけではないとなるわけです。
Rion氏の一問一答形式の回答は、議論のための空論でしかないと言わざるを得ませんね。皆さんよく見てください。ここで言われているような特定の企業を想定しようとしても世の中に存在しえないと気がつきますよね。ある部分では大企業が想定され、ある部分では中小企業が想定され、ある部分ではベンチャーが想定されますよね。いきなり資本金3億円を超えるような公開会社を起業するような方がおられるでしょうか(例外中の例外でしかない)。読んでいて私は宮村優子氏の名台詞を贈呈しそうになりました(中学生になら贈呈しませんが)。
>そもそも何故「会社は誰のものか?」という議論があるのかを考えると、所有と経営と経営目的の分離が起きてるからです。いまや昔と違い、会社の所有者が多様化し、経営者は所有者ではない。
資本そのものの質も多様化していますよね。機関投資家、金融機関、事業会社、持ち合い株、投資ファンド、個人投資家、経営者、従業員持株、外資、内資、違った投資行動が考えられますよね。従業員1,000人を超える会社に限っても会社によってもその構成はかなり多様なので、その意味でも一般化して議論するのは難しいですね。
>公開の本来の目的だった資金調達のメリットもいまや無く
(元々の株式会社の本来の目的はリスクの分散でしたよね。諸説があり類似のものは他にもあったが、英国で船舶貨物の損害のリスクを分散するために株式が考え出され、リスクをとった資本家が利益を得たというのが世界に広まったという説が有力ですよね。)
今では資金調達のメリットが大きいが、リスクの分散というメリットも注目したいですね。
日本では近年、銀行からの借り入れよりも資本市場からの資金調達にシフトしてきていたでしょう。メリットがあるからではないでしょうか。
>MBOは現実的に出来ない、超大企業だけが市場に残され、株式市場は金融投資の目的のために存在するだけになるんじゃないか。
メイリットが大きいのでそんなことは起こらないでしょう。IPOの大多数は中小企業でしょう。景気の問題で今はIPOは減っていますが、出て行く企業があっても入ってくる企業が埋めていくでしょう。
岩井氏の本はLilacさんのおかげでAmazonの在庫がなくなったようですね。取次ぎも驚いているかな。
明けましておめでとうございます。
実は、もう少し本の内容を紹介しようかなと長いエントリを書いていたのですが、やめたんです。
皆さんに読んでもらおうかな・・と思って。
西海岸在住のChikaさんに「買って」と言うのはコクかもしれませんが、紀伊国屋サンノゼ店などに売ってるかもなので是非。
文中にも書いたんですが、そもそも現在、Equityで真面目に資金調達してる企業ってないですよね。
それなのにコストだけがかかって、株式公開の意味合いって何よ、ってなってるのが問題だよね、って趣旨です。
>環境問題に真剣に取り組んでる企業にしか「貸付」しないファンドがあってもいいのでは?
これは、そういうファンドがあるのはいいこと、って意味合いで書いてます。
もともと書いてた長い文章をここで引用しておきますね。
>>>
株式公開は本来、重化学工業が主流になって以降、
一人の資本家(金持ち)では資本がまかなえないほど企業規模が拡大したため、個人の投資家からあまねく資金を調達するためだった。
今でも企業は、1)新規公開時(IPO)、2)その後も新株発行によって、市場から資本を得ることが出来る。
ところが、現代では企業の資金が枯渇したとき、多くの企業は新株発行による資本調達を出来るだけ避ける傾向がある。
新株発行は、自社による資金調達、社債や金融機関からの調達の二つが出来ない最後の手段として行われる(ペッキング・オーダーと呼ぶ)
と市場には解釈されるので、業績が思わしくないうえ、借金も出来ないヤバイ状態なのか、とみなされて、株価が大幅に下がってしまうためである。
またIPOも、アメリカを中心に、本来の資金調達を目的として使われることが減って来ている。
今の(アメリカの)新興企業は、ベンチャーキャピタルから主に資金調達。
IPOはその株式を保有するベンチャーキャピタルが儲ける手段として行っている。
余談だが、最近はシリコンバレーのベンチャーをはじめとして、IPOを選ばない企業が増えているという。
2008年のリーマンショック以降、ベンチャーキャピタルがIPOで儲けることが難しくなったのがきっかけに、
ウォール街の影響を受けやすいIPOに頼らず、Googleのような大企業に買収させる方向で、ポートフォリオを組みなおしてるのだそうだ。
余談終わり。
そんなわけで、株式公開の本来の目的である、資金調達のメリットは薄まってる。
<<<<
後半のシリコンバレーの話は、私がシリコンバレーにいたころに聞いた話で、ボストン界隈のVCの人たちも同じこと言ってましたが、千賀さんから見られて真偽の程はいかがでしょう?
別にequityで調達しなくていいじゃない?環境問題に真剣に取り組んでる企業にしか「貸付」しないファンドがあってもいいのでは?やっぱり「返す責任のない資金は欲しいけど、権利は渡したくない」っていう「いいとこ取り」は変じゃないかなぁ、と。
でも、きっと「会社はこれから・・・」には何かもっとすごいことが書いてあるのでしょうね。読んでないのでわかりませんが・・・。
中間解的にはGoogleみたいな種類株?