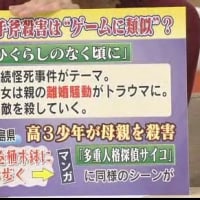・A級戦犯
靖国神社に合祀されている、いわゆるA級戦犯を含む戦犯とされた者たちに関して、政府は国内法上戦犯ではないとの答弁書を昨年10月26日閣議決定している。答弁書は「(東京裁判などで連合国戦争犯罪法廷が科した)刑は、わが国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と指摘している。
そして刑死者たちは、国内法上は他の戦没者らと同様に「法務死」とされ、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等もすべて平等の扱いを受けている。そして、このような扱いは昭和28年当時、自由党、改進党、右派・左派社会党らが賛成し、圧倒的多数をもって決定されている。
更に、サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)11条(極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。)によって日本が独立を回復した後も、1860名もの「戦犯」が依然として服役していたが、彼らを早期に釈放しようと国民運動が起こり、その署名数は4000万以上にのぼったと言われている。
もとより、国際法上は平和条約の締約によってはじめて戦争状態が終結するのであって、その意味ではいわゆるA級戦犯らが連合国による裁判を受けていたときは、日本は停戦状態なだけであって、まだ戦争は終結していなかったのだから、連合国の裁判によって処刑された者たちも「戦争中に亡くなった」と解釈することが可能であって、よって靖国神社に合祀されても不自然ではない。
・靖国神社
1869年(明治2年)に戊辰戦争で亡くなった方々の魂を慰めるのを目的に明治政府によって建立された神社。前身は「東京招魂社」。明治12年に明治天皇の命名で現在の名称に変更。「靖国」とは、「国を安らかにし、穏やかで平安にする」という意味。
靖国神社には、日清戦争、日露戦争、第一次大戦、満州事変、支那事変、大東亜戦争などで日本のために戦われた方々の霊、246万6000余柱(御霊は人ではなく柱と数える)が英霊として祀られている。この中には、坂本竜馬、吉田松陰、高杉晋作も含まれている。
しばしば「靖国神社は国家のために死んだ者しか祀っていない」という批判がなされるが、実は靖国神社には本殿に向かって左側に「鎮霊社」という世界中のあらゆる戦死者をお祀りしてある建物がある。加えて、戦没馬慰霊塔、鳩魂塔(きゅうこんとう)、軍犬慰霊像という戦争で死んだ動物たちも祀られている。ちなみに、海外の要人も靖国神社へ参拝をしている。一例を挙げてみる。
①昭和31年4月、張道潘中華民国立法院院長一行が参拝
②昭和35年3月、ビルマのウ・ヌー前首相が参拝
③昭和36年12月、アルゼンチンのフロンデシ大統領夫妻
④昭和38年6月、タイのプミポン国王夫妻が参拝
⑤昭和40年3月、西ドイツ練習艦隊士官候補生50人が参拝
⑥昭和41年1月、フランス練習艦隊の乗組員達が参拝
⑦昭和44年4月、在日米軍海軍司令官スミス少将以下25人が参拝
⑧昭和55年11月、チベット・ラマ教法王ダライ・ラマ14世が参拝
⑨昭和56年6月、インドネシアのアラムシャ・R・プラウィネガラ宗教大臣が参拝し、「アジア民族独立の歴史は日本の日露戦争勝利に勇気づけられた」と語った。
さらに、今年6月7日、李登輝元総統が靖国神社へ参拝したことは記憶に新しい。
なお、アメリカのアーリントン墓地には、ジェイコブ・スミス将軍という、フィリピンでの戦闘で、敵側の10歳以上の人間を皆殺しにするように命じたため、軍法会議で有罪となった人物が埋葬されているが、今や各国首脳がアメリカを訪問したとき、アーリントン墓地に赴き、献花するのは慣行となっている。安倍前首相もアメリカを訪問したとき、アーリントン墓地で献花を行っている。
韓国にも、毎年6月6日に「顕忠日」という、韓国のために戦い亡くなった愛国者を大統領が追悼する日がある。朝鮮日報2006年6月7日の社説によれば、「顕忠日は国のために亡くなった人たちに、その犠牲を無駄にすることなく、こんな誇らしい国を作り上げたと報告する日」だという。
・分祀(分霊)とは
正しくは分祀ではなく分霊という。分霊とは、特定の神社に祀られている祭神を、異なる場所において恒久的にお祀りすることをいう。本社の祭神の分霊(わけみたまもと)を祀ることになる。神道においては、分霊とは蝋燭の火を別の蝋燭に移すようなもので、分祀派の言うような「お前だけあっち行け」みたいな分霊はできない。要するに、分霊をしても本社には分霊の本体である祭神は変わらず祀られている。
身近な分霊が行われた神社といえば、稲荷神社がある。全国の稲荷神社に祀られている祭神は、すべて京都の稲荷山にある稲荷神社の総本山である伏見稲荷大社から分霊されたものである。
・日本政府は戦前に神社神道を強制したか
一般的に戦前の日本は神道を事実上の「国教」として扱っていたと考えられているが、これは誤りである。伊藤弘文の名で刊行した大日本帝国憲法の注釈書『憲法義解』には、「国教を以て偏信を強ふるは尤人知自然の発達と学術競進の運歩を障害する者」とあり、国教制を文明に逆行するものと考えていた。
よって、日本政府ははじめから神社参拝等を強制しようとは考えていなかった。神社参拝強制が特に問題となったのは満州事変以降であるし、憲法起草者であった伊藤や井上毅らは、「臣民ノ義務」に神道儀式への参列義務まで含めて考えてかなった。つまり、神社神道強制とは、戦前のごくわずかな一部の時期になされたに過ぎなかった。神道が国家的保護を受けていたというが、それはあくまで布教活動や葬儀などの宗教活動を禁止した上での措置であった。しかも、神社への国家の財政援助は微々たるものであったという。
戦前・戦中における国家権力による宗教に対する弾圧・干渉を言うならば、苛酷な迫害を受けたものとして、神道系宗派の一派である大本教などもあったのだ。
なお、現在の憲法の政教分離のモデルとなったと言われているアメリカでは、大日本帝国憲法制定時は、多くの州が公務員の資格としてキリスト教徒であることを条件としていたり、宗教的宣誓を課していたという。湾岸戦争時には、国家が教会の支持を求め、教会でのミサへの参加を呼びかけていた。
靖国神社に合祀されている、いわゆるA級戦犯を含む戦犯とされた者たちに関して、政府は国内法上戦犯ではないとの答弁書を昨年10月26日閣議決定している。答弁書は「(東京裁判などで連合国戦争犯罪法廷が科した)刑は、わが国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と指摘している。
そして刑死者たちは、国内法上は他の戦没者らと同様に「法務死」とされ、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等もすべて平等の扱いを受けている。そして、このような扱いは昭和28年当時、自由党、改進党、右派・左派社会党らが賛成し、圧倒的多数をもって決定されている。
更に、サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)11条(極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。)によって日本が独立を回復した後も、1860名もの「戦犯」が依然として服役していたが、彼らを早期に釈放しようと国民運動が起こり、その署名数は4000万以上にのぼったと言われている。
もとより、国際法上は平和条約の締約によってはじめて戦争状態が終結するのであって、その意味ではいわゆるA級戦犯らが連合国による裁判を受けていたときは、日本は停戦状態なだけであって、まだ戦争は終結していなかったのだから、連合国の裁判によって処刑された者たちも「戦争中に亡くなった」と解釈することが可能であって、よって靖国神社に合祀されても不自然ではない。
・靖国神社
1869年(明治2年)に戊辰戦争で亡くなった方々の魂を慰めるのを目的に明治政府によって建立された神社。前身は「東京招魂社」。明治12年に明治天皇の命名で現在の名称に変更。「靖国」とは、「国を安らかにし、穏やかで平安にする」という意味。
靖国神社には、日清戦争、日露戦争、第一次大戦、満州事変、支那事変、大東亜戦争などで日本のために戦われた方々の霊、246万6000余柱(御霊は人ではなく柱と数える)が英霊として祀られている。この中には、坂本竜馬、吉田松陰、高杉晋作も含まれている。
しばしば「靖国神社は国家のために死んだ者しか祀っていない」という批判がなされるが、実は靖国神社には本殿に向かって左側に「鎮霊社」という世界中のあらゆる戦死者をお祀りしてある建物がある。加えて、戦没馬慰霊塔、鳩魂塔(きゅうこんとう)、軍犬慰霊像という戦争で死んだ動物たちも祀られている。ちなみに、海外の要人も靖国神社へ参拝をしている。一例を挙げてみる。
①昭和31年4月、張道潘中華民国立法院院長一行が参拝
②昭和35年3月、ビルマのウ・ヌー前首相が参拝
③昭和36年12月、アルゼンチンのフロンデシ大統領夫妻
④昭和38年6月、タイのプミポン国王夫妻が参拝
⑤昭和40年3月、西ドイツ練習艦隊士官候補生50人が参拝
⑥昭和41年1月、フランス練習艦隊の乗組員達が参拝
⑦昭和44年4月、在日米軍海軍司令官スミス少将以下25人が参拝
⑧昭和55年11月、チベット・ラマ教法王ダライ・ラマ14世が参拝
⑨昭和56年6月、インドネシアのアラムシャ・R・プラウィネガラ宗教大臣が参拝し、「アジア民族独立の歴史は日本の日露戦争勝利に勇気づけられた」と語った。
さらに、今年6月7日、李登輝元総統が靖国神社へ参拝したことは記憶に新しい。
なお、アメリカのアーリントン墓地には、ジェイコブ・スミス将軍という、フィリピンでの戦闘で、敵側の10歳以上の人間を皆殺しにするように命じたため、軍法会議で有罪となった人物が埋葬されているが、今や各国首脳がアメリカを訪問したとき、アーリントン墓地に赴き、献花するのは慣行となっている。安倍前首相もアメリカを訪問したとき、アーリントン墓地で献花を行っている。
韓国にも、毎年6月6日に「顕忠日」という、韓国のために戦い亡くなった愛国者を大統領が追悼する日がある。朝鮮日報2006年6月7日の社説によれば、「顕忠日は国のために亡くなった人たちに、その犠牲を無駄にすることなく、こんな誇らしい国を作り上げたと報告する日」だという。
・分祀(分霊)とは
正しくは分祀ではなく分霊という。分霊とは、特定の神社に祀られている祭神を、異なる場所において恒久的にお祀りすることをいう。本社の祭神の分霊(わけみたまもと)を祀ることになる。神道においては、分霊とは蝋燭の火を別の蝋燭に移すようなもので、分祀派の言うような「お前だけあっち行け」みたいな分霊はできない。要するに、分霊をしても本社には分霊の本体である祭神は変わらず祀られている。
身近な分霊が行われた神社といえば、稲荷神社がある。全国の稲荷神社に祀られている祭神は、すべて京都の稲荷山にある稲荷神社の総本山である伏見稲荷大社から分霊されたものである。
・日本政府は戦前に神社神道を強制したか
一般的に戦前の日本は神道を事実上の「国教」として扱っていたと考えられているが、これは誤りである。伊藤弘文の名で刊行した大日本帝国憲法の注釈書『憲法義解』には、「国教を以て偏信を強ふるは尤人知自然の発達と学術競進の運歩を障害する者」とあり、国教制を文明に逆行するものと考えていた。
よって、日本政府ははじめから神社参拝等を強制しようとは考えていなかった。神社参拝強制が特に問題となったのは満州事変以降であるし、憲法起草者であった伊藤や井上毅らは、「臣民ノ義務」に神道儀式への参列義務まで含めて考えてかなった。つまり、神社神道強制とは、戦前のごくわずかな一部の時期になされたに過ぎなかった。神道が国家的保護を受けていたというが、それはあくまで布教活動や葬儀などの宗教活動を禁止した上での措置であった。しかも、神社への国家の財政援助は微々たるものであったという。
戦前・戦中における国家権力による宗教に対する弾圧・干渉を言うならば、苛酷な迫害を受けたものとして、神道系宗派の一派である大本教などもあったのだ。
なお、現在の憲法の政教分離のモデルとなったと言われているアメリカでは、大日本帝国憲法制定時は、多くの州が公務員の資格としてキリスト教徒であることを条件としていたり、宗教的宣誓を課していたという。湾岸戦争時には、国家が教会の支持を求め、教会でのミサへの参加を呼びかけていた。