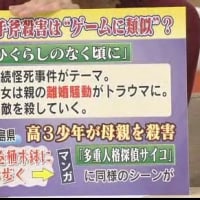9条改正 反対64%、賛成26% 朝日新聞世論調査(朝日新聞)
3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社が実施した全国世論調査(電話)によると、憲法9条を「変えない方がよい」が64%に達し、「変える方がよい」は26%にとどまった。憲法改正が「必要」とする人は53%いるが、その中で9条を「変える方がよい」とする人は42%、「変えない方がよい」が49%だった。
調査は4月18、19日に実施した。
9条に対する意見は、安倍内閣時代の07年4月に「変えない方がよい」49%、「変える方がよい」33%だったのが、福田内閣のもとでの昨年4月調査では66%対23%と差が大きく広がった。今回も昨年から大きな変化はなかった。
9条を「変える方がよい」と答えた人(全体の26%)に、どのように変えるのがよいかを二つの選択肢で聞くと、「いまある自衛隊の存在を書き込むのにとどめる」が50%、「自衛隊をほかの国のような軍隊と定める」が44%と意見が分かれた。
憲法全体について聞いた質問では、「改正必要」が53%で、「必要ない」33%を上回った。07年は58%対27%、昨年は56%対31%だった。
このような世論調査の欺瞞性については昨年の憲法記念日に「最近の朝日は看過できない その2」において論破したように、9条の1項と2項を一緒くたにして質問をしているため、改憲派の改憲案である、9条1項は残し、2項の戦力不保持という規定を変えて、自衛隊を自衛軍とするという主張への賛否を正確に反映できていないため、こうした「世論調査」をいくら繰り返したところで無意味である。
私の論理を裏付けるものとして、先日内閣府が行った、ソマリア沖への自衛隊派遣についての世論調査では、東アフリカ・ソマリア沖の海賊対策に自衛隊が参加することについて、「取り組んでいくべきだ」が27.8%、「どちらかと言えば取り組むべきだ」が35.3%で、「肯定派」が6割を超えた(毎日新聞)。
さらに、このとき内閣府が同時に行った世論調査では、自衛隊の印象について、「良い印象を持っている」との回答が80.9%、もし日本が外国から侵略された場合、どうするか聞いたところ、「何らかの方法で自衛隊を支援する」と答えた者の割合が48.9%と最も高かったこと、日本の安全を守るためにはどのような方法をとるべきかという質問においては、「現状どおり日米の安全保障体制と自衛隊で日本の安全を守る」と答えた者の割合が72.1%を記録したことなどからも言えよう。
つまり、多くの国民の意識は、自衛隊を憲法違反の存在とは捉えておらず(この時点で国民の多くが朝日の世論調査のような考えだとしても、「9条の会」のような考えにも、同時に与しないということになる。)、ただ、9条の「戦争の放棄」は変えるべきではない、と考えているという姿が見えてくる。こうした国民の多くの考え方は、2年前の憲法記念日に当の朝日自身が述べたように、「国民の多くは『憲法か、自衛隊か』と対立的にはとらえていない」のである。
だからこそ、9条の1項と2項を一緒くたにした聞き方をしたら、国民の多くは「9条を変えるべきではない」と回答するに決まっている。私だって9条1項の侵略戦争の放棄についての条項は残すべきだと思っているぐらいだ。これでは、国民はいつになっても改憲派の正確な主張を知ることができない。
なので、この世論調査の結果を、「9条の会」などの「護憲カルト集団」が自身の主張の正当化のための根拠として用いることはできない。「9条の会」をはじめとした多くの護憲派と呼ばれる者達は、自衛隊の縮小と日米安保撤廃を望んでいる。
しかし上記の内閣府の世論調査によれば、「日米安全保障条約をやめ,自衛隊も縮小または廃止する」と答えた者の割合が4.7%にとどまっており、自衛隊の防衛力についても、「今の程度でよい」と答えた者の割合が61.8%と、サイレント・マジョリティーは決して「9条原理主義」ではないことが分かる。したがって、9条護憲派がこの調査結果をもって、「自分たちが正しい」と言うことは、世論を読み違えているということになる。
唐突だが、「憲法」とは一体何か。それは国家の基本法である。ドイツでは憲法のことを「ボン基本法」と呼んでいる。「基本法」ということは、それが国家の最高法規であって、ゆえに法のヒエラルキーの頂点に君臨し、憲法に反する法は全て無効になる(憲法98条において、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定されていることからも、このことが窺えよう)。
何が言いたいのか。つまり、日本においては、実は我々のような立場が「反体制」であって、国家に存在する法の頂点を死守しようとしている左翼・リベラル勢力こそが「体制派」なのである。
現在の憲法は、作成したのがGHQの中でも特にリベラルで、当時アメリカで一定の影響力を持っていた「ニューディール左派」であったぐらいなので、左翼・リベラル=体制派にとって実に都合よく出来ている。人間、自分たちに都合のいいものは守ろうとするに決まっている。
たとえば労働三権(憲法28条)。神戸大学の大内伸哉教授によれば、労働三権すべてを憲法レベルで保障したのは、日本国憲法制定当時ではどこにもなく、日本だけであり、アメリカでは現在でも労働三権は憲法よりも下位の法律レベルで保障されるにとどまっているという。
それから改正条項(憲法96条)。憲法を改正するには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」憲法改正を発議するだけで、このハードルの高さである。これもまた、護憲を標榜する左翼・リベラル勢力にとって実に都合がいい。だからこそ、55年体制下では、社会党が各院の3分の1以上を占めていたから、憲法改正が実現できなかった。
そして何と言っても、憲法9条。
このように、国家の基本法たる憲法が左翼・リベラル勢力にとって非常に都合のいいシロモノである以上、これに抗う我々のような改憲派こそが、体制に立ち向かう勢力であって、世間で認識されているような、体制=保守・右派、反体制=左翼・リベラルという構図との齟齬がここで明らかになった。
憲法9条に関して言えば、あの条文を一般人が素直に読めば、通説の言うように自衛隊を否定し、一切の軍事力は違憲ということになりかねない。このような、軍事力に関して非常にシビアな(というか否定的な)憲法が法体系の頂点に君臨している以上、自衛隊法や○○特措法などの下位法でいくら自衛隊を普通の国の軍隊と同列にしようと、そこには必然的な限界が内包されている。
だから、政府や改憲派は当面の間、解釈改憲(いかに9条を骨抜きにするか。)によってこれを乗り切ってきたが、ソマリア沖への自衛隊派遣や北朝鮮のミサイル問題等を見ていると、これも限界になっているように思える。
はっきり言って、本当のところ、左翼・リベラル勢力にとって、このような下位法による9条の骨抜きなど、痛くもかゆくもないのだろう。だって、憲法という法のヒエラルキーの頂点は、常に自分たちの味方なのだから。
だからこそ、護憲派勢力は違法状態を故意に作出してまでも、国民投票法によって規定された憲法審議会の開催を引き延ばしているのだろう。おそらく体制派=護憲派は、私がさきに述べたようなサイレント・マジョリティーの考えは理解し、これを一番恐れている。なので、わざとあのような姑息な聞き方をして、憲法改正議論の熱を冷まそうとしているのだろう。
結局のところ、改憲派ができることはと言えば、その改憲の真意をきちんと正確に国民に伝え、9条に関する上記のような誤解を解き、粘り強く説得を続けるのしかないのだろう。
こういうことをいつも書いてきて思ったことがある。それは、正義とは、正しいことを言っていることではなく、顔の皮が厚く、声がデカイ勢力が正義になるのだ、ということだ。
3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社が実施した全国世論調査(電話)によると、憲法9条を「変えない方がよい」が64%に達し、「変える方がよい」は26%にとどまった。憲法改正が「必要」とする人は53%いるが、その中で9条を「変える方がよい」とする人は42%、「変えない方がよい」が49%だった。
調査は4月18、19日に実施した。
9条に対する意見は、安倍内閣時代の07年4月に「変えない方がよい」49%、「変える方がよい」33%だったのが、福田内閣のもとでの昨年4月調査では66%対23%と差が大きく広がった。今回も昨年から大きな変化はなかった。
9条を「変える方がよい」と答えた人(全体の26%)に、どのように変えるのがよいかを二つの選択肢で聞くと、「いまある自衛隊の存在を書き込むのにとどめる」が50%、「自衛隊をほかの国のような軍隊と定める」が44%と意見が分かれた。
憲法全体について聞いた質問では、「改正必要」が53%で、「必要ない」33%を上回った。07年は58%対27%、昨年は56%対31%だった。
このような世論調査の欺瞞性については昨年の憲法記念日に「最近の朝日は看過できない その2」において論破したように、9条の1項と2項を一緒くたにして質問をしているため、改憲派の改憲案である、9条1項は残し、2項の戦力不保持という規定を変えて、自衛隊を自衛軍とするという主張への賛否を正確に反映できていないため、こうした「世論調査」をいくら繰り返したところで無意味である。
私の論理を裏付けるものとして、先日内閣府が行った、ソマリア沖への自衛隊派遣についての世論調査では、東アフリカ・ソマリア沖の海賊対策に自衛隊が参加することについて、「取り組んでいくべきだ」が27.8%、「どちらかと言えば取り組むべきだ」が35.3%で、「肯定派」が6割を超えた(毎日新聞)。
さらに、このとき内閣府が同時に行った世論調査では、自衛隊の印象について、「良い印象を持っている」との回答が80.9%、もし日本が外国から侵略された場合、どうするか聞いたところ、「何らかの方法で自衛隊を支援する」と答えた者の割合が48.9%と最も高かったこと、日本の安全を守るためにはどのような方法をとるべきかという質問においては、「現状どおり日米の安全保障体制と自衛隊で日本の安全を守る」と答えた者の割合が72.1%を記録したことなどからも言えよう。
つまり、多くの国民の意識は、自衛隊を憲法違反の存在とは捉えておらず(この時点で国民の多くが朝日の世論調査のような考えだとしても、「9条の会」のような考えにも、同時に与しないということになる。)、ただ、9条の「戦争の放棄」は変えるべきではない、と考えているという姿が見えてくる。こうした国民の多くの考え方は、2年前の憲法記念日に当の朝日自身が述べたように、「国民の多くは『憲法か、自衛隊か』と対立的にはとらえていない」のである。
だからこそ、9条の1項と2項を一緒くたにした聞き方をしたら、国民の多くは「9条を変えるべきではない」と回答するに決まっている。私だって9条1項の侵略戦争の放棄についての条項は残すべきだと思っているぐらいだ。これでは、国民はいつになっても改憲派の正確な主張を知ることができない。
なので、この世論調査の結果を、「9条の会」などの「護憲カルト集団」が自身の主張の正当化のための根拠として用いることはできない。「9条の会」をはじめとした多くの護憲派と呼ばれる者達は、自衛隊の縮小と日米安保撤廃を望んでいる。
しかし上記の内閣府の世論調査によれば、「日米安全保障条約をやめ,自衛隊も縮小または廃止する」と答えた者の割合が4.7%にとどまっており、自衛隊の防衛力についても、「今の程度でよい」と答えた者の割合が61.8%と、サイレント・マジョリティーは決して「9条原理主義」ではないことが分かる。したがって、9条護憲派がこの調査結果をもって、「自分たちが正しい」と言うことは、世論を読み違えているということになる。
唐突だが、「憲法」とは一体何か。それは国家の基本法である。ドイツでは憲法のことを「ボン基本法」と呼んでいる。「基本法」ということは、それが国家の最高法規であって、ゆえに法のヒエラルキーの頂点に君臨し、憲法に反する法は全て無効になる(憲法98条において、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定されていることからも、このことが窺えよう)。
何が言いたいのか。つまり、日本においては、実は我々のような立場が「反体制」であって、国家に存在する法の頂点を死守しようとしている左翼・リベラル勢力こそが「体制派」なのである。
現在の憲法は、作成したのがGHQの中でも特にリベラルで、当時アメリカで一定の影響力を持っていた「ニューディール左派」であったぐらいなので、左翼・リベラル=体制派にとって実に都合よく出来ている。人間、自分たちに都合のいいものは守ろうとするに決まっている。
たとえば労働三権(憲法28条)。神戸大学の大内伸哉教授によれば、労働三権すべてを憲法レベルで保障したのは、日本国憲法制定当時ではどこにもなく、日本だけであり、アメリカでは現在でも労働三権は憲法よりも下位の法律レベルで保障されるにとどまっているという。
それから改正条項(憲法96条)。憲法を改正するには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」憲法改正を発議するだけで、このハードルの高さである。これもまた、護憲を標榜する左翼・リベラル勢力にとって実に都合がいい。だからこそ、55年体制下では、社会党が各院の3分の1以上を占めていたから、憲法改正が実現できなかった。
そして何と言っても、憲法9条。
このように、国家の基本法たる憲法が左翼・リベラル勢力にとって非常に都合のいいシロモノである以上、これに抗う我々のような改憲派こそが、体制に立ち向かう勢力であって、世間で認識されているような、体制=保守・右派、反体制=左翼・リベラルという構図との齟齬がここで明らかになった。
憲法9条に関して言えば、あの条文を一般人が素直に読めば、通説の言うように自衛隊を否定し、一切の軍事力は違憲ということになりかねない。このような、軍事力に関して非常にシビアな(というか否定的な)憲法が法体系の頂点に君臨している以上、自衛隊法や○○特措法などの下位法でいくら自衛隊を普通の国の軍隊と同列にしようと、そこには必然的な限界が内包されている。
だから、政府や改憲派は当面の間、解釈改憲(いかに9条を骨抜きにするか。)によってこれを乗り切ってきたが、ソマリア沖への自衛隊派遣や北朝鮮のミサイル問題等を見ていると、これも限界になっているように思える。
はっきり言って、本当のところ、左翼・リベラル勢力にとって、このような下位法による9条の骨抜きなど、痛くもかゆくもないのだろう。だって、憲法という法のヒエラルキーの頂点は、常に自分たちの味方なのだから。
だからこそ、護憲派勢力は違法状態を故意に作出してまでも、国民投票法によって規定された憲法審議会の開催を引き延ばしているのだろう。おそらく体制派=護憲派は、私がさきに述べたようなサイレント・マジョリティーの考えは理解し、これを一番恐れている。なので、わざとあのような姑息な聞き方をして、憲法改正議論の熱を冷まそうとしているのだろう。
結局のところ、改憲派ができることはと言えば、その改憲の真意をきちんと正確に国民に伝え、9条に関する上記のような誤解を解き、粘り強く説得を続けるのしかないのだろう。
こういうことをいつも書いてきて思ったことがある。それは、正義とは、正しいことを言っていることではなく、顔の皮が厚く、声がデカイ勢力が正義になるのだ、ということだ。