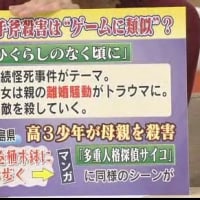捕鯨をめぐる日本とオーストラリアの関係が、どうやら外交問題にまで発展する可能性があるのだという。以下、毎日新聞の記事より引用。
日本が南極海で実施する調査捕鯨が、豪州との間で深刻な外交問題に発展する恐れが出てきた。31日に来日するスミス豪外相と高村正彦外相の会談でも、捕鯨問題が議題になる見通しだ。今年に入って豪州などの環境保護団体の活動家による妨害行為も続いている。文化の違いなどが根底にあり、打開策を見いだすのは容易でない。
「調査捕鯨は公海上の合法的な活動。妨害行為は関係者の身体・生命を危うくする許しがたい違法行為だ」。福田康夫首相は23日の参院本会議で、保護団体の抗議活動を批判した。22日にクリーン豪貿易相と会談した高村外相は「良好な日豪関係に悪影響を与えないようにする点で合意した」と強調したが、欧米メディアは鯨が血を流す映像などを繰り返し報じており、在外日本大使館や水産庁にも抗議が相次いでいる。
国際捕鯨委員会(IWC、加盟78カ国)の色分けは捕鯨反対42カ国に対し賛成36カ国。日本は支持拡大に努めるとともに、今年3月のIWC中間会合で「感情的対立ではなく、科学的データに基づく資源管理につながる冷静な議論を求める」(外務省幹部)方針だ。
ただ、7月の北海道洞爺湖サミットを控え、政府内から「主要国はクジラを環境保護のシンボルと位置づけている。捕鯨文化を守るメリットに比べ、失う国益が大きすぎる」との見方も出ている。
かつて水産庁に、捕鯨推進派のタフ・ネゴシエーターと呼ばれた小松正之博士がいた。彼は欧米諸国の捕鯨問題へのダブルスタンダードを痛烈に批判し、その姿勢はニューヨーク・タイムズから「日本では出る杭は打たれるが、小松は打たれても引っ込まない杭だ」と評されたという。
小松博士は、アメリカの先住民族マカや、イヌイットの捕鯨は許されて(しかも、日本近海に生息する鯨よりも、イヌイットらの捕獲する鯨のほうが絶滅の危機にあるにも関わらず)、日本の捕鯨は許さないというのは、明らかにダブルスタンダードだと、科学的根拠をもって国際会議などの場で言い続けてきた。小松博士は「海にはゴキブリ並みに鯨がいる」とも発言し、捕鯨議論を盛り上げたりもした。
ちなみに、小松博士は、ニューズウィーク2005年10月26日号、「世界が尊敬する日本人100人」のうちの一人に数えられている。捕鯨反対の国で刊行される雑誌にもかかわらず。
ところで・・・
>国際捕鯨委員会(IWC、加盟78カ国)の色分けは捕鯨反対42カ国に対し賛成36カ国
とあるが、この委員会、実は過去に全く捕鯨をしたことのない国、果ては内陸国まで加盟しており、その多くが捕鯨反対の国のロビィングによって支配されているという状況なのだ。日本も今まで以上に、日本の味方を多く獲得できるよう、開発援助等をちらつかせ、積極的にロビィングをし、根回しをていくべきだ。
それから・・・
>政府内から「主要国はクジラを環境保護のシンボルと位置づけている。捕鯨文化を守るメリットに比べ、失う国益が大きすぎる」
どこの誰かは知らないが、彼(彼女?)の言う「国益」とは具体的に一体何なのか?日本の文化を犠牲にしてまで得る「国益」とやらは、そんなに魅力あるものなのか?こういうことを言ってのける人間は、恐らく首相らの靖国参拝にも反対するために、似たようなことを言っていたのだろう。
どこかの国から圧力を掛けられたからと言って、自分の所属する国の文化までも犠牲にしてその国に尻尾を振ろうとする人間が国家を動かす機関に存在している限り、日本が、「国際社会において、名誉ある地位を占め」る(憲法前文)ことはできないだろう。
日本が南極海で実施する調査捕鯨が、豪州との間で深刻な外交問題に発展する恐れが出てきた。31日に来日するスミス豪外相と高村正彦外相の会談でも、捕鯨問題が議題になる見通しだ。今年に入って豪州などの環境保護団体の活動家による妨害行為も続いている。文化の違いなどが根底にあり、打開策を見いだすのは容易でない。
「調査捕鯨は公海上の合法的な活動。妨害行為は関係者の身体・生命を危うくする許しがたい違法行為だ」。福田康夫首相は23日の参院本会議で、保護団体の抗議活動を批判した。22日にクリーン豪貿易相と会談した高村外相は「良好な日豪関係に悪影響を与えないようにする点で合意した」と強調したが、欧米メディアは鯨が血を流す映像などを繰り返し報じており、在外日本大使館や水産庁にも抗議が相次いでいる。
国際捕鯨委員会(IWC、加盟78カ国)の色分けは捕鯨反対42カ国に対し賛成36カ国。日本は支持拡大に努めるとともに、今年3月のIWC中間会合で「感情的対立ではなく、科学的データに基づく資源管理につながる冷静な議論を求める」(外務省幹部)方針だ。
ただ、7月の北海道洞爺湖サミットを控え、政府内から「主要国はクジラを環境保護のシンボルと位置づけている。捕鯨文化を守るメリットに比べ、失う国益が大きすぎる」との見方も出ている。
かつて水産庁に、捕鯨推進派のタフ・ネゴシエーターと呼ばれた小松正之博士がいた。彼は欧米諸国の捕鯨問題へのダブルスタンダードを痛烈に批判し、その姿勢はニューヨーク・タイムズから「日本では出る杭は打たれるが、小松は打たれても引っ込まない杭だ」と評されたという。
小松博士は、アメリカの先住民族マカや、イヌイットの捕鯨は許されて(しかも、日本近海に生息する鯨よりも、イヌイットらの捕獲する鯨のほうが絶滅の危機にあるにも関わらず)、日本の捕鯨は許さないというのは、明らかにダブルスタンダードだと、科学的根拠をもって国際会議などの場で言い続けてきた。小松博士は「海にはゴキブリ並みに鯨がいる」とも発言し、捕鯨議論を盛り上げたりもした。
ちなみに、小松博士は、ニューズウィーク2005年10月26日号、「世界が尊敬する日本人100人」のうちの一人に数えられている。捕鯨反対の国で刊行される雑誌にもかかわらず。
ところで・・・
>国際捕鯨委員会(IWC、加盟78カ国)の色分けは捕鯨反対42カ国に対し賛成36カ国
とあるが、この委員会、実は過去に全く捕鯨をしたことのない国、果ては内陸国まで加盟しており、その多くが捕鯨反対の国のロビィングによって支配されているという状況なのだ。日本も今まで以上に、日本の味方を多く獲得できるよう、開発援助等をちらつかせ、積極的にロビィングをし、根回しをていくべきだ。
それから・・・
>政府内から「主要国はクジラを環境保護のシンボルと位置づけている。捕鯨文化を守るメリットに比べ、失う国益が大きすぎる」
どこの誰かは知らないが、彼(彼女?)の言う「国益」とは具体的に一体何なのか?日本の文化を犠牲にしてまで得る「国益」とやらは、そんなに魅力あるものなのか?こういうことを言ってのける人間は、恐らく首相らの靖国参拝にも反対するために、似たようなことを言っていたのだろう。
どこかの国から圧力を掛けられたからと言って、自分の所属する国の文化までも犠牲にしてその国に尻尾を振ろうとする人間が国家を動かす機関に存在している限り、日本が、「国際社会において、名誉ある地位を占め」る(憲法前文)ことはできないだろう。