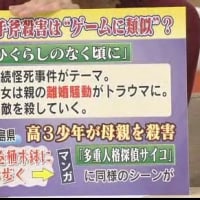「ザ・コーヴ」上映 6映画館で開始(スポーツニッポン) - goo ニュース
和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に取り上げ、抗議や街宣活動の影響で一時、公開が危ぶまれた米映画「ザ・コーヴ」の上映が3日、青森・八戸、仙台、東京、横浜、大阪、京都の6映画館で始まった。
東京・渋谷の映画館前では一時、上映反対グループが「漁師さんをいじめるな」などと書かれたプラカードを掲げ、警察官がグループを取り囲んで警戒したが、大きな混乱はなかった。
観賞した大学院生(24)は「イルカ漁を知って賛否を考えるきっかけにはなるのでは」と一定の評価。一方、太地町の三軒一高町長は「表現の自由はあるが、一方でルールや漁師の人権もあるんじゃないか。上映は残念」。同町漁協の組合員も「漁協は金もなく人もいないから、映画に反論する手段がない。普段通りに生活しているだけなのに…。太地町は力のある映画や団体に揺さぶられている」と悔しさをあらわにした。今後、ほかに18館でも上映される予定になっている。
さて、その1からの続きである。
8 アメリカによる乱獲により荒廃する太地
先述したように、江戸末期には欧米から近代化された捕鯨船が軒を連ねてやってくるようになり、太地町では慢性的な鯨の不漁が続いた。当時の太地町を訪れた者の記録によれば、村は貧困が蔓延し荒廃していたという。
今でもほとんど同じであるが、当時の太地での捕鯨というのは、沖合の黒潮に乗って回遊してくる鯨を、その回遊ルートから離れた沖合で捕獲しているに過ぎなかった。
太地の鯨組は陸での解体、流通等とのルートから離れて活動することは技術的に無理であったため、必然的にアメリカの捕鯨船と並んで捕鯨することはできず、したがって乱獲することは不可能であるので資源の枯渇という問題は考えられなかった。
要するに、アメリカの乱獲により資源量が激減し、太地の捕鯨は存続の危機に立たされることになった。そこで起こった悲劇が、先述した「大背美流れ」である。
9 近代化する捕鯨
こうした中、当時の捕鯨の最先端であったノルウェー式捕鯨(120トン程度の鋼鉄船に鯨を仕留めるための捕鯨砲を搭載し、基地から50~100マイル沿岸で操業する。)が、やがて日本にも上陸する。このノルウェー式の捕鯨をはじめて日本で本格的に導入したのが、山口県議会議員であった岡十郎である。1899年(明治32年)のことであった。
岡は「日本遠洋漁業株式会社」を設立し、捕鯨砲等の資材はノルウェーから取り寄せ、捕鯨砲の技術が当時の日本にはなかったため、ノルウェー人を雇い、後継の日本人を育成していった。岡はこの新技術と日本の伝統的な捕鯨文化との融合を目指した。
新技術の導入に伴い、岡の試みは大成功し、各地にあった不況に苦しんでいた鯨組を次々と吸収しつつも、そこでのノウハウ(解体技術や輸送技術等)は旧来のままを維持した。
太地には1905年(明治38年)に東洋漁業が事務所を開設し、翌年には神戸市に本拠を有する帝國水産が参入し、後に後者が前者を吸収した。こうした近代技術を持った会社の登場により、太地の鯨組の人々は再び職を取り戻し、村に活気が戻った。こうした会社の登場は、経済的効果のみでなく、太地の伝統であった捕鯨文化も再び活気づけた。
10 新技術の弊害
しかしながら、岡の導入した新技術には同時に次のような弊害も生じさせた。すなわち、新技術による大規模な捕鯨によって、他の漁に支障が出始めたのだ。
たとえば、解剖時の血や脂が海を汚染し、イワシやカツオなどの漁業に影響が出ているという苦情である。このような苦情は各地の漁村で提起されたものの、こうした苦情に対し捕鯨産業は迷信であると一蹴し、相手にしなかった。そのため、漁民らの不満は高まり、青森県ではホッキ貝の漁師らが捕鯨会社の関連施設を焼き打ちするという事件まで起きている。
11 乱獲による捕鯨数の減少
新技術の導入により、これまで活動範囲の限られていた捕鯨から、沖合にまで出て捕鯨が可能になった。そのため、捕鯨数は劇的に増加した。そこで次第に、鯨資源の枯渇が危惧されてくるようになる。
こうした危惧を受けて岡は、鯨資源の枯渇は心配ないと述べ、不安を収めようとした。一方で、いざという場合に備え、1909年(明治42年)に捕鯨会社により「日本捕鯨水産組合」が設立され、捕鯨の自主規制に乗り出した。
当時の自主規制は捕鯨産業の発展を優先し過ぎたため効果的ではなかったものの、1900年前後は世界各地で捕鯨を規制する動きが活発になり始めたところで、その中でも日本の規制は世界をリードするものであったという。
12 軍部と一体化した捕鯨
時代は少し下り1930年代になると、日本も欧米と同じように、鯨油の獲得を中心にした捕鯨に、一時的ではあるが、シフトしていく(なお、以前からも鯨油は取っていたものの、あくまでも目的は食肉であった)。
1930年代といえば、「最後のフロンティア」として、列強各国はこぞって南氷洋に捕鯨のため出て行った。日本もまた例外ではなく、南氷洋に捕鯨をするため船を向かわせた。とは言うものの、当時南氷洋で捕鯨をしていた各国と比べると、日本の捕鯨量は南氷洋全体で12.7%の3万894頭であった。なお、当時南氷洋で主に捕鯨をしていた国はイギリスとノルウェーであったという。太地の捕鯨船も南氷洋に向かった。
この時代はそれまでの捕鯨と異なり、捕鯨船が軍用タンカーに建造可能な仕様にされるなどして、戦争の準備と捕鯨が一体化していたので、捕鯨船建造について海軍が支援を行っていた。また、鯨油を活発に輸出し、不足していた外貨獲得に貢献した。
その3に続く。
和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に取り上げ、抗議や街宣活動の影響で一時、公開が危ぶまれた米映画「ザ・コーヴ」の上映が3日、青森・八戸、仙台、東京、横浜、大阪、京都の6映画館で始まった。
東京・渋谷の映画館前では一時、上映反対グループが「漁師さんをいじめるな」などと書かれたプラカードを掲げ、警察官がグループを取り囲んで警戒したが、大きな混乱はなかった。
観賞した大学院生(24)は「イルカ漁を知って賛否を考えるきっかけにはなるのでは」と一定の評価。一方、太地町の三軒一高町長は「表現の自由はあるが、一方でルールや漁師の人権もあるんじゃないか。上映は残念」。同町漁協の組合員も「漁協は金もなく人もいないから、映画に反論する手段がない。普段通りに生活しているだけなのに…。太地町は力のある映画や団体に揺さぶられている」と悔しさをあらわにした。今後、ほかに18館でも上映される予定になっている。
さて、その1からの続きである。
8 アメリカによる乱獲により荒廃する太地
先述したように、江戸末期には欧米から近代化された捕鯨船が軒を連ねてやってくるようになり、太地町では慢性的な鯨の不漁が続いた。当時の太地町を訪れた者の記録によれば、村は貧困が蔓延し荒廃していたという。
今でもほとんど同じであるが、当時の太地での捕鯨というのは、沖合の黒潮に乗って回遊してくる鯨を、その回遊ルートから離れた沖合で捕獲しているに過ぎなかった。
太地の鯨組は陸での解体、流通等とのルートから離れて活動することは技術的に無理であったため、必然的にアメリカの捕鯨船と並んで捕鯨することはできず、したがって乱獲することは不可能であるので資源の枯渇という問題は考えられなかった。
要するに、アメリカの乱獲により資源量が激減し、太地の捕鯨は存続の危機に立たされることになった。そこで起こった悲劇が、先述した「大背美流れ」である。
9 近代化する捕鯨
こうした中、当時の捕鯨の最先端であったノルウェー式捕鯨(120トン程度の鋼鉄船に鯨を仕留めるための捕鯨砲を搭載し、基地から50~100マイル沿岸で操業する。)が、やがて日本にも上陸する。このノルウェー式の捕鯨をはじめて日本で本格的に導入したのが、山口県議会議員であった岡十郎である。1899年(明治32年)のことであった。
岡は「日本遠洋漁業株式会社」を設立し、捕鯨砲等の資材はノルウェーから取り寄せ、捕鯨砲の技術が当時の日本にはなかったため、ノルウェー人を雇い、後継の日本人を育成していった。岡はこの新技術と日本の伝統的な捕鯨文化との融合を目指した。
新技術の導入に伴い、岡の試みは大成功し、各地にあった不況に苦しんでいた鯨組を次々と吸収しつつも、そこでのノウハウ(解体技術や輸送技術等)は旧来のままを維持した。
太地には1905年(明治38年)に東洋漁業が事務所を開設し、翌年には神戸市に本拠を有する帝國水産が参入し、後に後者が前者を吸収した。こうした近代技術を持った会社の登場により、太地の鯨組の人々は再び職を取り戻し、村に活気が戻った。こうした会社の登場は、経済的効果のみでなく、太地の伝統であった捕鯨文化も再び活気づけた。
10 新技術の弊害
しかしながら、岡の導入した新技術には同時に次のような弊害も生じさせた。すなわち、新技術による大規模な捕鯨によって、他の漁に支障が出始めたのだ。
たとえば、解剖時の血や脂が海を汚染し、イワシやカツオなどの漁業に影響が出ているという苦情である。このような苦情は各地の漁村で提起されたものの、こうした苦情に対し捕鯨産業は迷信であると一蹴し、相手にしなかった。そのため、漁民らの不満は高まり、青森県ではホッキ貝の漁師らが捕鯨会社の関連施設を焼き打ちするという事件まで起きている。
11 乱獲による捕鯨数の減少
新技術の導入により、これまで活動範囲の限られていた捕鯨から、沖合にまで出て捕鯨が可能になった。そのため、捕鯨数は劇的に増加した。そこで次第に、鯨資源の枯渇が危惧されてくるようになる。
こうした危惧を受けて岡は、鯨資源の枯渇は心配ないと述べ、不安を収めようとした。一方で、いざという場合に備え、1909年(明治42年)に捕鯨会社により「日本捕鯨水産組合」が設立され、捕鯨の自主規制に乗り出した。
当時の自主規制は捕鯨産業の発展を優先し過ぎたため効果的ではなかったものの、1900年前後は世界各地で捕鯨を規制する動きが活発になり始めたところで、その中でも日本の規制は世界をリードするものであったという。
12 軍部と一体化した捕鯨
時代は少し下り1930年代になると、日本も欧米と同じように、鯨油の獲得を中心にした捕鯨に、一時的ではあるが、シフトしていく(なお、以前からも鯨油は取っていたものの、あくまでも目的は食肉であった)。
1930年代といえば、「最後のフロンティア」として、列強各国はこぞって南氷洋に捕鯨のため出て行った。日本もまた例外ではなく、南氷洋に捕鯨をするため船を向かわせた。とは言うものの、当時南氷洋で捕鯨をしていた各国と比べると、日本の捕鯨量は南氷洋全体で12.7%の3万894頭であった。なお、当時南氷洋で主に捕鯨をしていた国はイギリスとノルウェーであったという。太地の捕鯨船も南氷洋に向かった。
この時代はそれまでの捕鯨と異なり、捕鯨船が軍用タンカーに建造可能な仕様にされるなどして、戦争の準備と捕鯨が一体化していたので、捕鯨船建造について海軍が支援を行っていた。また、鯨油を活発に輸出し、不足していた外貨獲得に貢献した。
その3に続く。