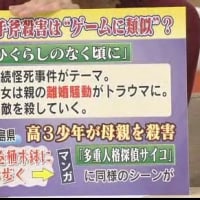「ザ・コーヴ」公開初日、渋谷では全回満席に(読売新聞) - goo ニュース
和歌山県太地町のイルカ漁を隠し撮りした米ドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映が3日、東京、大阪など全国6館で始まった。
抗議活動に備え警察官が警備にあたる映画館もあったが、東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムでは全回満席になるなど、関心の高さをうかがわせた。
同館では、午後1時から3回上映が行われ、約100の客席がすべて満席。正午ごろに同館前で、上映阻止を訴える団体と上映を支持する人々の小競り合いが見られるなど一時騒然となったが、その後は大きな混乱もなく、初日を終えた。映画を見終わった東京都内の大学生(18)は「イルカが日本で捕獲され、水族館に送られていることなど知らなかった。論議されるべき問題だと思う」と話した。
この映画の配給会社アンプラグドの加藤武史社長は「きょう一日無事上映ができてほっとしている。これから、映画の内容についての実のある議論が始められると思う」と話している。
またこの日の夜、東京・新宿のライブハウスで、上映を支援するジャーナリストらが参加した公開討論会が開かれ、上映の是非について語り合った。
1 基礎知識
この作品(のようなもの。)では、和歌山県太地町のイルカ漁を盗撮しているわけだが、まず、イルカと鯨の違いをご存知だろうか。イルカと鯨は同じクジラ目という種類に分類される、れっきとした仲間なのである。
それでは、鯨とイルカの違いはというと、成長した体の大きさが4メートル以下のものをイルカ、それ以上のものを鯨として区別しているという。これは英語圏でも同じで、4メートル以上のものをwhale、4メートル以下のものをdolphinと呼んでいるという。そこで以下では、イルカ漁も含めて捕鯨と言う。
前振りはこれぐらいにして本題に入ろう。
2 縄文時代から行われている捕鯨
太地町で行われている捕鯨であるが、それでは日本ではいつの時代から捕鯨を行っていたのだろうか。捕鯨の規模等については諸説あるが、どの説も縄文時代から捕鯨が行われていたということでは一致している。
たとえば、1982年に石川県鳳至郡能都町間脇遺跡から大量のイルカや鯨の骨が出土しているし、横浜市の称名寺遺跡などからもイルカの骨が出土している。なお、当時の人たちはイルカの骨を使い、アワビ採取のための銛などを作っていたという。
それでは、具体的にどのような捕鯨が行われていたのか。考古学者等の研究によると、見解は錯綜しているものの、大型の鯨を捕獲していた可能性は低いものの、小型の鯨類、すなわちイルカは縄文時代から積極的に捕獲されていたとする。中型や大型クラスの鯨は、たとえば死んで座礁している「流れ鯨」などを捕獲していたと考えられている。
3 太地町ではいつから捕鯨があったのか?
逐一時代ごとに検証しているとキリがないので、時代は下り、和歌山県太地町では長元8年(1035年)には捕鯨に関する記述が残っていることから、少なくとも今から1000年近く前より捕鯨は行われていたと推測される。
太地は、鯨の回遊の道に面し、地形的に鯨が陸に近寄ってくることが多かったので、これも納得できる。すなわち、太地はそれ自体が捕鯨に非常に適した地理的条件を有していたということだ。
4 捕鯨技術の進展(江戸時代まで)
捕鯨技術の進歩により、中型クラスの鯨なら積極的に捕獲ができるようになると、各地では捕鯨の専門家集団(鯨組)が出てくる。太地のある紀州では、文禄元年(1592年)に「尾佐津」と称する組が登場し、遅れて太地においても慶長11年(1606年)に、領主の和田氏が「刺手組」という捕鯨集団を組織している。なお、鯨組の詳細については割愛する(鯨組については、小松正之『クジラと日本人』(青春新書、2002年)を参照)。
太地に刺手組ができた当初は、1つの組(5組あった。)に40人程度がおり、4~5隻の船でゴンドウ鯨、マッコウ鯨、セミ鯨等を捕獲していたという。しかしながら、当時の技術では中型の鯨を捕るのがせいぜいで、死んでしまうと水中に沈んでいくタイプのザトウ鯨やイワシ鯨は捕獲できなかった。そこで開発されたのが「網捕り式捕鯨」である。
この捕鯨は、17世紀後半に登場してきたもので、鯨を巨大な網で取り囲み、動きを封じてから仕留め、鯨が沈んでしまう前に持双船舟が挟み込むようにして鯨を浮かせ、浜に運ぶというものであった。太地では、和田頼治が蜘蛛の糸に引っ掛かったセミを見て思いついたと伝承されているという。
5 豊穣の神としての鯨
古くから日本では、鯨は重要な生活資源であると同時に、自然界からやってくる特別な存在として認識されていた。このような考え方は、鯨を豊穣の神、すなわちエビス様として捉える信仰に結び付く。
たとえば、鯨組においては、鯨そのものが莫大な利益をもたらすことから(当時は朝廷等に献納されていたし、鯨一頭で7つの村が栄えるとまで言われていた。)、あるいは鯨はエビス様の贈り物と考えられていた。
だから鯨は、これが捕れたときには鯨組で独占するのではなく、村中で鯨を分け合って豊穣をお祝いした。お祝いの席では、捕鯨に携わった人たちが集まり、豊穣を感謝する儀式が行われていた。
また、鯨の肉や皮は、鯨組の最下層の者から、地方の神社や寺院、さらに藩の関係者にまで無償で配られたという。それから、鯨はイワシを運んで来てくれる有難い存在としても認識されていた。
捕鯨技術の進歩等により、鯨はやがて、一部の富裕層の食べ物から、庶民までが口にできるようになっていったのである。
6 母子鯨は捕るな―大背美流れという惨事―
鯨類の最も強い関係は母子関係と言われており、子鯨は4カ月は母鯨に依存し、なかにはこれが数年にもおよぶ種類もあるという。したがって、危険に見舞われると母鯨は子鯨を必死に守ろうとしたりするため、母子鯨の捕獲は非常に危険な作業であった。
なので古くから、鯨が子を思う気持ちは人間と同じであると認識されてきた。しかしながら、捕鯨で生計を立てる漁村では、母子鯨はまたとないチャンスであり、経済的理由から歓迎された。
太地町には「大背美流れ」という事件が言い伝えられている。これは1878年(明治11年)、太地の漁民が鯨の不漁で悩まされていたときに起こった惨事である。なお、なぜ当時太地では不漁に悩まされていたかというと、太地の人たちが捕っていたセミクジラを、沖合でアメリカの捕鯨船が大量に捕獲していたからである。しかし、日本の伝統的捕鯨では捕獲対象は陸の近くの鯨に限定されていた。
しかし、太地の人にとって鯨の不漁は死活問題であり、当時は12月ということもあり、鯨が捕れなければ年が越せないという事態にもなりかねない。そこへ子連れのセミクジラが泳いでいるのが見つかった。とは言うものの、当時の天候は非常に悪く、捕鯨に適しているとは言えないし、また、上記の理由により母子鯨は捕ってはならないと言い伝えられていたことから、漁を断念すべきとの声もあった。
しかし、背に腹は代えられぬということで漁に出た。ところが、これが大惨事を招くことになった。悪天候も手伝って、漁に出た124名が死亡するという痛ましい結果になった。これが「大背美流れ」である。これは現在においても、日本捕鯨史上最悪の遭難事故として記録されている。
7 鯨を弔う
日常的に残酷な捕鯨に従事する鯨組は、痛みや愛情という点から鯨を捉え、捕えた鯨は丁寧に埋葬して弔うことにしていた。とりわけ母子鯨や母体から胎児が見つかった鯨については、手厚く葬られていた。たとえば、土佐では7日間の間供養が行われ、番人が昼夜を通し付き添っていた。全国には130を超える鯨の墓が建立されているという。
また、捕獲した鯨に戒名を付けることもあった。戒名を与え、過去帳を作成して定期的に法要を行うところもある。たとえば、愛媛県東宇和郡明浜町(現西予市)の金剛寺の過去帳には、将軍や大名につける位の高い戒名が付けられた鯨が眠っている。太地町にも鯨の墓は存在する。
その2へ続く。
和歌山県太地町のイルカ漁を隠し撮りした米ドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映が3日、東京、大阪など全国6館で始まった。
抗議活動に備え警察官が警備にあたる映画館もあったが、東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムでは全回満席になるなど、関心の高さをうかがわせた。
同館では、午後1時から3回上映が行われ、約100の客席がすべて満席。正午ごろに同館前で、上映阻止を訴える団体と上映を支持する人々の小競り合いが見られるなど一時騒然となったが、その後は大きな混乱もなく、初日を終えた。映画を見終わった東京都内の大学生(18)は「イルカが日本で捕獲され、水族館に送られていることなど知らなかった。論議されるべき問題だと思う」と話した。
この映画の配給会社アンプラグドの加藤武史社長は「きょう一日無事上映ができてほっとしている。これから、映画の内容についての実のある議論が始められると思う」と話している。
またこの日の夜、東京・新宿のライブハウスで、上映を支援するジャーナリストらが参加した公開討論会が開かれ、上映の是非について語り合った。
1 基礎知識
この作品(のようなもの。)では、和歌山県太地町のイルカ漁を盗撮しているわけだが、まず、イルカと鯨の違いをご存知だろうか。イルカと鯨は同じクジラ目という種類に分類される、れっきとした仲間なのである。
それでは、鯨とイルカの違いはというと、成長した体の大きさが4メートル以下のものをイルカ、それ以上のものを鯨として区別しているという。これは英語圏でも同じで、4メートル以上のものをwhale、4メートル以下のものをdolphinと呼んでいるという。そこで以下では、イルカ漁も含めて捕鯨と言う。
前振りはこれぐらいにして本題に入ろう。
2 縄文時代から行われている捕鯨
太地町で行われている捕鯨であるが、それでは日本ではいつの時代から捕鯨を行っていたのだろうか。捕鯨の規模等については諸説あるが、どの説も縄文時代から捕鯨が行われていたということでは一致している。
たとえば、1982年に石川県鳳至郡能都町間脇遺跡から大量のイルカや鯨の骨が出土しているし、横浜市の称名寺遺跡などからもイルカの骨が出土している。なお、当時の人たちはイルカの骨を使い、アワビ採取のための銛などを作っていたという。
それでは、具体的にどのような捕鯨が行われていたのか。考古学者等の研究によると、見解は錯綜しているものの、大型の鯨を捕獲していた可能性は低いものの、小型の鯨類、すなわちイルカは縄文時代から積極的に捕獲されていたとする。中型や大型クラスの鯨は、たとえば死んで座礁している「流れ鯨」などを捕獲していたと考えられている。
3 太地町ではいつから捕鯨があったのか?
逐一時代ごとに検証しているとキリがないので、時代は下り、和歌山県太地町では長元8年(1035年)には捕鯨に関する記述が残っていることから、少なくとも今から1000年近く前より捕鯨は行われていたと推測される。
太地は、鯨の回遊の道に面し、地形的に鯨が陸に近寄ってくることが多かったので、これも納得できる。すなわち、太地はそれ自体が捕鯨に非常に適した地理的条件を有していたということだ。
4 捕鯨技術の進展(江戸時代まで)
捕鯨技術の進歩により、中型クラスの鯨なら積極的に捕獲ができるようになると、各地では捕鯨の専門家集団(鯨組)が出てくる。太地のある紀州では、文禄元年(1592年)に「尾佐津」と称する組が登場し、遅れて太地においても慶長11年(1606年)に、領主の和田氏が「刺手組」という捕鯨集団を組織している。なお、鯨組の詳細については割愛する(鯨組については、小松正之『クジラと日本人』(青春新書、2002年)を参照)。
太地に刺手組ができた当初は、1つの組(5組あった。)に40人程度がおり、4~5隻の船でゴンドウ鯨、マッコウ鯨、セミ鯨等を捕獲していたという。しかしながら、当時の技術では中型の鯨を捕るのがせいぜいで、死んでしまうと水中に沈んでいくタイプのザトウ鯨やイワシ鯨は捕獲できなかった。そこで開発されたのが「網捕り式捕鯨」である。
この捕鯨は、17世紀後半に登場してきたもので、鯨を巨大な網で取り囲み、動きを封じてから仕留め、鯨が沈んでしまう前に持双船舟が挟み込むようにして鯨を浮かせ、浜に運ぶというものであった。太地では、和田頼治が蜘蛛の糸に引っ掛かったセミを見て思いついたと伝承されているという。
5 豊穣の神としての鯨
古くから日本では、鯨は重要な生活資源であると同時に、自然界からやってくる特別な存在として認識されていた。このような考え方は、鯨を豊穣の神、すなわちエビス様として捉える信仰に結び付く。
たとえば、鯨組においては、鯨そのものが莫大な利益をもたらすことから(当時は朝廷等に献納されていたし、鯨一頭で7つの村が栄えるとまで言われていた。)、あるいは鯨はエビス様の贈り物と考えられていた。
だから鯨は、これが捕れたときには鯨組で独占するのではなく、村中で鯨を分け合って豊穣をお祝いした。お祝いの席では、捕鯨に携わった人たちが集まり、豊穣を感謝する儀式が行われていた。
また、鯨の肉や皮は、鯨組の最下層の者から、地方の神社や寺院、さらに藩の関係者にまで無償で配られたという。それから、鯨はイワシを運んで来てくれる有難い存在としても認識されていた。
捕鯨技術の進歩等により、鯨はやがて、一部の富裕層の食べ物から、庶民までが口にできるようになっていったのである。
6 母子鯨は捕るな―大背美流れという惨事―
鯨類の最も強い関係は母子関係と言われており、子鯨は4カ月は母鯨に依存し、なかにはこれが数年にもおよぶ種類もあるという。したがって、危険に見舞われると母鯨は子鯨を必死に守ろうとしたりするため、母子鯨の捕獲は非常に危険な作業であった。
なので古くから、鯨が子を思う気持ちは人間と同じであると認識されてきた。しかしながら、捕鯨で生計を立てる漁村では、母子鯨はまたとないチャンスであり、経済的理由から歓迎された。
太地町には「大背美流れ」という事件が言い伝えられている。これは1878年(明治11年)、太地の漁民が鯨の不漁で悩まされていたときに起こった惨事である。なお、なぜ当時太地では不漁に悩まされていたかというと、太地の人たちが捕っていたセミクジラを、沖合でアメリカの捕鯨船が大量に捕獲していたからである。しかし、日本の伝統的捕鯨では捕獲対象は陸の近くの鯨に限定されていた。
しかし、太地の人にとって鯨の不漁は死活問題であり、当時は12月ということもあり、鯨が捕れなければ年が越せないという事態にもなりかねない。そこへ子連れのセミクジラが泳いでいるのが見つかった。とは言うものの、当時の天候は非常に悪く、捕鯨に適しているとは言えないし、また、上記の理由により母子鯨は捕ってはならないと言い伝えられていたことから、漁を断念すべきとの声もあった。
しかし、背に腹は代えられぬということで漁に出た。ところが、これが大惨事を招くことになった。悪天候も手伝って、漁に出た124名が死亡するという痛ましい結果になった。これが「大背美流れ」である。これは現在においても、日本捕鯨史上最悪の遭難事故として記録されている。
7 鯨を弔う
日常的に残酷な捕鯨に従事する鯨組は、痛みや愛情という点から鯨を捉え、捕えた鯨は丁寧に埋葬して弔うことにしていた。とりわけ母子鯨や母体から胎児が見つかった鯨については、手厚く葬られていた。たとえば、土佐では7日間の間供養が行われ、番人が昼夜を通し付き添っていた。全国には130を超える鯨の墓が建立されているという。
また、捕獲した鯨に戒名を付けることもあった。戒名を与え、過去帳を作成して定期的に法要を行うところもある。たとえば、愛媛県東宇和郡明浜町(現西予市)の金剛寺の過去帳には、将軍や大名につける位の高い戒名が付けられた鯨が眠っている。太地町にも鯨の墓は存在する。
その2へ続く。