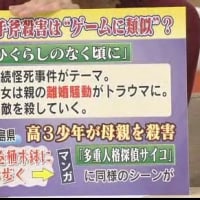映画「ザ・コーヴ」封切り 「是非問うなら見てから」(朝日新聞) - goo ニュース
和歌山県太地町のイルカ漁を扱った米映画「ザ・コーヴ」の一般公開が3日、仙台や東京、大阪など全国6映画館で始まった。当初は6月26日公開予定だったが、保守系団体の抗議予告で3館が降り、一部上映館を替えて1週間遅れの封切りとなった。
シアター・イメージフォーラム(東京都渋谷区)では午後1時の初回を前に、正午ごろには、東京都内の保守系市民団体のメンバー約30人が劇場前に集まり、拡声機で「反日映画は許さない」などと次々に叫んだ。現場に駆けつけた上映を支持する評論家と口論になり、制服姿の警官10人ほどともみ合いになるなど、現場は一時騒然とした。
これまで太地町を中心にわが国の捕鯨について書いてきたが、ここでは番外編として、捕鯨反対を訴える欧米人も過去には鯨肉を進んで食していたことを紹介したい。
しばしば、捕鯨反対を主張する国は欧米諸国が多いので、白人のエゴなどという批判が見受けられるが、同じ白人のノルウェーは熱心な捕鯨国(しかも商業捕鯨をしている。)なので、こうした批判は的外れだ。
しかしながら確かに、彼ら欧米人から反捕鯨の主張をされることには拭い難い違和感があるのもまた事実だ。というのは、彼らも昔は捕鯨を、しかも資源量を考慮することなく、乱獲的に行ってきたからだ。
歴史的に見れば、捕鯨を他の諸国にも広げたバスク人であるが、彼らは食肉を目的としてセミ鯨を捕獲していた。つまり、スペイン人やフランス人も過去には鯨を食べていたのである。
それだけではない。スペイン、アイスランド、ポルトガル、ノルウェーには過去もしくは現在において鯨を食べる食文化があるし、欧米人の捕鯨船の乗組員は船上で鯨肉を食べていたという記録が残っている。フランスの内陸部では、鯨の皮の塩漬けが売られていたりした。
アメリカでは、第一次大戦中、牛肉の価格高騰のため、鯨肉を食べることを奨励していた。1917年だけで北太平洋から1000頭の鯨肉が流入し、サンフランシスコでは美味と評判で人気があった。1918年には、アメリカの商務省が32の調理法を乗せた鯨肉奨励の文書を発表している。
さらに、19世紀から20世紀にかけて、欧米での鯨油の使用は革命的な変化を遂げる。それまでは鯨油は主に繊維産業用のソフトソープ等に使用されてきたが、油が一般的に脂肪酸とグリセリンからできていることに着目して、爆弾の原料として使用された。
1856年、メアリー・ローレンスという人物は、約5カ月の間捕鯨(イルカ漁)を行っており、イルカ肉をフライにしたりソーセージにしたりして調理していた。いわく、イルカのソーセージは豚肉のソーセージのように美味しく、メアリーはイルカが非常に美味であったと日記に残している。実は、イルカ食というのは日本だけではなく、現在でも世界各地でみられるものなのである。アイヌの人たちもイルカ漁を行っていた。
また、1929年には鯨油100%のマーガリンが開発されるなどした。なお、当初は鯨を食べるということへの抵抗が欧米人の間であったため、マーガリンの原料に鯨が使用されていることは秘密にされた。1930年代には、鯨油をめぐって列強間で熾烈な駆け引きが繰り広げられ、鯨油の争奪戦が起こった。
このように、鯨の利用を、日本と同じく、いやそれ以上に今まで欧米各国は行ってきたわけだ。したがって、仮に「今は」捕鯨をしていなくても、そもそも捕鯨反対運動の一因となった個体数の減少には欧米各国も無関係ではないことは周知のとおりである。
和歌山県太地町のイルカ漁を扱った米映画「ザ・コーヴ」の一般公開が3日、仙台や東京、大阪など全国6映画館で始まった。当初は6月26日公開予定だったが、保守系団体の抗議予告で3館が降り、一部上映館を替えて1週間遅れの封切りとなった。
シアター・イメージフォーラム(東京都渋谷区)では午後1時の初回を前に、正午ごろには、東京都内の保守系市民団体のメンバー約30人が劇場前に集まり、拡声機で「反日映画は許さない」などと次々に叫んだ。現場に駆けつけた上映を支持する評論家と口論になり、制服姿の警官10人ほどともみ合いになるなど、現場は一時騒然とした。
これまで太地町を中心にわが国の捕鯨について書いてきたが、ここでは番外編として、捕鯨反対を訴える欧米人も過去には鯨肉を進んで食していたことを紹介したい。
しばしば、捕鯨反対を主張する国は欧米諸国が多いので、白人のエゴなどという批判が見受けられるが、同じ白人のノルウェーは熱心な捕鯨国(しかも商業捕鯨をしている。)なので、こうした批判は的外れだ。
しかしながら確かに、彼ら欧米人から反捕鯨の主張をされることには拭い難い違和感があるのもまた事実だ。というのは、彼らも昔は捕鯨を、しかも資源量を考慮することなく、乱獲的に行ってきたからだ。
歴史的に見れば、捕鯨を他の諸国にも広げたバスク人であるが、彼らは食肉を目的としてセミ鯨を捕獲していた。つまり、スペイン人やフランス人も過去には鯨を食べていたのである。
それだけではない。スペイン、アイスランド、ポルトガル、ノルウェーには過去もしくは現在において鯨を食べる食文化があるし、欧米人の捕鯨船の乗組員は船上で鯨肉を食べていたという記録が残っている。フランスの内陸部では、鯨の皮の塩漬けが売られていたりした。
アメリカでは、第一次大戦中、牛肉の価格高騰のため、鯨肉を食べることを奨励していた。1917年だけで北太平洋から1000頭の鯨肉が流入し、サンフランシスコでは美味と評判で人気があった。1918年には、アメリカの商務省が32の調理法を乗せた鯨肉奨励の文書を発表している。
さらに、19世紀から20世紀にかけて、欧米での鯨油の使用は革命的な変化を遂げる。それまでは鯨油は主に繊維産業用のソフトソープ等に使用されてきたが、油が一般的に脂肪酸とグリセリンからできていることに着目して、爆弾の原料として使用された。
1856年、メアリー・ローレンスという人物は、約5カ月の間捕鯨(イルカ漁)を行っており、イルカ肉をフライにしたりソーセージにしたりして調理していた。いわく、イルカのソーセージは豚肉のソーセージのように美味しく、メアリーはイルカが非常に美味であったと日記に残している。実は、イルカ食というのは日本だけではなく、現在でも世界各地でみられるものなのである。アイヌの人たちもイルカ漁を行っていた。
また、1929年には鯨油100%のマーガリンが開発されるなどした。なお、当初は鯨を食べるということへの抵抗が欧米人の間であったため、マーガリンの原料に鯨が使用されていることは秘密にされた。1930年代には、鯨油をめぐって列強間で熾烈な駆け引きが繰り広げられ、鯨油の争奪戦が起こった。
このように、鯨の利用を、日本と同じく、いやそれ以上に今まで欧米各国は行ってきたわけだ。したがって、仮に「今は」捕鯨をしていなくても、そもそも捕鯨反対運動の一因となった個体数の減少には欧米各国も無関係ではないことは周知のとおりである。