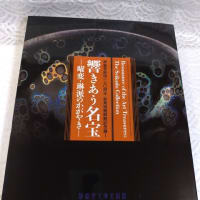信長公記首巻第二十「おどり御張行の事」で、
信長は天人の衣装をつけ小鼓を打ち女おどりを
舞います。のち信長が足利義昭をかついで上洛
したとき、慰労のための観世能を催す場面が
ありますが、このとき義昭が信長の鼓を所望
します。おそらく信長の小鼓・女舞い・小歌・
幸若舞・御鷹野などの趣味にまつわる話が事前
に京の都に伝わっています。
『天人』という語句については、源平盛衰記
巻四十四では「これやこの楽しみ尽きて悲しみ
来るなる天人五衰なるらん」とあり、『天人』
は「いずれ衰えていくもの」として描かれて
います。その出典は
「生ある者は必ず滅す、釈尊未だ栴檀之烟を免れず、
楽しみ尽きて哀しみ来る。天人猶五衰の日に逢へり」
(大江朝綱「和漢朗詠集」無常)
となっています。実は太田牛一が、首巻の段階で
『天人』という言葉を配置して、後の信長の運命
を実は暗示していた・・、と考えたりすると面白い
気がします。
【追記】上記の「おどり御張行の事」の段で、日付
が「七月十八日」となっています。ただ織田太郎左衛門
(信張)の衆が『地蔵』を演じていることから「地蔵の
縁日」と思われ、それならば「24日」が正しい。逆に
信長の演じた『天人』が実は観音様であったなら「観音
の縁日」は「18日」なので原文のままで間違いない、
ということになりますが、どちらなのでしょう?
 にほんブログ村
にほんブログ村
信長は天人の衣装をつけ小鼓を打ち女おどりを
舞います。のち信長が足利義昭をかついで上洛
したとき、慰労のための観世能を催す場面が
ありますが、このとき義昭が信長の鼓を所望
します。おそらく信長の小鼓・女舞い・小歌・
幸若舞・御鷹野などの趣味にまつわる話が事前
に京の都に伝わっています。
『天人』という語句については、源平盛衰記
巻四十四では「これやこの楽しみ尽きて悲しみ
来るなる天人五衰なるらん」とあり、『天人』
は「いずれ衰えていくもの」として描かれて
います。その出典は
「生ある者は必ず滅す、釈尊未だ栴檀之烟を免れず、
楽しみ尽きて哀しみ来る。天人猶五衰の日に逢へり」
(大江朝綱「和漢朗詠集」無常)
となっています。実は太田牛一が、首巻の段階で
『天人』という言葉を配置して、後の信長の運命
を実は暗示していた・・、と考えたりすると面白い
気がします。
【追記】上記の「おどり御張行の事」の段で、日付
が「七月十八日」となっています。ただ織田太郎左衛門
(信張)の衆が『地蔵』を演じていることから「地蔵の
縁日」と思われ、それならば「24日」が正しい。逆に
信長の演じた『天人』が実は観音様であったなら「観音
の縁日」は「18日」なので原文のままで間違いない、
ということになりますが、どちらなのでしょう?