 馬部隆弘著。
馬部隆弘著。
人生で何度か出会うであろう衝撃の1冊。
私にとっては野口悠紀雄さんの「超・整理法」や磯田道史さんの「武士の家計簿」がそれに当たります。
そして今回の「椿井文書」(つばいもんじょ)は、やはりその時と同じ衝撃で頭をフル回転させても、理解を追いつかせることがやっとです。
30年近く前、凡庸な大学生だった私は、歴史学を学んでいても、学者を志せるほどの探究心はありませんでした。
でも一貫して歴史学が好きです。
歴史研究はしていないので、歴史愛好家や歴史好きが1番近いと思っています。
歴史学の学生なら「偽文書(ぎもんじょ)」の存在は必ず習うはずです。
偽文書は、偽書(ぎしょ)とも言いますが、とくにニセの古文書をさします。
みなさんがご存じの偽書もいえば、アマビエが登場するかわら版です。
かわら版(印刷物)であることは、本物です。
でも内容は、アマビエという未知の海洋生物が予言をしたというフェイクニュースで、これが偽書たるゆえんです。
ただしアマビエは、分かりやすいフェイクニュースなので、現代人は騙されることはないです。
一方で椿井文書。
著者の解釈では、偽文書を作成した椿井政隆(つばいまさたか)1人が、江戸時代後期に様々な中世(室町時代等)文書を捏造しました。
その捏造した文書は、時代を経て、じつは自治体史等に採用されていて、それを元に地元の文化財指定の根拠になっていた…。
これは歴史学を学ぶ上では、これはちょっといただけないです。
20年ほど前ですが、旧石器捏造事件という考古学界を揺るがした大捏造事件が発覚しました。
これは現代の発掘現場で捏造が明るみになったのですが、その捏造が発覚しないまま100年、200年と経てば、嘘も真実になってしまったかもしれません。
椿井文書も最初は戯れ言と言い訳できるような内容だった可能性が高かったのに、余りにも精巧に歴史の穴を埋めてしまう大量の偽文書作成によって、正史の根拠になってしまったのです。
また最初の数ページで、著者自身への興味がガッチリとホールドされてしまいました。
大学で歴史学を学ぶ際、だいたい入学当初から学びたい時代というのは大まかに分かれます。
著者は元々近世を選択していたそうですが、自治体の正史編纂に関わる中で中世に鞍替えをします。
この専門とする時代を変更するのは、まずそうそうないはずです。
私の大学時代の同級生達で、入学当初に学びたいと思った時代を変更した人はいなかったはず。
1度時代を選択したら、ずっとその時代を追ってその道の専門家になっていくモノ…それが私には当たり前すぎて疑う余地がありませんでした。
しかも著者は「他の自治体や郷土史研究会で引用されている椿井文書は偽文書だ」と見破ったのが27歳のとき。
これも大学院出たての駆け出し研究者が、先達の研究を全否定するなんて、学会から抹殺されちゃうようなことに着想してしまうのです。
しかも椿井文書の対象地域は、滋賀県を中心とした広範囲に影響を及ぼしたのです。
調べれば調べるほど、椿井文書が壮大な偽文書だと気付き、先行研究では疑問を抱く研究者もいたことも確認しました。
でも「椿井文書」の信憑性の検証自体は、放置されてきたことが続いてきたそうです。
そりゃあ、先輩研究者達が「椿井文書」を引用や根拠にした研究をしていたら、偽文書もはなかなか疑いにくいです。
しかもその史料が巧妙に歴史の穴を埋めるように、絵図、家系図、関連する文書まで揃っていて矛盾点を見つけづらいように一式全部揃っていたらムリです。
一方で本人は戯れ言と言い訳できるような書き方をしていても、子孫はそれを知らなければ
次第に嘘も真実になってしまうのでした。
そして偽文書であることを見抜けなかった研究者達が引用することで、地域史を形づくる根拠になり、自治体史の史料集に掲載されていきました。
自治体史の史料集は活字化されるので古文書解読には、自治体の史編纂室、教育委員会、公立博物館、公文書館等が専門家が関わります。
そこでも見抜けなかったことで、活字化された史料は、各地の図書館等に収蔵されます。
そう思うと、偽文書を作成した椿井政隆は、作成してから180年ほど経って偽文書とやっと見抜かれたことをどう思っているのだろう。
この本に出会えて、常識、普遍的と思っていることを疑うや違和感への気付きの大切さを再確認しました。












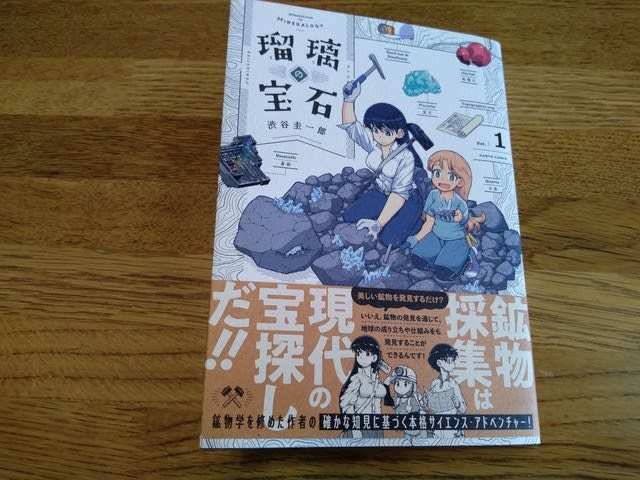


 馬部隆弘著。
馬部隆弘著。


