結果発表と言いつつ、使い始めてから二ヶ月以上経ってしまいましたが…。
『クレアボル(ハレオ)』というのは、読んで字のごとくでクレアチンを主体としたサプリメントなんですが、従来のクレアチンとは異なり、ローディングの必要がないという話を聞いたのが使い始めたきっかけです。プロであれば、40時間/週以上の練習時間を確保できるでしょうか、カンフー・パンダは、単なるトレーニング・ファンなので、10時間/週程度の練習時間が確保できれば良い方です。しかも、トレーニングをやる気は満々であっても、月例の飲み会とか、突然の飲み会とか、たまのデートで飲みに行ったりとかで、練習時間は削られてしまうのが常です。必ず、毎日トレーニングできる環境にあれば、クレアチンは良い選択しかもしれませんが、そうではない人の方が多い中で、ローディング期を設けた方が良い、デイリーで失われた分のクレアチンを補充摂取しなければ行けないというのは、なかなかに辛いものがあります。トレーニングに行かなくても、クレアチンだけが減っていくということになりますので…。
『クレアボル』を使っていたころは、トレーニングする度に挙上重量が上がるかレップ数が上がるかと言った状態でした。で、たぶん二年くらい前だったと思うんですが、『ハイパードライブ(ハレオ)』が発売されたので、そちらにスイッチしました。その後、色々と試行錯誤があって、『ハイパードライブ(ハレオ)』&『ベタイン(バルクスポーツ)』というスタックを使うようになりました。『ベタイン』の効果については、何度かレポートしているので、そちらを参照してみてください。
今年の初めに、『クレアボル・ブラックオプス(ハレオ)』が発売になったんですが、発売と同時に売り切れになってしまったという事情があったので、独自に、『クレアボル・インフューズド(ハレオ)』&『ベタイン(バルクスポーツ)』&『HMB(バルクスポーツ)』&『PS2000(バルクスポーツ)』というスタックでの人体実験を開始しました。『クレアボル』ではなくて『クレアボル・インフューズド』になっているのは単に売り切れていたからです。(^^;)。
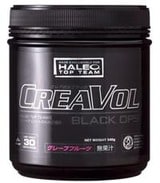
結果発表の前にまず、『クレアボル・ブラックオプス(ハレオ)』の成分は下記の通りです。
・クレアチン
・アルギニン
・グルタミン
・カルシウムHMB
・ベタイン
・フィチン
『クレアボル』に『ベタイン』と『カルシウムHMB』を追加したような形になっています。厳密に言うと『クレアボル』に配合されていたクエン酸が外されてます。『クレアボル・インフューズド』から見ると、シニュリンPFが外れている感じです。
ATPサイクルで、ATP(アデノシン三リン酸)がP(燐)を離してADP(アデノシン二リン酸)になるときにエネルギが放出される訳なんですが、このADPに素早くリン酸を供給してATPに戻してやれば、筋力のパワーアップや持久力アップが見込まれる訳です。クレアチンは、クレアチン燐酸の形で筋肉中に存在し、ADPに燐を供給してくれるわけです。
その他の成分については、血流量を増やすアルギニン、筋肉の回復を早めるグルタミン、クレアチンの生成を高めるグリシン、クレアチン燐酸の再合成を促進するフィチンという顔ぶれです。アルギニンやグルタミンは、筋肉中での保水効果もありますので、筋肉を十分にパンプさせる作用もある訳です。
ベタインについても、何度かレポートしていますが、2~3レップしか出来ないような高重量を扱っているときには余り体感はないんですが、6~12レップ程度の中重量を扱うときには明らかにレップ数が増えます。バーンが、本来ならば来るであろうレップ数よりも2~3レップは増える感じ。たぶん、運動によって生成される乳酸などを、素早く除去するような働きがあるのではないかと思っています。より追い込めるというわけですね。

HMBについては、余り体感はなかったんです。これについては後述しますが…。

で、結果なんですが、『クレアボル』&『ベタイン』のスタックの効果は当然のこととしてあります。トレーニングごとに扱える重量が増える、あるいはレップ数が増えるというところなんですが、ちょっと意外な効果としては、筋肉痛が軽くなっているような気がしています。『PS2000』でフォスファチジルセリンを摂取しているからだと思っていたんですが、『PS2000』を取らなくても、同様に筋肉痛は軽くなるような気がします。となると、カルシウムHMBの効果なんでしょうか?。

以前、HMBを使っていたころは、ポスト・ワークアウト・サプリメントという位置づけで使ってたんですが、『クレアボル・ブラックオプス』は、プレ・ワークアウト・サプリメントとして捉えていて、トレーニングの30分くらい前に使ってます。となると、HMBはトレーニング前に使った方が効果が出ると言うことなんでしょうか?。今回の人体実験からHMBを外せば答えはすぐに出ると思うんですが、すでに混合してしまっているので…。
HMBを、どういう目的で配合しているのかが疑問だったんですが、HMBがロイシン誘導体であることを考えると、トレーニング前に血中のロイシン濃度を上げることによって筋分解を抑止する効果があるのかもしれません。『ハイパードライブ』の場合は、BCAAとフォスファチジルセリンできん分解を極力抑えるものでしたが、BCAAに代えてHMBにした方が筋分解の抑止効果があるのかもしれません。ホスファチジルセリンを使わなくても良いくらいに…。
いずれにしても、このスタックはかなり気に入っているので、次回は『クレアボル・ブラックオプス』で再確認したいと思ってます。
『クレアボル(ハレオ)』というのは、読んで字のごとくでクレアチンを主体としたサプリメントなんですが、従来のクレアチンとは異なり、ローディングの必要がないという話を聞いたのが使い始めたきっかけです。プロであれば、40時間/週以上の練習時間を確保できるでしょうか、カンフー・パンダは、単なるトレーニング・ファンなので、10時間/週程度の練習時間が確保できれば良い方です。しかも、トレーニングをやる気は満々であっても、月例の飲み会とか、突然の飲み会とか、たまのデートで飲みに行ったりとかで、練習時間は削られてしまうのが常です。必ず、毎日トレーニングできる環境にあれば、クレアチンは良い選択しかもしれませんが、そうではない人の方が多い中で、ローディング期を設けた方が良い、デイリーで失われた分のクレアチンを補充摂取しなければ行けないというのは、なかなかに辛いものがあります。トレーニングに行かなくても、クレアチンだけが減っていくということになりますので…。
『クレアボル』を使っていたころは、トレーニングする度に挙上重量が上がるかレップ数が上がるかと言った状態でした。で、たぶん二年くらい前だったと思うんですが、『ハイパードライブ(ハレオ)』が発売されたので、そちらにスイッチしました。その後、色々と試行錯誤があって、『ハイパードライブ(ハレオ)』&『ベタイン(バルクスポーツ)』というスタックを使うようになりました。『ベタイン』の効果については、何度かレポートしているので、そちらを参照してみてください。
今年の初めに、『クレアボル・ブラックオプス(ハレオ)』が発売になったんですが、発売と同時に売り切れになってしまったという事情があったので、独自に、『クレアボル・インフューズド(ハレオ)』&『ベタイン(バルクスポーツ)』&『HMB(バルクスポーツ)』&『PS2000(バルクスポーツ)』というスタックでの人体実験を開始しました。『クレアボル』ではなくて『クレアボル・インフューズド』になっているのは単に売り切れていたからです。(^^;)。
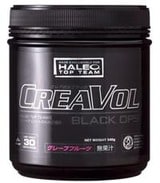
結果発表の前にまず、『クレアボル・ブラックオプス(ハレオ)』の成分は下記の通りです。
・クレアチン
・アルギニン
・グルタミン
・カルシウムHMB
・ベタイン
・フィチン
『クレアボル』に『ベタイン』と『カルシウムHMB』を追加したような形になっています。厳密に言うと『クレアボル』に配合されていたクエン酸が外されてます。『クレアボル・インフューズド』から見ると、シニュリンPFが外れている感じです。
ATPサイクルで、ATP(アデノシン三リン酸)がP(燐)を離してADP(アデノシン二リン酸)になるときにエネルギが放出される訳なんですが、このADPに素早くリン酸を供給してATPに戻してやれば、筋力のパワーアップや持久力アップが見込まれる訳です。クレアチンは、クレアチン燐酸の形で筋肉中に存在し、ADPに燐を供給してくれるわけです。
その他の成分については、血流量を増やすアルギニン、筋肉の回復を早めるグルタミン、クレアチンの生成を高めるグリシン、クレアチン燐酸の再合成を促進するフィチンという顔ぶれです。アルギニンやグルタミンは、筋肉中での保水効果もありますので、筋肉を十分にパンプさせる作用もある訳です。
ベタインについても、何度かレポートしていますが、2~3レップしか出来ないような高重量を扱っているときには余り体感はないんですが、6~12レップ程度の中重量を扱うときには明らかにレップ数が増えます。バーンが、本来ならば来るであろうレップ数よりも2~3レップは増える感じ。たぶん、運動によって生成される乳酸などを、素早く除去するような働きがあるのではないかと思っています。より追い込めるというわけですね。

HMBについては、余り体感はなかったんです。これについては後述しますが…。

で、結果なんですが、『クレアボル』&『ベタイン』のスタックの効果は当然のこととしてあります。トレーニングごとに扱える重量が増える、あるいはレップ数が増えるというところなんですが、ちょっと意外な効果としては、筋肉痛が軽くなっているような気がしています。『PS2000』でフォスファチジルセリンを摂取しているからだと思っていたんですが、『PS2000』を取らなくても、同様に筋肉痛は軽くなるような気がします。となると、カルシウムHMBの効果なんでしょうか?。

以前、HMBを使っていたころは、ポスト・ワークアウト・サプリメントという位置づけで使ってたんですが、『クレアボル・ブラックオプス』は、プレ・ワークアウト・サプリメントとして捉えていて、トレーニングの30分くらい前に使ってます。となると、HMBはトレーニング前に使った方が効果が出ると言うことなんでしょうか?。今回の人体実験からHMBを外せば答えはすぐに出ると思うんですが、すでに混合してしまっているので…。
HMBを、どういう目的で配合しているのかが疑問だったんですが、HMBがロイシン誘導体であることを考えると、トレーニング前に血中のロイシン濃度を上げることによって筋分解を抑止する効果があるのかもしれません。『ハイパードライブ』の場合は、BCAAとフォスファチジルセリンできん分解を極力抑えるものでしたが、BCAAに代えてHMBにした方が筋分解の抑止効果があるのかもしれません。ホスファチジルセリンを使わなくても良いくらいに…。
いずれにしても、このスタックはかなり気に入っているので、次回は『クレアボル・ブラックオプス』で再確認したいと思ってます。











