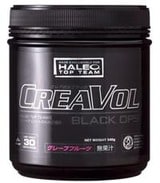プレワークアウト・サプリメントと言えば『ハイパードライブ(ハレオ)』なので、まずこちらを復習しておきます。

トレーニング中とトレーニング後のしばらくは、筋分解が優位になるんですが、その後、筋合成が優位になります。筋合成が優位になるタイミングを狙って、筋肉合成の材料になるプロテイン等を摂取しておくというのが旧来のサプリメントの使い方であった訳なんですが、最近では、トレーニング中の筋分解を出来るだけ押さえるような方向でサプリメントを摂取する方向に変わってきています。筋分解後の筋合成に期待するというのは、一歩下がって二歩進む的な感覚がある訳なんですが、トレーニング中の筋分解を押さえ込むことが出来れば、二歩進むことが出来る訳です。
成分は、
・EAA(Essential Aminno Acid)
・アルギニン、シトルリン
・緑茶エキス
・フォスファチジルセリン
・バイオペリン
です。
筋合成のスイッチは、血中のアミノ酸濃度、特にロイシンの濃度で決まるとされていますので、EAAを摂取して血中アミノ酸濃度を上げることにより、筋合成のスイッチを入れておく訳です。
フォスファチジルセリンは、大豆由来の成分なんですが、トレーニングによるコルチゾールの分泌を抑える働きがあります。コルチゾール等のは、筋分解ホルモンなので、この働きを抑えることにより、筋分解を押さえ込むと言うことです。
ロイシンをはじめとするEAAにより筋合成のスイッチを入れ、フォスファチジルセリンによるコルチゾール分泌抑制のダブルの効果で筋分解を押さえ込むという訳です。
アルギニン&シトルリンは、血中NO(一酸化窒素)レベルを高める働きがあり、EAAなどの成分を筋肉に送り込む働きを昂進する訳です。
バイオペリンは黒胡椒から抽出される訳なんですが、栄養素の腸管における吸収率を高める作用を持っています。
さて、今回は『ハイパードライブ』ではなくて、筋分解ホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制するフォスファチジルセリンのみを単体で摂取した場合にどうなるかと言うことをテーマに人体実験をしてみた訳です。使ってみたのは『PS200(バルクスポーツ)』です。

結論なんですが、『PS200』のみでも筋肉痛(遅発性筋肉痛)は軽くなります。年を取ると、筋肉痛の発生が遅くなるという話もありますが、筋肉痛を発生させるような強度の運動を、無意識に避けるようになるためであって、高強度のトレーニングを行えば、ある程度の年齢であっても、即日、筋肉痛は発生します。カンフー・パンダの場合、午前中にトレーニングを行うと、夕刻には筋肉痛が始まります。
私見なんですが、フォーストレップ法とかのテクニックを使ってトレーニングする場合、要は、より高強度なトレーニングを行うテクニックや精神力を持っているアスリートにより有効な気がします。あるいは、クレアチン、ベタイン、イミダゾール・ペプチドを使って筋肉の最大出力を上げているとかレップ数を上げているなどで、筋肉に高い負荷がかかる場合は、ある意味で必須のサプリメントかもしれません。クレアチン&ベタインのスタックを使って、フォスファチジルセリンを使わずにトレーニングを行うと、トレーニングを行ったことを後悔するくらいの筋肉痛に襲われます。スクワットなどをやった翌日は、階段の昇降がイヤなので、エスカレータとかエレベータとかを探したりしますし、歩く姿自体がギクシャクしてるんじゃないかと不安になったりしますが、そうしたことが少しでも軽減されるのであれば、フォスファチジルセリンを使う意味はあるんじゃないかと思います。
もう一つ私見なんですが、フォスファチジルセリンを使った日に飲酒すると、二日酔いがひどいです。『ハイパードライブ』を規定量使ったときのフォスファチジルセリンは200mg、『PS200』を規定量使ったときは400mgなんですが、『PS200』を使い始めてから二日酔いがひどくなったような気がします。なので、トレーニング後に飲酒する可能性があるときは、意識的に使用量を減らします。アルコールの分解を行うのも筋分解に関与しているコルチゾールですので、コルチゾールの分泌を抑えるフォスファチジルセリンを使うと、アルコールの分泌も遅れるのではないかと推測していますが、どういったメカニズムになっているのか、あるいは単純な思い違いなのかは分からないです。

トレーニング中とトレーニング後のしばらくは、筋分解が優位になるんですが、その後、筋合成が優位になります。筋合成が優位になるタイミングを狙って、筋肉合成の材料になるプロテイン等を摂取しておくというのが旧来のサプリメントの使い方であった訳なんですが、最近では、トレーニング中の筋分解を出来るだけ押さえるような方向でサプリメントを摂取する方向に変わってきています。筋分解後の筋合成に期待するというのは、一歩下がって二歩進む的な感覚がある訳なんですが、トレーニング中の筋分解を押さえ込むことが出来れば、二歩進むことが出来る訳です。
成分は、
・EAA(Essential Aminno Acid)
・アルギニン、シトルリン
・緑茶エキス
・フォスファチジルセリン
・バイオペリン
です。
筋合成のスイッチは、血中のアミノ酸濃度、特にロイシンの濃度で決まるとされていますので、EAAを摂取して血中アミノ酸濃度を上げることにより、筋合成のスイッチを入れておく訳です。
フォスファチジルセリンは、大豆由来の成分なんですが、トレーニングによるコルチゾールの分泌を抑える働きがあります。コルチゾール等のは、筋分解ホルモンなので、この働きを抑えることにより、筋分解を押さえ込むと言うことです。
ロイシンをはじめとするEAAにより筋合成のスイッチを入れ、フォスファチジルセリンによるコルチゾール分泌抑制のダブルの効果で筋分解を押さえ込むという訳です。
アルギニン&シトルリンは、血中NO(一酸化窒素)レベルを高める働きがあり、EAAなどの成分を筋肉に送り込む働きを昂進する訳です。
バイオペリンは黒胡椒から抽出される訳なんですが、栄養素の腸管における吸収率を高める作用を持っています。
さて、今回は『ハイパードライブ』ではなくて、筋分解ホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制するフォスファチジルセリンのみを単体で摂取した場合にどうなるかと言うことをテーマに人体実験をしてみた訳です。使ってみたのは『PS200(バルクスポーツ)』です。

結論なんですが、『PS200』のみでも筋肉痛(遅発性筋肉痛)は軽くなります。年を取ると、筋肉痛の発生が遅くなるという話もありますが、筋肉痛を発生させるような強度の運動を、無意識に避けるようになるためであって、高強度のトレーニングを行えば、ある程度の年齢であっても、即日、筋肉痛は発生します。カンフー・パンダの場合、午前中にトレーニングを行うと、夕刻には筋肉痛が始まります。
私見なんですが、フォーストレップ法とかのテクニックを使ってトレーニングする場合、要は、より高強度なトレーニングを行うテクニックや精神力を持っているアスリートにより有効な気がします。あるいは、クレアチン、ベタイン、イミダゾール・ペプチドを使って筋肉の最大出力を上げているとかレップ数を上げているなどで、筋肉に高い負荷がかかる場合は、ある意味で必須のサプリメントかもしれません。クレアチン&ベタインのスタックを使って、フォスファチジルセリンを使わずにトレーニングを行うと、トレーニングを行ったことを後悔するくらいの筋肉痛に襲われます。スクワットなどをやった翌日は、階段の昇降がイヤなので、エスカレータとかエレベータとかを探したりしますし、歩く姿自体がギクシャクしてるんじゃないかと不安になったりしますが、そうしたことが少しでも軽減されるのであれば、フォスファチジルセリンを使う意味はあるんじゃないかと思います。
もう一つ私見なんですが、フォスファチジルセリンを使った日に飲酒すると、二日酔いがひどいです。『ハイパードライブ』を規定量使ったときのフォスファチジルセリンは200mg、『PS200』を規定量使ったときは400mgなんですが、『PS200』を使い始めてから二日酔いがひどくなったような気がします。なので、トレーニング後に飲酒する可能性があるときは、意識的に使用量を減らします。アルコールの分解を行うのも筋分解に関与しているコルチゾールですので、コルチゾールの分泌を抑えるフォスファチジルセリンを使うと、アルコールの分泌も遅れるのではないかと推測していますが、どういったメカニズムになっているのか、あるいは単純な思い違いなのかは分からないです。