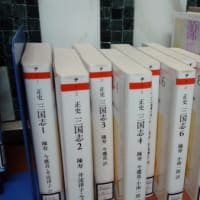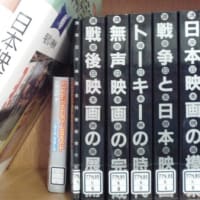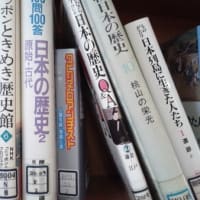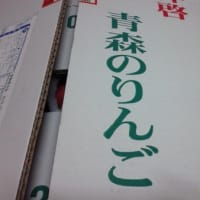障がいのある人と無い人とをつなぐのは、突然では難しい。
いろんな家庭がいることを知って、いろんな家庭で育った友だちと異なる価値観を持ちながら、一緒に生きていく術を身につけるのは、子どもの時から。
障がいのある人も同じ。
発達障がいにレッテルがつくようになって、心身の障がいのある人無い人は分けられていく施策をどんどん良しとする傾向を感じるのは私だけ?
発達障がいについても、その他の障がいについても、
早期発見早期の専門的なケアがあることは本当にそうなのだけれど、その先。
その先には、そのようなケアがあり、サポートがあれば、
普通のクラスの中で一緒に育っていくことがとってもとっても当たり前にできるのに、
分けようとするのはこの地域だけなのだろうか?
学習支援員をがっつり増やしてちょっぴり勉強もしてもらって、
サポートにつけていく方が、
特別支援学校の箱モノを作るよりもよほどよほどお金がかからないでしょ。
子どもたちにとって、学習支援員という職業があるんだということを
知る機会にもなる。
一緒に生活していく仲間なんだと思えたら、ちょっとの違いなど
するする超えていけるのが子どもたち。
風雷社中の中村さんが、親ごさんと一緒に暮らせてる子どもだったら、
ケアに専門家はいらない、と言った。
ある部分での知識は必要な場面があるかもしれない。
でも専門家じゃなくたって、どんな子どもも育てていくことはできる。
育っていくことはできる。
その延長線上にある障害者雇用の問題で行き詰まるのは、
すごぅく昔の、私が生まれたころからの、
障害者を施設型からホーム型でケアしていこうという流れに逆行する、
子どもたちを特別支援学校で育てようという教育の在り方。
言ってしまえば、教育行政は退行してるといってもいい。
子どもの権利委員会が勧告している
・区別、差別の撤廃
・過度な競争による子どものストレスの緩和
両方とも、的を射ている。
自分の地域だけのことだから、
他の地域、国全体ではどうなのかわからないけれど、
下記の障害者雇用問題の数値を見る限り、そういうことだと思う。
(これは見出しは過去最高とあるけれど、
決して実数では進んでいるとは言えない、
誉められない数字じゃないかと思う)
障がいのある子と無い子と、個性の強い子とそうでない子と、みんな一緒くたになりながら好きな場所を子どもが自分で決めて育つ地域をつくりたい。そんな地域で子どもを育てたいと、つくづく思う。
日本人材ニュース 2010-11-01 - 雇用・賃金
http://www.jinzainews.net/article/body/674518db9f9d508a178d94626422322b
障害者の法定雇用率達成企業は47%、雇用率は過去最高 厚生労働省が発表した6月1日現在における障害者の雇用状況についてまとめた結果によると、1.8%の法定雇用率を達成している企業(従業員56人以上)は前年に比べて1.5ポイント上昇し、47.0%であることが分かった。雇用率は1.68%(前年比0.05ポイント上昇)で過去最高となった。
企業に雇用されている障害者の数は34万2973.5人で、前年より3.1%(1万162人)増加した。うち、身体障害者は27万1795人、知的障害者は6万1237人、精神障害者は9941.5人。
雇用率を企業規模別にみると、1000人以上1.90%、500~999人1.70%、300~499人規模企業1.61%、100~299人規模企業1.42%、56~99人規模企業1.42%となっている。
産業別では、医療,福祉2.02%でトップ。電気・ガス・熱供給・水道業1.94%、生活関連サービス業,娯楽業1.90%、運輸業,郵便業1.88%、複合サービス業1.82%と続く。
法定雇用率未達成企業は3万8088社。うち、障害者を1人も雇用していない企業は63.9%となっている。
特例子会社の認定を受けている企業は283社で、雇用されている障害者の数は、1万4562.5人だった。
いろんな家庭がいることを知って、いろんな家庭で育った友だちと異なる価値観を持ちながら、一緒に生きていく術を身につけるのは、子どもの時から。
障がいのある人も同じ。
発達障がいにレッテルがつくようになって、心身の障がいのある人無い人は分けられていく施策をどんどん良しとする傾向を感じるのは私だけ?
発達障がいについても、その他の障がいについても、
早期発見早期の専門的なケアがあることは本当にそうなのだけれど、その先。
その先には、そのようなケアがあり、サポートがあれば、
普通のクラスの中で一緒に育っていくことがとってもとっても当たり前にできるのに、
分けようとするのはこの地域だけなのだろうか?
学習支援員をがっつり増やしてちょっぴり勉強もしてもらって、
サポートにつけていく方が、
特別支援学校の箱モノを作るよりもよほどよほどお金がかからないでしょ。
子どもたちにとって、学習支援員という職業があるんだということを
知る機会にもなる。
一緒に生活していく仲間なんだと思えたら、ちょっとの違いなど
するする超えていけるのが子どもたち。
風雷社中の中村さんが、親ごさんと一緒に暮らせてる子どもだったら、
ケアに専門家はいらない、と言った。
ある部分での知識は必要な場面があるかもしれない。
でも専門家じゃなくたって、どんな子どもも育てていくことはできる。
育っていくことはできる。
その延長線上にある障害者雇用の問題で行き詰まるのは、
すごぅく昔の、私が生まれたころからの、
障害者を施設型からホーム型でケアしていこうという流れに逆行する、
子どもたちを特別支援学校で育てようという教育の在り方。
言ってしまえば、教育行政は退行してるといってもいい。
子どもの権利委員会が勧告している
・区別、差別の撤廃
・過度な競争による子どものストレスの緩和
両方とも、的を射ている。
自分の地域だけのことだから、
他の地域、国全体ではどうなのかわからないけれど、
下記の障害者雇用問題の数値を見る限り、そういうことだと思う。
(これは見出しは過去最高とあるけれど、
決して実数では進んでいるとは言えない、
誉められない数字じゃないかと思う)
障がいのある子と無い子と、個性の強い子とそうでない子と、みんな一緒くたになりながら好きな場所を子どもが自分で決めて育つ地域をつくりたい。そんな地域で子どもを育てたいと、つくづく思う。
日本人材ニュース 2010-11-01 - 雇用・賃金
http://www.jinzainews.net/article/body/674518db9f9d508a178d94626422322b
障害者の法定雇用率達成企業は47%、雇用率は過去最高 厚生労働省が発表した6月1日現在における障害者の雇用状況についてまとめた結果によると、1.8%の法定雇用率を達成している企業(従業員56人以上)は前年に比べて1.5ポイント上昇し、47.0%であることが分かった。雇用率は1.68%(前年比0.05ポイント上昇)で過去最高となった。
企業に雇用されている障害者の数は34万2973.5人で、前年より3.1%(1万162人)増加した。うち、身体障害者は27万1795人、知的障害者は6万1237人、精神障害者は9941.5人。
雇用率を企業規模別にみると、1000人以上1.90%、500~999人1.70%、300~499人規模企業1.61%、100~299人規模企業1.42%、56~99人規模企業1.42%となっている。
産業別では、医療,福祉2.02%でトップ。電気・ガス・熱供給・水道業1.94%、生活関連サービス業,娯楽業1.90%、運輸業,郵便業1.88%、複合サービス業1.82%と続く。
法定雇用率未達成企業は3万8088社。うち、障害者を1人も雇用していない企業は63.9%となっている。
特例子会社の認定を受けている企業は283社で、雇用されている障害者の数は、1万4562.5人だった。