――――
「……またのご来店をお待ちしております」
フランケンシュタインに見送られながら、僕たちは店を出た。
時計を見れば、時刻は午後九時三十七分を指していた。
帰る先は、首都圏にある社宅と、女性一人でも住める防犯意識が行き届いた郊外のマンション。互いに一人暮らししている僕たちの住む場所は、まったくの逆方向なのだが、帰る駅は同じ、使う路線も同じだった。駅まで十分程度の短い道のりを、会話を続けながら僕らは歩く。
しかし、まだ、僕は彼に「すき」を言えないでいる。
「真央さん、そろそろ駅ですよ」
「あ、ああ」
気付けば言葉の後に、もうついてしまったか、と付きそうなぐらい自然に残念そうな表情をしていた。
色々思うところはあったが、結局彼との時間は楽しかったのだ。それだけに、彼の「好き」に「すき」と応えられない自分の不甲斐なさに少し落ち込む。
でも、まだ日にちはある。今日、「すき」と言えなくても、来週。来週、「すき」と言えなくても、再来週。彼と僕が、恋人であり、普通に生きている限り、言うチャンスは幾らでもある。だから別に、今日言わなくても良いんだ。いつか言えばいい。そうだ、そうなんだ。もしかしたら、彼の言葉一つで、何もこんなに緊張することもなかったのかも知れない。
そう思うと、いくらか僕の気持ちにも余裕が生まれてくるものだ。
緊張の解れが、楽しい時間を少しでも楽しもうという素直さを引き出してくれる。
「帰りの電車まで、少し時間があるな。なあ、中島君、その……なんだ……電車一本遅らせてくれないか?」
「別に僕は近いから良いですけど、どうしたんですか?」
「もう少し、落ち着いて君と話をしたいなと思って」
「わかりました。僕も、もうちょっと真央さんと話したいなと思ってたんですよ」
不思議な距離感のある二人の関係が、やっと同じ位置に戻った感じだ。
僕たちは人ごみを避け、線路沿いにある駅近くのシャッターの閉まった菓子商店の前で話すことにした。
ゴトン
「このメーカーのミルクティー、真央さん好きでしたよね」
「ああ、そうそう。これのホットが、この秋口には一番だよ」
僕は彼の手に二本抱えられたプルタブ式のスチール缶に入ったホットミルクティーを、地肌では火傷してしまうからと、スーツの両手の袖を伸ばして、まるで殿様から大層な褒美でも貰うように受け取った。受け取った時、彼は僕を見て笑った。僕の何が面白かったのか、理解はできなかったが、彼の微笑を引き出すに値する事を僕はやったらしい。こういう小さな事に笑っている彼の顔を見るたび、僕は安心してしまう。
辺りには涼しいというより、少し寒い風がふいていた。彼と僕の口からは、喋るたびに白い息が出ているのが見える。袖で持ったホットミルクティーを体で包むように抱えながら、飲む適温になるまで待っていた僕の隣で、パカンっと缶のプルタブを空ける音がする。
「やっぱり俺には大分甘い味です、これ」
「そうかい?」
前に聞いた話だが、彼は甘い物は余り得意ではないらしい。随時飲むものはコーヒーだし、洋菓子と一緒にコーヒーを飲むのは邪道だと言い切る、硬派なコーヒー党でもある彼の、ゴクリと喉のなる音を近くで聞きながら、僕もプルタブを空ける。
袖で器用に缶を傾けて、ゴクッと、一口飲んでみる。
暖かい液体が、食道を通って胃に染み渡る前に、甘ったるくて、充足を促す匂いが、僕の鼻腔をつつき、立ち昇る暖かい空気が、僕の眼鏡を少し曇らす。
「ふー、落ち着く。最後のティラミスがちょっと苦かったから、僕には丁度良いよ」
「それは良かった。真央さん食事してるとき、なんだか思い詰めてたみたいだから」
「そ、そんなこと」
「またまた。僕にはわかりますよ。真央さん、何かを言おうとして迷ってた」
ギクりと僕の胸を射す彼の勘の鋭さ。僕の態度がわかりやすかったのかもしれないが、おそらく同姓なら、彼の勘は相当鋭いほうじゃないんだろうか。こんな普通じゃない僕の行動や仕草を、ここまで理解しているのも、凄いことだと思う。
しかし何故、その鋭さを、僕が食事の時に言った一言に生かせなかったのか。
僕は、今じゃないだろ、と言いそうになってしまった気持ちを、熱いミルクティーを含んで濁す。
「無理して言わなくてもいいですよ。俺だって、真央さんに隠してる事ありますから」
「いや、だから。君が推測している何かを言おうなんて、僕はしてないよ」
僕は嘘をつき、突かれた真実の隠蔽に奔走した。
それまで商店のシャッターを背中に、正面を向きながら喋っていた僕だが、弁解の真実味を増すために、横にいる彼の顔を見て話そうとして振り返ると、なぜか彼はいつになく切ない顔していた。
「そうですか。じゃあ俺の勘違いですね。真央さんに隠し事があったら、俺の隠し事も言おうと思ってたのに」
「僕は君に隠し事をするわけないじゃないか。……でも、気になるな。なんだい、その君の隠し事って」
嘘で固めた自分の気持ちの隠蔽にばかり気がいってしまっていたが、彼の言う隠し事に興味がわいた僕は、思い切って彼に尋ねる。彼は、缶に入った甘いミルクティーをグイッと飲むと、自販機の横に設置してあるゴミ箱に空になった缶を投入した。
「僕の隠し事。そんなに知りたいですか?」
「あ、ああ。出来るなら知りたいね」
それまでにこやかだった彼の目じりと眉、そして唇が、妙に強張るのが見えた。
何を言うつもりなんだろうか。
「俺が何を言っても、後悔しませんね。真央さん」
「あ、ああ」
僕の前に一歩彼が進むだけで、伝わってくる雰囲気の違い。
真面目なのは知っているが、この真剣さはなんだ。いつもと違う彼の気迫は、僕の心を動揺させる。
「俺と真央さんが付き合って五ヶ月たちましたよね」
「う、うん」
「俺は真央さんにとって、恋人ですよね」
「ああ、そうだ」
「俺は真央さんにとって、かけがえの無い人ですよね」
「えっ、あ、う、うん。たぶん、そうだと思う」
言い切れない、たぶんという僕の声を聞いた彼は、何かが吹っ切れたように言う。
「たぶんじゃ駄目だ! たぶんじゃ嫌だ!」
僕は、その声に驚いた。
彼がこんなに声を張り上げたのは、付き合って初めてだ。
子どものように純粋な、理性で感情を抑えることが出来ない声。何かを得ようと、駄々をこねるというわけじゃないが、それに近い思いは、声の強さに伝わって、僕の心と耳を刺激する。
「俺は真央さんの事をかけがえのない人だと思っているから、真央さんも俺のことをかけがえのない人と思ってくれないと、俺は……俺は、心配なんです!」
「お、落ち着いてくれ中島君。冷静に、冷静に」
なだめようとする僕の声は、すでに彼に届いているのかわからなかった。
そして彼は、眼鏡の奥の僕の黒い瞳を直視しながら、強く言った。
「……あと三日もすれば、真央さんと会えない、遠くに行っちゃうんですよ、俺は!」
ガッシャァァン!
僕の背にあった商店のシャッターが大きな音をたてて揺れる。
その原因は、彼が僕を逃がさないように両手をシャッターに思い切り突き立てたからだ。
僕を覗く彼の姿に、普段の生真面目で好感の持てる、にこやかな微笑みなどない。あるのは、何かしら必死さを思わせる、焦燥というべき焦りの感情が爆発したものだった。
しかし、僕には彼が焦りを示す理由、それが何だかわからなかった。
怒ったような、悲しいような、切ない表情を浮かべる彼にそれを質問するのはどうかと思ったが、こうなっては仕方がない。僕も聞きたいことは、全部聞こう。
「な、中島君。遠くに行くって、どういうこと?」
「食事の時言ったでしょ、俺の配属先が変わったって」
「言ってたけど……」
「直属の上司が馬鹿やらかして、その部下の俺が署内での居所が無くなって、配属先、遠くになっちゃったんですよ」
「ち、ちなみにそこは何処なんだ?」
「北の北です……ここから新幹線で片道三時間。しかも主要駅から交通整備の状況が悪くて、殆ど陸の孤島って場所ですよ……」
「なんだって、それじゃあ」
僕が言う前より早く、彼のほうが痺れを切らしていた。
「だから真央さんから聞きたいんです! 俺をどう思ってるか、どう思われてるのか! このまま付き合って良いのか、悪いのか! 真央さんの顔で、真央さんの声で、真央さんの素直な心で聞きたいんですよ!」
「そんなこと言われたって……僕は」
普通の恋愛なんてしたことない僕が、そんな突然に、滑るように愛の言葉を言えるわけないじゃないか。
僕にもあった、この付かず離れずの不思議な距離感を保つ関係に抱く、確かな不安は、彼にもあったという事実が、僕の心を揺さぶる。しかし、彼の現実は待ってくれない。だから彼も微笑みの裏で、確認するために焦っていたのだ。それが示せる時間が今日だけであり、今この瞬間しかチャンスが無いことが、僕には急すぎて信じられなかった。
「もう待てないんです! 俺はもう真央さんが言うのを、待てないんです!」
「……」
ここまで言われても、僕は眼をそむけてしまう。
しかし、もう僕が逃げこめる場所と時間はない。
彼の真剣さに対して僕が黙ったり、何処かへ逃げ込んだり、誠意もなく曖昧に応えたら、それこそきっと、彼は気を使って僕の手から離れてしまう。実際距離は届くかもしれないが、心の距離は永遠に、永遠に届かなくなる。
これが、最期なんだ。
これが、本当に最期なんだ。
何度も自己暗示をかけて自分を追い込み、彼を目の前にして、たった一言を言い切る勇気をひねり出す。
「真央さん……」
吐息を潰したような、切ない篭った声が、シャッターに手をつきながら、俯く彼の口から小さく放たれた。
刻一刻と流れる僕と過ごす夜の時間は、彼にとって焦りを増徴させる止め処ない麻薬のようなもの。
彼の感情の爆発が引き、僕と彼の心の距離が永遠に開くまで、もう時間は無い。
物語のシンデレラと同じ、十二時の鐘が鳴れば、僕らの魔法はとけるのだ。
その鐘を鳴らすのは、誰でもない。
僕だ。
「すっ……ぃ……」
それでもまだ、僕の思いは口を伝わってでない。
僕は不甲斐ない自分を呪った。そして自分の体に鞭を入れるように、自分の心にキツイ言葉を投げつけた。
洗面台の鏡の前で練習したことなど忘れろ。頬の火照りを感じさせる羞恥心など捨てるんだ。
音をつめて、そう聞こえるようにした偽物の言葉と、誰かが聞いてると思ってすぼめた感情なんかじゃ、真剣な彼に伝わるはずが無い。
言うんだ、僕は、彼に。
たった二つの音で伝えられる、思っている事を。
「すっ……」
「真央さん、すいませんでした。もう、やめます俺。これ以上やったら無理矢理言わせてるのと同じです。真央さんを苦しめたら元も子もない」
僕が言うよりも早く、俯く彼が乾いた微笑みを僕に当てた。そして、商店のシャッターに突っ張った自分の手をどけると、彼は申し訳なさそうに振り返り、寂しそうに小さくなった背を僕に見せる。
鐘は鳴ってしまった。魔法は解けた。
シンデレラは、ガラスの靴も残さず、僕の前から去ろうとしていた。
「はは、じゃあ。今日はこの辺で。真央さん、このごろ寒いですから。風邪なんかひかないでくださいよ」
彼が行ってしまう。遠くへ。
「ああ、そうそう。僕の送別の時間はメール送りますけど、無理しなくていいですよ」
嫌だ。行かせるものか。
「じゃあ、さようなら……」
それまで知らなかった感情を僕に初めて教えてくれた人は、君以外に居ない。
これからも、居ない気がする。
いや、居ないんだ!
「えっ?」
彼を失う寂しさとか、消失感とか、そんな何かを考える前に、体が彼を追いかけていた。
足早に走る手には、すっかり冷え切ったミルクティーと、彼の手首がガッシリとつかまれていた。
僕は、もう何処にも逃げない。
「僕は……誰よりも君のことが好きだッ!!」
彼は僕の言葉に振り返った。
その顔は二十歳を超えたというのに、年甲斐もなくボロボロと泣いていた。
線路の奥から電車が猛スピードで過ぎ、爆音めいた音と振動が辺りには鳴り響いた。
だが、僕の言葉は確実に、彼に伝わった。
――――
「真央さん次の電車が来るまで、後三十分もありますよ」
「今日は新記録続きだな」
「新記録? ああ、退社時間のことですか」
「退社時間と、電車を使って帰る時間、そして君と会っている時間も、新記録だ」
場所を変え、すっかり閑散となった駅のホームのベンチに座る二人。
気持ちの告白は、僕の心を魔法のように取り替えた。それまで恥ずかしくていえなかったことも、スラスラ出てくるようになり、やっと二人は、普通の恋人同士になれた気がした。
「良い顔になりましたね。俺の好きな真央さんは、そうであって欲しいです」
「何を言ってるんだ。君だって、相当無理して顔つくってたんだろ」
「へへへ、バレました?」
「当たり前だ。君に僕の動揺がわかってしまうように、僕も君の変なところぐらいわかる」
聞いてみれば、実は彼も、この不思議な距離感を持つ関係が好きなんだそうだ。
これには彼の過去の恋愛経験が関係している。彼は、前に劇団員の女優と恋に落ちたことがあり、その女性から真面目な雰囲気が好みと言われて、真面目に徹し、あくまでもプラトニックな付き合いをしていたらしいが、当の彼女は相当なアバズレだったらしく、彼の友人関係も巻き込んで、複雑な恋沙汰が発生したという話しだ。友からの信頼を失い、彼女から裏切りにあい、そのショックから、彼は距離を置く付き合いしか出来なくなったという話だ。
「しかし、切羽詰っていたのはわかるが、なんで転勤の事を最初から言わなかったんだ」
「さっき言ったじゃないですか。聞きたかったんですよ、真央さんの口から。自然に」
「自然に出るものとは、限らないだろう?」
「出ますよ。距離を離して付き合う事が大好きな僕が、ここまで熱心になってしまった真央さんだから」
「そ、そんなこと言われても。……あ、そうか、前はこういう口説き方だったんだな。ふーん、元々は随分口が軽いんだな」
「いや本心ですよ。真央さん」
「ふふ、どうだか」
微笑は自然に出て、会話は自然に弾んで、高ぶる気持ちにブレーキはなく、話す言葉は全て本当で、二人には、もう偽りの感情はなかった。
普通じゃない。だからこそ、僕らは付き合っていけたのかもしれない。
しかし、本当に普通じゃないのは、そこからだった。
「真央さん」
「何だい?」
「結婚しましょう」
「えっ!?」
まばらだが人の居る駅のホームのベンチを立ち、僕は思わず声をあげてしまった。
確認のための告白からそれほど時間は経っていないのに、唐突過ぎるプロポーズ。
彼に対して心を開いた僕も、それには流石に戸惑って、即答できなかった。
かけた眼鏡が落ちそうになるほど、動揺し、顔は赤面していた僕は、言葉に詰まってどもってしまった。
「な、ななな、中島君! な、何を言ってるんだ。まだ僕らは付き合って五ヶ月なんだぞ!」
「付き合ってる時間なんて関係ないですよ。それに僕は覚悟出来てますから」
そういうと、彼はスーツの内ポケットから、小さな紫色の箱を取り出した。
そして、動揺を隠せない僕の前で、その箱を開いて見せた。
「え、あ、こ、これは」
「エンゲージリング。俺がもっと稼ぐような奴なら、もっと高いものも買えたんですが」
箱の中に入っていたのは、俗に言う結婚指輪だった。
彼の計画的犯行というか、周到さに驚くばかりの僕だったが、まだそれを受け取れるような心構えができているはずがない。さっきやめたはずの、いつもの悪い癖がでる。
「ぼ、僕は結婚なんて。だ、第一! 僕は君と手を組んで歩いたことも無いんだぞ!」
「じゃあ、しましょうか」
「えっ、あ」
彼がムクッと立ち上がったのが見えた時には、もう腕をつかまれて、優しく抱き寄せられて手を組んでいた。
近すぎる接近は、僕の頬の紅潮を最大に上げ、沸騰するように伝わる熱は余波となって口を閉ざさせる。
「他に何か、真央さんが思ってる、結婚にいたる段階なんてありますか?」
男を感じさせる厚い胸と、スーツの合間から漂ってくる男の匂いが、僕の心を少女のようにたきつける。
開かれた彼という無垢な心は、ただ、愛という欲望を求め、止め処ないほど、目的の障害を取り除き、したい事をする。
こういう時、真顔でそういうことをする彼は、世界中で息をしている誰よりもズルイと思う。
そして、それを知りながら、次の言葉を吐く僕も、ズルイと思う。
「僕らはまだ、き、キスだってしていないし」
誰かが見ているのなんか、もう考えていなかった。
言葉を言いきる前に、僕の目は閉じられ、唇は彼の顔へむいていた。
ミルクティーのような甘い味と、ティラミスのような苦い味が、愛という熱を帯びて体を駆け巡った。
十二時の鐘は鳴り、魔法は解けたが、シンデレラと王子は、そのまま踊り続けた。
普通の恋人になれなかった、アブノーマルな二人の横には、自分たちが帰るための最終電車がホームに飛び込んで来ていた。
【了】
「……またのご来店をお待ちしております」
フランケンシュタインに見送られながら、僕たちは店を出た。
時計を見れば、時刻は午後九時三十七分を指していた。
帰る先は、首都圏にある社宅と、女性一人でも住める防犯意識が行き届いた郊外のマンション。互いに一人暮らししている僕たちの住む場所は、まったくの逆方向なのだが、帰る駅は同じ、使う路線も同じだった。駅まで十分程度の短い道のりを、会話を続けながら僕らは歩く。
しかし、まだ、僕は彼に「すき」を言えないでいる。
「真央さん、そろそろ駅ですよ」
「あ、ああ」
気付けば言葉の後に、もうついてしまったか、と付きそうなぐらい自然に残念そうな表情をしていた。
色々思うところはあったが、結局彼との時間は楽しかったのだ。それだけに、彼の「好き」に「すき」と応えられない自分の不甲斐なさに少し落ち込む。
でも、まだ日にちはある。今日、「すき」と言えなくても、来週。来週、「すき」と言えなくても、再来週。彼と僕が、恋人であり、普通に生きている限り、言うチャンスは幾らでもある。だから別に、今日言わなくても良いんだ。いつか言えばいい。そうだ、そうなんだ。もしかしたら、彼の言葉一つで、何もこんなに緊張することもなかったのかも知れない。
そう思うと、いくらか僕の気持ちにも余裕が生まれてくるものだ。
緊張の解れが、楽しい時間を少しでも楽しもうという素直さを引き出してくれる。
「帰りの電車まで、少し時間があるな。なあ、中島君、その……なんだ……電車一本遅らせてくれないか?」
「別に僕は近いから良いですけど、どうしたんですか?」
「もう少し、落ち着いて君と話をしたいなと思って」
「わかりました。僕も、もうちょっと真央さんと話したいなと思ってたんですよ」
不思議な距離感のある二人の関係が、やっと同じ位置に戻った感じだ。
僕たちは人ごみを避け、線路沿いにある駅近くのシャッターの閉まった菓子商店の前で話すことにした。
ゴトン
「このメーカーのミルクティー、真央さん好きでしたよね」
「ああ、そうそう。これのホットが、この秋口には一番だよ」
僕は彼の手に二本抱えられたプルタブ式のスチール缶に入ったホットミルクティーを、地肌では火傷してしまうからと、スーツの両手の袖を伸ばして、まるで殿様から大層な褒美でも貰うように受け取った。受け取った時、彼は僕を見て笑った。僕の何が面白かったのか、理解はできなかったが、彼の微笑を引き出すに値する事を僕はやったらしい。こういう小さな事に笑っている彼の顔を見るたび、僕は安心してしまう。
辺りには涼しいというより、少し寒い風がふいていた。彼と僕の口からは、喋るたびに白い息が出ているのが見える。袖で持ったホットミルクティーを体で包むように抱えながら、飲む適温になるまで待っていた僕の隣で、パカンっと缶のプルタブを空ける音がする。
「やっぱり俺には大分甘い味です、これ」
「そうかい?」
前に聞いた話だが、彼は甘い物は余り得意ではないらしい。随時飲むものはコーヒーだし、洋菓子と一緒にコーヒーを飲むのは邪道だと言い切る、硬派なコーヒー党でもある彼の、ゴクリと喉のなる音を近くで聞きながら、僕もプルタブを空ける。
袖で器用に缶を傾けて、ゴクッと、一口飲んでみる。
暖かい液体が、食道を通って胃に染み渡る前に、甘ったるくて、充足を促す匂いが、僕の鼻腔をつつき、立ち昇る暖かい空気が、僕の眼鏡を少し曇らす。
「ふー、落ち着く。最後のティラミスがちょっと苦かったから、僕には丁度良いよ」
「それは良かった。真央さん食事してるとき、なんだか思い詰めてたみたいだから」
「そ、そんなこと」
「またまた。僕にはわかりますよ。真央さん、何かを言おうとして迷ってた」
ギクりと僕の胸を射す彼の勘の鋭さ。僕の態度がわかりやすかったのかもしれないが、おそらく同姓なら、彼の勘は相当鋭いほうじゃないんだろうか。こんな普通じゃない僕の行動や仕草を、ここまで理解しているのも、凄いことだと思う。
しかし何故、その鋭さを、僕が食事の時に言った一言に生かせなかったのか。
僕は、今じゃないだろ、と言いそうになってしまった気持ちを、熱いミルクティーを含んで濁す。
「無理して言わなくてもいいですよ。俺だって、真央さんに隠してる事ありますから」
「いや、だから。君が推測している何かを言おうなんて、僕はしてないよ」
僕は嘘をつき、突かれた真実の隠蔽に奔走した。
それまで商店のシャッターを背中に、正面を向きながら喋っていた僕だが、弁解の真実味を増すために、横にいる彼の顔を見て話そうとして振り返ると、なぜか彼はいつになく切ない顔していた。
「そうですか。じゃあ俺の勘違いですね。真央さんに隠し事があったら、俺の隠し事も言おうと思ってたのに」
「僕は君に隠し事をするわけないじゃないか。……でも、気になるな。なんだい、その君の隠し事って」
嘘で固めた自分の気持ちの隠蔽にばかり気がいってしまっていたが、彼の言う隠し事に興味がわいた僕は、思い切って彼に尋ねる。彼は、缶に入った甘いミルクティーをグイッと飲むと、自販機の横に設置してあるゴミ箱に空になった缶を投入した。
「僕の隠し事。そんなに知りたいですか?」
「あ、ああ。出来るなら知りたいね」
それまでにこやかだった彼の目じりと眉、そして唇が、妙に強張るのが見えた。
何を言うつもりなんだろうか。
「俺が何を言っても、後悔しませんね。真央さん」
「あ、ああ」
僕の前に一歩彼が進むだけで、伝わってくる雰囲気の違い。
真面目なのは知っているが、この真剣さはなんだ。いつもと違う彼の気迫は、僕の心を動揺させる。
「俺と真央さんが付き合って五ヶ月たちましたよね」
「う、うん」
「俺は真央さんにとって、恋人ですよね」
「ああ、そうだ」
「俺は真央さんにとって、かけがえの無い人ですよね」
「えっ、あ、う、うん。たぶん、そうだと思う」
言い切れない、たぶんという僕の声を聞いた彼は、何かが吹っ切れたように言う。
「たぶんじゃ駄目だ! たぶんじゃ嫌だ!」
僕は、その声に驚いた。
彼がこんなに声を張り上げたのは、付き合って初めてだ。
子どものように純粋な、理性で感情を抑えることが出来ない声。何かを得ようと、駄々をこねるというわけじゃないが、それに近い思いは、声の強さに伝わって、僕の心と耳を刺激する。
「俺は真央さんの事をかけがえのない人だと思っているから、真央さんも俺のことをかけがえのない人と思ってくれないと、俺は……俺は、心配なんです!」
「お、落ち着いてくれ中島君。冷静に、冷静に」
なだめようとする僕の声は、すでに彼に届いているのかわからなかった。
そして彼は、眼鏡の奥の僕の黒い瞳を直視しながら、強く言った。
「……あと三日もすれば、真央さんと会えない、遠くに行っちゃうんですよ、俺は!」
ガッシャァァン!
僕の背にあった商店のシャッターが大きな音をたてて揺れる。
その原因は、彼が僕を逃がさないように両手をシャッターに思い切り突き立てたからだ。
僕を覗く彼の姿に、普段の生真面目で好感の持てる、にこやかな微笑みなどない。あるのは、何かしら必死さを思わせる、焦燥というべき焦りの感情が爆発したものだった。
しかし、僕には彼が焦りを示す理由、それが何だかわからなかった。
怒ったような、悲しいような、切ない表情を浮かべる彼にそれを質問するのはどうかと思ったが、こうなっては仕方がない。僕も聞きたいことは、全部聞こう。
「な、中島君。遠くに行くって、どういうこと?」
「食事の時言ったでしょ、俺の配属先が変わったって」
「言ってたけど……」
「直属の上司が馬鹿やらかして、その部下の俺が署内での居所が無くなって、配属先、遠くになっちゃったんですよ」
「ち、ちなみにそこは何処なんだ?」
「北の北です……ここから新幹線で片道三時間。しかも主要駅から交通整備の状況が悪くて、殆ど陸の孤島って場所ですよ……」
「なんだって、それじゃあ」
僕が言う前より早く、彼のほうが痺れを切らしていた。
「だから真央さんから聞きたいんです! 俺をどう思ってるか、どう思われてるのか! このまま付き合って良いのか、悪いのか! 真央さんの顔で、真央さんの声で、真央さんの素直な心で聞きたいんですよ!」
「そんなこと言われたって……僕は」
普通の恋愛なんてしたことない僕が、そんな突然に、滑るように愛の言葉を言えるわけないじゃないか。
僕にもあった、この付かず離れずの不思議な距離感を保つ関係に抱く、確かな不安は、彼にもあったという事実が、僕の心を揺さぶる。しかし、彼の現実は待ってくれない。だから彼も微笑みの裏で、確認するために焦っていたのだ。それが示せる時間が今日だけであり、今この瞬間しかチャンスが無いことが、僕には急すぎて信じられなかった。
「もう待てないんです! 俺はもう真央さんが言うのを、待てないんです!」
「……」
ここまで言われても、僕は眼をそむけてしまう。
しかし、もう僕が逃げこめる場所と時間はない。
彼の真剣さに対して僕が黙ったり、何処かへ逃げ込んだり、誠意もなく曖昧に応えたら、それこそきっと、彼は気を使って僕の手から離れてしまう。実際距離は届くかもしれないが、心の距離は永遠に、永遠に届かなくなる。
これが、最期なんだ。
これが、本当に最期なんだ。
何度も自己暗示をかけて自分を追い込み、彼を目の前にして、たった一言を言い切る勇気をひねり出す。
「真央さん……」
吐息を潰したような、切ない篭った声が、シャッターに手をつきながら、俯く彼の口から小さく放たれた。
刻一刻と流れる僕と過ごす夜の時間は、彼にとって焦りを増徴させる止め処ない麻薬のようなもの。
彼の感情の爆発が引き、僕と彼の心の距離が永遠に開くまで、もう時間は無い。
物語のシンデレラと同じ、十二時の鐘が鳴れば、僕らの魔法はとけるのだ。
その鐘を鳴らすのは、誰でもない。
僕だ。
「すっ……ぃ……」
それでもまだ、僕の思いは口を伝わってでない。
僕は不甲斐ない自分を呪った。そして自分の体に鞭を入れるように、自分の心にキツイ言葉を投げつけた。
洗面台の鏡の前で練習したことなど忘れろ。頬の火照りを感じさせる羞恥心など捨てるんだ。
音をつめて、そう聞こえるようにした偽物の言葉と、誰かが聞いてると思ってすぼめた感情なんかじゃ、真剣な彼に伝わるはずが無い。
言うんだ、僕は、彼に。
たった二つの音で伝えられる、思っている事を。
「すっ……」
「真央さん、すいませんでした。もう、やめます俺。これ以上やったら無理矢理言わせてるのと同じです。真央さんを苦しめたら元も子もない」
僕が言うよりも早く、俯く彼が乾いた微笑みを僕に当てた。そして、商店のシャッターに突っ張った自分の手をどけると、彼は申し訳なさそうに振り返り、寂しそうに小さくなった背を僕に見せる。
鐘は鳴ってしまった。魔法は解けた。
シンデレラは、ガラスの靴も残さず、僕の前から去ろうとしていた。
「はは、じゃあ。今日はこの辺で。真央さん、このごろ寒いですから。風邪なんかひかないでくださいよ」
彼が行ってしまう。遠くへ。
「ああ、そうそう。僕の送別の時間はメール送りますけど、無理しなくていいですよ」
嫌だ。行かせるものか。
「じゃあ、さようなら……」
それまで知らなかった感情を僕に初めて教えてくれた人は、君以外に居ない。
これからも、居ない気がする。
いや、居ないんだ!
「えっ?」
彼を失う寂しさとか、消失感とか、そんな何かを考える前に、体が彼を追いかけていた。
足早に走る手には、すっかり冷え切ったミルクティーと、彼の手首がガッシリとつかまれていた。
僕は、もう何処にも逃げない。
「僕は……誰よりも君のことが好きだッ!!」
彼は僕の言葉に振り返った。
その顔は二十歳を超えたというのに、年甲斐もなくボロボロと泣いていた。
線路の奥から電車が猛スピードで過ぎ、爆音めいた音と振動が辺りには鳴り響いた。
だが、僕の言葉は確実に、彼に伝わった。
――――
「真央さん次の電車が来るまで、後三十分もありますよ」
「今日は新記録続きだな」
「新記録? ああ、退社時間のことですか」
「退社時間と、電車を使って帰る時間、そして君と会っている時間も、新記録だ」
場所を変え、すっかり閑散となった駅のホームのベンチに座る二人。
気持ちの告白は、僕の心を魔法のように取り替えた。それまで恥ずかしくていえなかったことも、スラスラ出てくるようになり、やっと二人は、普通の恋人同士になれた気がした。
「良い顔になりましたね。俺の好きな真央さんは、そうであって欲しいです」
「何を言ってるんだ。君だって、相当無理して顔つくってたんだろ」
「へへへ、バレました?」
「当たり前だ。君に僕の動揺がわかってしまうように、僕も君の変なところぐらいわかる」
聞いてみれば、実は彼も、この不思議な距離感を持つ関係が好きなんだそうだ。
これには彼の過去の恋愛経験が関係している。彼は、前に劇団員の女優と恋に落ちたことがあり、その女性から真面目な雰囲気が好みと言われて、真面目に徹し、あくまでもプラトニックな付き合いをしていたらしいが、当の彼女は相当なアバズレだったらしく、彼の友人関係も巻き込んで、複雑な恋沙汰が発生したという話しだ。友からの信頼を失い、彼女から裏切りにあい、そのショックから、彼は距離を置く付き合いしか出来なくなったという話だ。
「しかし、切羽詰っていたのはわかるが、なんで転勤の事を最初から言わなかったんだ」
「さっき言ったじゃないですか。聞きたかったんですよ、真央さんの口から。自然に」
「自然に出るものとは、限らないだろう?」
「出ますよ。距離を離して付き合う事が大好きな僕が、ここまで熱心になってしまった真央さんだから」
「そ、そんなこと言われても。……あ、そうか、前はこういう口説き方だったんだな。ふーん、元々は随分口が軽いんだな」
「いや本心ですよ。真央さん」
「ふふ、どうだか」
微笑は自然に出て、会話は自然に弾んで、高ぶる気持ちにブレーキはなく、話す言葉は全て本当で、二人には、もう偽りの感情はなかった。
普通じゃない。だからこそ、僕らは付き合っていけたのかもしれない。
しかし、本当に普通じゃないのは、そこからだった。
「真央さん」
「何だい?」
「結婚しましょう」
「えっ!?」
まばらだが人の居る駅のホームのベンチを立ち、僕は思わず声をあげてしまった。
確認のための告白からそれほど時間は経っていないのに、唐突過ぎるプロポーズ。
彼に対して心を開いた僕も、それには流石に戸惑って、即答できなかった。
かけた眼鏡が落ちそうになるほど、動揺し、顔は赤面していた僕は、言葉に詰まってどもってしまった。
「な、ななな、中島君! な、何を言ってるんだ。まだ僕らは付き合って五ヶ月なんだぞ!」
「付き合ってる時間なんて関係ないですよ。それに僕は覚悟出来てますから」
そういうと、彼はスーツの内ポケットから、小さな紫色の箱を取り出した。
そして、動揺を隠せない僕の前で、その箱を開いて見せた。
「え、あ、こ、これは」
「エンゲージリング。俺がもっと稼ぐような奴なら、もっと高いものも買えたんですが」
箱の中に入っていたのは、俗に言う結婚指輪だった。
彼の計画的犯行というか、周到さに驚くばかりの僕だったが、まだそれを受け取れるような心構えができているはずがない。さっきやめたはずの、いつもの悪い癖がでる。
「ぼ、僕は結婚なんて。だ、第一! 僕は君と手を組んで歩いたことも無いんだぞ!」
「じゃあ、しましょうか」
「えっ、あ」
彼がムクッと立ち上がったのが見えた時には、もう腕をつかまれて、優しく抱き寄せられて手を組んでいた。
近すぎる接近は、僕の頬の紅潮を最大に上げ、沸騰するように伝わる熱は余波となって口を閉ざさせる。
「他に何か、真央さんが思ってる、結婚にいたる段階なんてありますか?」
男を感じさせる厚い胸と、スーツの合間から漂ってくる男の匂いが、僕の心を少女のようにたきつける。
開かれた彼という無垢な心は、ただ、愛という欲望を求め、止め処ないほど、目的の障害を取り除き、したい事をする。
こういう時、真顔でそういうことをする彼は、世界中で息をしている誰よりもズルイと思う。
そして、それを知りながら、次の言葉を吐く僕も、ズルイと思う。
「僕らはまだ、き、キスだってしていないし」
誰かが見ているのなんか、もう考えていなかった。
言葉を言いきる前に、僕の目は閉じられ、唇は彼の顔へむいていた。
ミルクティーのような甘い味と、ティラミスのような苦い味が、愛という熱を帯びて体を駆け巡った。
十二時の鐘は鳴り、魔法は解けたが、シンデレラと王子は、そのまま踊り続けた。
普通の恋人になれなかった、アブノーマルな二人の横には、自分たちが帰るための最終電車がホームに飛び込んで来ていた。
【了】











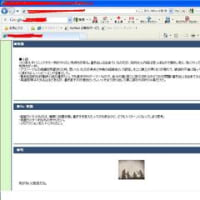







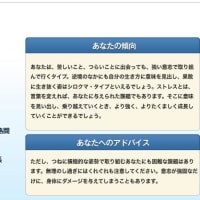

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます