私は1984年の1月にデュッセルドルフ大学医学部病理学研究所で医師としての第一歩を踏み出しました。
当時、学生時代からお世話になっていた博士論文の指導教授であるピッツァー氏に病理医を目指したい意向を伝えると、研究費で医局員を一人雇えるので、まず細胞病理から始めることを提案してくれ、彼の教室に有給医局員として入局することになったのですが、これは私にとって最高の状況でした。病理学への足掛かりをつかむことになるし、博士論文の為の実験とデータの整理は終わっていましたが、まだ執筆の途中であったからです。

大学病院敷地内の教会
ところが、ここで思いがけずドイツの官僚主義に悩まされることになります。1980年代、外国人は医師の資格を取った時点で本国に帰り、自国の医学に貢献することをドイツ政府から期待されていました。もちろん日本人には当てはまらないけれども、外国人留学生の受け入れを開発途上国援助の一環と位置付けていたのです。それで厚生省は医師免許を発行してくれず、役所の外人局は医師免許がなくて働けないという理由で滞在許可証を発行せず、大学の事務局は医師免許も滞在許可もない外国人に医局員のポジションはやれないというのです。さて困りました。ピッツァー教授に相談すると、彼は大学事務局と交渉して、一枚の証明書を出させました。それには、 「OO(私のこと)はピッツァー教授にとってどうしても必要な人材である。」と極端に誇張し、「医師免許と滞在許可が発行されれば、大学はOOを雇用するつもりである。」 とありました。私が医師として働き始めることが出来たのはまさにピッツァー教授のお陰です。彼はそれから1年も経たないうちに学部長になったので、学部内でかなりの力を持っていたのでしょう。
さて細胞病理の業務で義務となっていたのは、朝10時くらいから夕方5時くらいまでの細胞診断でした。教授と背中合わせになる位置で所見と診断をカセットテープレコーダーに口述していくのですが、難しい症例はサッと後ろを向いて教示を仰ぐことが出来ました。勉強する者にとっては最高の環境です。朝の2時間と診断業務の後の2時間ぐらいは論文の執筆に使いました。博士論文の内容はドイツ病理学会で発表する機会があり、ピッツァー教授のもとで多くのことを学ばせてもらったことを今更ながら実感しています。ピッツァー教授と通常二人の細胞診断技師、ケーニヒさんとカンメルさん、そして私で診断業務を行った部屋には片隅にソファーセットがあり、そこで時々一緒にお茶を飲んだりしたのを思い出します。お互い信頼し合っていて家庭的な雰囲気でした。


細胞病理学教室 全体像 ・ 入り口
細胞病理を13ヶ月やった後、ピッツァー教授の口利きで元来の病理学教室に移ることが出来ました。主任教授はホルト教授です。
毎朝8時、ごく短いミーティングで1日が始まるのですが、私は7時半には剖検事務室に行きました。そして自分に割り当てられた解剖があれば、その患者に関する臨床医の手書きのメモを読むのですが、臨床科で使う略語が多用されているし判読困難な走り書きですので、独語を母国語としない私には患者の病歴を整理するのに多少時間がかかるのです。患者の死に至った病歴を、そのミーティングの時に教授を含む全スタッフの前で手短に説明しなければならないので、いつも緊張を強いられていました。
新しく入局した医師の最初の仕事は病理解剖でした。他の多くの医局員は臨床に進む前に少し病理を勉強するのが目的でしたが、私は病理を一生の仕事にしようとしていたので、常に緊張感を持っていたし真面目に仕事に取り組みました。具体的には、昔に比べてかなり減少したらしいのですが、それでもあの当時、年に700体程の剖検業務があり、それを真剣にこなしていきました。一年で100体の剖検を一人で行った年もあります。この年は最後の剖検を大晦日の夜まで一人で解剖室に残ってやって、新年2日の最初の解剖も私が担当しました。病理専門医試験の受験資格の一つが剖検300例であったので、その数にこだわっていたのです。この時期には実に多くのことを学びました。病気の実態についてはもちろんのこと、生と死について、そしてそれにまつわる人間模様についてです。それのみならず、剖検業務ではいつも、日本では講師から准教授にあたると思われる病理専門医が指導者としてついてくれたのですが、特にボルヒャルトとフレンツェルの両教授からは病理学そのもの以外にも、病理医のあり方など得るものが多かったのです。


病理学研究所 全体像 ・ 入り口

病理学研究所 大講義室(外から)
解剖業務のなかで楽しかったのは、いわゆる出張剖検です。これは、近隣の病院から依頼を受けて、その病院まで出かけて解剖し、臨床医に結果を説明してから臓器を大学の研究室に持ち帰るというものでした。楽しいと感じたのは、冬季にはまだ暗いうちに出勤し、終日研究所の中で過ごし、帰宅する時はもう真っ暗になっているという毎日の中で、外が明るいうちに新鮮な空気と暖かい太陽光線を浴びることで、 〈幸せホルモン〉が分泌されたのでしょう。剖検の後、解剖扶助のスタッフが全臓器を大きなビニール袋に入れて、それをトランクに押し込んでタクシーで帰るのですが、タクシーを使うことが本当は法律で禁じられていることを、ある事件があって知ることになりました。ある事件とは、、、、その解剖扶助のスタッフが、出張した病院の解剖室がある地下室から階段、フロア、廊下、ロビーと、そのトランクを運んだのですが、その間ずっと血の混ざった体液がトランクから滴っていたのです。その後、解剖臓器は翌日手術検体を運ぶ医療用車両で運ばれるようになりました。
ボスであるホルト教授が一応剖検をマスターしたと判断した病理学を目指す医局員は、各種の内視鏡の検体及び手術材料の切り出し業務にまわされました。この仕事は手術で切除された病変のある臓器の一部から、録音機に口述しながら、病変部をプレパラートにのる大きさと適度な厚さに切り出していくのですが、大変に神経を使う仕事で、毎日12時から17時半ぐらいまで立ちっ放しで行っていました。4年間、私がほぼ専属のような形でやっていたので、それによって私の、病変を肉眼で判断する能力は非常に高まったと思いますが、病理医にとって最も大事な顕微鏡診断の時間をとるのが難しかったのは残念です。同じ理由で研究の仕事は殆んど出来ませんでした。数回の症例報告と共同研究者としての仕事があるだけでした。しかしながら、この時期は病理医としてのルーティーン業務を学ぶのに私の興味が集中していて、研究が出来ないことは苦痛でもなんでもなかったのです。
〔2015年7月〕〔2022年9月 加筆・修正〕










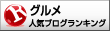
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます