「戦後史」関連で、25年前に買った、金森久雄『わたしの戦後経済
史』を引っ張り出してきた。
あらためて読むとおもしろい。50年の戦後経済史を「わたし」(金
森久雄:1924[T13]-2018[H30])の立場で振り返ったものだ。
個人的な想いをユーモアを交えて綴っている。
戦争直後について、「同時代史」的記述がおもしろい。いわく、
昭和20年8月15日、日本は戦争に負けてアメリカに占領された。このときは前途
はまったく混沌としていた。世界も日本もどのようになるか分からず、五里霧中
であった。米ソによる分割統治の可能性があった。終戦がもう少し遅れていれば、
北海道はロシアのものになっていたかもしれない。天皇制が存続するかどうかは
っきりしなかった。マッカーサーの機嫌しだいでは、天皇制は廃止されていたか
もしれない。
たしかに、現在の新コロナウイルス対応と同様、「この先」がどう
なるか分かっていれば、それなりに対応できるものかもしれないが、
「お先真っ暗」の世界は不安なものだ。
父(注:徳次郎→こちら)が、戦争中でも節を曲げず、天皇機関説を譲らなかっ
たことをみていたためか、私は多少時流に反抗する精神を持つようになった。
・・・・・・一昨日まで自由主義を唱えていた人が、戦争中は全体主義者となり、戦後
は民主主義者となったのを見て人間の弱さを知り、寛容の気持を持つようになっ
た。
何といっても最大の問題は、食べるものがないことであった。戦争中から食糧難
はひどかったが、敗戦で規律がゆるんだためか、一層ひどくなった。配給も遅れ
がちで、飢え死の一歩手前であった。顔を合わせると、大の男が食べものの話ば
かりしていた。
帯には、「50年の歴史は、悲観論者の完敗、楽観論者の完勝の歴史
である」(本文より)とある。
エコノミストだけあって、本文中には経済分析上の具体的な数字が
ポンポンと出てくる。イデオロギッシュなものからは遠い世界だ。
話はまた横道にそれるが・・・・・・
大熊ゼミの卒業コンパ(--三田の何とかという割烹で行った。)
で大熊一郎先生は、われわれ卒業生へのはなむけの言葉として、
「これからは(「イデオロギッシュ」ではなく)、プラクティカル
(とおっしゃったか、プラグマティックと言われたか?10年前まで
は覚えていたが・・・・・・。)を大切にして行ってください」
と言われた。
同期生でどなたか覚えているかな?
金森久雄『わたしの戦後経済史』(東洋経済新報社)
-----------------------------------
5月10日(日)
最新の画像[もっと見る]















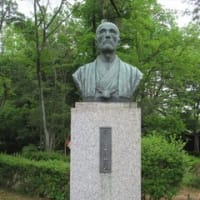


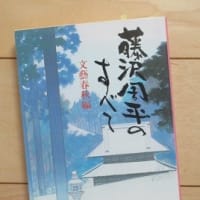
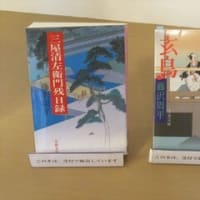





さっそく混声版を拝聴しました。作曲が中田先生、作詩が深尾須磨子(!)なんですね~。戦後の作曲でしょうか。
昭和30年の作品とすれば、深尾67歳、中田32歳の作品ですネ~。